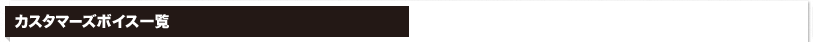
ヴィーナス・アンド・マース [SHM-CD+ポスター+ステッカー]<初回生産限定盤> / Paul McCartney & Wings
|
|
金星と火星を現した黄色と赤の球体が寄り添うシンプルなジャケットだが、収録された13曲は実にバラエティに富んでいて、とってもカラフルだ。この頃のポールはバンド活動に軸足を置いていたのだろう、”ロック・ショー”を意識した、ステージで再現可能な楽曲だけで構成されている。
「ワインカラーの少女」や「メディシン・ジャー」、「コール・ミー・バック・アゲイン」といったストレートで硬派なロック・ナンバーが要所を締めているが、脇を固めるライトな小品たちも決して軟派な”繋ぎ役”ではない。ミスティーな「歌に愛をこめて」、コケティッシュな「幸せのアンサー」、コミカルな「磁石屋とチタン男」など、確かな存在感と個性が立っている。また「遥か昔のエジプト精神」に漂うアフリカの匂いは、明らかに前作『バンド・オン・ザ・ラン』の残り香だ。終盤には「トリート・ハー・ジェントリー~ロンリー・オールド・ピープル」といった中高年層にも届く穏やかなバラードも忘れてはいない。アルバムの幕の引き方に納得がいかなかったのか(?)、床屋の理髪師が最後の仕上げに僅かにハサミを入れるように「クロスロードのテーマ」というインストゥルメンタルを付け加えている。
個人的な出色は無敵のポップ・チューンの「あの娘におせっかい」だ。後の「心のラヴ・ソング」へと磨かれていく原石となった楽曲だと思っている。歌詞もメロディもポジティヴだし、歌声もコーラスもポップコーンのように弾けていて、軽快なクラリネットとの追いかけっこも心地好い。最後は映画のサウンド・トラックのようにダイナミックに着地する。余談だが、財津和夫 氏は、この曲にインスパイアされて「ぼくがつくった愛のうた(いとしのEmily)」を書いたのではないか(?)、と思っている。
黄色い金星と赤い火星の間には青い”地球”があることを忘れてはいけない。
2
|
商品詳細へ戻る
ねずみ1960さんが書いたメンバーズレビュー
|
|
ロバータ・フラックといえば力量感のある歌を歌っていた”最初の印象”が強い(決して”やさしく”はなかった)のだが、70年代の中頃以降は、重い鎧を脱いだような”ため息”混じりのライトでソフトなR&Bにシフト・チェンジしてしまったように思う。
本作は、1978年に大ヒットしたソフトでムーディーな「私の気持ち」の後のブレイクがあって、ラルフ・マクドナルド総指揮の下、フュージョン系のミュージシャンで固められたスタッフによるコンテンポラリーなアルバムだ。言い過ぎかもしれないが、全編フェンダー・ローズの甘い音色に包まれている、といった感じがする。感覚として、聴いていると身体が5cmくらい浮いているみたいで、実に心地よい。
楽曲の方も、グローヴァー・ワシントン・Jrの『ワインライト』で聴き馴染みのある「イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ」を筆頭に、ウィスパーな「メイキング・ラヴ」やビター&スウィートなタイトル曲など、同系色を重ねているにもかかわらず、色調を変化させることで上手く個性が引き出されていて、楽曲の"流れ"を意識した絶妙なラインナップも抜け目ない。
白眉は何と言っても「朝が来るまで…」。マイルドなストロークといい、ウォーミーでチャーミングなメロディ・ラインといい、やさしく語りかけるような歌声を引き立てる控え目な演奏といい、心安らぐ夜のパートナーとして最良かつ最高のMORだ。
0
|
|
|
アルバム未収録の隠れた人気曲(特に日本だけでリリースあるいはCM使用されたもの)を入手することは極めて困難だ。大抵はコアな企画盤での収拾に期待するしかないのだが、稀に、気を利かした発売元が復刻盤にボーナス収録してくれることもあったりして、そんな時は嬉しくなって即買いしてしまう。例えば、アメリカの「シンプル・ライフ」や、E・ダン&J・F・コリーの「キープ・ユア・スマイル」、スティーリー・ダンの「センチュリー・エンド」などがそんなキラー・チューンだ。
本セット2枚目の「ヒル・ストリート・ブルースのテーマ」も、いわゆる手に入れたいのだが見つけにくいアイテムだった。マイク・ポストとタッグを組み、TVドラマ絡みで全米でスマッシュ・ヒットしたイージー・リスニングな逸品なのだが、サウンドトラック仕様だし、権利関係の綱引きもあったためか、これまでベスト盤にも収録されることはなかった。手元にEPレコード盤はあるが回すことができないので、長年CDを探していたのだが、偶然にも本セットに収録されていることを発見してしまった。これだから編集盤は曲目リストをしっかりとチェックしなければいけない。つまりはメーカー側の仕掛けた罠に見事にハマってしまったわけだが…。そんなことはどうでもいい。要するに、この手のラッキー・アイテムを求めているリスナーもいるということなのだ。
実に地味なネタでお茶を濁したが、最後に看板曲の「Room 335」について一言だけ。この楽曲のリズムの刻みはリアルにスティーリー・ダンのプロトタイプだと思っている。自身が参加した「麗しのペグ」の匂いがする。余談だが、高橋拓也がリリースした不思議の国のアリスの間奏で弾けているギターでは、この曲の2分10秒辺りからのフレーズが引用されている。
これも個人の感想だが、ラリー・カールトンは超絶かつ軽妙ながらも芯の通った主張するギター・サウンドも魅力的だが、GRP時代の”子どもの手袋”のようなやさしいタッチのメロディックなストリームもいい。
0
|
|
|
このアルバムには”解説”が必要だ。逆に言えば、一つひとつの楽曲の背景にあるストーリーを知ることで”距離”は縮まるし、”深み”も増す。和訳を読むだけでは十分に伝わってこないし、ましてや即興歌謡のような自由奔放な歌声に振り回されていると、入口の扉を開けても中に入ることを躊躇ってしまう人もいるのではないだろうか。自分がまさにそうだった。若い頃、巷の高評価と滄溟(そうめい)なジャケットに魅了されて扉を開けてはみたが、深い霧の立ち込める森の中に迷い込んだように視界を失い、その孤高かつ独特の恋愛私小説的な空気感に馴染むことができなかった。
数多のレコードは”静物”として存在し、針を落とすことでその叙情と温もりに触れ、それを共有することで安息の時を得ることができるのだが、本作は違っている。まるで”生物”のように意思を持ち、呼吸をし、姿形を変えながら、こちらの弱い部分を見つけ出しては俊敏に襲いかかってくる、”魔物”のような稀有なアルバムだ。
ところが最近になって、本作を丁寧に”解説”した書き物を読み、”魔物”の正体を知ることができた。おかげで自分の中の濃い霧は少しだけ晴れた。後は恋愛小説的な空気感に馴染むだけだ。理解する必要はない。感じればいい。そのようにして、”青”から""藍”よりももっと濃い"蒼”の小部屋に入って行くことになるのだろう。沼は"深い"。
0
|
|
|
お目当ては「Lose Again またひとりぼっち」。シングル・カットされのだが、成績が芳しくなかったのか、どのベスト盤にも収められていない。だから、このアルバムを買うしかない。
1976年、冬。ラジオから流れてきたこの曲との出遭いはとても衝撃的だった。映画主題歌のように叙情的でダイナミックな佳曲を力強く歌うリンダ・ロンシュタットの熱量に圧倒されてしまった。”切ない想い”だけで綴られているシンプルなフレーズを、魂の叫びのように情感たっぷりと歌い上げる様は、まさに鳥肌モノだ。この曲がシングルとして奮わなかったのは、彼女の“情念”のような歌唱に”凄み”があり過ぎたせいかもしれない。
アルバムの内容は悪くない。同じくカーラ・ボノフのしっとりとした「誰か私のそばに」も秀曲だし、ヒットした「ザットル・ビー・ザ・デイ」も古き良きアメリカの空気をしっかりと伝えている。他の収録曲もバラエティに富んでいて、音楽の間口は広いし、奥は意外と深い。個性的な楽曲が目立つのは、この先の方向性を模索していたからなのかもしれない。試行錯誤の跡が覗えるが、アルバム自体に”落書き帳”のような”散漫”な印象はない。
個人的には、”やさしさ”や”しなやかさ”に包まれた、”大人しい”アルバムといった印象を持っている。
0
|
|
|
1曲目から長いタイトルが続く。R・ストーンズと距離を置いていた自分が本作を買う気にさせたのが、同じく長いタイトルのシングル&カヴァーの「エイント・トゥー・プラウド・トゥ・ベッグ」だった。
前作『山羊の頭のスープ』は”コマーシャルなアルバム”と評されていたが、本作もその流れを汲んでいる。当時中学生だった自分でも難なく受け入れることができたし、同時期に聴いたライヴ盤の重厚で粘っこいブルースや癖の強いロックン・ロールなどは影を潜めていて、別世界のアルバムのようだった。
N●Kで放送された”若い音楽ショー”を観て素直に”カッコいい”と思った「ティル・ザ・ネクスト・グッドバイ」や、センチメンタルでメランコリックな「悲しみのアンジー」の系譜と思っている「マイ・フレンド」など、彼らにしては”軟派”で”ポップ”な(親しみやすい)楽曲が並んでいる。アウトローを扱った「フィンガープリント・ファイル」でさえスタイリッシュに面取りされていて、「ドゥー・ドゥー・…」をさらにスマートに焼き直したようにも聴こえる。メインストリートで格闘するならず者たちには物足りない、もっと言えば、魂を売ってしまったような女々しい音楽に聴こえるかもしれない。だが、こんなアルバムがあっていい。彼らも歌っているように、”たかがロックン・ロール”なのだから…。
そんな中、単調なフレーズの繰り返しなのに、知らず知らずのうちにツボにハマってしまう「ダンス・リトル・シスター」は、”中毒性”の高い劇薬だ。エキセントリックにグイグイと押してくる執拗さが癖になる。仕舞には”心地よい”とさえ感じてしまうくらい危険だ。真綿で首を絞めるように攻めてくるタイトル曲とは違った魅力(あるいは魔力)と、いい塩梅の威圧感がある。
0
|
|
|
失当かもしれないが、3作目の(個人的には名盤)『windless blue』が”洋楽”に寄り過ぎていた反動なのか、本作は、巻貝ジャケットが物語るように、軸足を”邦楽”に戻して(原点回帰を意識して)作られたアルバムでは?…などと思っている。解説にある”初の海外(LA)レコーディングにより完成させた…”といのが信じられないくらい、”和”のテイストを強く感じてしまう。
楽曲のタイトルを見ても、”Sea Breeze”の爽やかなイメージは微塵もない「海風」や、言葉遊びのように当て字を使った「冬京」、”美しい”という言葉こそないが”純和風”な「歴史と季節の国」など、”国産”に拘っているような姿勢が覗える。もしかしたら、”西海岸サウンドを手にした”のは伊勢正三ではなく、相棒の大久保一久の方だったのかもしれない。軽快なギターがリードする「おそかれはやかれ」はスマートでファッショナブルだし、アコースティックにダンスする「トパーズ色の街」の甘酸っぱくも爽やかな夏の名残りの空気感が心地よい。
本作には、「海風」や「防波堤」といったストレートに”海をテーマにした歌”だけでなく、”海をイメージさせる歌”もあったりする。「デッキに佇む女(ひと)」もそんな”海歌”の一つだ。冬の海を航くフェリーでの一コマが歌われている。独りの女性に目を奪われてからの一時の妄想も、直ぐに現実に引き戻される、といった俳句的な描写もいい。”侘び寂び”の世界観がここにはある。シンプルで、余計な音は足されていない。とても控え目なアレンジなのに、演奏は一級品だ。この辺りが、”フュージョン/クロスオーバーといった当時の最先端を吸収した…”と言える所以なのかもしれない。
0
|
|
|
コックピット写真をジャケットにした勇ましいアルバムだが、内容はそこまで硬派(ハード)ではない(尖ってはいない)。
彼らの敬愛するザ・ビートルズの通称『ホワイト・アルバム』をモチーフにしていて、オープニングの「TAKE OFF」は「バック・イン・ザ・U.S.S.R.」を模しているし、続く「明日の風」は「ディア・プルーデンス」にしか聴こえない。レコード盤ではB面冒頭の「あの、ゆるやかな日々」のピアノと間奏のアレンジは「マーサ・マイ・ディア」にそっくりだ。ついでに、レコードには切り取り写真がスクラップされたポスターサイズの歌詞カード(もはやカードではない)が”六つ折”封入されていたのだが、これもホワイト・アルバムと同じ仕様となっている。
彼らの”ビートルズ愛”はそれだけに止まらない。「おしえておくれ」の主旋律と粗っぽさは「ヘイ・ブルドッグ」だし、「セプテンバー」は「ゲッテング・ベター」のギター・リフで始まって「愛こそはすべて」の隠し味も添えている。本盤収録のユニゾン歌唱の方がマイルドで聴き心地がよい「青春の影」は、本人たちがどう否定しても「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」以外の何物でもない。
“ピカソの遺言”っぽく始まる「悲しみはいつも」からのメドレー・リレーは、『アビー・ロード』のB面というよりもP・マッカートニー&ウィングスの『レッド・ローズ・…』のラスト4曲のチームに近い(締めのリフレインは「パワー・カット」っぽかったりする)。
リリースから半世紀経ったこともあって、”前衛”というよりも、長閑で平和でレトロな”昭和”の雰囲気が漂う重要無形文化財級の"懐かしいアルバム”、といった感じがする。
0
|
|
|
個人的に杉 真理の最高傑作だと思っている。個々の楽曲のクオリティの高さといい、宝石箱を開けたようなシーケンスといい、アルバムとしての完成度、充実度の高さはピカ一だ。
ジャケットの地球型ラジオ局のイメージもあって、アルバムのタイトル曲だと思い込んでいた「Key Station」は、やはり本作の旗艦曲といっていい、しっかりとした存在感がある。伊藤銀次や佐野元春をゲストに迎え、後に杉 真理が主宰した『WINTER LOUNGE』で結実するリレー歌唱の原点であり布石がここにある。せっかく”達郎のハーモニー~”と歌っているのだから、伊藤銀次のように”高気圧ガール~”みたいに唸ってほしかったが、そこまでは”いつもうまくゆかない”のだろう。ラジオをテーマとしたプレイリストには、ユーミンの「Valentine's RADIO」や南 佳孝の「憧れのラジオガール」、MIKKOの「1-2-3」などとともに、この曲は欠かせない。
アルバムにはドゥーワップやロックン・ロール、スペクターふう音壁やバーバンク・サウンド系のナンバーが詰め込まれていて、中には壮大なシンフォニーの制作を歌った本当のタイトル曲「交響曲第十番」や、サーカスの開演を想わせる「永遠のShangri-la」など、個性豊かで聴き応えのある楽曲でいっぱいだ。
個人的な好みでピックアップするが、「Sentimental Dancing」のジャイヴ感がたまらない。チャールストンでも踊っているような、リズミカルで、キラキラしていて、チャーミングでイノセントな音楽が平凡な世界をバラ色に変えてくれる。嫌なことがあっても、この曲を聴いていれば気分は晴れる。
アルバム・ジャケットは緑黄色系のくすんだトーンだが、中身は総天然色の華やかで彩り豊かな楽曲集に仕上げられていて、永遠に色褪せることはない。
0
|
|
|
Jポップの”クリスマス・アルバム”の企画盤といえば、本作が至高の決定盤といえる。数多の既発曲収集盤とは違う書下ろしのみの構成に加え、豪華アーティストの共演によるレコーディング作品が3曲も収められている。"至宝"以外の何物でもない。
ほぼタイトル曲と言っていいスターターの「Yellow Christmas」は、主催者+アルファの豪華ゲスト陣による”バンド・エイド”スタイルのヴォーカル・リレーが楽しめる。クレジットには歌手表記があるが、歌声や歌詞のフレーズを聴いているだけで誰が歌っているのかが直ぐにわかる。実際は個別収録なのかもしれないが、スタジオ集合によるマイク・リレーのような一体感があって、パーティーを盛り上げるには打ってつけのイントロデュース・ナンバーだ。
レコードA面のラストを飾るとびきりポップな「Wonderful Christmas」は、歌われるエピソードも含めて、ご機嫌で愉快なスキップ・ソングだ。途中、クリスマス・スタンダードのメロディも登場するし、メインを務める楠瀬誠志郎の歌声もキュートで清々しい。
B面には杉 真理の十八番ともいえるウォーミーなバラード「最後のメリー・クリスマス」が冷たい聖夜をほんのりと暖めてくれるし、ラストの「くつ下の中の僕」はワンダフルな連中による祝宴のお開きソングなのだが、閉宴を惜しむかのような粘りの楽屋トークが追加収録されている。ついでに、おまけのモンキーズも御愛嬌だ。
余談になるが、南 佳孝の「再会」は和風ハードボイルドの色が濃い分、結果論として、アルバムの中では浮いている。邪推かも知れないが、そんな”場違い感”を挽回したい想いから、本作のスピンオフ盤『SUMMER ROUNGE』には「Vacances Bleu」というスタンダードになり得る極上のリゾート・ナンバーを提供している。イタリア女優が再登場しそうなこのスローなブギは、自身のオリジナル・アルバム未収録の希少な佳曲であり、もちろん、”佳孝節”全開の秀曲でもある。
0
|
|
|
冒頭のファンファーレは山下達郎の「SPARKLE」ほど刺激的ではないが、常夏の楽園への扉を開く合図としては十分なインパクトを持っている。しかし、それだけではない。後に続くベースラインのドライヴ感が半端ない。次の「ホワッチャ・ゴナ・ドゥ」もそうだが、躍動するリズム隊のテンポの刻みが、”コンマ数秒速いのでは?”と思わせるくらい、フライングぎりぎりのタイミングで前へ前へとサクサク進んで行く。ドラムもピアノもコーラスも、高速レースを楽しんでいる。真夏の陽射しが容赦なく降り注ぐ”太陽の当たる場所”は完璧に常夏の楽園だ。
しかし、ここまで前のめりに走っておいて、後続は爽やかな西海岸サウンドにシフト・チェンジしてしまうのだから面白い。それも、減速ではなく、安定走行しているのだからアッパレだ。要所要所でテクニカルなプレイを披露しながら、レコード盤のB面では舞台の早変わりのような切れの目ない楽曲リレーを難なくやってのけている。
終盤には「アトランタ・ジューン」というセンチメンタルな佳曲が、アルバム後半の”バランスウェイト”として、しっかりとした存在感を放っている。夕暮れが近づいて、そろそろ家に帰る時間の音楽だ。過度に湿っぽくならないように、一定のストロークを保ったままで泣ける旋律を紡いでいる。余談だが、シングル・リリースもされていないこの曲を、二名敦子がカヴァーしていたとは、ちょっとした驚きだった。
アルバムの最後には、南の島のファイアーダンスを想わせる情熱的なギター乱舞がクライマックスを迎える中、”燃えたぎる炎”に背を向けるようにして、"太陽の放浪者"は、恋の水平線の彼方にある次のリーフブレイクへと旅立って行く。
“ハード・ロック”よりもライトでポップだし、ソフトでメロウなのだが、“サーフ・ロック”というヤワなジャンルとは明らかにモノが違う。
唯一残念なのは、日本発売の紙ジャケット仕様盤の音量・音圧が異常に低いことだ。これではダイナミックなミッド・サマー・サウンドを楽しむためにボリュームを10時の位置まで上げなければならない。なんとか再度リマスターしてもらえないだろうか?
0
|
|
|
2 in 1の国内流通仕様盤を47日待ってキャンセルされた。
ずっと以前、古い輸入盤を買っていたのだが、1回通して聴いただけで棚の奥に眠らせていた。国内盤AOR BEST SELECTION 1300 シリーズで廉価販売された時も、他のSELECTIONに目が泳いで、購入リストに入れずじまいだった。完全に自業自得というわけだ。
さて、本作は、良くも悪くも冒頭の「うつり気な炎」に牽引されている。1977年当時、ホール&オーツの弱R&B系の焼き直しな印象を抱いていたこともあって、綿菓子のような食感を甘く、いや、軽く見ていた。最近になって、思い出したように件の輸入盤を聴き直してみたら、こともあろうに小躍りするくらいにハマってしまった。
ひと言でいえば、”パ・マル”、”悪くない”アルバムだ。馴染みのタイトル曲も、半世紀近く経っているのに少しも色褪せていないし、脱力系ポップスのご機嫌なフローターは意外と仕掛けの多い構成力と展開力があって、万華鏡のように楽曲の表情が豊かなことに気づいてしまった。
後続の楽曲群もハイ・クオリティで、完成度の高さは平均点を超えている。気になる湿地など微塵もないどころか、聴いていて飽きのこない良質なコンテンポラリー・サウンドが詰め込まれている。久しぶりにいい再会を果たすことができた。
というわけで、性懲りもなく、40日経過後の強制キャンセル覚悟で2016年盤の発注にリベンジ・トライしてみようと思ったが、カートに入れたところで"注文不可"と、はじかれてしまった。良盤なのでそのうちに再発されるのだろうが、かといって後期高齢者になるまで待ってはいられない。
0
|
|
|
本作に関しては、極めて偏った評価となることをご容赦いただきたい。
ズバリ、「サムワン Someone」一択。これに尽きる。もちろん、他の楽曲も平均点を超えているし、アルバムとしてのまとまりもいい。特にソフトでメロウなバラード群はどれも聴き心地のいい佳曲ばかりだし、所々で顔を出すアップテンポのナンバーはいい感じで、アルバムのアクセントとなっている。それでも、鉄板「サムワン Someone」は他の追随を許さない。無敵だ。本作の中でも別格と言っていいくらい、夜空の一等星のように、明るく光り輝いている。
過大評価なのかもしれないが、親元のグループであるデバージの「I Like It」と「All This Love」、それに佳曲「時のささやき Time Will Reveal」のいいとこ取りをしているようなミディアム・フローの名曲だ。スムーズな転調のスラロームの心地よさは、スティービー・ワンダーの「今はひとりぼっち Summer Soft」や「愛を贈れば Send One Your Love」を想わせる。甘い香り漂う夜の静寂が似合いそうだ。同じテイストとしては、あくまでも個人的な好みだが、ジョージ・ベンソンの「僕の愛を君に I Just Wanna Hang Around You」や、ギャリー・グレンの「Do You Have To Me」、ボビー・コールドウェルの「Don’t Lead Me On」辺りに近いものを感じる。
稀に、日本編集のAC系コンピレーション盤にさり気に取り上げられていたりするのだが、この曲が入るだけで選集(企画盤)の充実度は格段に上がる。まさに選者のセンスの良さを見せつけることができる必殺アイテムだ。
0
|
|
|
値段が…、高い。
円安と海外盤の価格高騰に引っ張られているのだろうが、1枚もののCDが”国内流通仕様” 盤で4千円超えというのは異常だ。もちろん、レアな音源も取り上げられているので、それなりの希少価値は認めるが、高田みち子ふうのジャケットアーティスティック・インプレッションを加点したとしても、この価格設定は野心的過ぎないか? "国内流通…って、日本語表記の帯とコメントが付くだけでしょ? SOLIDさん!"
ということで、本盤についての文句はここまで。
収録曲のラインナップは”松”クラスなのだろうが、監修者のボブ・スタンリー氏が何者なのか知らないし、肝心の”音”を聴いていないので、手放しで五つ星は付けられない。拙速ではあるが、自分にとって生活必需品であるCDの価格が青天井化していくことに抗う意味でも星は3つに止めたい。この値段なら”洋楽隠れ名盤”シリーズなら3枚は買える。正直、やってられない。
もしも、年明けの落ち着いた頃に、安定した精神状態で聴いてみて、想像以上だったら(あるいは4千円に見合うと実感できたら)コメントを書き換えるし、星の数を増やしたいと思っている。
1
|
|
|
2 CD SETのうち、『Night Owl』についてレビューする。
ミステリアスな「霧のベーカー街(ストリート)」の成功に牽引されて大ヒットした『City To City』から時間を置かずにリリースされた本作は、いい意味で前作の流れを引き継ぐ、K点近くまで飛距離を伸ばした良盤だ。フェアウェイの芝は良く手入れされているし、リスナーを悩ませる意地悪なバンカーもない。
同じような大ヒット作の後続盤としては、ボズ・スキャッグスの『ダウン・トゥー・レフト』やビリー・ジョエルの『ニューヨーク52番街』といった前作とは違う切り口で新境地を切り開いたのもあれば、スティーヴ・ミラー・バンドの『ペガサスの祈り』やスティーヴ・ウィンウッドの『トーキング・バック・トゥ・ザ・ナイト』のように前作のいいとこ取りで飛躍を試みた”続編”もある。本作は後者に近い。
個人的には、ジェリー・ラファティーの歌声にハマる。それに加えて、本作には聴き込むごとにクセになる中毒性の高い楽曲がいくつかある。オープニングの「Days Gone Down」が代表格だ。タイトル曲の「Night Owl」や「Get It Right Next Time」辺りも同じく味わい深いのだが、「Days Gone Down」はその魅力に取り憑かれてしまうと簡単には抜け出せない”竜宮城音楽”的な魔力を秘めている。アル・ステュアートの「ラジオを聴いて」のように、緩くて心地よい時間を届けてくれる。ついついリピートしてしまうから、いい意味で厄介だ。どこまでも続くフラットで真っ直ぐなハイウェイを定速走行しているみたいで、余計なことを考えずにハンドルを握っていればそれでいい。日当たりは良好だし、視界も開けている。何の心配もいらない。
アルバム自体が前作と比べて控えめである分、存在感に秀でた前作との抱き合わせでセット販売されたのだが、経年により、とっくに入手困難となってしまっている。忘れた頃に海外復刻盤として高額販売される前に、”洋楽隠れ名盤”シリーズでの”発掘!”していただきたいものだ。
0
|
|
|
穏やかに始まる珠玉の「有名な神話」から完成度の高い良質のハーモニー・ポップ全開なのだが、単に爽やかで心地よいソフト・ロック系サウンドとはひと味違い、一つひとつの楽曲が持つエネルギー(つまりは”歌力”)が強くて、どれも天然果汁100%のフルーツ・ジュースのように新鮮で味が濃い。
音作りも、例えば「ザ・コンティネンタル」などは、カンガルー日和のぽかぽか陽気に包まれたパノラマ・ソングなのだが、聴き進んでいくと、ドリーミーなコーラス&ハーモニーに欧風の旋律を奏でるブラスが絡むなど、スパイスを効かせた細かいアレンジが奏功していたりする。
ハイライトの「ザ・ジェット・ソング」は、思いっきりビートでジャンプしながら大空へと飛翔するのだが、途中サイケに時空を超えたかと思うと一瞬でトリップから戻ってきたりして、終盤には転調を繰り返しながら成層圏まで高度を上げていく、といった、練りに練ったユニークな楽曲に仕上げられている。
アルバムの後半にかけても楽曲のクオリティは落ちることがない。むしろその熟度は上がっているし、気づいたらボーナス・トラックも含めて、あっという間の14曲、充実した48分間が過ぎている、といった感じだ。
思えば、1960年代は男女混声のハーモニー・ポップ系グループが全盛期だった。スモール・サークル・オブ・フレンズを筆頭に、ソルト・ウォーター・タフィーやエターニティーズ・チルドレンなど、男女という異なるオクターブのケミストリーが暖かい春の陽射しのようにソフトでブライトなポップスを届けてくれた。本作がワン・アンド・オンリー盤の”ザ・グループ”も、そんなソフト・ロック史の記憶と記録に留めておきたい”輝く星座”の一つであることには違いない。
1
|
|
|
個人的には『MIMI』以来、久しぶりのCD購入になるが、本作は、往年のグイグイと圧してくる”力強さ”は影を潜め、ずい分と落ち着いた感じの秀曲が並ぶアルバムといった印象だ。
オープニングの「MI」はテイラー・スウィフトの「the 1」(by『フォークロア』)のような”はじまり”の雰囲気を持つ。続く「PLAY THIS SONG」の入りなどはスマートなFM番組のジングルを聴いているみたいで心和む。以降、バラードの熱量はほどよく抑えられ、ビターな楽曲の矛は尖り過ぎず、いい意味で軽いし、やさしい。
カヴァー曲の「MY LOVE」もオリジナルに負けていない。あまりにもベタな選曲なのだが、原曲が描く美しい夕映えの情景をそのままマライア色に染め直している。これまでも、二ルソン、アリシア・キーズ、ジャーニー…と、鉄板バラードを自分ぴったりの衣装に仕立て直し、披露してきた。そのセンスとフィット感は、カーペンターズよりもマイケル・ボルトンのリフォームに近いものを感じる。失敗は一つもない。
収録曲にはアルバムを引き締めるR&B寄りのヒップでホップしているナンバーもあるのだが、全体の趨勢として、ライトでメロウなソフト・バラードが主導権を握っている。
どの楽曲も一口サイズのミニ・チョコレートのように、アルバムというパッケージの中でコンパクトに詰め合わされている。特別なラッピングは要らない。モノクロームのポートレートで十分だ。短尺集なのに物足りなさを感じないのは、一つひとつの楽曲を丁寧に歌い上げているからだと思う。”凄み”もない分、”エグみ”もなく、マイルドでとても聴きやすい。
0
|
|
|
タイトルどおり、ブラジルの香り漂うコンセプト・アルバムだ。ボサ・ノヴァ調のギターに導かれて、ムードたっぷりの甘いラテンの風が心地よく吹き過ぎて行く。
収録曲の半分は既発の自作曲をリメイクしたものだが、例えば、定番の「オン・アンド・オン」などは、もともとオリエンタルな雰囲気を持つ穏やかな曲調ということもあって、リズムの刻み方を少し変えただけで南半球テイストになってしまう。
そんな中、白眉だったのは底抜けに明るく弾けていた「セイヴ・イット・フォー・ア・レイニー・デイ」のボサ・ノヴァ・スタイルだ。原曲ではクラプトンのギターから襷を受けたフィールズ・ライトなマリンバが躍っていた、思いっきり陽気なサウンドスケープだったのだが、こちらの方は賑やかなコパカバーナ・ビーチからアダルトなイパネマ海岸へと舞台を移したみたいに、落ち着いた雰囲気が漂う、癒し系のMORにリニューアルされている。だからといって、オリジナルの持つポップでカジュアルな空気感は損なわれていない。
原曲以上にネジを緩めた(リラックスした)「ビッシュズ・ハイダウェイ(ひとりぼっちの渚)」や、逆に原曲の完成度の高いクワイエットなストリームをスマートにデッサンした「セパレート・ライヴズ」も出色だ。
本作は、原盤のラインナップをよりアコースティックに再演したイングランド・ダン・シールズの『In A Quiet Room (1995)』や、アンプラグドなラウンジを意識したクリストファー・クロスの『カフェ・カーライル・セッションズ』よりも、ラテン系サウンドにフォーカスしたロバート・ラムの『Bossa Project』に近いものを感じる。隠れた、いや、隠れてはいないけど、名盤だ。
0
|
|
|
邦題のように”長い夜”が似合う良盤だ。ジャケットは色調もスナップ・ショットもポップだが、中身はそこまで弾けていない。コントラストの強い新奇でユニークなアート・ワークがテクノポップな印象を与えるとしたら、本作の評価にプラスになっているとは言い難い。
タイトルに“night”というワードが入る楽曲が過半を占めている。名実ともに”夜”をテーマにしたアルバムだ。前半はメロディアスでハードなナンバーも織り交ぜながら真夜中を突っ走るが、中盤から終盤にかけては少しずつ夜が深みを増していくように、しっとりとしたバラードがその領域を拡げていく。原盤のタイトルはアーティスト名だが、個人的には3曲目の「ハーフ・ムーン」がアルバムの主題曲だと受け止めている。なぜなら、少し線は細いが、この楽曲の持つシルクのような淡い銀色の月明かりが、アルバム全体に漂う”夜”の静寂をやさしく照らしているからだ。
ハイライトは中軸を任された「翳りゆく夜」だろう。後の「悲しみにさよなら」もそうだが、ポートノイの真骨頂と言っていい独特の節回しがタペストリーのように紡がれていて、穏やかなのに洗煉された旋律が心に刺さる。最後を飾る「おやすみ SAY GOODNIGHT」も、甘美なポートノイ節が冴える。静かに幕を下ろすミュージカルのラスト・ソングのような佳曲だ。余韻として、オルゴールのような音色が夢の国に誘うかのように短く添えられている。
本作は、クリス・モンタンの『エニー・ミニッツ・ナウ』やゲイリー・ベンソンの『ムーンライト・ウォーキング』と並ぶ、秋の夜長に聴いていたい、ハートフルなアルバムだ。
0
|
|
|
“何を今さら…”と叱責されそうだが、オリジナルの収録曲数以上のボーナス・トラックとそのインデックスに釣られて買ってしまった。選に漏れたレアな録音もあって、デモにしては完成度が高いし、楽曲のクオリティも上々だ。1枚モノのCDが輸入盤でも3千円超えが当たり前の時代にあっては、むしろお買い得と言うべきだろう。バーニー・グランドマンもマイケル・グレイブスも知らないが、今回のマスタリングには並々ならぬ力が注がれているのだろう。きっと。
実は、本アルバムに関してはあまりいい印象を持っていない。巷で騒がれるほど”傑作”とは思えないのだ。理由の一つに、グラミー賞の主要4部門を独占したという快挙が引っかかっていて、当時も”過大評価だ”と思っていた。オープニングの「セイ・ユール・ビー・マイン」もフリートウッド・マックをコンテンポラリーに温め直しただけのようにも聴こえたし、安易にシングル・カットしてしまうところもいただけなかった。その一方で、スリリングに疾走する「愛はまぼろし」や、オール・ライトな「もう二度と」は癖になるくらい大好きだったりもする。要は”天邪鬼”なのだろう。
このアルバムの個人的な評価を左右するのは、最終コーナーを回った辺りの「セイリング」と「ジゴロの芸人」の2大巨頭だと思っている。最高賞に輝いた「セイリング」が凡庸に聴こえるようではクリストファー・クロスの音楽に賛辞を贈ることはできないし、「ジゴロの芸人」から脱力系の”第三世界の男”をイメ―してしまうようではアルバムの奥深さを語ることはできないのだろう。”禅”という世界観を今一つ理解できないでいる自分にとっては、未だ”南から来た男”の正体を掴みきれずにいる。同じところを回っている、というか、回らされている。裏返せば、まだまだ開拓の余地のあるアルバムだ、と言うこともできる。
このようにして、自らの”フラミンゴ・キッド”を見つけ出す旅は続いていくのだろう。
0
|
|
|
微妙だ。
“拡張版”って何?、から始まる。”新たなミックス”ってどういうこと?、時代は”リマスター”から”リミックス”に変わっていくのか?、オリジナル・レコーディングの再現性は保たれているのだろうか?、ところで”スティーヴン・ウィルソン”って一体誰?…。謎は深まるばかりだ。
今回の復刻(再発)は自分にとってあまりにも突然で、正直、混乱している。ターゲットが『ブラック・アンド・ブルー』というのも微妙だし、しかも豪華版のリリースが錯綜する”魔の11月”発売というのも微妙だ。それに、そもそも本作の発売50周年は来年ではないのか!? ストーンズには”そんなの関係ねぇ”のか?
本作も70年代にリリースされたデラックス仕様セットの仲間入りとなるが、これで『山羊の頭のスープ』と『イッツ・オンリー・…』のコマーシャルで軟派なアルバムは、山陽新幹線の西明石や姫路のようにスルーされることとなってしまった。何とも、微妙だ。
さて、青黒のガンバ大阪のサポーターとしては本復刻盤を買わないわけにはいかない。狙い目は懐へのダメージの少ない4,400円のCD2枚組なのだが、年末にかけての相次ぐ大物盤の集中リリースに手も足も出ない。
まあ待て、落ち着け! まずは静観しよう。”完全生産限定盤”の表記はされていないし、ストーンズは逃げはしないのだから。
6
|
|
|
1年前に『A面…』が発売された時に気づくべきだったのだが、老害のせいで頭が固くなり、"続編がリリースされるかも…"、といった発想が全く浮かばなかった。ありがたい企画なのだが、年末にかけて大御所の高額な選集盤が集中発売される中、4千円超えの出費は正直、イタい。3枚組で4.180円(税込み)というのは”良心的”なのだが、『A面…』の時以上に”これってCD2枚に収まらないか?”って疑いたくなる。ただし、昨今のCD価格の高騰の流れから推察すれば、2枚組にまとめたとしても、3,960円(税込み)というのがオチなのかもしれない。
さて、内容についてはルール設定が明確なので文句の言いようがない。シングルCD時代以降はオケ版もボーナス収録されているので、複数曲を拾うべきとの意見もあるだろうが、”B面”という縛りで1曲に絞ることとするならば、必要十分なラインナップではないかと思う。
個人的なハイライトは、ようやくフル・アルバムに取り上げられた「表参道」だ。この1曲だけでも本盤を買う価値はある。そのくらい素晴らしい中期ビートルズのオマージュが詰め込まれている。原曲は「オー・シャンゼリゼ」で、ベースは「愛こそはすべて」なのだが、”B面”収録だった「…ウォルラス」を筆頭に、「ストロベリー・フィールズ…」&「ペニー・レーン」などのサウンド・コラージュが随所に散りばめられていて、ビートルズ信者に”けしからん!”と言わせないくらい完璧なアンソロジーを創り上げている。原宿の表参道を舞台に、パリの雰囲気を感じながら、思いっきりビートルズに浸ることができる、まさにワールドワイドな至福の時間がここにある。
2
|
|
|
“もうこのくらいで勘弁してくれよ!”と言いたくなるのだが、ユニバーサルやキャピトル・レコードの社員のボーナスを出すためなのか、年末を控えて信者へのお布施の通知が届いてしまった。何セット目のベスト盤なのだろうか(?)、手を変え品を変え、本作まで捻りだしてしまうとは…。迷ってはいけないのかもしれない。
収録内容を見ると、ヒット曲を主軸にアルバム・オンリーも無難な楽曲がセレクトされている。”WINGS”と銘打つからには「メアリーの子羊」や「アイルランドに平和を」辺りも拾ってほしかったが、大人の事情もあるのだろう。リーダー以外のメンバーの影も薄い。
個人的には、ちょっと前の紙ジャケット仕様盤の再リリースで『ロンドン・タウン』と『バック・トゥ・ジ・エッグ』が飛ばされた悔しさもあって、「たそがれのロンドン・タウン」や「ゲティング・クローサー」の”2022 Remaster”表記に無条件で降伏させられてしまった。それ以外に本作を購入する大義はない。あれが入っていて、これが漏れている、といった不平もない。熱量は下がってしまっているが、購買意欲を無くしてはいない。棚にある聴かなくなった中古盤を有償処分すればいい。CDが売れないご時世に、自分のような老いぼれのためにCDを企画・製造・販売してくれるレコード会社の社員の懐を潤すのであれば、それも本望だ…、と自分に言い聞かせることにした。
17
|
|
|
『ホンキー・シャトウ』以降、2枚飛ばしで本作に辿り着いてしまった“50周年記念盤”だが、稀代の名作『黄昏のレンガ路』は30年目にもセット盤がリリースされていたし、撃たれそうになったピアニストや囚われのカリブ・ランチには申し訳ないが、順当な中抜きリリースなのかもしれない。今にして思えば1975年は豊作の年だった。
本作は、歓びの歌をつくるエルトン・ジョンとバーニー・トーピンの”ライティング”コンビの成功までの足跡が音盤のタペストリーに綴られている。LPレコードに添えられたブックレットもファンタスティックなイラスト・ジャケット同様、豪華版だったし、収録されている長短10篇の楽曲はどれも良質で、唯一無二のエルトン節が冴え渡っている。タイトル曲のドラマチックな展開も大河ドラマを観ているようだし、「バベルの塔」の静と動、陰と陽のコントラストも、「汽笛が鳴ったらおしえて」のスリリングに起伏するユニークな転調も、エルトンにしか書くことはできないマスター・ピースだ。
圧巻は「僕の瞳に…」を凌ぐ、厳粛で壮大なバラード「僕を救ったプリマドンナ」なのだが、当時、中学生だった自分は”怠いな~”などと罰当たりな感想を抱いていた。だが、晩秋の中年期を過ぎた頃からこの曲の魅力に惹き込まれ、終には虜になるほど浸かってしまった。バラードつながりでいえば、ラストの「ベールの中の遠い思い出」などは、名探偵ポアロの最後の事件を想わせる、まさに”ある男の終曲”だ。
CDには(以前からそうだが)、K点超え連発のオリジナル・アルバム収録曲に加え、当時のシングル・リリースのみの佳曲が拾われている。中でも、長尺ながら癖になる(半ば中毒性のある)「フィラデルフィア・フリーダム」は、聴いているだけで元気を充填してくれるエナジー・ドリンクだ。
0
|
|
|
今回の4枚の企画盤の中で1枚を選ぶとしたら、個人的には本作になる。”一択”と言ってもいい。
ユーミンにはシングル曲のみという条件でオーダーしていたのだろう。B面も含めてシングル・リリース向けの佳曲揃いだ。こうして並べてみても、ベスト・アルバムからの定番曲セレクションといった感じで、特別な目新しさはない。結局、企画のルールに従うと、こうなってしまうのだろう。唯一、価格に関して不満はあるが、今さらSony Music Directに愚痴を言っても始まらない。CDを聴くことしか楽しみのない一般市民は素直に受け入れるしかない。
さて、ユーミンの作品はどれも良質で瑞々しい。松本 隆さんのピュアで彩り豊かな歌詞に、自身の音域を超えた野心的なメロディが乗せられている。”野心的”というのは尋常な表現ではないが、ユーミンは(歌詞の世界観も含めて)自分では歌えない(”歌うことができない”、と言うと失礼なのだが…)楽曲を、松田聖子という天才ヴォーカリストに託したのではないだろうか。もう一人のユーミンがそこにいる。松田聖子というフィルターを通してユーミンが透けて見える。時にはピッコロトランペットのように高音域を滑空し、時にはクロージェーヌ・ロンジェのようにスモーキーなウィスパー・ヴォイスで語りかける…、そんなミラクルな歌声を松田聖子は持っているのだ。「蒼いフォトグラフ」なんて、相当ハードルを上げているのに、松田聖子は難なく飛び越えている。結果、ユーミンの"野心的"なチャレンジは、松田聖子の一つの金字塔を打ち立てたのだ。
余談ではあるが、ユーミン先行のカヴァー曲「恋人はサンタクロース」については、ユーミン自身が自分のために紡いだ渾身のクリスマス・ソングだけあって、個人的には『SURF&SNOW』収録のユーミン版に軍配を上げたい。
5
|
|
|
CDの帯には”クレイグ・ランク待望の第2弾!!”と記してあって、ジャケットに登場するイラストの赤い車は、第1弾とは違って精巧に描かれている。アルバムの内容やアーティストの情報は封入されているライナー・ノーツに金澤寿和氏が詳細かつ丁寧な解説を書かれているので、そちらをご参照いただきたい。
アルバム収録曲は、冒頭の新タイトル曲からライトで軽快なポップ・ソングが並ぶ。初夏のそよ風のように心地よいサウンドを聴いていると、なんだか幸せな気持ちになる。例えるなら、ブルース・ヒバードの「You’re So Good To Me」のような穏やかで懐かし香りのする、いい意味での”脱力系ポップス”といった感じのラインナップだ。旧タイトル曲の「True Love」など、グレン・フライが届けてくれた同名の姉妹曲のようにも聴こえる。
全体的に甘味がやや効き過ぎている感じもするが、決して嫌な"甘さ"ではない。気分を落ち着かさせてくれる、身体が求める"甘さ"だ。リズミカルだし、耳にやさしいし、どの曲を聴いても癒やされる。中でも自分にとってのフラッグシップは「You're So Beautiful」だ。カントリー・ポップスの系譜も感じるが、粋なハーモニカの音色と洒落たコーラスが絡むアレンジは都会的で洗練されている。完璧だ。
第2弾の本作には、大人の事情として(?)第1弾のレガシーであった「Baby Blue」と「You're All That I Need」、「You Are My Inspiration」の3曲が同じテイクで再収録されている。サンドイッチされている渾身かつ珠玉のバラード「One Love」が、第2弾である本作の締めのナンバーではなかったのかと推察する。
個人的なサプライズは「Time For Christmas」で、ハートウォーム系のクリスマス・ソング・コレクターにとっては嬉しいボーナス収録だ。この後には、どういうわけか季節が反転して”夏歌”が3曲続く。容赦なく降り注ぐ眩しい夏の陽射し、コバルト・ブルーの海に包まれた南の島、そして終わらない夏の王国で過ごすロング・ヴァケーション…。ファースト・クラスでビーチ・ベイビーを探しに行きたいくらいだ。
0
|
|
|
”深夜”をイメージしたシンプルな版画絵のようなイラスト画が描かれているジャケットなので、もっとムーディーで大人しいアルバムかと思っていたら、結構ビートの効いた華やかな楽曲が多いのに驚いた。
オープニングの「It's Still You」をSteely Danっぽいと言うと”ちょっと言い過ぎかなぁ~?”かもしれないが、”いいと思います!”と力強く肯定してほしい気もするくらいの雰囲気を持っている佳曲だ。いきなり振れ幅の広さを披露してくれている。
「Night Room」のホーン隊のキレもいいし、Boz Scaggsの「Lowdown」をサンプリングしたような「Love On A Summer Night」のスムーズなジャズの香のするトロンボーンのソロも秀逸だ。言われるように、確かにジョージ・ベンソンの「Love X Love」のテイストがする。
タイトル曲は王道を征くダンサブルなディスコ・ナンバーで、70年代半ばのシルヴァーズのようなご機嫌な匂いがプンプンする。途中で割って入るウィスパーな語りも”スリラー”ふうの”ソウル・ドラキュラ”を想わせる。先の「Night Room」といい、後の「Torn In Two」といい、楽曲のハードルを下げてくれているので、耳馴染みがいいし、とても聴きやすい。
スローな3曲はどれもタイプが違っていて、一つとして同じものはない。A面でしっとりとしたソロを聴かせておいて、B面では渾身のデュオ・バラードで黙らせておいて、最後は夜の静寂に降りてきた女神が歌うゴスペルでクワイエットに締めている。
0
|
|
|
旧友(盟友)Paul Williamsの『We've Only Just Begun … Songbook』が発売された際、アルバムのレビューで(個人的は”決定版”だと思っている)Roger Nicholsとのコラボ盤『Songbook』に触れたことがある。本作もPaul Williams単独の”歌集”同様、後続の再編集盤なのだが、CD2枚に拡張収録されたことで、ほぼ完璧なラインナップとなっている。
“欲を言えば、この楽曲は〇△□のレコードの方が…”といった、半ばリスナー側の我がままは聞こえてきそうだが、アルバムを通して聴いてみると、R・ニコルス色がしっかりと出ているし、楽曲のトーンが揃えられているので、イージーにリスニングできる”歌集”として楽しめる。むしろ、アート・ガーファンクルの「青春の旅路」などは”超定番”的なオーラがあって、少し浮いた感じがしないでもない。
ちなみに、個人的に大好きな「The Drifter」は、オリジナルのThe Small Circle Of Friends版の演奏を忠実にトレースしたレコードが取り上げられていた。
余談(半ば文句)だが、本企画盤の発売元はSony Music Japan Internationalで、CD2枚組で2,860円(税込み)という良心的な価格設定で新譜発売されている。一方、1991年リリースの谷村有美のミニ・アルムの再編CD盤は1枚モノで3,850円(税込み)だ。発売元はSony Music Directとなっている。同じ系列会社で、和洋の違いはあるが、後者は新譜CDイコール3,500円(税抜き)の”壁”を破る先駆者としての使命感に燃えているのだろう。CDが売れない時代における会社のベクトル(あるいはアプローチ)の違いが鮮明に表れている。
0
|
|
|
本作は選曲が渋い。渋すぎる、と言ってもいい。だが、この渋さこそが、このライヴの厳粛で凜とした空気感のようなものを伝えている。派手なヒット曲はなく、その代わりにアルバムの中ではあまり陽の当たらない地味な楽曲が多いのだが、それでも、いや、だからこそ聴衆はエルトン・ジョンの演奏に集中している。
いくつかの楽曲では、共演するレイ・クーパーのさり気なく要所を締める効果的な打楽器の音色が、演奏のクオリティを格段に高めている。特に「アイドル」と、続く「さすらいの弾丸(ロバート・フォードの拳銃) 」で聴かせる鉄琴の伴奏は素晴らしい。
1977年といえば、エルトン・ジョンにとって揚揚と吹いていた順風が止み、次の風を待っていた時機だ。決して”暗黒”ではなかったが、"飛ぶ鳥を落としていた"時代は終わっていた。しかし、ここでのパフォーマンスにそのような”翳り”は一切感じられない。むしろ瑞々しいとさえ思えるくらい、歌声は活き活きしている。
もともとエルトン・ジョンの楽曲にはピアノだけで十分聴かせる楽曲が多いのだから、このようなアコースティック・オンリーのピュアなライヴが成立することは容易に理解できるのだが、静粛な会場でのこうしたライヴ・パフォーマンスがアーカイブとして残されていたことには感謝したい。激しい曲はバンドを引き連れた大舞台で激しく演奏すればいい。「土曜の夜は僕の生きがい」を大人しく歌っても、”あばずれさん”は帰って来ないのだから。
個人的には、当時の近作であり大好きなアルバムでもある『蒼い肖像』から「かごの小鳥(エディット・ピアフに捧げる歌)」や「アイドル」という隠れた名曲が取り上げられ、収録されていることが嬉しい。
本作を聴いていると、KANのワンマン・ライヴであった“弾き語りばったり”を思い出してしまう。KANは独りでピアノと向き合って自身の歌う姿からは、シンプルに“歌を聴かせたい”という想いが伝わってきた。余計なことだが、KANはビリー・ジョエルを敬愛していたのだが、残念ながらエルトン・ジョンとは距離を置いていたみたいだ。
1
|
|
|
本作の商品説明には佐藤 博 自身のコメントも含めて実に丁寧に解説されているので、それ以上、特に何も言うことはない。
アルバム自体の印象としては、全体的にジャケット写真のような薄紫色の淡いトーンに包まれていて、タイトルにあるような実験的なニュアンスも感じてしまう。次作以降、ポップで親しみやすいサウンドへと傾斜していく過渡期的なアルバム、といったところだろうか。本作でのビートルズ・カヴァーはド直球の「抱きしめたい」が取り上げられている。
ひとつだけ、個人的にお気に入りの楽曲について触れておきたい。それは、アルバムのラストを飾る「宇宙のエトランゼ」だ。本アルバムで唯一の日本語タイトルの楽曲で、スマートなアルバムの"締め"に相応しい、緩やかにして壮大なスケール感を持つパノラマ・バラードだ。時刻は、”深夜 -midnight-”というよりも日が暮れて一番星が瞬きだす”宵 -evening-”といった感じがする。仕事帰りに通勤車中でこの曲を聴いていると、疲れた心と身体が自然に癒される。そのまま宇宙の彼方へと旅立てそうだ。
不謹慎だが、この曲だけを切り取って、安部恭弘の「CLOSE YOUR EYES」や大貫妙子の「あこがれ」、大江千里の「コンチェルト」や杏里の「ALL OF YOU」、風(大久保一久)の「あとがき」やユーミンの「丘の上の光」といった、夜の入り口の時間に聴いていたい楽曲をミックスしたコンピレーションに使っていた。もちろん、ラストを飾るナンバーとして。
0
|
|
|
1984年リリースの2015年再発売だが、リマスターが施された紙ジャケット仕様で税込み2,750円というのは、この時代、破格の復刻盤CDと言っていい。本作でのビートルズ・カヴァーは癖のある「EIGHT DAYS A WEEK」と「I FEEL FINE」で、お得意のインスト曲も織り交ぜての”粘っこいアルバム”といった印象だ。
だが、ここでのレビューは本作から外れて、翌85年にコンピレーション盤として発売された『THIS BOY』に触れたい。本作からもウキウキ系の「LOVE IS HAPPENING」とミディアム・フローの快作「ALWAYS」、それにご機嫌なファンキー・サウンドに全面改装された「SWEET INSPIRATION」が取り上げられているが、それらに加えて、当時、ジャン●ン@コ●ギ産業のCMで使われ、シングル盤のみでリリースされていた「サン・グロウ」や「アンジェリーナ」といったレアで貴重な音源が収められているのだ。これら2曲は”夏”の定番曲として、山下達郎や角松敏生などとの相性が抜群だったので、自分も邦楽の”夏モノ”を集めたカセット・テープにミックス録音して楽しんでいた。
手元に当時のCDはあるのだが、音量(音圧)が低めなので、既にリマスター復刻された本作などのオリジナル・アルバムのスピンオフとして、『THIS BOY』の高音質化での再発を強く望んでいるのだが、昨今の中古盤市場での高騰ぶりを見ると、復刻の見込みは薄いのかもしれない。それならば、切り口を変えて、”ジャン●ンCMシリーズの編集盤”というのでも構わないので、金熊印でも付けた音源集をリリースしてほしいのだが…、たぶん、そちらの方がもっとハードルが高そうな気もする。
0
|
|
|
本書の概要と書評は”商品説明”に記載されているとおりであり、特に何も言うことはない。
アルバム『14番目の月』のジャケットはギフト包装のようなデザインが施されていて、嫁いで行くユーミンから祝福するファンへの贈り物のような意味が込められているようにも思える。
そんな愛すべきアルバムにフォーカスした本書だが、一つだけ、気になった点がある。決して”間違い”とかではなく、あくまでも自分の見解との相違なので、余計なことなのかもしれないし、本書の解釈に賛同される方も多いとは思うのだが…。
それは本書58ページにマトリクスとして掲載されていた収録曲の(歌われている)”季節(観)”の記載だ。9曲目の「グッド・ラック・アンド・グッドバイ」が、”(おそらく夏)”と標記されている。理由は、”雨”(日本で梅雨は夏…)ということなのだが、自分には”…夏”というのが引っ掛かる。
ちなみに、この曲の後半の歌詞は、次のように綴られている。
”ふりかえる大通り あのひとに見えるように
混んだバスの くもった窓に書く
大きく Good luck and Good bye”
梅雨時でも外気温によっては窓ガラスが曇ることはあるのだろうが、自分の中で浮かんでくるのは”冬”、それもクリスマス・シーズンの情景だ。主人公の二人や雑踏を急ぐ人たちもコートを着ているし、降りだした雨も冷たい。”別々の恋人が待つ場所へと…ゆく”時刻には既に日が暮れていて、街には灯りがともっている。
この曲の前後に収録されている楽曲が”夏”の曲なので、この曲も”夏”のレッテルが貼られていると考えるべきなのかも知れないが、ユーミンの楽曲は一つひとつが短編小説のように独立しているので、単純に同じ”季節”の楽曲が一括りにされているとも思えない。
以上はどこまでも自身の想い込みであって、失当かもしれない。もしかしたら、ゆったりとした仄かな温かさを持つ曲調に惑わされているだけなのかもしれない。
真実はユーミンのみが知っている。
0
|
|
|
本作は”オリジナル音源で20曲入り”というお買い得な企画盤で、バンバンやハイ・ファイ・セット(いずれも3曲ずつ収録)のイメージが強過ぎたためにずっと”購入候補リスト”に眠らせていたのだが、最近になってアグネス・チャンの歌う「白いくつ下は似合わない」がどうしても聴きたくなって、他所で裏技購入してしまった。
ほぼユーミン色に染められた楽曲ばかりだが、中には提供先のアーティストに寄せた(と思われる)ものもあったりする。そんな中、遅まきながらこのアルバムで知った石川セリの2曲には完全に降伏させられた。石川セリといえばフワ・WOWなイメージとは結びつかない目力の鋭いポートレートに後ずさりしてしまうのだが、「霧の桟橋」みたいなソフトで穏やかな楽曲をトレースできるのならオリジナル・アルバムの領域に足を踏み入れてもいいとさえ思える。
太田裕美の「青い傘」はセンチメンタルな"雨だれ"を受け止めるような、しっかりとした存在感がある。太田裕美にはもう一曲、作曲のみ(作詞は松本 隆)を担当した「袋小路」という秀作があるが、本企画盤が”作詞作曲”を基本としていることから外されたのだろう。こちらの方もマイナー・コードで紡いだユーミン節全開のマスターピースだ。
この他にもユーミン・ブランドの”隠れた名曲”が散りばめられていて、夏の日の恋を思わせる「恋人と来ないで」byパイシスやバーバンクふうの「二人は片想い」byポニー・テールといった耳に馴染みのあるメロディも心地良かったりするなど、まさに"贈り物"と言っていい充実した内容の楽曲集だ。
個人的には、松島トモ子が歌う「過ぎたことだから」が予想外の大きな収穫だった。
0
|
|
|
またしてもBIG PINKが大仕事をやってくれた。半ば諦めていた希少かつ貴重なアルバムを復刻したのだから”偉業”と言っていい。アンテナを張っていると、時々このようなビッグ・ニュースにめぐり逢える。
BIG PINKは海外レーベルということで、タワーレコード・オンラインでは輸入盤も取り扱かわれていた。最近は円高の影響もあって輸入盤よりもVIVID SOUNDの国内仕様盤の方が廉価なのだが、再会を急ぎたければ”在庫わずか”な輸入盤を入手する選択肢もある。
さて、本作は1999年に日本盤がCD発売されているが、オリジナルのリリースは1980年に遡る。いわゆる”AOR”が成熟していた時代の隠れた名盤として、マロングラッセのような甘美な色調のジャッケトの本作には"トワイライト・アワーズ"という邦題が付けられていた。<1999年盤のオビには欠いてある>
その名のとおり、アルバム全体にマイルドなアダルト・コンテンポラリーの”あまく危険な香り”が漂っているのだが、内容に関しては約2年前に書き込んだレビューのとおりなので、一部を修正して下記のとおり引用する。
オープニングの「イズ・ディス・ザ・ウェイ・オブ・ラヴ」は、切ないハーモニカで始まるミディアム・フローの佳曲だ。ローレン・ウッドをパートナーに選んだことも正解だし、2人のソフトでナチュラルなデュエットが聴く者に”安らぎ”と”癒し”を与えてくれる。シルクのように滑らかなメロディ、キーボード主体のメロウで控え目なアレンジ、波に流されないように舵をとる小気味よいドラミング…。完璧だ。
続く「エニー・ミニッツ・ナウ」も負けてはいない。甘さを抑えた良質のビター・チョコレートのような”ほろ苦い”失恋ソングだ。悲しみに心折られながらも、それを乗り越えようとする葛藤が唄われていて(個人的にはそう感じている)、切なくも前を向く姿が胸を打つ。ライトでメロウなポップス好きの琴線に触れる1曲だ。
その他の楽曲も聴き心地の良い秀作が揃っていて、棄て曲は一切ない。アルバム全体が、やさしく穏やかな”秋色”に彩られていて、月明かりに包まれた秋の夜長に聴いていたい心和ませる1枚だ。
1
|
|
|
どこかで”50周年記念盤”というアナウンスを聞いたが、金色ジャケットを含めて、ここまでダイナミックに改訂(個人的な感想としては"改悪")されると、正直、引いてしまう。これでは何度もリリースされてきた既発の詰め込み式ベスト盤と変わらない。いったい”偉大なる星条旗”というサブ・タイトルを付けられた9作目が存在していたという現実を把握している者はいるだろうか?、と思ってしまう。
エルトン・ジョンの『グレイテスト・ヒッツ』もそうだったが、個人的には余計な(オマケを付ける)ことをしてほしくない。ベスト盤ではあるが、LPレコードを土台とした、アルバムの構成や楽曲の流れを意識して収録曲を厳選し、配置した、ひとつのオリジナル・アルバムとしての体をなしていた、というのに…。
あえて直近のアルバムからは選ぶことをせず、心を鬼にして選から外したヒット曲だってあったし、個性の強い楽曲の橋渡しとして意外な小品を持ってきたりもしていた。そうして”グレイテスト”な”ヒット”曲集が創られたのだ、と思っている。
同じくCDの容量を睨んで目いっぱい拡張されたのがビートルズの赤盤・青盤のリニューアルだが、ここでその話はやめておこう。
本作は、エルトン・ジョンの最初の『GH』同様、完全な年代(リリース)順ではない。頭で2ndアルバムの代表曲「長い夜」をもってきているが、すぐに1stに戻って「いったい現実を…」でクール・ダウンさせて、ラストは同じく1stの「ビギニングス」で延々とリフレインしながら締める、といった原点回帰からの未来志向へとベクトルを向けた"ベスト・オブ・マイ・ラヴ"あるいは"クロコダイル・ロック"的な選曲となっている。2ndの”ぼくらの”シリーズにもスポットを当てながら、サンドイッチされた5thから7thまでのアルバムに収められていた個性的なヒット曲が宝石のように繋げられて輝きを競い合っている。
ジャケットを金色に着色するのはいいから、原盤の”偉大なる星条旗”のコンテンツに戻して復刻ほしいと切に願っている。
2
|
|
|
“値段が高い”とクレーマーのような書き込みをしたので、遠くから、”だったら買うなよ!”とか、”RYUSENKEIだぜ、16曲入りなんだぜ、それくらいの価値がして当然だろ!”とか、”これからは1枚モノのCDは税抜き3,500円が相場なんだよ!よく覚えとけ!”などといった非難の声が聞こえてきそうだ。なのでCDの内容に関係のない書き込みは削除することにした。
改めて、本作だが、これぞ”RYUSENKEI”といったド直球の定番曲を集めているように思う。変化球を1球も放らずに三振が取れるピッチングに徹している。個人的には遊び球も見たかったが、容赦しないところが”RYUSENKEI ブランド”なのだろう。当然、棄て曲などないし、冗長な楽曲も上手い具合にre-edit編集されている。自分の推し曲の「タソガレ」は外されているが、『ILLUSIONS』で楽しめばいい。オリジナル・アルバムごとにグルーピングされているが、繋ぎ目の変化は感じないし、リリース時期に時間差があっても新旧の違いや経年劣化や遜色などは全く認められないので、思い切ってシャッフルしても良かったような気がする。
実をいうと『シティミュージック』を聴いていない(持っていない)ので、今回の”最適な”ベスト盤で「フライデーナイト」と出逢えたのは大きな収穫だった。こちらも継ぎ目”・”のない、滑らかな流線形をしている”グラマー”な”プロフェッション”だ。
0
|
|
|
3人の作品がほぼ等分に収録されているトライアグル盤だが、個人的にはグラハム・ナッシュの抒情的でセンチメタルな4曲に惹かれる。他の2人の楽曲に比べると作品自体は(いい意味でも悪い意味でも)”軽い”のだが、クロスビーとスティルスとの協働と繊細なコーラス・ワークが楽曲に厚みと深みとしっかりとした存在感を与えている。どの曲も抒情的でセンチメンタルで心に沁みる。
傷心と喪失感だけが綴られているような「キャリード・アウェイ」、アル・スチュアートの歴史絵巻を想わせる「大聖堂」、極太のギターとたおやかなハーモニーが調和して潤いのある心地よい空気感を醸し出している「ジャスト・ア・ソング(ビフォー・アイ・ゴー)」…。アルバム全体を覆っている鉛のような雲から降り注ぐのは、やはり「冷たい雨」だった。
それでも最後は、フリートウッド・マックの「アイム・ソ・アフレイド」を想わせるエネルギッシュな「アイ・ギヴ・ユー・ギヴ・ブラインド」が湿っぽさを吹き飛ばして幕を閉じる。いいアルバムだ。
ところで、どうしようもなくマヌケな話を一つ。今回の再発盤のページを見て、アルバム・ジャケットの写真が差し替えられていることに気づいてしまった。間違い探しの”だまし絵”ほどでもないのに、全く気がつかなかったとは…。棚にある77年のLP盤は3人が仲たがいしているように別の方向を向いている。一転、2025年盤では睦まじく談笑しているスナップが使われている。台紙はダークだが、プリントされた写真は明るい。
0
|
|
|
ジュリア・フォーダムを知ったのは、J-WAVEの”繋ぎ”あるいは”隙間”時間を埋めていた番組(なのか?)AZ-WAVEのコンピレーションCD『LOVE NOTES』だった。収録されていたのは、もちろん「Happy Ever After」。
同じシリーズで知ったケヴィン・レトー(もちろん「Another Season」。)はスマートなサンバのリズムに乗せてブラジルの香りが漂っている佳曲だが、こちらの方は骨太でゆったりとしたアフリカのエモーションに支えられた秀曲だ。見えてくるのはサバンナの雄大な草原で、ジュリアの歌声は、大きな深海魚のようにオクターブの低い重厚で濃密な低音域を回遊しながら、時に、巨大な海洋哺乳類が水面から頭を出して呼吸するように、高音域までダイナミックにジャンプする。
当時、勢いに任せて7曲入りの日本編集盤を買ったのだが、最近になってデビュー・アルバムの復刻を知り、未開のジャングルに足を踏み入れてみたくなって、本作を入手した。全体的に80年代後期のシャープで洗煉された”サウンド”をベースとしているが、メロディはシンプルだし、アレンジはそこまでラディカルでもアグレッシヴでもない。ゆったりとしたアフリカのエモーションが沼の底を対流しているし、ジュリアの歌声はその中をダイナミックに回遊している。
ただし、油断していると、「Woman Of The 80’s」のスタイリッシュな”モダン・ガール”のパワフルな一撃にKOされてしまうことになる。
0
|
|
|
“位相幾何学”なるサブタイトルが意味深だが、これまでのシリーズを振り返ればそれほどの特別感はない。”タワーレコード限定”盤ということで、いつものレーベル縛りに比べてレア度は格段に高く、自分にとって未踏の地の産物ばかりがコンピレーションされていて、思いっきりギャンブル購入だったのだが、ベットした分は十分取り戻せたし、それどころか思いもよらない収穫もあっりして、リスク以上のハイ・リターンだったと満足している。
好印象だった”synchronicity”同様、等身大のクールでスマートな楽曲が詰まってる。レゲエふうのトロピカル・テイストだったり、テクノ・ポップっぽい近未来的音楽との融合だったり、アンビエントなアトモスフィアに包まれた脱力系BGMだったり…。多国籍なのに無国籍な共通言語のポップスが心地よく流れている。緩めだが緩々ではないし、薄味だが味がないわけでもない。カジュアルで、オーディナリーで、いい感じでリラックスした楽曲集だ。不思議なくらいスキップすることなく楽しむことができるコンピレーションだと思う。心地良すぎて居眠りしていまわないように、やさしい”刺激”も仕組まれていたりする。
ところで、このような自主・独立系のマイナーな(自分が知らないだけなのだが…)クリエイターの楽曲ばかりを集めた企画盤の発売をよくタワーレコードの幹部は認めたものだと感心するが、社内決裁が下りたのも、クニモンド瀧口氏のお墨付きがあってのことだろうと推察する。それにしても、このようなメジャーではないアーティストの良質のミックス盤を聴いていると、日本の都市系音楽制作者の層の厚さと裾野の広さを実感できて、何となく嬉しくなってしまう。
余談だが、スペーシーに始まるオープニングの「Ameagari no …」の主旋律はユーミンを想わせるし、「さよならサマー」の入りはマリア・マルダーの「真夜中のオアシス」みたいで懐かしい。
0
|
|
|
どう見ても安西水丸といったイラスト・ジャケットに誘われて”収録曲”を眺めていたら、”夏色”&”海もの”鉄板曲「渚にて」のセルフ・カヴァーが入ってるというので、45秒間試聴して、その流れで購入ボタンを押してしまった。
南 佳孝は気障でクールでアヴァンチュリエールな楽曲が合っている、という思い込みがあって、個人的には「Vacances Bleu」や「夏服を着た女たち」「避暑地の出来事」といった夏の匂い(あるいは残り香)のするスローなナンバーを気に入っている。その一方で、深夜のラジオ放送を愛聴していた自分には、電子音のエフェクトで電波の満ち引きが上手く再現されていた「憧れのラジオ・ガール」なども”胸のシンバル”を鳴らしてくれる佳曲だったりする。
本作は、セルフ・カヴァーと書下ろしのスクランブルで構成されているのだが、新旧の楽曲がしっかりと溶け合っていて、一体感のあるアルバムにまとめられている。個人的なスペシャルは、心地よい”気だるさ”の「渚にて」だが、その他の旧譜も地味ながら存在感のある良作がセレクトされている。一方、新作も負けてはいない。鮮度が高い取れたてヌーボなのに、熟成された年代物のワインのような味わい深さがある。
楽曲も見事ならアレンジも見事だし、何よりも南 佳孝のヴォーカルが素晴らしい。ちっとも枯れていないし、それどころか、しっかりと音符を踏みしめながら、艶っぽくも瑞々しい歌声を聴かせてくれる。
少し外れるが、個人的に大好きな映画でバリー・レビンソン監督の『ダイナー』という作品があるのだが、この映画を知ったきっかけが、南 佳孝のアルバム『LAST PICTURE SHOW』だった。1950年代終わりの古き良きアメリカの地方都市ボルチモアが舞台で、少しマニアックな青年たちが繰り広げる些細なエピソードがオムニバスのように紡がれている。レコード・マニアには”あるある”の挿話もあって、結構楽しめるグラフィティ作品だ。
1
|
|
|
いろいろな意見があるので、パッケージのレビューではなく、個人的にお気に入りの3曲について、個人的な感想だけを述べたい。
「レモネードの夏」は、音符の起伏の激しい楽曲の一つなのだが、ちゃんとスピードに乗って、振り切られることなく、また、旗門不通過もなく、軽快にスラロームしてゴールしている。レモンの甘酸っぱさとソーダ水の発泡感はあの夏のフレッシュさのままだし、”今は私も20歳(はたち)…”という歌詞の件も、とても自然に耳に届いてくる。時は流れtが、魔法は解けていない。
「蒼いフォトグラフ」は、音符を追いかけるのに苦戦しているみたいだ。声の調子の悪い日のレコーディングだったのか、最初の一音から音符に届いていない。彼女のキャリアの中でも個人的に一番のお気に入りなので、楽曲に”負けてしまう”というのはちょっと残念ではあるのだが、決して、"セピア色に褪せる日”が来ているわけではない。逆に言えば、それほど原曲の完成度が高かったのだ。ピュアな”青さ”が弾けていたオリジナルへの果敢なチャレンジには素直に拍手を送りたい。
「Pearl-White Eve」は、現在進行形の松田聖子が、等身大の松田聖子として焼き直した、完璧なセルフ・カヴァーだと思う。「蒼い…」とは真逆で、若い頃のナイフのような切れ味鋭いオフェンシヴな歌唱が、いい感じで面取りされて、楽曲にちょうどいい力加減に落ち着いたように感じる。年を重ねたことで誕生した、もう一つの”大人の”スタンダード・ナンバーと言っていい。
3
|
|
|
クリス・レアの「青春のいたずら」の匂いのする(タイトルにも”Fool”が入っている)オープニングを聴いていると、いわゆる久しぶりのカム・バック作にありがちな”イキっている感”が伝わってくるのだが、その後は、スタンダード・ジャズっぽい洒落た演奏でリラックスしてペースを掴むと、気の置けないカジュアルなスタイルに落ち着いてきた。懐かしいリメイクを含むアコースティックで穏やかな楽曲群にどっぷりと浸っていると、自然に心は和んでくる。
特にタイトル曲の「Out Of The Blues」から舞台は変わる。時間があの頃に戻ったような、昔と変わらない、瑞々しいメロディとやさしい歌声が戻ってくる。もう何も言うことはない。
さて、本作の「ふたりのラヴ・ソング」には趣きの異なる2つのバージョンが収められていて、6曲目の演奏はカーペンターズのリメイク版に近い。あえて明るいアレンジにすることで、かえって失恋の傷手が少し癒えた頃の”ほろ苦さ”が感じられる。ボーナスとして添えられたもう一つの方は、アルバム『Hay Mr. Dreamer』収録の原曲に近い。静かに、しっとりと歌い上げられていて、心の傷が癒えていない頃のセンチメンタルな”切なさ”が伝わってくる。原曲のオリジナル版は”サントリー・サウンドマーケット”のAOR特集でクロージングに選曲されていた。リタルダンドから再始動するリフレインが、悲しみからのリトリートを描いているみたいで、癒やされるし、元気をもらえる。
アルバムは「You Can Get Your Love Right Here」で一旦幕を閉じるのだが、ラスト3曲のボーナス曲がアンコールのように添えられている。アート・ガーファンクルのガラス細工のように透き通った歌声が印象的だった「悲しきラグ・ドール」と件の「ふたりのラヴ・ソング」、そして大トリを任されたハートフルな小品「Where Do I Fit In」だ。特に十八番のバラード2曲から襷を受けた「Where Do I …」は、ドナルド・フェイゲンの「雨に歩けば」のように軽快だ。最後の最後は”リスナーを笑顔にさせて終わらせる”、という大役を見事に果たしている。
0
|
|
|
翻訳ソフトでは“セダカの背中”と直訳されている。それがスタンダードな和訳なのかもしれないが、自分としては”セダカの復帰”の方がしっくりくる。棚にある20世紀末リリースのCD盤から四半世紀経っての再発なので、音質向上を期待している。
70年代中頃、NHKの石田 豊さんがやっていた”リクエスト・コーナー”の”水もの(雨や涙を歌った楽曲)特集”では常連だった「雨に微笑みを Laughter In The Rain」が出色だ。個人的な印象だが、東洋ふうの音階に親しみを覚えるし、春先の明るい空から落ちてくるキラキラとした暖かくて優しい雨粒が、ユーモラスな”笑い声”のように聴こえてくるみたいで、何ともコミカルで心躍るハッピーな雨の唄だ。B.J.トーマスの「雨に濡れても」の続編みたいで、爽やかな湿っぽさが心地よい。
本作には他にもキャプテン&テニールの「愛ある限り」や静かな力強さを感じる「The Immigrant」など、秀曲も多いが、次作の『The Hungry Years』にも心に沁みるタイトル曲を始め、スロー・バラード調にリメイクされた「Breaking Up Is Hard To Do」やエルトン・ジョンのLittle Helpで大ヒットした「Bad Blood」など、本作に勝るとも劣らない充実した楽曲集なので、こちらの方も後追いでの再発を期待したい。
0
|
|
|
思いがけないところで、気づかなくてもいいことに気づいてしまった。
自作編集の"1981年洋楽ヒット曲集"を何気なく聴いていて、流れてきた本作音源の「Take It Easy On Me」(邦題「思い出の中に」)の入りのヴォーカルに違和感を覚え、聴き進むにつれて不協和音は拡がり、終には”あの頃聴いたバージョンとは違う”という確信に辿り着いてしまった。直ぐにネットや棚にある別のベスト盤の音源と聴き比べてみたのだが、そうしたら、明らかにヴォーカルが録り直されていた。
ついでに本作のすべての楽曲を聴き返したのだが、結果、違っていたのはこの曲だけだった。ただし、モスキート音が聞こえないほど老化した耳なので、違いがわかったのがこの曲だけだった、のかもしれないが…。
本作はレコード発売された『グレイテスト・ヒッツ』の装丁のまま18曲入りに拡張し、音圧向上が施されたお買い得盤なのだが、「Take It Easy On Me」はオリジナルではない。当時の音源を求めるのなら、他の編集盤(『DEFINITIVE COLLECTION』など)を入手するしかない。決してリメイク・バージョンが劣っているわけではなく、単にリアル・タイム懐古派の独りよがり過ぎないのだが…。
個人的にはカモノハシ・マーク入りの水泳ジャケットを気に入っているので、LP盤とお揃いの12曲入り元祖『グレイテスト・ヒッツ』の復刻を切望する。
0
|
|
|
発売当時、本作に付けられた”Brand”というニュアンスがうまく落とし込めなかった。だからといって、“Taste”でも”Color”でも”Style”でもしっくりとこない。やはり、このふわっとしたセレクションには”銘柄”という”…らしさの括り”の方が相応しいのかもしれない。
商品説明にある”『ひこうき雲』『MISSLIM』『COBALT HOUR』から選曲された1976年発表のベスト・アルバム…”というのは間違っている。本作に車の両輪として収録されている「あの日にかえりたい」と「翳りゆく部屋」はどちらもオリジナル・アルバム未収録だし、一方で件の3枚のアルバムを牽引するエース級の楽曲(たとえば「雨の街を」や「卒業写真」など)は収録されていない。さらに言えば、シングルのA・B面からのセレクションをルールとしているはずなのに「ひこうき雲」は選ばれていない。たぶん、「ひこうき雲」はB面曲でありながら”アルバムを牽引するエース級の楽曲”だからだろう。本作はアルバム未収録の2曲のために企画・編集されたセレクションと言っていい。
ついでに、ビートルズでいえば「ラヴ・ミー・ドゥ」と同格の「返事はいらない」が外されている辺りは、何となくだが、デビュー・シングルの選択を巡ってレコード会社との意見の相違があったようにも邪推する。
※全くの当てずっぽうなので、間違っていたらごめんなさい。
個人的に、本作は、初期の3枚のアルバムとその後のベスト盤が手元にあるので、あえて入手する必要はないと思っていた。ところが最近になって、本作収録の「やさしさに包まれたなら」(カップリングの「魔法の鏡」も)の音源は、オフコースの「こころは気紛れ」同様、シングル・バージョンであることを知ってしまった。実に間抜けだった。この曲は軽快なアルバム・バージョンが”定番”とされているようだが、個人的には、その昔テレビで聴いていたスロウで瑞々しいタッチのシングル・バージョンも、あの頃の穏やかな空気の中で息づいているのだ。
というわけで、半世紀経ってしまったが、あの日の”やさしさ”に包まれたくて、本作を入手して、ついでに、三色刷りのアナログな3D画像ジャケットの立体的な見え方を手元で確かめてみようと思っている。
0
|
|
|
いい意味で”安定飛行”に入っている。予習をせずに買っても外すことはない。
ひとつ前のオリジナル・アルバム『DREAMIN’』と比較すると、あくまでも個人的な”好み”としてではあるが、個々の収録曲は『DREAMIN’』だが、ジャケットとタイトル曲は本作に軍配を上げたい。
特にフラッグ・シップの「Horizon」は鮮烈だ。軽いリフの波に乗ったエネルギッシュなギターのイントロが流れてきただけでゾクゾクが止まらない。グラン・ブルーの海原の先に見える水平線の彼方を目指す海鳥のように、風をつかまえて雲を縫うように飛翔し滑空する爽快感がたまらない。途中、エア・ポケットから一気に上昇気流に乗っていくジェットコースター・ライドのようなジャンクの歌声を聴いているだけで"元気"をチャージできる。ここ最近、気がつけば頭の中を”Riding on the wind …”というフレーズが駆け巡っている。自分にとって、とんでもなく中毒性が強い一曲だ。
この後も秀曲は続くのだが、個人的には朝の清々しさをパッケージした「Essence」と終盤の3曲に惹かれる。
安定した”夏の定番曲”「夏のマーメイド」は80年代の角松敏生の世界観と重なる本作のサブ・タイトル曲だし、スムージーな「Tokyo highway disco drive」のコーラスはノーナ・リーヴスのポップで豪奢なダンス・ミュージックを想わせる。そしてラストの「大切なもの」は入りがアトランタ・リズム・セクションの「Do It Or Die」っぽいが、(ちょっと強引ではあるが、)どこか山下達郎の重厚長大な「蒼氓」をカジュアルにしたような印象を受ける。楽曲そのものは夕凪のように穏やかだし、ブライトなアルバムの”締め”に相応しいナンバーだ。
さて、前作のカヴァー・アルバムでは往年の”シティ・ポップ”にもチャレンジしているのだが、もし、第二弾が企画されるのであれば、是非、佐藤 博の「アンジェリーナ」を取り上げてほしい。いきなりファルセットから入るクールで切れのいい”夏の定番曲”なので、ジャンク節で思う存分歌い上げてもらいたい。
0
|
|
|
2作前の『HAPPINESS』からジャンクが変わった。『SHINE』の流れを継ぐ今作も、いい意味で力みが取れて、聴き手もリラックススして楽しむことができる。それでいてジャンク独特の清涼感、エネルギーはそのままだ。いいアルバムを届けてくれたことに感謝したい。
オープニングのタイトル曲から「CATCH THE RAINBOW」へと成層圏まで一気に高度を上げていくような展開がなんとも爽快だ。後を引き継ぐ「NIGHT CRUISING」は、炸裂するスラップ・ベースに強気のサックスが絡んで夜の都会を疾走する。続く三拍子の極上のバラード「SOUTHERN CROSS」は、山下達郎の「FUTARI」に勝るとも劣らないバラード・チューンとしてアルバムのセンターをとっている。ソウルを感じるジャンクの歌声と艶やかなアルト・サックスの音色が心に沁みる。
一転、夏の名残りをスケッチしたような「あれはたしかSEPTEMBER」からは心地よい熱風を感じるし、グレイッシュ・ブルーなメロディから始まる「雨あがりの街」は、雲が流れて行った後に降り注ぐ陽射しの眩しい街並みへとフォーカスを変えていく。その後に続く柔らかいベースとやさしいトロンボーンが絡む「STEP BY STEP」も前向きだし、軽いサンバのリズムで夏のトロピカル・バカンスを描いた「MID-SUMMER」もジャンクの”十八番”といった感じで安定している。
アンカーを任された山川恵津子のペンによる「UTOPIA」は、どこか久保田利伸のテイストを感じさせるシックな楽曲で、フリューゲル・ホーンの慎ましい音色がアダルト・コンテンポラリーしていて、イノセントでスマートなアルバムに”深み”というか”奥行き”を与えている。
最後に添えられた「君は薔薇より美しい」が気絶するほど悩ましくて、個人的には、本作の影のハイライトとなった。原曲に対するリスペクトも感じられるし、何よりも懐かしい”春”の匂いを届けてくれている。本作は、前々作からの系譜でいえば、まさに”ホップ、ステップ、ジャンク”な傑作だ!
0
|
|
|
切り抜き写真をはめ込んだようなジャケットがレトロな旅行ガイドブックの表紙を想わせるが、前作から3年経って、音楽はさらに進化している。”シャングリ・ラ”の次の旅が始まったみたいだ。
冒頭の「STEVIE & SLY」はベース・ラインから50年前へタイム・スリップするのだが、決して闇雲にノスタルジアを再現を目指しているわけではない。途中、AWBが「Help Is On The Way」で披露した脱力系スライダーを独自のスタイルで落とし込むなど、高度な技術を駆使しながら現在進行形のクールな楽曲として送り出している。言うまでもなく、主戦場を70年代にも拡げていて、タイムマシーンのように現在と過去を瞬間移動しながら最先端のコンテンポラリーな音楽を創り上げている。
続く「BORN TO DREAM」には完璧にやられてしまった。これほどまでに洒脱でスマートな攻撃を受けるとは…。もう無条件降伏するしかない。”オマージュ”もここまで来ると”神業”と言うしかない。良質の中古部品を使って最新型のマシンを創り上げてしまっている。M・マクドナルドやその周辺の楽曲に親しんできた者が聴いても、文句の付けようがないくらい、ストロークは安定しているし、クオリティは高い。何よりも先人へのリスペクトが感じられる。個人的にはブルックリン・ドリームスの「I Won't Let Go」を聴いているみたいで、気持ちが和む。
フリートウッド・マックのストライドとスティービー・ニックスのブルージーな雰囲気が漂う“深夜の最終列車”まで快速で飛ばしてきたので、一息つくのかと思っていたら、その後も懐かしいサウンドの進化形が次から次へと繰り出してくる。
「BURNING DAYLIGHT」はブルース・ヒバードの匂いがするし、「HOLDING BACK THE FIRE」の入りはホール&オーツの「追憶のメロディ She’s Gone」を早送りしているみたいだし、「PUT UP YOUR DUKES」のクライマックスはランディ・グッドラムの「Duse」を想わせる。
ラストは8曲目の「THE GREATEST LOSER」で締めたいところだが、あえて「ONE HORSE RACE」を選択したことで、アルバムにちょっとした”緊張”を加えることに成功している。
何だか屋根裏部屋で宝探しをしているみたいで、理屈抜きで楽しめる良盤だ。
1
|
|
|
紙ジャケット盤を買った5年後にボーナス入り廉価盤として発売された”新名盤探検隊”まで手を出していたというのに、不覚にも、何年もの間、棚の奥に眠らせていた。
結論から言うと、ブルー・アイドなR&Bにコンテンポラリーなポップ・サウンドがブレンドされた、カラフルでゴージャスな(ディスコ向け)楽曲集といった感じの良盤だ。“失敗しない”ヒット・メイカーのソング・ライター・チームの仕事なので、当然のことだが”外れ”はない。
ネガティブなことを言えば、オープニングの”掴み”を任されたタイトル曲がやや弱い(気がしている)。ツボを押さえたスマートでコンパクトな楽曲なのだが、個人的な印象として、やや線が細い。だが、ご安心を。2曲目からエンジンがかかり始める。
中盤から終盤にかけてはギアをどんどん上げていく。特に後半は十八番のシスター・スレッジ仕様だけではなく、ブラザーズ・ジョンソンやシャラマー辺りを意識したご機嫌なダンス・チューンで畳みかけてくる。途中、熱いハートをクール・ダウンさせるための泣きのバラード「メモリーズ」や、ミディアムで前向きな佳曲「ソー・マッチ・イン・ラヴ」を挟み込むといった粋な演出もあったりして、プロの仕事ぶりを見せつけている。
それにしても、ジャケットだけを見ると、”ブガッティ&マスカーというユニットの『ザ・デュークス』というタイトルのアルバム?”と思ってしまうのだが…。
0
|
|
|
オープニングの「CHECKPOINT CHARLIE」からスティーリー・ダンを感じる。饒舌なサックスがリードする滑らかでゆったりしたフローターは「Aja」のセッションを想わせる。だからといってスタイルや手法を単に模倣しているわけでもないし、過去の名盤のプロトタイプを作ろうとしているわけでもない。”精度”よりも”純度”が高いのは、フェイゲン=ベッカー組へのリスペクトだけではなく、自身の抽斗をいっぱい持っているからだろう。”聖域は侵さない”というモンキー・”ハウス・ルール”だってしっかりと守られている。
収録されている15のアイテムは同じ遺伝子を持っているが、それぞれに独特な個性と確かな存在感があって、同じような(=同じように聴こえる)楽曲は一つもない。みんな違って、みんないい。
個人的には、ポップな作風に移行する分水嶺となっている「DECEMBER GIRLS」(曲の入りで、なぜか大江千里の「BOY MEETS GIRL」=クリス・クリスチャンの「Don’t Give Up On Us」を想わせる)を気に入っている。琥珀色の夕暮れ時が似合うナンバーだ。
本作のジャケットについて、遠目にはバルタン星人の襲来のように見えるが、近くで見ると王冠型のアンテナを被った電波塔らしき建造物が、まるで”本丸”をカムフラージュする分身のように群立している。そんな電波塔本部から発信される楽曲のすべてが都会的で洗練されていて、スマートで瑞々しくて最高に心地よい。
次作の『レフト』以降は3年周期で新作をリリースしており、毎回”前作を凌ぐ”といったレビューを目にするが、確かに熟度や深みは増しているなど進化を遂げているものの、研ぎ澄まされ過ぎて”つけ入る隙”がない分、敷居が高くなっているように感じる。その意味でも本作がこれまでのベスト・レコードだと思っているのだが…。果たして、まもなくやっていくる”ハウル”の出来栄えはどうだろうか?
0
|
|
|
本作に辿り着くまでに2年半もかかってしまった。
というのも、1、2作目の好印象を受けて購入した3作目の『Canyons』が自分としては期待外れだったからだ。大きな路線変更があったわけではなく、単に自分の波長と合わなかっただけなのだが、結果、自分の中で勝手に”彼らのアルバムは2作目まで”と終止符を打ってしまっていた。何とも勿体ない話だ。
ところが最近、偶然にも本作の収録曲をいくつか耳にして、自分の波長とぴったりと合ってしまい、好印象だった1、2作目の記憶が蘇ったこともあって、冬眠から醒めたように食指が動きだした。一応、P-VAINのアルバム購入の前準備として収録曲をひととおり試聴したのだが、どの楽曲も期待どおりのクオリティだったので、ややワイルドなジャケットに怯むことなく購入ボタンを押すことができた。結果、遠くへ行ってしまった彗星は、あの頃の輝きのまま戻ってきてくれた。
P-VAIN、UK、ネオ・ソウル、銀キツネというユニット名…、”いかにも”といった感じのクールなワードが並ぶが、ニュー・カマーにありがちな”スタイル先行”といった音楽ではない。70年代後半から80年代にかけてのコンテンポラリーでスムーズなサウンドをベースに、00年代の鋭敏な感覚でしっかりと練られている。楽曲によっては特定のアーティストや楽曲を想起させるフレーズがミックスされているが、エッセンシャルな部分でのリスペクターであり正統なフォロワーであると捉えたい。個人的には「West Side Jet」や「Rolling Back」、「Simple Imagination」といったソフトな楽曲を気に入っている。ついでに言えば、国内盤のボーナスとして追加されている「Chances Are」は出色だ。
0
|
商品詳細へ戻る