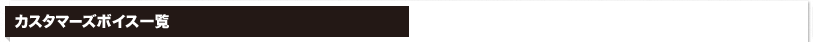
冨田恵一 WORKS BEST~beautiful songs to remember~<通常盤> / Various Artists
|
|
冨田カラーの配色は独特で、聴けば直ぐにそれと判るが、コラボレーションしているどの楽曲も、アーティストの個性を活かしながら、絶妙な色合いに染め上げている。
出色は坂本真綾が歌うオープニングの「エイプリルフール」で、暦の上では、春休み後半の”4月”のグループに属する”春”の定番曲だ。3月の終わりと4月の始めでは、年末と正月ほどではないが、世の中の事象や環境の変化に併せて、漂う空気も大きく変化する。”四月になれば彼女は”変わってしまうのかもしれない。この曲は、そんな4月1日の黄昏時にフォーカスしている。特別なアニバーサリー(?)を背景とする”嘘”にまつわるエピソードは、坂本真綾の甘いヴォーカルと、温もりのある穏やかなメロディでスケッチされていく。4月1日にこの曲を聴くたびに、この日をしっかりと抱きしめていたくなる。
|
商品詳細へ戻る
ねずみ1960さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
EPOのアルバムは”外れ”がない。選択に困ったら、お気に入りの楽曲が入っているアルバムを選べばよい。特にベスト盤で拾われていない推しの楽曲が収められていたりしたら、これはもう買うしかない。
そんなわけで復刻盤の買い換えとして、自分としては「Girl in me」目当ての『う・わ・さ・に・な・り・た・い』と本作に絞ったわけだが、こちらのアルバムのターゲットは何といっても「涙のクラウン」だ。この一択と言ってもいい。かつて” オレたちひょうきん族”のエンディングでも使われていたコミカルな小品で、土曜の夜のウキウキする感じが詰め込まれている。途中の”サンタクロースがやってくる”っぽい旋律など、どこかクリスマスの雰囲気も漂っていて、聴いていて温かい気持ちにさせてくれる。
本作は、オープニングのタイトル曲から猛スピードで駆け抜けるのかと思いきや、結構シックでクールな楽曲が並ぶ。そんな中、件のジングル・コーラスの佳曲と並んで、あどけない高見知佳を思いっきり輝かせてくれたオリエンタルな「くちびるヌード・咲かせます」も絶品だ。
|
|
|
2023年12月にカラー・ポートレートの78年盤が復刻された際、勝手な思い込みで96年の編集盤(追加曲入り変則 2 in 1)の再現を期待していたが、実はモノクロ・ポートレートの80年盤の復刻も予定されていたとは…。彼女のキャリアのことを全く知らずに文句を言っていた自分が恥ずかしい。
取り上げられた楽曲に関しては、ジャズやラテンのスタンダード・ナンバーよりも、気の置けない英米ポップスの丁寧なカヴァーに魅力を感じる。本作でいえばビル・ラバウンティの「25 Words Or Less」辺りがそれに当たる。原曲のポップでライトな空気感を保ちながら、ナチュラルなトーンで再生されていて、とても聴き心地が良い。
ブラジル由来の楽曲群に関しても、あくまでも個人の印象として、北欧と南米という環境や景色の違いを微塵も感じさせない”居心地の良さ”がある。清楚なジャケットとのコントラストなど全く気にならない。それどころか、灼熱の太陽の下で生まれた楽曲を熱唱する彼女の歌声には十分な熱量を持ったクールな焔を感じる。
|
|
|
自分の知り得る限りハイ・ファイ・セットの最高傑作だと思う。どの楽曲もクオリティが高く、カラフルでバラエティに富んでいて、個性豊かな充実したアルバムだからだ。
オープニングのミディアムなフローターから癒される。高速道路で偶然見つけた遠い故郷ナンバーの「水色のワゴン」。穏やかな夏の午後の素敵なサプライズが、甘酸っぱい想い出の1ページを捲ってくれる。何といっても、並走するワゴンが”水色”というのがいい。淡いソーダ水を想わせる”ペパーミント・ブルー”な楽曲は、邦楽の”夏の定番”として欠かせない。
”夏”つながりでいえば「7月のクリスマス」も素晴らしい。海辺のリゾートでの粋な夏のメロドラマが楽しめる。気取った会話が少々耳障りだが、アガサ・クリスティのミステリー小説をアイテムとして使っているので許すとしよう。クリスマス・ソング集には使いづらいが、「ジュ・マンニュイ」同様、”夏歌”のプレイリストにエントリーしたいところだ。
マンハッタン・トランスファーを想わせる「Viva ! オフ・ローダー」はアクロバティックでスピード感溢れる痛快なジャズ・ナンバーだ。息の合ったコーラス・ワークは当時の彼らの十八番でもあり、これぞ This Is ”ハイ・ファイ・セット”といったところだろう。
アルバムの締めくくりは、胸を詰まらせるセンチメンタルな絶品バラードの「Good-bye school days」がアンカーを任されている。「最後の春休み」同様、「卒業写真」とは違う、進行形の”卒業”を描いた佳曲がアルバムの”有終”を飾っている。
一つだけ勝手な注文として、レコードでいうB面1曲目のビターでシリアスな攻めのナンバーをもう少しファッショナブルな楽曲に差し替えてしてほしかった。例えば、前出のM・トランスファーでいえば「トワイライト・ゾーン・…」のようなスリリングでスタイリッシュな直球勝負でも"締まる"ような気がするのだが…。
|
|
|
“代表作”というレッテルに偽りなしの”名盤”だ。全体がジェントルなランキン色に彩られていて、カヴァー曲もオリジナルの域に達している。ビートルズの2曲など非の打ちどころのないくらい完璧に蘇生させていて、原曲を知る者に新しい景色を見せてくれる。
タイトル曲の”銀世界”がやや重だが、耽美でクワイエットなバラードや心弾ませるリズミカルな小品など、一つひとつの楽曲の粒立ちが良く、粋で、個性的で、確かな存在感があって、しっかりとした聴き応えのあるアルバムに仕上げられている。
軽いジャズの香りと甘くやさしいメロディがアコースティックの領域の中でほどよくブレンドされていて、最良かつ至福のひとときを届けてくれる”名曲集”だ。
|
|
|
2008年の紙ジャケット・シリーズ化の際、予算の関係で4枚だけの入手だったが、いずれも個性的な秀作で、”ベスト盤で十分と云うなかれ”を実感してしまった。もちろん96年の『Peaceful: The Best Of』のセレクションは素晴らしく、ケニー・ランキンの代表曲が網羅されていて、彼の魅力を余すことなく詰め込んではいるのだが…。
さて、オリジナル・アルバムの中でも本作は比較的大人しいタイプの楽曲集という印象を持っている。クラシカルな匂いのするジャケット同様、純朴で控え目な楽曲が並ぶ。定番のビートルズ・カヴァーの他に、ランキン節のアレンジが施されたイーグルスの「いつわりの瞳」などが素朴な料理に彩りを添えている。
構成としてインタールードを挟んではいるが、三幕とも展開に大きな変化はない。穏やかな音楽が緩やかに流れる時間と協調しながら、日々のストレスで傷んだこころをやさしく癒してくれる。ピースフルでイージーなフィーリングの好盤だ。
|
|
|
新顔≓アンダーグラウンドなアーティストのコアな楽曲集と構えていたら、意外にもライトでポップなテイストがセレクトされているのに驚いた。もっと尖っていて刺激的で野心的な楽曲をコンパイルしているものと思っていたのだが、どれも滑らかで緩やかでシンプルなマインドを持っていて、底辺には都市生活の”心地よさ”が流れている。これなら還暦を過ぎた爺さんでも十分楽しめる楽曲集だ。
そこまで前衛的でもなければスタイリッシュでもない、極めて自然体でありながらオーガニックでもない、要するにポップスの枠組みの中でフリー・スタイルで泳いでいるのだ。インディーズはどれも上を目指してハングリーでアグレッシヴなのだとと誤解していたが、真摯に音楽と向き合っているピュアなアーティストも多いということが良くわかった。
それにしても6月リリースの『… anagram』とは音楽的な立ち位置がかなり違っている。山手線でいえば”西日暮里”と”恵比寿”くらいの距離感の違いだ。どちらも”東京”には変わりはない、のだが…。
|
|
|
シリーズの”お薦め度”の評価としての”★”は3つだが、自分的には、不覚にも結構ハマってしまった。それも"深み"に。
本作にシャープで洗練されたファッショナブルな楽曲集を期待していると痛い目に遭うだろう。フォーマットはピュアな”和テイスト”なのだが、エスニックでオリエンタルで、時にエキセントリックな匂いさえする。もちろん、ディープな闇を抱えているような怪しい湿地などは存在しないが、楽曲によっては”あまく危険な香り”が漂っていて、聴いていてクセになりそうな中毒性を秘めたものもあったりする。
歳を取ったせいか、ある種の単純な西洋かぶれとは一線を画する”洋楽っぽい歌謡曲”に浸っていると、妙に心地よさを感じてしまうから不思議だ。
当然、自分の肌に合わない、どうにもこうにもブルドックな楽曲はあったりするわけだが、それでも十分元は取れている。昭和生まれの爺さんにとっても初体験の”昭和”を届けてくれる"魅惑"のコンピレーションだ。
|
|
|
P-VAINは時々やってくれる。欧州のお洒落なコンテンポラリー系専門レーベルという先入観を抱いていると、時に骨太のスラッガーを連れてきたりする。
本作も、70年代のアダルト・コンテンポラリーをリアル・タイムで楽しんできた老いぼれには嬉しい発掘で、爺さんが安心して聴ける耳馴染みのよい楽曲群で構成された良盤だ。唯一の難点は、個々の楽曲の尺が短いくらいだが、楽曲そのものの完成度は高く、物足りなさは感じない。
ホーン隊もしっかりと管を吹いているし、力業でねじ伏せるような重厚感などはなく、むしろ爽やかなブラスの響きに心地よさを感じる。個人的にはシカゴの『Ⅹ(カリブの旋風)』やボズ・スキャッグスの『シルク・ディグリーズ』の音楽性とシンクロしてしまうのだが…。もちろん、いい意味でノスタルジックだ。
ジャケット同様、豪奢に彩られたカラフルな意欲作だと絶賛したいところだが、本作はあえて”★”を4つにしておこう。次作の大躍進に期待したいから。
|
|
|
久しぶりに訪れた福岡店で、目に留まった線画のとてもシンプルなジャケットに惹かれて、気が付いたらレジに運んでいた。
本作は1974年の既発表曲中心のスタジオ録音盤だが、映画『Let It Be』への再挑戦というよりは、ツアーに向けたリハーサルのような雰囲気を感じる。ビートルズ時代のように演奏を途中で止めてしまうこともなく(実際は録り直しもあったのだろうが)、全ての楽曲を完奏している。
そんな、いわゆる一発録りを聴いて個人的に想ったのが、かつて噂されていた『Red Rose Speedway』のダブル・アルバム化構想だ。次の『Band On The Run』はグループ制作されたアルバムだったので『Red Rose …』とは色調が大きく異なっており、トラックの共有などは想像し難い。一方、2枚組のために当時のシングル盤オンリーの楽曲(B面を含む)をかき集めるというやり方をポールは好まない。
そんな個人的な疑問に答えてくれたのが『Red Rose …』のデラックス版でボーナス収録されていた未発表音源だったが、どれも完成度が低く、心を揺さぶるようなクオリティとは程遠い代物だった。たぶん、どれもサンプル素材のレベルだったのかもしれない。
ところが今回、本作収録の未発表曲を聴いてみて驚いた。どれもレコードとして出せるレベルまでに仕上げられていたからだ。これなら、お蔵入りしていたサンプル素材も、磨き上げればしっかりとした楽曲として完成するのかもしれない、そんな期待を抱かせてくれた。根拠などはない。だが、もしもメンバーの離脱がもう少し後だったら、錬金術師ポールであれば、赤いバラのレース場をダブル・トラックの豪奢な重層構造に仕上げることは容易いことだったのかもしれない。バンドがアフリカの荒野を駆けていたかどうかは別として…。
本作は、そんな景色さえ見せてくれたタイム・カプセル盤だった。
|
|
|
タイトルやジャケット写真に惑わされてはいけない。
これはベスト・セレクションのスタイルを借りた2in1のお買い得盤で、しかもそのうちの1枚(後半の10曲)は名盤『ソー・メニー・フレンズ(So Many Friends)』の全楽曲というのだから驚きだ。件のアルバムがCD化されたのが2004年で、当然のことながら既に廃盤となっていて、LPレコードとしてリリースはされてはいるが、再発の兆しは見られなかった。それが、まさかこんな形で復刻されるとは…、想定外のサプライズだと言っていい。
本作は”ゴールデン☆ベスト”と銘打った仕様であり、ストック音源をそのまま焼き付けたものと思われるので、リマスタリングによる音質や音量(音圧)の向上といった気の利いたプレゼントは期待できないが、この価格で五つ星のフル・アルバムが楽しめるというのはありがたい。反面、『ソー・メニー・フレンズ(So Many Friends)』の音質向上盤としての復刻が遠のいたようで残念ではあるが…。
今後、この手法が使えるのであれば、是非とも高橋拓也やスプリングスといったサイドウォークの寡作なアーカイヴスにも応用してもらいたいものだ。
|
|
|
“クイーンをベスト盤で済ませてしまおうとする根性が気に入らねえ!”と叱責されそうだが、このアルバムでほぼ満足している自分がいる。もちろん、中学生の頃の”一家に一枚”盤だった『オペラ座の夜』も持ってはいる、のだが…。
この決定版“グレイテスト・ヒッツ”には続編があるが、どういうわけか「炎のロックン・ロール Keep Yourself Alive」が収録されていない。自分にとっては初期の看板曲であり、彼らのスリリングでハードでスピード感あふれる秀作として外せない1曲であるにもかかわらず、リンダ・ロンシュタットの「また、ひとりぼっち Lose Again」同様、ベスト盤に拾われていない。たぶん、純粋なクイーン・ファンであれば誰もが知っている”事情”があるのだろうが、外様大名のように叱責を受ける身の自分はその”事情”や”経緯”を知らない。”手をとりあって”いる場合ではないのに、と不届きなことを書くと大炎上してしまいそうだが、この曲の欠落は何とも不条理で合点がいかない。
だからといって戦慄の1stに手を出すわけでもなく、何となくモヤモヤしているうちに『オペラ座の夜』のエクスパンデッドで漁夫の利を得てしまった。”ラッキー!”なんて書くと”なに~?!、この罰当たり野郎が!”と火に油を注いでしまうかもしれないが、これでパズルは完成した。
もう1曲、手に入れたいピースがある。続編収録の「Radio Ga Ga」だ。この曲のエピソードといえば、ドラマ”あまちゃん”を思いだす。フレディ・マーキューリーの恰好で登場した伊勢志摩さんが、小池徹平の”次も、またレディ・ガ・ガ?”という失言に、”よ~く見ろ!”と啖呵で返す、何とも痛快なシーンだ。おそらく、わかる人にしか、わからない。そんな”遊び”をさり気なく入れる、宮藤官九郎は天才だ。
|
|
|
そもそもの狙いは1曲目の「僕の想い入れ」だった。79年に全米トップ40入りした時から、その純朴で屈託のない明るさに魅了され、以来、気分が下がったときの元気回復ソングとして何度もお世話になっている。
ポップにステップする愉快なキーボード・サウンドに導かれて、ワクワクするような右肩上がりのメロディが心弾ませる。圧巻は終盤の最高に心地よい転調だ。最終コーナーでギア・チェンジして、一気に加速しながらゴールテープを切るような爽快感がたまらない。まるで天国から聴こえてくる音楽のような神々しささえ感じる。この1曲のためにアルバムを買っても損はない、と思う。
2曲目以降、「僕の想い入れ」を凌ぐ秀曲に出逢うことはないが、足を取られるような湿地もない。そんな中、7曲目の「ダンスしようよ」はアダルトでオリエンテッドなサウンドにポップな味付けが施された佳曲だ。フルーツ味のキャンディのように甘く爽やかで、炭酸の効いたソーダ水のように口の中でクールに弾けてのどを潤す。
アルバムの立ち位置はP・マッキャンやK・ノーランの1作目に似ている。AORとしての評価は2作目の方が高いようだが、個人的には、心に刺さるヒット曲を持ち、アルバム全体のバランスが良い1枚目を推したい。
|
|
|
連続する2枚のオリジナル・アルバムがどちらも”名盤”と評されている場合がある。
仮に”どちらか1枚を選ぶとしたら?”と訊かれたら、最終的には自身の好みに委ねられるとは思うが、中には簡単には決められないものもあったりする。
自分の場合は、イーグルスの『呪われた夜』と『ホテル・カリフォルニア』、フリートウッド・マックの『ファンタスティック・マック』と『噂』、ビリー・ジョエルの『ストレンジャー』と『52番街』辺りがそれに当たる。
反対に、スティーリー・ダンの『エイジャ』と『ガウチョ』だと、迷うことなく前者と答えてしまうのだが…、異論も多いとは思う。
ジャーニーの『エスケイプ』と本作はどうだろう(?)。個人的には、殻をぶち破って大躍進を遂げた大出世作に怯むことなく躍進を続けた本作の開拓者精神に敬意を表したい。実際、楽曲のクオリティ、演奏の重厚感、全体のバランスの良さなど、前作を凌ぐ完成度の高さを感じる。自分など、第一弾シングルかつオープニングの泣き節ロックが苦手で、長らく距離を置いていたのだが、改めて本作と向き合ってみて、ダイオードのように発色する神秘的な青色の世界に惹きこまれてしまった。けだし、”名盤”だ。
|
|
|
こういうスタイルの男女デュオというのは、日本ではあまり見かけない。
ムード歌謡系とは趣が違うし、「カナダからの手紙」のようなポップスには当てはまらない。村田和人と竹内まりやの「SUMMER VACATION」は爽やか過ぎるし、雰囲気の近いEPOに鈴木雅之が絡んだ「DOWN TOWNラプソディー」はイーブンに掛け合うデュエットではない。
改めて本作は、ジャケットのように黒いドレスとタキシードの似合うゴージャスな夜にぴったりのデュエット・アルバムだ。オープニングの「星空のふたり」など、1977年の幕開けに相応しい佳曲で、フルートの旋律が自由なフィラデルフィアの風を運んできてくれる。真冬の寒い夜でも心の炎は熱く燃えている。同じくカッコつきのタイトルを持つ「虹をわたる恋」だって負けてはいない。愛のちかいも抱擁も眩いし、ソフトで優雅なダンス・ミュージックは永遠だ。
バルーンで旅立って行った第五次元のスーパースターの二人が、今宵、最高のショー・タイムのために帰って来た。輝く星座から、ようこそ地球へ、”おかえりやす”。
|
|
|
ハービー・ハンコックの音楽について、本作しか語れない自分のような不届き者に何かを言う資格などない。処女航海に出たこともなければ、ジョニ・ミッチェルへのリスペクトにも触れていない異邦人が、偶然出遭った本作に魅了されてしまったという単純なストーリーに過ぎないのだから、スイカ男に首を絞められても文句は言えない、
ハンコックのキャリアを知っている友人の話では、ジャズやファンクに軸足を置いてはいるものの、その音楽は一つのジャンルに止まることなく、河の流れのように流転し、あるいはカメレオンのように七変化しながら、時代を超えて第一線で音楽を創り続けている、とのことだ。ベスト盤も編集できないし、代表作を1枚に絞ることも難しいらしい。”フランク・ザッパみたい”というと、双方のファンから罵倒されてしまうかもしれない。
本作の位置付けについて、横軸に難易度、縦軸に密度(濃度あるいは重度)のチャートにプロットするとしたら、最も解かり易く最も軽くて淡いゾーンにぽつんと1枚だけ置かれている異色のアルバムなのかもしれない。極めてポップだし、魂を抜いたR&Bといった感じさせする。もしかしたら、彼は自身のクレジットから外してほしいと思っているかもしれない。
だが、アダルト・コンテンポラリー好きの自分にとっては極上の楽曲が詰め込まれた”秀作盤”であり、あまり人には教えたくない秘密の”お宝盤”であることに違いはない。流れるようなスポットライトの似合う派手なダンス・ナンバーが目立つが、決してそれだけではない。ライトでメロウな”楽園”だって、ここにはある。
|
|
|
以前、2ndの浮世絵アルバム『マウンテントップ』と2in1で発売されていたが、今回はセパレートでの再発となっている。”CCM”というカテゴリーなのだが、Cool Soundが発掘したアダルト・コンテンポラリー寄りの隠れた快作だ。ブルース・ヒバードの『ネヴァー・ターニン・バック』やマイケル・ジェイムス・マーフィーの『サレンダー』などの”特A”クラスとは言わないが、十分”A”ランク評価には値する。
1stと2ndに劇的な変化は感じられないので、2枚をまとめたCDを通して聴いても違和感はなかったし、気になる湿地や落ちこぼれ曲などもない。どちらのアルバムも良質で買って失敗はないと思う。
とにかく、オープニングの「Paradise」からご機嫌なのだが、自分にとって最も気持ちを上げてくれる栄養ドリンクは、中盤の「Eternity」から「Love Is Forever」へと引き継がれる完璧なリレーだ。特に後者の小気味よいブラスにはタウリン以上に元気を貰える。魔法学校の優等生が指先から発した閃光を全身で浴びているみたいだ。聴いているだけで気持ちは一気に右肩上がりになるし、小さなイライラも吹き飛んでしまう。要するに、This Is “CCM”なのだ。
このアルバムに魅了された方は、もう一つの山登り盤を楽しんでみるのもいい。朝かステーキを食べるというのも、時には必要だ。
|
|
|
カラフルなイラスト・ジャケットがユーモラスな本作には心揺さぶる至宝の2曲が収められている。「I Won't Last a Day Without You」と「Traveling Boy」だ。
前者はカーペンターズの「愛は夢の中に」として、後者はアート・ガーファンクルの「青春の旅路」として、それぞれが原曲の持つ穏やかでクールな情熱の焔をトーチで受け継ぎ、自らのスタイルに落とし込んで、もう一つのスタンダードを完成させている。「愛は夢の中に」のリリカルな感傷はカーペンターズのものだし、「青春の旅路」のエネルギッシュなパッションはアート・ガーファンクルのものだ。
しかし、ここに収録されているのは紛れもないオリジナルであり、加工が施される前の原石だ。シンプルだが、何とも言えない独特の深い味わいがある。ランディ・グッドラムなどもそうだが、佳曲のソングライターがシンガーとして、こうして自ら歌ってレコードにしてくれたことで、最高のドラフトを楽しむことができる。そのことに対して素直に感謝しなければならない。
|
|
|
本当に“コンプリート”なのか、という議論は置いといて、この2枚組には5枚のオリジナル・アルバムに収められていないシングルズ・オンリーが収録されている。かぐや姫時代のメガ・ヒットは置いといて、あとの2枚は風の古暦を語る上で外すことはできない。
「ささやかなこの人生」は「暦の上では」と並ぶ”卒業ソング”の定番だ。カントリー・ポップスふうの爽やかなギター・サウンドに乗せて、サクラ色のそよ風が通り過ぎていく春の風景が描かれている。歌詞に綴られているのは懐かしい昭和の時代の”青春謳歌”だ。1970年代の穏やかな時間に学生時代を過ごした者に捧げられた”贈る言葉”のようでもある。背中が少し痒くなるようなニュアンスだが、これこそが”昭和”の”青春”だったのだ。
「夜汽車は南へ」はボズ・スキャッグスの「港の灯」をテンポアップしたような滑り出しで始まる。伊勢正三の歌には”汽車”がよく出てくる(「北国列車」は別だが…)。決して蒸気機関車というわけではなく、イス席が並ぶ客車を牽引するEF58の電気機関車だったとしても、やはり汽車は”汽車”なのだ。歌詞の語呂からは仮名3文字が上手く収まるが、”東へ”ではなく”南へ”としたところに都会から地方へと向かう”汽車”であることが覗える。イス席の客車を機関車が牽く編成の夜行列車が走っていたのも、やはり”昭和”だった。
|
|
|
決してネタが尽きたわけではないし、キワモノを選んだわけでもない。子ども向けの教育テレビと侮るなかれ、この楽曲群は本物(マジモノ)だ。
長くなるが、個人的な十傑は以下のとおり。本作に収録されていないものがあることはご容赦願いたい。いずれも原曲の美味しいところをしっかりと持ってきて、次代を担う子どもたちに洋楽(一部は邦楽)の素晴らしさを伝承しようとする姿勢が覗える。
【ランキング】 ※順位/タイトル/元ネタを記載
①「ボス豚」◆ボストン「ドント・ルック・バック」+「宇宙の彼方へ」
②「カキはえいゆう」◆トム・ジョーンズ「よくあることさ」
③「ホタル・カリフォルニア」◆イーグルス「ホテル・カリフォルニア」
④「スワローアゲイン(夏が来る)」◆ギルバート・オサリヴァン「アローン・アゲイン」+S&G「コンドルは飛んでゆく」
⑤「燃えよ!クチバシ ~カモノハシへの道~」◆ビリー・ジョエル「ストレンジャー」
⑥「ナメク☆ジノバネリ ~NEVER LOSER~」◆ジノ・ヴァネリ「アパルーサ」
⑦「チョー(E)!」◆ビートルズ「シー・ラヴズ・ユー」
⑧「サーモンU.S.A.」◆ビーチ・ボーイズ「サーフィンU.S.A.」
⑨「水の中の小さなクマ」◆はっぴいえんど「風をあつめて」
⑩「哀愁のヨーロッパ・バイソンやねん」◆サンタナ「哀愁のヨーロッパ」
次点「ピーター・プランクトン」◆ピーター・プランプトン「ショー・ミー・ザ・ウェイ」
1位から3位は文句なく素晴らしい。特に「ボス豚」は、Bostonの独特のギター・サウンドを再現しているだけでなく、間奏の構成・展開力もそっくりだし、それに加えて歌詞が泣かせるという完璧な仕上がりの楽曲だ。言葉遊びのような「ホタル・カリフォルニア」も、ドン・フェルダーが仰天するほどの見事なギターワークが楽しめる。
かつての邦楽にありがちな中途半端な”焼き直し”ではない。半分”訴えられたって構わない”くらいの覚悟と潔さがある。ここまでくると“パロディ”の領域を完全に超えており、原曲に対する奥深い"愛情"と真摯な”リスペクト”を感じる。
|
|
|
“アコースティックなポール・サイモンが帰ってきた”、といった感じのアルバムだ。センスのいい皮肉も和やかだし、呟くような歌声も心地よいし、一つひとつの楽曲も控え目で大人しい。何よりも音楽が薪ストーブのように周りを暖めてくれる。ジャケットもデジタルふうだが、ブラウン管の映像のような味のある粗さがある。
冒頭の「アレジー」は少し神経質で張り詰めた空気が漂っているが、タイトル曲以降はシンプルで落ち着いた楽曲が続く。
とりわけ「犬を連れたルネとジョルジェット」は、ルネ・マグリット夫妻が犬と佇むスチル写真から貰ったイメージを綴ったものだと聞くが、やわらかい陽射しが暖かく感じられる晩秋の景色が浮かんでくる。幻想的で奇想天外な絵画と穏やかな家族写真とのコントラストも一興だ。
ポール・サイモンの楽曲には”車”が登場するものが多いが、このアルバムには”車”の楽曲もあるが、さり気なく”汽車”も走らせている佳曲がある。鉄道好きの自分には嬉しい楽曲だが、汽笛が本物かどうかはわからない。それでも機関車”ネゴシエイションとラヴ・ソング号”は人生の光と影を縫って走り続ける。重なり合うハミングのコーラスも実に心地よい。
「レイト・グレイト・ジョニー・エイス」は締めの佳曲だが、アルバム『時の流れに』の「マイ・リトル・タウン」のような浮いた感じがしている。決して違和感ではないし、アルバムの重鎮としての存在感もあるのだが、他の楽曲と比べて、少しだけ色調が暗いような気がする。"死"の影が漂っているせいかもしれない。
この原点回帰ともいえる秀作アルバムの後、ポール・サイモンは遥かアフリカ大陸へと旅立ってしまう。久しぶりの里帰りだったが、居心地の悪さを感じたのだろうか…。
考え過ぎかな?
|
|
|
NHKの映像アーカイブで残っているのは番組最終回の放送分だけらしい。当時のヤングの躍動は僅かに残された写真でたどるしかないが、歌声はCDで楽しむことができる。
個人的なビッグ・フォーは「涙をこえて」、「人生すばらしきドラマ」、「怪獣のバラード」、そして「若い旅」の4曲だが、五指を選ぶとすれば、中村八大のペンによる和製ポップスの名曲「恋人中心世界」を加えたい。それぞれのテイクはレコーディングの時期によってメイン・ヴォーカルが変わって(引き継がれて)いるのて、人によって好みは分かれるところだが、楽曲自体の”素晴らしさ”は変わることはない。どの楽曲も聴く(あるいは口ずさむ)者に”勇気”と”希望”を与えてくれる"パワー"を持っている。
このアルバムでは番組後期の佳曲が拾われている。当時のグラム・ロックの匂いのする「ジャングルジム」やクールな「にくい太陽」を思いっきりシュールでモダンにしたような「僕が五年前に考えたこと」など、自分としては懐かしい楽曲ばかりだ。
2枚組の1枚目にはオリジナル曲、2枚目には彼らの十八番でもある洋楽カヴァー曲を中心にまとめられているが、そんな中、終盤の特選邦楽カヴァーの中で太田裕美が歌う「あなた」が、"Your Song"ふうのアレンジも含め、原曲の空気感に寄り添ってトレースされていて、個人的には大きな収穫だった。
|
|
|
輸入盤でCD3枚組というボリュームだが、カーペンターズはこれくらいの容量がなければベスト盤として十分とはいえない。
このアルバムの「Yesterday Once More」は、後のリ・アレンジで歌い出しの”私を笑顔にさせてくれる”へと移る直前に施された変調コードへの差し替えではなく、当初のシンプルでフラットな録音の方が選曲されていて、当時のレコードに親しんできた者にとっては何ともありがたい復刻となっている。もっとも、『ナウ・アンド・ゼン』のテイクなので、エンディングのエンジン音も添えられているが…(AIを使って剥がせないものだろうか?)。
ところで、今さらながら「愛のプレリュード」は不思議な魅力を持つ名曲だと思う。アルバム『遥かなる影』ではオープニングに起用されているが、自分が最初に買った来日記念のベスト盤ではアルバムのラストを飾っていた。どちらもそこが定位置であるかのように、とても収まりがよく馴染んでいる。タイトルどおり新たな始まりの”プレリュード”であるし、第一幕を締めくくる”エピローグ”でもある。激動の60年代が幕を閉じ、平穏な70年代を願うように、繊細なバラードは静かに始まり、途中、ふたりの誓いを力強く宣誓した後、再び穏やかな夜明け前の時間へと戻っていく。
|
|
|
夏色の落ち着いたアルバムだが、ポイントはそこではない。洋楽カヴァー曲の「夜も泣いていた」だ。タイトルで浮かぶのはエディ・マネーだが、実は、レスリー・パールの佳曲「おしゃれな関係 If The Love Fit Wear It」だということを聴いている途中で気づかされた。まるで巧妙に仕組まれたアリバイを解いたような、個人的には大発見だった。
この手の意表を突く洋楽の日本語カヴァーとしては、井田リエ&42NDストリートの「ひらめきラヴ」や、しばた はつみの「バイバイ・ジュエル」などがあるが、どれも聴いているうちに謎が解けていく、それも"わかる人にはわかる"といった凝った(?)仕掛けになっている。特に「バイバイ・ジュエル」なんて、原曲のメロディだけを貰ってきていて、かつてのステージ101の洋楽の翻訳カヴァーでもやっていない大胆な反則技を展開している。
話を『him』に戻して、本作に収録されている「曇りのち"Easy"」は、岡崎友紀の「Cafe B.H」やKAITAの「LOOKING FOR LOVE」、指田郁也の「パラレル」などと同様、M・マクドナルドの匂いがする。
|
|
|
サマンサ・サングといえばビージーズの全面サポートで大ヒットした「愛のエモーション」のワン&オンリーだろうと侮っていったが、それは大きな間違いだった。このアルバムはシングルヒットにあやかって半ばやっつけ仕事で作られたB救品ではなかった。
エリック・カルメンの「チェンジ・オブ・ハート」以外の邦題は、優しい日本語でラッピングされていて邦人リスナーに寄り添っているのだが、一方で有名カヴァー曲などが邦題に隠されてわかり難いこともある。例えば、「私は行かない」なんて、ブルース・ロバーツ自身も歌っている「I Don’t Wanna Go」の直訳なのだが、サンプルを聴くまで全く気がつかなかった。結論から言えば、個人的にはいい意味のサプライズだったし、原曲の持つ甘酸っぱい雰囲気を損なうことなく歌い上げていたので、アルバム購入の背中を押してくれる1曲になったことは確かだ。
他にも佳曲ばかりを取り上げていて、内容も充実しているが、ビージーズのカヴァー曲「愛のシャレード」は本家のオリジナル版「Charade」に軍配を上げたい。好みの問題だが、アルバム『ミスター・ナチュラル』の冒頭で魅せた3兄弟のウィスパーなコーラス&ハーモニーは絶品で、まるで深い夜の静寂に仄かに揺らぐ港の灯を想わせる完璧な”おやすみソング”の完成形だからだ。
最後に、この物価高の時代に税込み2,200円というリーズナブルな価格設定には感謝しかない。欲しいものリストにも入れていなかったが、レーベルのことも考えると無理をしてでも早めに買っておく必要がある。
|
|
|
アルバム全体としての印象は”シャープ”で”スタイリッシュ”なのだが、個人的にはそれほど熱心にお薦めはしない。ということで★は3つ。
唯一、(これも個人の感想として)秀逸なのがオープニングの「リフレッシュ!」だ。
自分の中でのこの曲は”夏のリゾート・ソング”の定番だし、これまでも随分と活躍してくれた。世の中が好景気に浮かれていた頃、24時間働けていたビジネス・マンが束の間の休暇を楽しむための”応援歌”だと受け止めている。フリーウェイに加速しながら侵入する時のようなスピード感と、爽やかに吹き抜ける涼風の清涼感が何とも心地よい。聴いているだけで南太平洋に浮かぶ客船のデッキに佇んでいるみたいで、身体の芯から”リフレッシュ”できる。優雅な夏の過ごし方を提案してくれる佳曲だ。
プレイリストの候補曲としては、この曲を筆頭に崎谷健次郎の「夏のポラロイド」や南 佳孝の「Vacances Bleu」、佐藤 博の「アンジェリーナ」、角松敏生の「FLY-BY-DAY」辺りを合わせたい。ベタな選曲になるが、山下達郎の「SPARKLE」で始めて、後半の山場に大瀧詠一の「ペパーミント・ブルー」を持ってきてから、最後を村田和人の「Summer Dream」で締める、といった流れもいい。ついでに、季節は少し外れるが、伊勢正三の「9月の島」や稲垣潤一の「夏の行方」辺りのアシストもアクセントとして欠かせない。収録時間とにらめっこしながらカセット・テープを作っていた時代が懐かしい。
|
|
|
『プライヴェート・ダンサー』の30周年記念盤を買いそびれて仕方なく辿り着いたのが、この2004年発売の2枚組ベスト盤だったが、これが大当たりだった。
最初は新しい3枚組の方を考えていたのだが、資金繰りに行き詰まり、不本意ながら古い方を購入したのだが、20年前の編集盤とは思えないくらい音圧(音量)がしっかりしていて、年代の新しい楽曲は音もクリアで、経年による遜色は全く感じられなかった。
それ以上に素晴らしかったのが内容だ。自分の場合、ビルボード・チャートに登場するヒット曲とグラミーを逃した件のアルバムしか知らず、特に後者の”山姥”のような渋谷系の風貌としゃがれた歌声(大いに失礼)に翻弄されて、本質の”歌の旨さ”に気づかずにいたという、何とも間抜けなリスナーであったことに気づかされてしまった。
とにかく凄かった。演っている音楽もソウルやR&Bといった領域に止まらず、本物のロックにも軸足を置いていた。それも威風堂々と。厄介な暴れ馬にも真正面から立ち向かい、いとも簡単に乗りこなしていた。そのパワフルでエネルギッシュな歌声は、聴く者の心の奥底に届き、魂までも揺さぶる力を持っていた。
もちろん、個々の楽曲そのものも素晴らしいのだが、それらに命を吹き込んでいるのは、紛れもなく”ロックンロールの女王”、ティナ・ターナーなのだ。
|
|
|
カーペンターズといえば、少し苦味のある副菜も添えられたオリジナル・アルバムよりも、ヒット曲を目いっぱい詰め込んだベスト盤で十分楽しむことができるアーティストなのかもしれない。それでも、「イエスタデイ・ワンス・モア」をメイン・テーマに架空のラジオ番組というコンセプトでひと昔前の懐かしいポップスをメドレーで繋いだ『ナウ・アンド・ゼン』のB面のような圧巻のトラック集など、ドーナツ盤と同時進行でリリースされたオリジナルのLP盤も結構侮れない。
この淡い紫色のジャケットがメランコリックな本作には、シックで落ち着いたトーンの楽曲が並ぶ。控え目な素材に彩りと奥行きを与えているのが、カレンの軸のブレないしっかりとした歌声とリチャートのペンによる包み込むようなコーラス&ハーモニーだ。70年代が始まったばかりに届けられた珠玉の一枚と言っていい。
白眉は何と言っても無敵の「遥かなる影 (They Long To Be) Close To You」に尽きる。この70年代屈指の名曲は、四拍子なのにワルツのように聴こえる、魔法のポップス・チューンだ。ゆったりとしたテンポでフロアを踊りながら、ゆっくりと”憧れの人に近づきたい”と願う乙女心が唄われる。やがて優雅なひとときは少しずつフェイド・アウトしていくが、アルバムでは、終わったと思わせて再び登場するアンコール・テイクが加えられていて、幸福な時間をもう少しだけ楽しむことができる。これもオリジナル・アルバムでなければ味わうことができない特典だろう。だが、余計なことに、一部のベスト盤では<自分が人生で最初に買ったLPレコードも同じく>、この曲のロング・バージョンが収録されている。それはそれで"幸運なサプライズ"ではあるのだが…。
|
|
|
70年万博のパビリオン”○◇□△ロボット館”のようなジャケットが愉快だ。カラフルなスケルトンの巨大ロボットもフレンドリーで憎めない顔をしていて、”いずれは人間を支配する”といった警鐘も聞こえない。
静かにフェイド・インする二部構成のタイトル曲「アイ・ロボット」は、エネルギーを投入されて動き始めるAI内蔵のロボットの創生が描かれている(ように感じる)。その後の展開も、まるで近未来を舞台とするSF映画のサウンド・トラックを聴いているみたいに壮大でドラマティックだ。あちらこちらにアラン・パーソンズがエンジニアとして関わった『狂気』のプロトタイプを想わせる匠の技も認められるが、本作はそこまでの重苦しい空気感やシリアスな問題提起といったものはないし、人の心の奥に潜む”闇”を描いているわけもない。特撮映像を観ているようなミステリアスな美しさを描いた「核」や「皆既食」なども、いい意味で”軽い”。
“私はロボット”に対して”君は他人”と距離を置いていた関係性が、曲折の果てに”創世紀”に辿り着くのだが、待っている結末は”協働”なのか”支配”なのか、わからない。そんなに難しいことを考えずに、川の流れのようにゆったりと流れる音楽に身を任せて、総天然色のファンタジーを心ゆくまで楽しめばいい。それが正解だ。
|
|
|
極めて個人的な感想だが、このLP盤2枚組は、それほど悪くない。かつての神々しい名作群と比べると見劣りするかもしれないが、棄て曲はないし、内容もそれなりに充実している。特大ホームランこそないが、全員安打でしぶとく繋いで勝利を収めている。
一方で、持ち上げておいて言葉は悪いが、EW&Fがスペクトラムのスタイルに寄せてきたようにも感じる。太陽の化身たちは、宇宙から地上に降りてきて、我々に分かりやすい音楽を説いているみたいだ。冒頭の「明日への讃歌」など、硬派で辛口のファンクで最後まで押してくるのかと思いきや、後半のコーラス・パートなどは『魂』の「サタディ・ナイト」のようにポップで軽快にまとめている。ロックやAORに”魂”を売ったような楽曲も見受けられるが、だからかといって決して”緩々”ではない。2枚組となると全体が間延びしてしまいがちだが、色調の異なる17曲をコンパクトに刈り込んで繋げているので、聴いていて飽きがこない。痒いところにもちゃんと手が届いている。
最後は角松敏生の「Heart Dancing(あいらびゅ音頭)」のような盆踊りから始まる長尺のタイトル曲だが、途中で針を上げたくなるような冗長さはない。
セールス面で”成功”とは言い難い結果に終わったこともあって、次作では長岡秀星のイラストで天空を駆け巡る本来のスタイルに戻ってしまったが、このアルバムでの表情豊かなチャレンジは決して”失敗”に終わっていない、と思っている。
|
|
|
アイドル寄りの女性歌手(全員ではないけれど…)による日本語版カヴァー曲集で、いわゆる”トリビュート”的な企画盤としてリリースされている。真っ赤なハートがデザインされた72年のアルバム『ア・ソング・フォー・ユー』を想わせるジャケットも素晴らしい。
起用した女性歌手のセレクションも秀逸だ。楽曲との意外な組み合わせが思いがけない奇蹟の化学変化を起こしていたりする。個人的には、斉藤由貴と石野真子が"思いがけない"サプライズだった。どのナンバーも原曲への深い愛情が感じられて、聴いていて心が和むし、癒される。
本作は初期の楽曲に重心を置いているが、それでも選出されなかった名曲はたくさんある。個人的には「雨の日と月曜日は」と「愛は夢の中に I Won’t Last A Day Without You」は外してほしくなかった。どちらもポール・ウィリアムス絡みだが、70年代初めの頃の甘く切ない空気感を漂わせている佳曲だ。もしも続編があるのなら是非とも取り上げてほしい。その際、決まり事として既に唄っているシンガーとソング・ライター(竹内まりや大貫妙子など)を外すのなら、前者は伊東ゆかりか岩崎宏美、後者は今井美樹か石川ひとみ辺りでお願いしたい。もちろん、歌詞は日本語て、アレンジは原曲のままで。
|
|
|
重厚で陰鬱なアルバム、といった印象を持っているが、ずっと、このアルバムに惹かれている。
出発の「アレンタウン」はエネルギッシュだ。基幹産業の衰退の煽りを受けて、かつて栄えた工場の街は寂れてしまったが、労働者たちは生活の糧を失ってもこの街で前を向いて生きて行こうとしている。傾斜のきつい坂を登る機関車のように、彼らの熱量は衰えていない。昔、”この曲は自分の暮らす北九州を唄っているみたいだ”と呟いた者がいた。”鉄は冷えても、魂は熱いままだ”と伝えたかったのだろう。生きる力を与えてくれる”応援歌”だ。
2曲目以降は重苦しい楽曲が続く。依存と愛情の中途半端な距離感、過度に張り詰めた緊張感の中で容赦なく襲ってくる抑圧、封じ込めた心の奥で徘徊し続ける戦争の記憶、プログラムどおりに進行する恋愛物語、共有できない価値観を持つ者同士の共同生活…。どの状況から脱することも、目的地に辿り着くこともできない。
タイトで辛口のR&Rの後に続く終盤の3曲は、さらに迷走する。ここまでのタールのような重苦しい流れに呑まれていると、不協和音にも違和感を覚えなくなってしまう。”驚き”がないのではない。捉える側の感覚が麻痺しているのではないか、と思う。
村上春樹が小説『ノルウェイの森』の執筆中にリトル・ヘルプを貰ったというビートルズの『サージェント・ペパーズ・…』は、ビリー・ジョエルにも第9革命のような”人生の1日”のインスパイアを与えた。鼓笛隊に導かれて、時空の歪みのような”旋律の溶解”が始まる。針葉樹の深い森の中に引き込まれないように、スカンジナビア半島の上空を音速で飛行しなければならない。
アルバムの最後は穏やかな楽曲で幕を閉じる。魂を抜かれたような無表情の旋律は、終末の葬送曲のようにも聴こえる。空っぽの劇場に一人残されて、歌劇が始まるのを待っているが、肝心のオーケストラがいない。”安息”の向こうから聴こえる微かな「アレンタウン」のメロディに癒され、やがて、黄色いナイロン・カーテン越しに” 永遠の静寂”がやってくるのだろう。
重厚で陰鬱なアルバムだが、何度も聴ける”迷盤”であり、”名盤”だ。
|
|
|
おそらく初めてのベスト・アルバムで、代表曲が”ほぼ”網羅されている。”ほぼ”というのは、意図的に外されたと思われるものもあったりして、続編のために残したのだろう。反対に”これを選んだか…?”といった選曲もあるが、クリスマスの匂いのする「三人目のパートナー」などは、自分にとって嬉しいサプライズだった。
一つ疑問だったのは、「コンチェルト」の歌詞のリメイクだ。アルバム『乳房』では”お腹のすかした<彼女>を 入口で待たしたまま~”と唄っていたが、自分の記憶が正しければ、ここでは”<彼女>”を”<きみのこと>”に唄い直している。おそらく、入口で待たしているのは<きみ>=”恋人”なのだろう。関西では女性の恋人のことを<彼女>と言うが、三人称だと伝わり難いと思ったのかもしれない。
それとは別に、この楽曲もそうだが、歌詞に”仕事”とか”働く”といった言葉が出てくると、いい意味で電撃が走る。例えば「POWER」には”わき目ふらずに 働き続けたい”という決意表明がある。このフレーズを聴いているだけで、大きな”力”を貰えたような気がして、元気が湧いてくる。
そういえば、大貫妙子の「突然の贈りもの」にも”仕事”が登場する。最後のところで”皆とはじめた 新しい仕事にもなれて~”と唄われるが、何気ない言い回しだが、頑張っている様子が覗えて、何となく微笑ましい。
|
|
|
男女混成のロック・バンドは他にもあるが、主力の男女メンバーが”自ら曲を作り、自ら歌う”といったスタイルは、70年代半ば以降のフリートウッド・マックくらいしか成功例を知らない。しかも、飛行機から宇宙船へと進化した”ジェファーソン号”には老若男女が乗り込んでいて、ほぼオムニバス・アルバムのように個性的なパーツが巧みに組み合わされている。まるで”足の数は多いが、赤いハート型の胴体は一つ”、といった感じだ。
勢いのある俊足ロックでスタートしたかと思えば、一転、マーティ・バリンの”泣き節”がハート悲しく登場する。いきなりのシフト・チェンジだが、ここで切り札を出せる辺りがこのアルバムの凄いところだ。シングル・バージョンは10ccの「アイム・ノット・イン・ラヴ」同様、ラジオ向けにエディットされているが、この曲の良さはフルで聴かなければ伝わらない(と思っている)。この曲と同じ匂いのするエアロスミスの「ドリーム・オン」も、この時期に大ヒットしたセンチメンタルな”泣き節”バラードだ。ちなみに、本作にはもう一曲、姉妹曲ともいえる「タンブリン」が用意されていて、こちらも聴く者のハートを悲しくさせる”奇蹟”の佳曲だ。
アルバムには陽気なフィドルのリード曲が存在感を示しているが、他のストレートなロック・ナンバーにも弦の音色が絡んでいて、乗組員総出の”プレイ・オン”がタコ足盤の一体感を作り出している。何とも”愛・ガ・リ・マ・ス”な一枚だ。
終盤にはスティクスの「永遠の航海」のような成層圏を突き抜けていくプログレッシヴなインストにもチャレンジしている。後にマーティ・バリンが唄った「ランナウェイ」では、地球を飛び出して、壮大な宇宙の彼方まで”逃亡”している。
|
|
|
表題曲でもある「ミント・ブリーズ」は、個人的な”夏”の和モノを集めたプレイリストでクール・ダウンさせてくれるインスト曲として欠かせないナンバーだ。アタックの強いTokyo Ensemble Labの「Lady Ocean」やカシオペアの「タッチ・ザ・レインボー」などとは異なるアプローチで、ミディアムな鈴木 茂の「コーラル・リーフ」や松任谷正隆の「イマージュ」などよりもソフトでジェントルな、”涼”を届けてくれる楽曲として貴重なアイテムとなっている。
今田 勝 との出逢いは『モーニング・ドリーム』という”裏”(あるいは”次点”)ベスト盤に遡る。ラテンの匂いの強いハート・カクテルふうの楽曲やジャズに特化した”表”ベスト盤を聴とは違い、聴き心地のよい”イージー・リスニング”感が漂う小品が集められていて、その延長線で入手した本作のメロディアスな”夏色”に魅せられてしまった。
爽やかに通り過ぎて行く夏のよそ風を深呼吸するように吸い込めば、ライト・グリーンの仄かな薄荷の香りを感じることができる。自分の中では、村松 健 のアルバム『緑の想い』の空気感とも共鳴している。
|
|
|
初打席で「アンダーカヴァー・エンジェル」という特大ホームランを放ち、その後、疾風のように去って行った(とはいえ2枚目のアルバムも出している)アラン・オディの美味しい料理が楽しめるアルバムだ。レシピはアラン・オディ自身のものだが、キッチンには愉快な仲間達が集い、カジュアルだがしっかりとした味付けで調理されている。ドクター・フックのような惚けた調子の楽曲もあるが、真摯に音楽に向き合った佳曲もあって、大衆酒場で誰もが口ずさめる歌謡曲や場末の女性コーラス隊を絡めたコミカルなポップ・ソングに浸かっているわけもない。“棄て曲なし”とは言い難いが、”拾い物”もいくつかあるので、”★”は4つとしたい。
ソング・ライターとしての実績もあり、本作でも彼自身のペンによるヘレン・レディのシックな全米No.1ヒット「アンジー・ベイビー」を自ら歌っている。余談になるが、ライチャス・ブラザーズのノスタルジックな「ロックンロール天国」も彼の作品というのだから音楽レシピのストックは豊富だ。
偶然だが、同じ頃、ソング・ライターのピーター・マッキャンも、初打席初ホームランとなる「恋人たちの午後」を大ヒットさせ、1作目となるアルバムでは彼自身のペンによるジェニファー・ウォーンズのスマッシュ・ヒット「星影の散歩道」を自ら歌っている。少し脱線するが、このアルバムのラストを飾る「If You Can't Find Love」は、リッチー・ヒューレイの「I Still Have Dreams」を想わせる、聴く者に勇気を貰える佳曲だと思っている。
|
|
|
世間ではそれほど評価もされさない平凡なアルバムでも、その人にとっては大切な想い出とリンクする”特別な1枚”というものがある。自分にとって本作は、そんな”特別な1枚”だ。長年CD化を待ち望んでいたが、願いは届かず、諦めかけていたところに朗報が飛び込んできた。埋もれたLPレコードに陽を当ててくれたのは、やはりBIG PINKレーベル(VIVID SOUND 配給)だった。
温もりのあるやさしいメロディを繊細な歌声で紡いでくれたメアリー・マッグレガーの「過ぎし日の想い出」が全米No.1に輝いたのは、時間が今よりも穏やかに流れていた1977年2月のことだった。少し経って、この曲の収められたデビュー・アルバムの発売を知り、セピア・カラーのモノクロ写真がプリントされたバースディ・カードを想わせるジャケットに惹かれてLP盤を購入した。
アルバムの最後を締めくくる「過ぎし日の想い出」を凌ぐ佳曲と出逢うことはなかったが、それでも、オープニングの「ママ」に始まる9曲は、昔ながらの焼き菓子のような懐かしい味がした。全体のトーンも落ち着いていて、楽曲たちはどれも控え目で、純朴で、ナチュラルで、やわらかな春の陽射しのように1977年の穏やかに流れる時間に寄り添ってくれていた。
そんなわけで、自分の評価は”★”五つだが、それは決して客観的な評価ではない。名曲「過ぎし日の想い出」は、ヒット曲を集めたコンピレーション盤で楽しむことができるので、温もりのあるやさしいメロディとメアリー・マッグレガーの繊細な歌声に癒されたいのなら、そちらの編集盤をお薦めする。それでも、昔ながらの焼き菓子のような懐かしい味をお求めなら、この愛すべきオーガニックな本作を聴いてみていただきたい。
|
|
|
硬派なジャズ・ファンクを下敷きにした、ほぼインストゥルメンタル・ナンバー「ピック・アップ・ザ・ピースス」の印象が強烈なAWBが、黒いジャガー印の重い鎧を脱ぎ捨てて、洗練されたアダルト・コンテンポラリーにシフトした改作アルバムである。EW&Fを彷彿とさせるオープニングからノリに乗っている。続くミディアム・スローなナンバーのエッセンシャルはエアプレイだ。だが、決して世の中のトレンドに”魂を売った”わけではない。デヴィッド・フォスターの力を借りた暗黒、いや、新境地への挑戦だと受け止めたい。
収録された楽曲には痛快な新風ばかりだが、アルバムの顔の一つとなっているのが「レッツ・ゴー・ラウンド・アゲイン」だ。流れるような回転(ラウンド)は、モノクロからカラーへと装いを一変したダンスフロアで映える楽曲として、ミラーボールのように”輝いて”いる。後にKANが80年代のディスコ・ブームをノスタルジックに綴った「DISCO 80's」でコラージュしたのは、間違いなくこの曲だと確信している。それほどダンサブルでスムーズな”ディスコ・ミュージック”の定番として完成されている。
とにかく疾走は続く。休みなく。後半の「ヘルプ・イズ・オン・ザ・ウェイ」など、ここぞという場面で琴線のメロディを持ってきて、リスナーの心をしっかりと捉えて離さない。最後はバラードで締めるのかと思わせて、どこまでも"輝き"続けて大空へと舞い上がる。何とも爽快なアルバムだ。
CDにはボズ・スキャッグスでヒットした「ミス・サン」が(カヴァー曲として?)追加収録されているが、リズム・テンポやアレンジも含め、全くの瓜二つに仕上げられている。決して”魂を売った”わけではない。
|
|
|
ジェネシスというバンドとは少しばかり距離を置いている。その証拠に、3種類の複数組ベスト盤でお茶を濁している。オリジナル盤で棚にあるのは『アバカブ』だけで、それ以前のプログレッシヴなアルバムには一切手をつけていない。
本作も3枚組というボリュームだが、1枚目がヒット曲中心のコマーシャルな入門編で、2枚目が少し難易度を上げた中級編、そして3枚目が難解かつ冗長な大作を集めた上級編といったヒエラルキー構成となっている。進学校のクラス分けのようなレベル別の編成だ。2枚目で「ついて来れるか?」と訊かれ、3枚目では「お前、本当に俺たちの音楽が解かるのか?」と試される、3枚目は軽い気持ちで踏み入れてはいけない領域だ。
例えは良くないが、シカゴ(Chicago)でいえば、1枚目が『Chicago Ⅸ Greatest Hits』で、2枚目には『Ⅱ』の「ぼくらの…」シリーズや、『Ⅵ』に収められていた陰鬱な「ハリウッド」、『Ⅶ』からはファンキーな佳曲「ママが僕に言ったこと」などを集めて小テストされ、3枚目になるとデビュー盤の「1968年8月29日シカゴ、民主党大会」や『Ⅶ』の「エアー」からの「悪魔の甘い囁き」を聴かせて本物のファンかどうかを見極める、といった感じだろう。ビートルズなら「レボリューション 9」や「ブルー・ジェイ・ウェイ」、「ユ―・ノウ・マイ・ネイム」辺りが並べられるのかもしれない。ただし、決定的に違うのが、これらがジェネシスではベスト盤収録曲として成立しているということだ。
自分はどうかと訊かれれば、2枚目の途中で方向感覚を失ってしまい、3枚目に至ってはフルで聴き通すことができなかった。完全な落第生だ。まだ追試に間に合うのかもしれないが、難攻不落な3枚目を突破するにはいささか歳をとり過ぎていて、チャレンジする力も失せてしまっている。3人が残る以前のアルバムを聴く資格はない。
|
|
|
とにかく”エグい”2ndだ。デビュー・アルバムも素晴らしかったが、本作はそれを悠々と超えてきた。
1曲目の「心のきずな」から独特の”エグい”世界観に圧倒される。まるでベテラン俳優の演じる”一人芝居”を観ているように、もの凄い音楽が聴き手の心の奥深く入り込んできて、魂までも揺さぶっていく。大作「ウェスタン・スロープ」もそうだが、楽曲の展開が目まぐるしくて、速球と変化球の投げ分けに全くついて行けず、ただただ翻弄されている。それも心地よい翻弄だ。自由なのだが、規則性を残している。”ジャズ”ではない。アシッドでプログレッシヴな”現代音楽”だと受け止めている。
「リヴィング・イット・アップ」も”静”と”動”の二つの顔を持つドラマティックな佳曲だが、他の追随を許さない前述の2曲に比べると、はるかにポップな印象を受ける。リードの旋律は穏やかで親しみやすいし、歌声はやさしくて温もりがある(ように感じる)。最後には歌姫の華麗な輪舞を想わせるクライマックスが用意されていて、6分半のショート・ムーヴィーは幕を閉じる。
アルバム中盤のスローな「スケルトンズ」や「ラッキー・ガイ」も、決して休ませてはくれない。凪のような静けさの中にも研ぎ澄まされた”緊張感”が潜んでいる。”安息”は、むしろ「スロー・トレイン・トゥ・ペキン」の気の置けないトラッドな楽曲の中にあるのかもしれない。前作のゆっくりと走る夜汽車とは違い、ガタゴトと疾走する賑やかな列車だが、乗り心地はよい。
というわけで、ジャケットの永遠の一コマを切り取った白黒写真も含め、彼女の渾身の1枚だと思っている。傑作だ。
|
|
|
発売元は“P-VAIN”のはずなのに“Light Mellow”というレーベル名となっていたり、大手サイトが発売前の注文を受け付けていなかったりと、謎の多いリリースなので、本当に発売されるのか不安を抱いている。
クリス・スミスのアルバムは、デビュー盤と思い込んでいた『REAL THING』に始まり、次の『BACK TO YOU』と、それに続く『LET THE BALL ROLL』まで、それぞれのリリース時に買い揃えてきた。3枚とも個々の楽曲の質が高く、何度聴いても飽きることはないアダルト・コンテンポラリーの的を射た良盤だ。
最初に入手した『REAL THING』のジャケットが自主制作を想わせる工作員のような顔写真に戸惑い、1曲目の変則なグルーヴ感にも馴染めなかっただが、2曲目以降の安定したラインナップがメジャー作品を凌ぐ出来栄えだったことで、結果、大きな収穫を得た。次作のおちゃめなジャケットの『BACK TO YOU』からはジャズの風を入れ、宇宙から地球を眺める『LET THE BALL ROLL』でも楽曲の質を上げていった。
それ以降、音沙汰がなかった(自分が見つけることができなかった)が、ここに来て、鳴り物入りの”デビュー・アルバム”が発掘されたのだ。これは何としても入手しなければ、と意を決し、ネット購入を受け付けているサイトでオーダーしてみたのだが…。タワー・レコードをはじめとする大手サイトの違和感のある対応に気持ちがザワついている。
|
|
|
自分の中での村松 健は、昭和から平成に繋がる時代を”旬”と捉えている。
音楽の加速について行けなくなった当時、”癒し”と”安らぎ”を届けてくれたのが、”村松スタイル”ともいえるリズム・マシン(違っていたら失礼)を相棒に、二人三脚で紡がれる童謡のような親しみと温もりのあるピアノの旋律だった。
このアルバムはその頃のセレクト集だが、サブ・タイトルにあるように、フュージョンに寄っている。1枚目は、初期2枚のアルバムを中心に、都会的で洗練された楽曲で構成されている。個人的な出色は「HYDRANGEA -into the morning dew」だ。N〇KのFM番組”公園通り21”のメイン・テーマとして使われていた。
個人的な”お気に入り”は2枚目に多く収録されている。アルバム・カラーが澄んだブルーからナチュラルなグリーンへと移行した時期のオーガニックな楽曲たちだ。爽やかな音風景の中に”和の匂い”を感じる「水平線の見える部屋」や、唄いながらペダルを漕いでいる「スピード -自転車旅行-」、”別れ”の切なさをやさしく包み込み”出逢い”のときめきに眩い陽光を注ぐ「出逢いと別れ」が該当する。
もしも”~EASY LISTENING TRACKs”として続編が企画されるなら、取り上げてほしい楽曲がある。突然の夕立ちと蝉時雨がシンクロする「レインフォーレスト -ひぐらしの森で-」や、穏やかな冬景色をスケッチした「SCHI S\HEIL -スキーに幸あれ-」、緑の草原をゆっくりと散歩する「春の野を行く」や、”植物図鑑”を想わせる楽曲の中から、フィトンチッドに溢れる「フローティング~睡蓮の開く朝」と「ムラサキツユクサの影」も忘れないでほしい。
軌道は外れるが、アルバム『子供の時間』に収録されていた「夢のほとりで」も素晴らしい。ミディアム・テンポの安定飛行が続く冗長な楽曲だが、途中に幸せそうな会話のコラージュやB・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」のフレーズがさり気なく添えられていて、10分超という時間の経過を全く感じさせない、クリスマスの寒い夜を暖めてくれる逸品だ。
ベスト盤もありがたいが、欲を言えば、初期の瑞々しいオリジナル・アルバム群の高音圧(音量)化での再発を熱望する。
|
|
|
“メロウ”で”ロマンティック”なアダルト・コンテンポラリーのスタイルは本作が確立した、と言っていい。シルクのように滑らかな大人のサウンドはボズ・スキャッグスが先行だが、ボズは、どちらかといえば硬派なロックに寄っていた。ボビーは甘美で艶っぽいR&Bに寄っている。ついでに言えば、確立したのはスタイリッシュな音楽性だけではない。タイトルに準えた影絵や夜空に描かれた月のイラストも、後の彼のジャケット・デザインのスタンダード(標準仕様)となった。
先行シングルでもある実質的なタイトル曲の「風のシルエット」がラジオから流れた当時、不覚にも黒人のニュー・フェイスを疑わなかった。曲調や歌唱法だけではない。スマートでエレガントなベース・ラインや、コンダクターのように歌に寄り添うブラス、仄かに揺らぐキーボードの音色といったアレンジも、極上のR&Bのテイストそのものだったからだ。
途中EW&Fっぽいインタールードやハミングだけの洒落たナンバーを織り交ぜた振れ幅の広い楽曲群にあって、アルバムの一番の聴かせどころとして絶賛したいのが冒頭の「スペシャル・トゥ・ミー」だ。入りはボズ・スキャッグスの「スティル・フォーリング・フォー・ユー」よりもギアを踏み込んでいる。タイトなリズムとウェットな旋律が絶妙にブレンドされていて、心地よいグルーヴ感を加速させながら、ミドル・オブ・ザ・ロードを一気に駆け抜けて行く。ストリングスとホーン隊のコラボレーションも息が合っているし、とにかく、すべてが自分にとって”特別”なのだ。
余談だが、大らかな佳曲「キャント・セイ・グッドバイ」は、後にジム・フォトグロがリリースした「フール・イン・ラヴ・ウィズ・ユー」を想わせる。もちろん、フォトグロはこの曲を焼き直したわけではないが、伸びのあるサックスがミディアムな曲調に合っていて、良質のポップ・ソングに仕上げられている。
|
|
|
アルバムとしての”トータル性”は影を潜めているが、個々の楽曲は良質で聴き応え十分なので、作品としての完成度は高いと思っている。女性ヴォーカルをメインに据えるなど、スタイルの違いを楽しむことができるアルバムでもある。”トータル性”は先の『運命の切り札』で楽しめばいい。
相変わらず”音”の解像度は高く、研ぎ澄まされているし、個人的な印象として、いい意味で”軽い”(つまり”重くない”)。緊迫感のあるインストゥルメンタルもあるし、天国にいるような安息から不穏な”兆し”が毒牙のように覗く楽曲もある。ジャケットの”肖像”にもサイレントな”棘”が仕組まれている。こちらの方は、サウンドの”軽さ”を補うかのように、いい意味で”重い”。
個人的な白眉は、アルバムのラストを飾る「願い」だ。FMの深夜番組でこの曲に出逢い、その美しくも儚いバラードに一瞬で心奪われてしまった。惹きつけるのは、何といっても英国的な美しい旋律だ。精巧に創られた模型のように、仕上がりが完璧に近いほど、美しくて、哀しい。楽曲の最終盤で繰り返されるタイトル・コールが、心の扉を叩き続けているようにも聴こえる。後の「アンモニア・アヴェニュー」や組曲「運命の切り札」の系譜ともいえる、英国的な耽美な名曲だと思っている。
|
|
|
廃墟のような室内とその窓から見える風景が実に明るく鮮やかで美しい。半ば”ジャケ買い”で購入したアルバムだが、その内容はジャケット同様、明るく鮮やかで美しいものだった。
トミ・マルムに関する情報は専門家に任せるとして、アルバムの印象としては、プロデューサーが自分名義で制作したコンピレーションと捉えている。クインシー・ジョーンズのアプローチを連想するが、どちらかといえば冨田恵一のラボラトリーに近いものを感じる。
1枚もののCDだが、ボーナス・トラックを含めた全17曲という内容は、アナログ・レコード時代の2枚組LPに相当するボリュームだ。冒頭の”第2の波”から大作を匂わせる。たまたま同じ時期に聴き返したビー・ジーズの『オデッサ』のように、楽曲の編成は異なるが、長短のインストゥルメンタルやインタールード的な繋ぎ、タイプやカラーの異なる楽曲を巧みに配置するなど、奥行きと拡がりのあるアルバムに仕上げられている。
”サーフィンからアヴァンギャルドまで”とはいかないまでも、アダルト・コンテンポラリーの枠組みの中での振れ幅は大きい。楽曲ごとにヴォーカル・パフォーマーを変える手法も、自分名義のアルバムを制作できるプロデューサーの特権だ。とはいえ、自身がデザインした衣装に合ったモデルの選択はしっかりとできていて、敏腕プロデューサーの実力が如何なく発揮されている。スタイリストのように、人に合わせて衣装を選んではいない、と思っている。
全くの余談だが、途中、竹内まりやを想わせるフレーズが聴こえたような気がした。たぶん、それは”空耳”に違いない。何せ、自分は、かぐや姫の「神田川」の弦楽部分を聴いてビートルズの「イエスタデイ」を思い浮かべてしまうくらいの粗末な耳の持ち主なのだから…。
|
|
|
ずっしりとした”重み”を感じるアルバム、というのがこのアルバムに対する個人的な印象だ。原液を薄めてあるのに、それでも結構”濃い”。だが、苦い薬がよく効くように、パワフルでミラクルな上質の果汁100%は五臓六腑に染み渡る。
冒頭のコーラスを聴いた一瞬で宇宙の果てまでワープする。うねるように波打つベースに揺さぶられながら、天空へと一気に駆け上がり、シャッフルされてコーラスのループへと戻される。「トゥー・ハイ」はその繰り返しだ。いきなりもの凄い楽曲からアルバムは始まる。
途切れることなく静寂が訪れる。宇宙空間のようでもあり、深う海の底のようでもある”内なるヴィジョン”だ。ここは本当に「愛の国」なのだろうか(?)。わからない。続く大都会の日常に蔓延る”抑圧”と”抵抗”を描いたドキュメンタリーのような「汚れた街」が終わると、決してプラトニックではない「ゴールデン・レディ」が待っている。後半の高揚は後の「アナザー・スター」のリフレインを想わせる。
レコードを裏返すと、このアルバムで特に惹かれる「ハイアー・グラウンド」が始まる。この曲の魅力を引き出してくれたのが大都会”東京”だ。行き交う人の波に揉まれて感じた”緊張感゛が、この曲の躍動するリズムとシンクロしてしまい、頭の中を旋回し続けたのだ。続くインタールードのような「神の子供たち」にもしっかりとしたファンクのスピリットが宿っている。それに気づいたのは、このアルバムと出逢って相当の年月が経ってからだ。楽曲の余韻を遮るように耽美なバラード「恋」が始まる。ジョン・レノンの「ラヴ」よりも「オー・マイ・ラヴ」に近い、静かなエモーションを感じさせる佳曲だ。そんな”恋”の美しさに陶酔していると、突然、ラテンの旋風が吹いてくる。「くよくよするなよ」だ。自信を失くして折れそうになった心を力強く励ましてくれる。やがて熱量を持ったカーニバルは終わる。最後に穏やかに始まる「いつわり」は、軽いゴスペルのようにも聴こえる。ゆったりとした旋律に乗せて、呪文のように” He's Misstra Know It All”と繰り返され、そのうちに”真実”と”嘘”、”善”と”悪”の区別がつかなくなってくる。
もの凄いアルバムだ。
|
|
|
これ以上掘っても何も出ない、ゴールド・ラッシュ終焉後の選択肢は2つある。埋もれている鉱物の採掘か、新たな鉱脈の発掘か。前者に取り組んでいるのが”Big Pink”で、後者を進めているのが”P-VINE”だ。それぞれ得意とする分野は違うが、どちらもレアな作品中心に、CDとして届けてくれる点で共通している。
とりわけ”P-VINE”は、個人的な印象として、日本で”AOR”に分類される都会的でエッジの効いた新鋭アーティストを多く取り上げていて、70年代後半から80年代にかけて確立されたコンテンポラリー・サウンドのフォロワーたちが創る”現在進行形”のプロトタイプが目につく。もちろん、音楽性はそれぞれ違っているのだが、ルーツやDNAを受け継ぎ、共有している分、トーンやベクトルは類似している。どれを選択するかは個人の”好み”の問題だ。
さて、本作が自分にとって大きな収穫であることには違いない。シックなモノクロのジャケットだが、内容はカラフルで充実している。同類の作品同様、洗練されたスマートでスタイリッシュな空気を引き締めるように、歌唱は”攻撃的”だが、そんなアグレッシヴさが耳に心地よい。あくまでも個人的な”印象”だ。
本作にはムラがない。タイプの異なる楽曲で構成されているが、どれもしっかりと作られていて、少しも手を抜いていない。いわゆる”棄て曲”がないのだ。これも個人の”好み”だが、例えば、スティーリー・ダンを意識し過ぎて複雑なコード進行を多用したり、玄人受けを狙った難解な仕掛けを施したりせず、ストレート主体のピッチングに徹している。
唯一の問題はラスト2曲だ。
おそらくアルバムの本来の終演は「REAL LOVE」だろう。曲の入りからしばらくは、この曲がドゥービー・ブラザーズのカヴァーとは気づかなかった。カーペンターズの「涙の乗車券」のように全く別の切り口で仕上げられているが、原曲の持つリアルな雰囲気は損なわれていない。個人的には素敵なサプライズだった。
あとに続く2曲はコメントが難しいので、ここまでとしたい。ある意味、”別物”として聴きたい。
|
|
|
個人的に岡崎友紀といえば、テレビ・コメディの“おくさまは18才”に主演し、歌番組の司会もやっていた”アイドル系タレント”というイメージが強い。歌手としても最初はキュートなキャンディ・ポップスが中心だったが、少し落ち着いてきた頃にはユーミンの「グッド・ラック・アンド・グッドバイ」といった切ないバラードも唄っていた。
自分の中では”アイドル”の領域だったので、2004年に本作がCDリリースされた時も、正直、距離を置いていたのだが、発売当時、タワーレコード小倉店で何気に本作を視聴し、その内容の素晴らしさに不覚にも圧倒されてしまった。
オープニングの「S-O-O-N」から弾けていた。歌声こそ初心者マークが外せない危なっかしさを感じたが、楽曲は極上のアダルト・コンテンポラリー仕様の特級品だった。特筆すべきはシャープでスマートなアレンジだ。小気味よいブラスとベースのブレンドが絶妙で、軽快に跳ね回るギターのファンタスティックでワンダーランドなエンディングが乾いた西海岸の涼風を届けてくれた。
続いて流れてきたのは心地よい”ドゥービー・サウンド”のルールに則った「SWEET JOKE」だった。M・マクドナルドというよりも、それをリスペクトしたロビー・デュプリーのテイストに近い。A面の2曲目には必要不可欠な楽曲だ。
中盤の「CAFE B,H」辺りは、タイトルこそトニー・シュートの「CAFE L.A.」を想わせるが、グイグイと押してくるラッシュライフでスノッブな雰囲気は、ライトでメロウなスケープとは全くの”別物”だった。攻めるギターもジェイ・グレイドンふうで切れがいい。
全体的に王道を征くAORのエッセンスを余すところなく”和”の様式に落とし込みながらも、所々にオールド・ファッションドなポップスやボサノヴァを下地にしたシックな楽曲をミックスするなど、最後まで手を抜くことなく、完璧な”和製AORアルバム”に仕上げている。音楽への向き合い方が"ストイック"だし、"真摯"だし、"妥協"といったものが微塵も感じられない。
本作は、同時代の”時流に乗って海外録音してみました”的なスタイル先行のアルバムとは明らかに一線を画している。岡崎友紀というアーティスト名や小悪魔的なショットのジャケットに騙されてはいけない。間違いなく、”買い”だ。
|
|
|
春爛漫。ドーナツ盤やカセットテープの時代が懐かしい。
ほぼ平等に三分割された合作アルバムには、古き良き時代のアメリカン・ポップスのエッセンスが宝石のように散りばめられている。どの楽曲も、どこか懐かしい香りを漂わせながらも、中味は80年代している。
前半をリレーする若い二人は、それぞれにハイエンドな楽曲を書き下ろし、レコーディングに臨んでいる。楽曲のクオリティの高さをみれば、二人がその持てる力を十二分に発揮していたことがよくわかる。まるで、ジョン・レノンに"いい曲だ"と認められたくて頑張っていたポール・マッカートニーのように…。
終盤は大御所の登場だ。前作のプロトタイプの作品が並ぶ中、締めくくりにはコミカルでカラフルなハニー・トラップ型ドタバタ恋愛活劇が用意されている。テキーラの紅(あか)が完熟オレンジに変身する様子も覗えて、とても痛快なラヴ・コメディに仕上げられている。恋のレーザービームに照射されて、マシンガンのように高鳴る色男の心臓の鼓動が聞こえてきそうだ。
今では叶わないが、Vol.3を期待していた。
大瀧さんのデモ・テープが残っているのなら、流行りのAI加工を施して(楽器音と歌声を分離して)、” Niagara Triangle”の最新作が創れる(生成できる)のを密かに期待している、のだが…。
|
|
|
ビリー・ジョエルのライヴ盤に”ハズレ”はない。しっかりと声も出ているし、エネルギッシュな演奏も含め、パフォーマンスは完璧だ。飛ぶ鳥を落としていた頃のエルトン・ジョンのように、安心して”聴ける”。
唯一気になる点があるとすれば、録音状態だ。テープの劣化よりも、そもそもスタジオとは異なるホールでの一発録りなので、マイクやレコーダーといった機材によって音質は左右されてしまう。1970年代の公演であれば、音の解像度はそれなりのものとして受け入れなければいけない。反面、若い頃の張りのある歌声が楽しめるので、よほどの海賊盤レベルの劣悪な録音でない限り、聴き得感は十分にあると思う。
さて、本作だが、いつもどおりのハイ・パフォーマンスで、釣り揚げられたばかりの活きのいい魚のようにステージ上で躍動している姿が目に浮かぶ。録音状態も意外と(予想以上に)クリアで良好だ。
余談だが、自分は”ライヴに行かない派”なので、ライヴ・アルバムはオリジナル盤とは”別物”と捉えている。なので、スタジオ収録とは異なるアレンジや演奏スタイルを期待してしまう。一方、”ライヴに行く派”の友人などは、オリジナル盤で慣れ親しんだ歌唱や演奏を”生”で楽しみたい、と言う。つまり、原曲をステージで忠実に再現してほしいらしいのだ。ビリー・ジョエルの場合、基本、後者だが、そのライヴ・パフォーンスは、スタジオでは収録しきれない”生”の”迫力”を伝えてくれている。
|
|
|
裏ジャケットと連鎖して”夜”のホテルをイメージさせるが、そこには映画『シャイニング』のような得体の知れない”恐怖”はない。
タイトル曲も”夜の静寂”をウォッチしているが、視界を遮る深い霧のような”不吉”な空気はきれいに吹き飛ばされ、ドゥービー・ストリートで”闇の世界”から解放される「サムワン・スペシャル」のようにクリアだ。以降、「イージー・ドライヴァー」から「ダウン・ダーティー」へと軽快で視界良好なロック・ナンバーが続く。
レコード盤を裏返すと、心に残る爽やかな佳曲が待っている。エヴァ―ラスティングな「二人の誓い」は、オープニングのコーラスから涼風が吹き抜ける。この前向きな楽曲にはいつも励まされる。憂いのある歌声のスティービー・ニックスをパートナーに選んだのは冒険だったと思うが、結果、歌声のコントラストがはっきりしていて、起用は”大正解”だった。続く「ウェイト・ア・リトル・ホワイル」は、エルトン・ジョンの「ライティング(歓びの歌をつくる時)」同様、小鳥の囀りが聴こえる”初夏の朝”が似合う。DAPのプレイリストでは”Morning Selection”として活躍している。最終コーナーを回った辺りから再び”夜の影”が忍び寄るが、決して怪しい迷宮へと誘われることはない。最後は振り出しの”夜の静寂”へと戻って行く。
ケニー・ロギンスはこのアルバム以降、映画の助けも借りながら、”明日へ向かって”大きく飛躍していくことになる。
|
商品詳細へ戻る