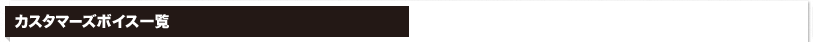
Grieg: Piano Concerto, etc / アレクセイ・ズーエフ、他
|
|
冒頭、ドラムロールから一転、ピアノが最低音のAを目掛けて大瀑布のようになだれ込むところで、ズーエフは九十九折のように何段階か止まる。その時点から、クセのあるテンポ設定が鼻につく。妙なところで溜めるのだ。オケも、録音のためかモサッとした響きで、北欧の清涼感とは程遠い。結局、ピリオド楽器を使って好き勝手にやっている、という印象しか残らなかった。ルプー&プレヴィン盤が恋しい。星3つは希少価値に対して。
|
商品詳細へ戻る
楽長さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
ロシアのショパン、開陳!
年を追うごとに神秘主義のアブナイ方向にイッちゃったスクリャービンであるが、若い頃はラフマニノフと覇を競うほどのコテコテのロマン派だった。このことがよく窺えるのがこの1枚。
大柄でオクターヴを鷲掴みしてしまうラフマニノフに対して、スクリャービンは小柄な身体つきだった。しかしその分、細やかな指遣いで陶酔的な音楽を紡いでいったのである。
ショパンやラフマニノフがお好きな人、《法悦の詩》や《プロメテウス》なんかで拒否反応を示してしまった人、スクリャービンのロマンティシストな一面を知ることが出来ますよ。
|
|
|
ラフマニノフの盟友、ロマンと技巧の融合!
メトネルはラフマニノフの盟友として知られ、作風もよく似ている。つまり溢れんばかりのロマンを超絶技巧に落とし込むという具合だ。
特に第2番が聴き物。競合盤としてはアムランやトーザーが知られているが、彼らより速いテンポでキレッキレのテクニックを見せてくれるのが、このデミジェンコだ。
ラフマニノフ好きの人ならハマること請け合い。同シリーズのボルトキエヴィチ共々、心から推薦したい。
|
|
|
忘れられたロマンが蘇る!
アレンスキーもさることながら、ボルトキエヴィチが秀逸。大体、無名な作品というのは、キャッチーなメロディを作れなかったり、仮に作れたとしても構成がグデグデで冗長だったりするものだ。だがボルトキエヴィチは、ラフマニノフもかくやと言わんばかりのロマンティックなメロディを惜しげもなく紡ぎ、しかも主題の展開や回帰などをして構成的にもしっかりした作品を書いているではないですか。
特に第1楽章第2主題が究極の美メロ! これが回帰するところなどロマンの極み。第3楽章にもちゃんと関連付けをして、抜かりがないところも憎い。
演奏、録音も申し分ない。ボルトキエヴィチにご興味の方は、交響曲第1番に赴かれると吉。チャイコフスキーの交響曲第4番に酷似した構成と、ラストの《神よツァーリを護り給え》に狂喜すること必定!
|
|
|
父子鷹の競演!
レニングラード・フィルと言えば当然ムラヴィンスキーの名が挙がるが、彼の来日公演盤の多くは、「歪む、割れる、揺れる」の三拍子揃った低音質、おまけに彼方此方でゴホゴホと咳払いが混入するという代物であった。
当BOXのうち、父君アルヴィド氏の方は1970年の録音ということで、音質に一抹の不安があったが、聴いてみてビックリ。中々の高音質である。
ところが、レニングラード・フィルにしては珍しく、何故か低弦右側の通常配置なのだ。ムラヴィンスキーは、有名なDG盤のチャイコフスキー:後期三大交響曲を除いて、ほぼ両翼配置(対向配置)を採用していたはずである。
演奏自体は申し分なく、金管が突き刺すように響く辺りは流石と言える。もっとも、チャイ5の第3楽章でclが盛大にリードミスをお見舞いするところがあり、ズッコケそうになったが…。
対するマリスの方は両翼配置。ただしチャイ4のカッティング・レベルがかなり低く、第3楽章のピチカートなど、ぐんと音量を上げないと音が飛び込んでこない。
だが演奏自体は燃焼度が高く、終楽章ラストなどスヴェトラーノフと互角の畳み掛けを施す。白眉は《幻想交響曲》で、両翼配置の面目躍如たる音響と、ヒンヤリとした狂気が入り混じった怪演である。こちらは音質も良好。
総じて、本番一発撮りの故の瑕疵も無きにしも非ずだし、録音やオケの配置に多少の不満もある。だが、燃焼度の高い演奏が披瀝されているという点を加味して、星4つとしておこう。
|
|
|
N響、ロシアのオケに化ける!
良くも悪くも優等生的と言われるNHK交響楽団だが、良い指揮者との出逢いで豹変する強みもある。
スヴェトラーノフの場合もその好例。まるでロシアのオケに様変わりする。金管や低弦がパワーアップ。一方で、スヴェトラーノフならではのカンタービレの精神も聴かれ、殊に緩徐楽章が甘美濃厚である。
《雪片のワルツ》に見る天使の歌声にうっとりし、チャイ4の怒濤のクライマックスに胸を熱くし、ラフマニノフの連綿たる歌に酔い痴れること請け合いだ。
1つ注文をつけるとすれば、収録曲。グリンカが被っている上に、ロシア物とは言えないモツ34番が入っている。個人的には、これらの代わりに、カリンニコフの1番とチャイ5を入れて欲しかった。特に後者は、第2楽章がダイアナ妃の追悼として奏でられた名演だ。それと《スラヴ行進曲》があれば言う事なしである。
その分減点しても良いのだが、演奏の魅力が有り余っており、総合評価で星5つ!
|
|
|
歌心に溢れたマーラー!
オケ配置は通常配置ながら、Pentatoneの優秀な録音ゆえか分離が良く、音の見通しが素晴らしい。
それ以上に、オケの質感がいい。シルキーで艶がある。その美質は、例えば第4楽章の阿鼻叫喚でさえ、決して下品にならないところからも窺い知れよう。勿論迫力にも事欠かないのだが、迫力だけで押してくる演奏とは明らかに一線を画している。
何より、「マーラーってこんなにも歌心があるんだ」ということに改めて気付かされる。もっとも、よくよく考えれば、《巨人》は《さすらう若人の歌》と密接な関わりがあり、それゆえ曲にカンタービレの精神が根付くのは当然と言えば当然なのだが、このことをここまで如実に意識させられる演奏もそう多くないのではないか。
時折、蠱惑的とも言うべきポルタメントや、息を呑むほどのピアニシモも聴かれ、一音一音を慈しむかのようである。
憑依型とも分析型とも、まして時代考証型とも異なる、充実したマーラーを聴けた。
よって文句なしの星5つ!
|
|
|
狂気の両翼配置!
《幻想交響曲》は、やはりヴァイオリン両翼配置でやると2倍3倍に楽しめる。弦の掛け合いや揺れから、「阿片中毒に陥った青年芸術家」の心情や「固定楽想」の移ろいがよく分かるのだ。
このことは最近ではグザヴィエ・ロトも証明済だが、ここでのヤンソンスの演奏は「狂気」の面で一日の長がある。
勿論「狂気」のみを取るのならば、ミュンシュの1967年のライヴ盤にトドメを刺すだろうが、ヤンソンスも健闘している。なにより、ムラヴィンスキーからテミルカーノフへの移行期のレニングラード・フィルの音が良い。ひんやりと透明感のある弦、骨太の木管、切り裂くような金管、鉄槌のような打楽器、これらが、「狂気」を見事に表現している。
《マイスタージンガー》や《悲しきワルツ》も両翼配置の面目躍如たるものがある。対位法が見事に解されたり、死神と乙女の立ち位置がよく分かったりする。
音質もよく、拍手付きでライヴの臨場感もある。文句なしの星5つ!
|
|
|
これ、本当に「美音」なのか?
ヴィブラートがキツい上に、音が掠れたり裏返ったりする。時折、黒板を引っ掻いたような厭な音を出すという具合。
プログラム自体は魅力的で、ジャケットも美麗そのもの、ライナーノーツも充実しており、音質も言うことないのだが、肝心の演奏が頂けない。
よって星3つが妥当か。
このローラ・ボベスコという人のCD、中古市場だと稀にとんでもない値が付いている場合が見受けられるが、そこまでいい演奏なのだろうか?
|
|
|
「曲の持つ攻撃性は抑え目にし、一見穏やかな中に燃え盛る心を閉じ込める」という謳い文句のプロコフィエフだが、それでは正直つまらない。
例えばロジェストヴェンスキー辺りの、コテコテの旧ソ連的イケイケドンドンな演奏に慣れている耳からすると、何ともお行儀が良すぎ、ソフィスティケートされすぎな印象を受ける。
音が全体的に丸い。透明感はあるが覇気がない。テンポものんべんだらりとしている。聴き込むほどに何かあるのかと期待したが、退屈でしかなかった。
しかし、お祭り騒ぎな演奏では聴き取れない細やかな音を作り出すところに面白さを感じる向きもあるだろうから、間を取って星3つ!
|
|
|
トスカニーニこだわりの両翼配置をステレオで!
複雑な対位法が持ち味のワーグナーだからこそ、ヴァイオリンを両サイドに振り分けるのが正解だ。つまり、通常配置およびモノラル録音では、ちょっと物足りない。
その点、奇跡的にステレオで残されたこの盤は面白い。勿論、音響が人工的だとか違和感があるだとかいう意見も分からなくはない。だが、年代を考えてみれば、1954年の録音に今のスタンダードを求めるのは無理があるだろう。それよりも、途中記憶障害を起こしたトスカニーニの異常をいち早く察知し、ギリギリ持ち堪えたオケの底力を高く評価したい。何より、それをステレオで聴けることに、素直に喜びたい。
|
|
|
プログラムと顔触れこそ「そそられる」かも知れないが…。
フランチェスカッティも余り本調子ではないようで、時折黒板を引っ掻いたような嫌な音を出す。メインのベト7も、冒頭から何やら音程が狂っている。
ステレオだがヒスノイズが多く、音像の広がりも今一歩である。まあ、年代とライヴであることを鑑みれば無理もなかろう。
ただ、完成度こそ落ちるが、臨場感と伸びやかさに鑑みて星3つとしておこう。
|
|
|
両翼配置が活きたブラームスとエルガー!
注目はブラームス。EMIの全集盤も良い出来だったが、ここではライヴならではの熱さも込められている。とはいえ流石は英国紳士のボールト。フォルムはあくまできっちりとしている。
対するエルガーは、作品自体がやや冗長である。循環形式だということは分かるのだが、例えばフランクの交響曲のような引き締まった構成力を感じられない。とはいえ、時折ノーブルな、如何にもイギリス的な格調高さも聞かれなくないから、「これはスルメ的作品なんだ」と言い聞かせて聴いている。
録音は年代相応と言ったところで、ヒスノイズや分離の悪さも無きにしもあらずだが、老境のボールトの至芸を堪能するのに不足はないレベルだろう。
|
|
|
有名なEXTON盤をも超える奇跡的名演!
連綿と歌われる美しき旋律の波。スヴェトラーノフの息は長く、時に音楽が止まる寸前にまで溜めに溜める。一方でラストのように感情の限りを尽くして爆発することも厭わない。要はこれ以上ない情感の振幅があり、それがバシバシ決まる爽快感があるという具合だ。
EXTONの全集が、やや感情過多なイメージもあったが、ここでは客演先ということもあって、バランスがよいのもポイント。
ラフマニノフ・イヤーも間もなく千秋楽だが、ここでどうか聴いて欲しい。プレヴィンやアシュケナージ、マゼールなどが淡白に聞こえる程、濃厚なロマンと滾る情熱に打ちのめされること請け合いだ。
|
|
|
端正にして愉悦に満ちた名演!
流石はクリーヴランド管の黄金期。セルの棒はやはりタイトだ。そしてカサドシュもまた、端正な演奏スタイルを身上としている。セルからの信頼も厚かった。
この最高の組み合わせによるファリャとモーツァルトが、悪かろうはずはない。曲がファリャだろうが何だろうが、雰囲気に流されずキッチリ仕立てる。ピアノの粒立ちも煌めいている。モーツァルトも、ヒスノイズこそ多めながら、明確なフォルムを持っている。それでいてリラックスして聴けるところが不思議だ。
円安かつ物価高のこのご時世に、こんな廉価でいいんですかね?(笑)
|
|
|
シューベルトの哀しみが胸に迫る!
ブリテンが弾くピアノの前奏から引き込まれる。ふと間を置くところなど、まるで涙に濡れるシューベルトその人の心の襞に触れるかのようだ。そしてロストロポーヴィチのチェロが、これまた深い味わいで入ってくる。
これぞ、高い音楽性を持ち得る者同士だからこそ成し得た歴史的共演である。録音状態もよく、決定盤の1つに数えるのに吝かではないと思う。よって文句なしの星5つ!
|
|
|
ピリオド派の指揮者がモダンオケを振って成功した事例というのを余り知らない。アーノンクール然りノリントン然り。
さて、このガーディナーが丁と出るか半と出るか。
結果は、何とも中途半端に終わっている。いわゆるピリオド奏法でも両翼配置でもなく、モダンオケそのものの奏法であることに加え、例えば《ハンガリー舞曲》の緩急や間の取り方も、アッサリとし過ぎていて民俗的なニュアンスに欠ける。何より、選曲も地味である。もっとも《チェコ組曲》は『のだめカンタービレ』で少しは注目されたようであるが。
ただ、知名度の低い作品を敢えて取り上げる気概と、録音が比較的良好であることに鑑みて、星3つにしておこう。
|
|
|
フォーレの諸作品を網羅するBOX!
しかも演奏家はフランス勢で統一!
これだけ揃ってこの価格は有難い。但し、音質には少し不満あり。ピアノ曲や室内楽曲は年代相応ながら良好であるが、問題は管弦楽曲。どうも音場が狭苦しく、潤いに欠けた音なのである。一番酷いのが《レクイエム》。音圧レベルが蚊が鳴くように貧弱だし、ボリュームを上げればヒスノイズに苛まれるし、鑑賞に差し支える。
とはいえ、これだけの名曲を揃いに揃えた点や、ピアノ曲や室内楽曲で滋味溢れる演奏を聴ける点、またコスパの面を鑑みて、総合点で星4つ!
|
|
|
線の細すぎる神経質なヴァイオリンと、自由奔放すぎるピアノ。
有名アーティストの共演が、必ずしも同じ方向性で一つの音楽を作れるわけではないことを指し示した悪例。
それを「個性的」と捉える向きも一定数いるだろうから、星3つにしておく。
因みにこのカップリングなら、断然オイストラフ&オボーリン盤を薦めたい。
|
|
|
スペイン交響曲もさることながら、ツィガーヌが聴き物!
指揮者のロザンタールはラヴェルの薫陶を受けているし、ラムルー管弦楽団は《ボレロ》の初演団体でもある。つまり、ラヴェルを演奏するにはこの上ないコンビなのだ。
そこにソリストとして現れたグリュミオーは、美音をもって知られるヴァイオリニストである。重音奏法が頻出する高難度のこの曲を、美しい音色を保って弾き切る度量に感服させられる。
philipsのステレオも優秀である。
|
|
|
あっさり快速のラフマニノフ。
この曲を聴くならまずプレヴィン辺りから始めて、慣れてきたらスヴェトラーノフに酔い痴れるのが王道。
マゼールはどうも快速すぎて、もっと歌って欲しいところもあっさり通過。何をそんなに急いでいるのかね。
しかしながらベルリン・フィルの合奏能力が、ラフマニノフの濃厚なロマンの影に隠れがちな微細な音を拾いきり、細密さを感じさせる。だから決して拙速という訳ではない。
その辺りを買って、星3つにしておこう。
|
|
|
オイストラフのブラームスはこちらが正解!
後年、セル指揮クリーヴランド管弦楽団と再録音しているが、どうリマスタリングを変えても音割れや歪みが改善されることはないようである。
その点、この録音はステレオ初期ながら実に良い音で聴けるし、クレンペラーの指揮も万全。かつ、オイストラフの技巧もこちらの方に軍配が挙がる。
|
|
|
ヴァイオリンと音割れと歪みのための狂想曲!?
ハッキリ言ってクレンペラー盤の方が格段に音が良い。オイストラフのテクニックも充実している。
因みに当盤、あらゆるリマスタリングが試されているが、マスターテープそのものに瑕疵があるらしく、あちこちで音質の不満が囁かれている。
|
|
|
両翼配置のモダンオケでシューマンを聴くならこれだ!
勿論クレンペラーでもよいのだか、あれは些か重すぎる。
その点クーベリックは、時折思い切ったタメなどを見せることもあるが、テンポが中庸で聴きやすい。
何より両翼配置の採用が面白く、ヴァイオリンの掛け合うさまが実に見事。
音質も、アナログ後期の聴きやすいものだ。
|
|
|
あっさり快速のラフマニノフ。
この曲を聴くならまずプレヴィン辺りから始めて、慣れてきたらスヴェトラーノフに酔い痴れるのが王道。
マゼールはどうも快速すぎて、もっと歌って欲しいところもあっさり通過。何をそんなに急いでいるのかね。
しかしながらベルリン・フィルの合奏能力が、ラフマニノフの濃厚なロマンの影に隠れがちな微細な音を拾いきり、細密さを感じさせる。だから決して拙速という訳ではない。
その辺りを買って、星3つにしておこう。
|
|
|
ステレオとモノラルを継ぎ接ぎしたような変な録音。
いつものRCAの鮮烈極まるLiving Stereoからはちょっと想像がつかない。
演奏内容が良いだけに残念。
|
|
|
肝心要の《花のワルツ》にまさかのカットあり!
音質も演奏内容も頗る優秀であるが、なぜ余計なカットをしてくれたんだ?
|
|
|
歌心に溢れたマーラー!
マーラーに対するアプローチは実に様々である。苦悩する作曲家に寄り添うかのようなワルター、峻厳なクレンペラーから、憑依型のバーンスタインやテンシュテット、更には分析家タイプのブーレーズやジンマン、また最近ではピリオド奏法を取り入れたグザヴィエ=ロトなど、様々であり、それぞれに全く異なる作品像を見せてくれた。
それでバルビローリはというと、歌心溢れるアプローチである。曲の隅々にカンタービレの精神が息づいており、マーラーが歌曲を元に交響曲を書いていることを改めて思い起こさせてくれる。
確かに録音は古く、歴史的遺物と見做す気持ちも分からなくはない。が、もしこれが歴史的遺物なら、ワルターもクレンペラーもメンゲルベルクも尽く歴史的遺物になってしまうだろう。演奏を受け継いできた巨匠達への敬意を持って、価値を見出したいものである。
とはいえ、流石に1957年録音の《巨人》は音が悪い。この年代だと、DECCAはffrrを、RCAはLiving Stereoを採用し、目の覚めるような鮮烈なステレオ技術を持っていたことを考えると、当時のEMIは大きく水をあけられていたと言わざるを得ない。
勿論、一応は「ステレオ」ということにはなっているが、それはステレオと呼ぶより「疑似ステレオ」と呼ぶべきチープな音響であり、この名演の価値を大きく損ねている。他が素晴らしいだけに残念である。
《巨人》の分をマイナスして星4つ!
|
|
|
やはりチャイコフスキーとボロディンは、ボロディン弦楽四重奏団の専売特許であろう。
どうもこのドロルツ盤は、カラヤン時代のベルリン・フィルの悪いところ、即ちレガートたっぷり、ビブラートごってり、ピッチは上擦って、縦の線が微妙にずれるという悪癖を、ギュッとコンパクトに凝縮してしまっているようなところがある。それゆえ、落ち着いて聴いていられないのである。
やはりボロディン弦楽四重奏団の、極寒の冬景色を外に見ながらペチカの前で暖を取るかのような、柔らかであたたかな風合いが、この2曲には相応しい。
せいぜいが星3つだろう。
|
|
|
《春》と《クロイツェル》の決定盤の1つ!
オイストラフのヴァイオリンは、豊潤で厚みがあり、コクもある。ヴァイオリニストによっては、線が細くて神経質でキンキンいう音を出す人もいるが、オイストラフには全くそういうところがない。大らかで、温かみがあって、人間味がある。
勿論テクニックの素晴らしさも言わずもがなであるが、如何にも技巧をひけらかしているようには聞こえないところが、オイストラフの美しいところである。
オボーリンとの足並みもピタリと揃って、見事なアンサンブルを聴かせている。
音質も年代離れした良い音である。これは星5つだろう。
|
|
|
ハスキル盤の音質にご不満な方はこちらをどうぞ!
グリュミオーのモーツァルトといえばハスキルとの共演盤が有名であるが、ステレオとモノラルが混在している上に、肝心のステレオの方も、ヴァイオリンとピアノのバランスが悪い。勿論、演奏は非の打ち所が無いのだが、ハスキルのピアノが右前方からガンガン鳴り、グリュミオーのヴァイオリンが左後方からか細く聴こえるというような変な録音だった。
その点、このクリーン盤はデジタル録音ということもあり、ノイズにも苛まれることなく、楽器同士のバランスも良く録れている。グリュミオーのテクニックも衰え知らずであり、まさに円熟の極み。
文句なしの星5つだろう。
|
|
|
1950年代後期の破格のステレオ!
デームスとウィーンの名手による《鱒》ということで楽しみではあったが、1958〜59年の録音ということで音質に一抹の不安があった。
ところが、聴いてみてビックリ仰天!
まるで時空を超えて、つい先日録音したかのような新鮮さ、鱒がピチピチ跳ねるような音の若々しさに、古い録音であることをすっかり忘れ、ただただ美しいアンサンブルに身を委ねることが出来た。
これは数多ある《鱒》の中でも屈指の名盤ではあるまいか?
文句なしの星5つ!
|
|
|
デジタル録音で音割れとはこれ如何に?
ロドリーゴはデジタル録音であるが、《アランフェス》の第1楽章の終わり際で耳をつんざかんばかりに音が割れる。SONYさん、一体どういうことですかね?
併録のヴィラ=ロボスはアナログ後期の録音であるが、もさぁっとした音で何とも締まりが無い。
まあ、廉価盤にケチを付けるのも野暮といえば野暮だが、philipsの廉価盤にはペペ・ロメロの決定盤がある。「安いから多少音が悪くても許してね」という言い訳は無用である。
演奏自体まとまりがあるだけに残念だ。
|
|
|
リマスタリングが硬すぎる!
どうもタワレコさんのバイビット・ハイサンプリング盤は当たり外れが多い。外れの場合の傾向は、大体において高音がキンキンするのだが、残念ながら当盤もその1つ。ドヴォルザークの《新世界》もその1つに数えられよう。ところがコダーイになると見違えるほど良い音になっていたりする。一体どういう訳だろうか?
ステレオ初期のモーツァルトの交響曲集は、ベーム&ベルリン・フィル盤があれば充分。とはいえ、死の淵を幾度となく垣間見たフリッチャイの全身全霊の演奏は、モーツァルトの暗の部分を炙り出すようで、これはこれで聴き物である。
総合点で星3つにしておこう。
|
|
|
これぞウィーンの室内楽の愉悦!
カラヤン&ベルリン・フィルの向こうを張って、ベームと蜜月関係にあった当時のウィーン・フィル、その屋台骨を支えた名プレイヤー達が揃いに揃って、ご自慢のアンサンブルを披瀝する。もうこれだけで贅沢である。
名コンマス、ヘッツェルもさることながら、モーツァルトの協奏曲集でも名演を残しているトリップやプリンツの活躍も素晴らしい。ウェーバーでの技巧の確かさ、ハイドンでの清涼感、ベートーヴェンやシューベルトでの味わい深さ、何れも絶品だ。
気心知れたメンバー達の、肩肘張らない、それでいて格調高い演奏は、音楽をすることの悦びに溢れている。
|
|
|
下手ウマとはこのことか?
諸氏絶賛の当盤だが、現代の演奏水準からすると、かなり危なっかしい点が散見される。音がひっくり返ったり縦の線が大きくズレたりする。もしクナッパーツブッシュの名を伏せた状態でこれを数人に聴かせたら、どこのアマチュアオケかと思う人も出てくるかも知れない。
とかく精神性がどうとか、無為の境地がどうとか、言う人は言うだろう。しかし、そこしか褒めるところがないとすれば考えものである。
まあ、確かにスケールが大きく息遣いもたっぷりしていて、雄渾さを感じなくもないから、星3つくらいにしておこう。
|
|
|
遊び心満点のクナの至芸!
クナッパーツブッシュというと、強面で、ワーグナーやブルックナーといった大曲を好むという印象がある。それゆえ、こんなコンサート・ピースなんか合うわけないと思う人もいることだろう。
ところがどっこい、クナッパーツブッシュはこういう曲も実に聴かせるのだ。
特に《ウィンザーの陽気な女房たち》が名演中の名演! 思い切りがよくて、並のワルツ集では絶対に聴けないスケールの大きな演奏である。
|
|
|
賛否両論拮抗するリマスタリング?!
賛成派は「ダイナミックレンジが広がった」と言うし、反対派は「初期盤に限る」と言うし、自分の耳で確かめるにはやや気が張る値段だし、一体どうなのよ? とレビューを見て思っている方も多いだろう。
これは中々に批評が難しいのである。というのも、手放しで賞賛するにはちょっと不満が残るリマスタリングなのだ。
それは強奏部で顕著である。どうも、頭打ちになっているような、スカッと抜けない音と響きなのだ。慥かに、従来盤と比べたら音にコクも厚みもある。「燻し銀」と喩えられるシュターツカペレ・ドレスデンの音である。だから評価が難しいのだ。
まあ、DENONの廉価盤よりマシだろうことは確かである。だが、値段相応の高音質かと言われれば、そうでもない。
|
|
|
これがピリオド奏法の先駆者による《幻想交響曲》だ!
最近ではグザヴィエ・ロト盤が注目の的になったが、両翼配置の採用やハープの振り分け、オフィクレイドの使用などは既にノリントンが先便をつけていたのである。
その上、第5楽章の鐘がいい。ものによっては「のど自慢」の1点のような鐘で拍子抜けすることもあるが、ノリントンが採用した鐘こそ地獄の響きに相応しい。
さて、《幻想交響曲》といえばどうしてもミュンシュの存在が大きい。まるで阿片中毒者そのもののように荒れ狂い、地獄へとまっしぐらなそのさまは余人の追随を全く許さないものであり、特にパリ管とのライヴは、かの盤鬼・平林直哉氏をしていくつ言葉を並べても表現できないと言わしめる程の凄絶極まる演奏であった。
だが残念なことに、ミュンシュの存在が余りにも大きいゆえに、我々には数多の演奏が生温く感じるという「ミュンシュの呪い」をかけられてしまっているようである。
ここはミュンシュのことを一度忘れて、虚心坦懐に聴く心構えをしなくてはいけない。《幻想交響曲》とはそういう曲であるが、それを全く別角度から面白く表現してみせたノリントンは、やはり只者ではないのである。
その意欲に鑑みて星5つ!
なお、リマスタリングは、かのXRCDでも腕を振るった杉本一家氏であることも明示しておこう。
|
|
|
Living Stereoは、やっぱり凄い!
もし「1956年録音」という言葉に引っ掛かって「音質が悪いんじゃないの?」と訝る人がいたとしたら、実に勿体ない。この頃のRCAの録音技術たるや破格で、下手なデジタル録音を凌駕するほどの音質である。
さて肝心の演奏であるが、ラフ2のアナログ期の名盤と言えば真っ先にリヒテルの名が挙がるだろう。強靭な打鍵と粘り気のあるテンポは、あたかもノイローゼを克服したラフマニノフの心の叫びのように響いてくる。
一方当盤のルービンシュタインは、リヒテルのようなタッチとは違い、音にふくよかさやまろやかさを感じさせる。だからといって詰めが甘いなどということは微塵もなく、ラフマニノフの抒情的な側面を見事に表現している。
《パガニーニ狂詩曲》を挟んで最後に前奏曲《鐘》を入れるのも心憎い。鐘に始まり鐘に終わるようにCD1枚が構成されているのだ。
さて、ルービンシュタインは後に、オーマンディ指揮フィラデルフィア管とラフ2を再録音している。オーマンディとフィラデルフィア管と言えば、ラフマニノフから直に薫陶を受けたコンビである。このライナー指揮シカゴ響よりも一段とゴージャスかつロマンティックな演奏を楽しめる。聴き比べも一興であろう。
|
|
|
冒頭のティンパニの一撃でノックアウト!
近年ではブラームスも時代考証に基づいた演奏がトレンドとなっている。例えばアンドラーシュ・シフの弾き振りなど、独特のフォルテピアノの音色や両翼配置かつ小振りのオケなどに特長があり、大変見通しの良い音楽になっている。
だが、やはり迫力という面において、ピリオド派はどうしても不利になる。
その点、このカーゾン&セル盤は凄い!
DECCAのアナログ期の優秀録音の一つで、ケネス・ウィルキンソンが手掛けている。独特のトリルといいペダリングの音といい、怒濤の迫力である。手に汗握る熱演であり、その熱気まで録音に捉えられている。
併録の《エロイカ変奏曲》は、交響曲第3番《英雄》の第4楽章の主題によるバリエーションだ。余談になるが、ベートーヴェンはこの主題をえらく気に入っていたらしく、計4曲に登場させているらしい。
|
|
|
旧企画もパサついた音で、演奏が良いだけにやや不満が残っていたものだ。
そこへ来てタワレコさんがリマスタリング盤を出してくれた訳だが…。
「おいおい、エンジニアよ、何をしてくれたんだ!」
と怒り心頭に発するほど、高音がギッチギチのキンキンに改竄されているではないか!
リマスタリングの大失敗の一例を垣間見た。いくら技術が優れても、最後はエンジニアの耳と腕に掛かっているということを、痛いほど思い知らされる「迷盤」。
|
|
|
若い頃、ラフマニノフ自身をして「私より上手い!」と言わしめたホロヴィッツのラフ3。しかしやはりモノラル録音というのが惜しい。どんなに厚化粧を施しても所詮モノラルはモノラルである。
ホロヴィッツとしては1978年録音のオーマンディ指揮ニューヨーク・フィルのライヴ盤がある。テクニックはやや劣るが、よい音質と作曲者ゆかりの指揮者で聴けるのがよい。
このライナー盤は1951年の録音だが、あと5年くらい待てば、ホロヴィッツ全盛期のラフ3をLiving Stereoで聴けたのにと思うことしきりである。
|
|
|
通常盤では、ラフマニノフの2番もしくはプロコフィエフの3番とカップリングされることの多い録音だが、チャイコフスキーの1番しか収録せずにこの値段というのは、いくら高音質盤とはいえちょっとコスパが悪い。
肝心のクライバーンの演奏も、些か真面目過ぎるところがあり、ドラマに欠ける。
もっとも、音質は年代離れした素晴らしいものであるが、年々リマスタリング技術が発展している現在、敢えてこれを選ぶ必要もなかろうと思う。
まあ、高音質盤の先鞭をつけたところを買って、星3つが妥当だろう。
|
|
|
これ、本当に高音質盤なのか?
高音がキンキンと耳障りであり、少なくとも一般的なリマスター版の方が遥かに聴きやすい。
オリジナル・マスターテープに忠実であることが、必ずしもリスナーに忠実であるとは限らない悪しき一例。
|
|
|
まさか、このご時世にあのゲルギエフの、しかも《キーウの大きな門》を終曲に持つ《展覧会の絵》を大特価で売り出すとは…。
|
|
|
既に指摘があるように、Living Presenceの名録音として名高い《1812年》が、劣悪なモノラル録音に変貌している。一体このレーベルはどこから音源を調達しているのか。
とはいえ、他はマーキュリー原盤の比較的状態の良いものが収められており、鑑賞の妨げになるようなことはない。
つくづく《1812年》の劣悪ぶりには参った。まあ値段も値段だから星3つにしておくが、どの音源がステレオかモノラルかくらいは、商品説明に明記して欲しいものである。
|
|
|
このBOXとは別に25枚組のものがあり、画像を共用しているようだが、紛らわしいので別々にして頂きたい。
内容はどれもSONYとRCAの屈指の名盤揃いだが、ボリュームとコスパの面で、やはり25枚組に一日の長がある。再販を希望したい。
|
|
|
この曲の組み合わせでの名盤は数多ある。特にアナログ期ではリヒテルが筆頭だろう。特にラフマニノフは、ノイローゼからの復帰という「暗闇から光へ」のドラマを見事に作り上げており、作曲者の心情がひしひしと伝わってくる名盤である。
一方のルービンシュタインも負けてはいない。何しろバックは、ラフマニノフとの自作自演も残しているオーマンディ指揮フィラデルフィア管である。フィラデルフィア・サウンドと呼ばれるゴージャスな音作りが身上であり、聴かせどころを弁えた息遣いが実に自然である。
対するラインスドルフをバックにつけたチャイコフスキーも雄弁そのもの。あからさまにテクニックをひけらかすことなく、作品の持つ魅力を引き出してみせるのは、流石ルービンシュタインと言えるだろう。
音質も年代離れした素晴らしいもので、RCAの技術の程が窺われる。
群雄割拠するこのカップリングの中でも屈指の名盤として、是非とも多くの方にお聴き頂きたいと思う。
|
|
|
ショパンの第2番に関して。
これはBOX及びスリップケースの記載ミスであり、オケはオーマンディ指揮フィラデルフィア管で間違いない。ルービンシュタインによるMastersの廉価盤BOXにはショパン名演集(品番:88697687122)が別にあり、そちらにはウォーレンスタインとの旧録音が入っている模様である。比較するとタイミングなどが全く異なっているので、明らかに別録音だと分かる。
さて、その他、全般的な出来は言うことなし。誇張のない解釈、演奏を、比較的良好なステレオ(シマノフスキを除く)で聴けるのが有難い。
誤植こそマイナスだが、内容が素晴らしいゆえ、星5つをつけたい。
|
|
|
正真正銘の自作自演はこちらだ!
2023年7月、「コンドン・コレクション」というレーベルから、ドビュッシーの自作自演と銘打ったCDが発売された。が、中身を見て唖然呆然。何と、自作自演は前半だけで、後半は全く違う奏者の寄せ集めなのである!
そうなると、ドビュッシーの自作自演に該当する曲目数では、皮肉なことに当盤の方が多いことになるのだ。しかもラヴェルの自作自演まで入っているのだから文句なしだろう。そのうえ、当盤の方が音がクリアである。
「コンドン・コレクション」よりも断然こちらを薦めます。
|
商品詳細へ戻る