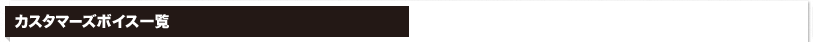
商品詳細へ戻る
楽長さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
ゴージャスな協奏曲と甘美な交響曲!
まずは協奏曲から。ラフマニノフの名盤というと、リヒテルやホロヴィッツ、ミケランジェリの名前を挙げる人も少なくない。だが、往年の名盤ばかりに寄り掛かり、アップデート出来ないのは考えものだ。名盤の価値は尊重しつつ、新たな録音にも耳を傾けたい。
その意味で、このルガンスキー盤は、過去の名盤に勝るとも劣らない名演である。しかも、先のレビューにもある通り、奏者の個性よりも曲そのものの美しさを際立たせた演奏になっている。オケのサポートも相俟って、実にゴージャスだ。録音も頗るつきに優秀である
交響曲の方は言わずもがなの名盤。特に第2番に関しては、カットなしの完全全曲演奏による世界初録音として名高い。なお、リマスターは古いものを使用しており、プレヴィン全集のものよりやや古めかしい音になっているのが玉に瑕だが、鑑賞には差し支えないだろう。
|
|
|
曲そのものをして語らしめるラトル!
マーラーの名盤には様々な系統がある。古くは、マーラーに寄り添うようなワルターや峻厳なクレンペラーがあり、次いで憑依したかのようなバーンスタインやテンシュテットが高く評価された。その反動からか、クールなインバルやブーレーズなどが台頭し、分析型のジンマンが驚きを持って迎えられ、更にはロトが時代考証の口火を切った。それぞれに個性があり、様々な角度からアプローチを試みられたと言える。
ではラトルはどうか。一言で言えば、曲そのものをして語らしめるタイプと言えよう。激情渦巻く訳でも、一歩引いている訳でもない。テキストを丹念に具体化しつつ、感情に溺れず知に働きすぎず、絶妙なバランス感覚を保っている。長く愛聴するにはちょうどよいだろう。おすすめだ。
|
|
|
グラズノフの交響曲全集としては、スヴェトラーノフの絶対的名盤があり、他の演奏はどうしても二番手以下になってしまう。そんな中でも、ネーメ・ヤルヴィ盤と双璧のハイレベルな演奏がこのセレブリエール盤である。
では何故星3つを下したのかと言うと、作品そのものが余り魅力的ではないからである。確かに、連綿と歌われるロシアのロマンがそこここに聞かれるが、グラズノフはそれらを有機的に展開する構成力が乏しいのである。唯一の例外が交響曲第5番であろう。ボロディンやリムスキー=コルサコフが好きな人には良いかも知れない。
もし、グラズノフに構成力が備わっていれば、チャイコフスキーやラフマニノフのように、人気、実力ともにもっと評価されて然るべきだろう。
|
|
|
どうも、グザヴィエ・ロトに対する「過剰さ」が目に付く。謳い文句然り、評価然り。そこまで良い演奏なのか?
もっとも、レ・シエクルとの一連の録音は、こだわりの時代考証によって、一応の成果を挙げていると言える。独特な管楽器の音色や、ノンビブラートの弦楽器の響き、就中、両翼配置での掛け合いなど、ハッとさせられることも多々あった。
しかし、そのセオリーをモダンオケに強いるとなると、何ともギクシャクする。アーノンクールやガーディナー、ノリントンなんかも、モダンオケを振ったものはどうも賛否両論あるようだ。せっかくのモダンオケの機能性を抑圧してしまっているようで仕方ない。
これは録音の貧弱さも手伝ってのことだと思う。LSO LIVEシリーズは「高音質」を謳っているらしいが、どれを聴いてもホール音響がデッドで潤いがなく、薄っぺらで、音圧レベルも低い。オケの自主制作盤で言えば、RCOやBRSOの足許にも及ばない。このレーベル、結構こまめにセールが開催されているが、多くのデッドストックを抱えているんじゃないかと勘繰りたくなる。
ロトの煮えたぎらなさと録音の悪さで最低評価を下しても良いのだが、話題性を斟酌して星3つにしておこう。
|
|
|
老舗オケの味わい深いシューマン!
旧東独時代のシュターツカペレ・ドレスデンは、同じく老舗のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管と双璧の「燻し銀」オケとして名高い。シューマンの交響曲全集でも、ゲヴァントハウスのほうにはコンヴィチュニーやマズアの名盤があり、聴き比べが面白いところだ。
さて、サヴァリッシュのシューマンは、そんな燻し銀のオケの良さを充分に発揮しつつ、弾むような若々しさも加味するという離れ業をやってのけている。重心を低く取りつつ、決して重怠くならない。
これはティンパニのゾンダーマンの貢献が大きいだろう。要所要所でバシバシと決められるティンパニによって、リズム感が際立ち、フレッシュな印象を与える(特に第2番!)。
なお、リマスターに関しては、SACDもしくは初期リマスターの方が断然上である。このartリマスターは、肝心要なゾンダーマンのティンパニがちょっと奥まって聴こえるきらいがあるのだ。とはいえ鑑賞に差し支えることはなく、全体的なまとまりはよいので、これはこれでアリだろう。ただ、例えばケンペ指揮のリヒャルト・シュトラウスの全集が、廉価盤ながらSACDのリマスターを使っていることからすると、何故こちらはartリマスターのままなのかと思ってしまう。願わくば最新のリマスターの上、再販してほしいものだ。
|
|
|
名人芸炸裂のリヒャルト!
ケンペが遺した絶品であり、シュターツカペレ・ドレスデンの各奏者の巧さが際立つ名演揃い。ペーター・ダムの円やかなホルンや、ペーター・ゾンダーマンのマッシヴなティンパニを始め、要所要所で「これぞSKD!」と思わせる見せ場が満載。
音質も、2013年盤を境に劇的に改善された。紛失したとされていたオリジナル・マスターテープが発見され、SACD用にマスタリングされただけあって、それまでの廉価盤BOXにありがちな薄手の音から決別し、実に味わい深い音に生まれ変わった。
また、従来盤では省かれてしまった《月の光の音楽》も蘇り、ペーター・ダムのとろけるようなホルンに酔い痴れることが出来るのも大きい。
魅力たっぷりのこのBOXがお値打ち価格で入手可能とあらば、マストバイであろう。
|
|
|
初演指揮者の矜持!
この《惑星》を世界初演したボールト本人による、鮮烈極まるステレオ録音! 78年盤をも凌ぐ音質!
それ以上に、両翼配置の採用がオーケストレーションの面白さを再現しつくしていることを、声を大にして言いたい。
例えば『水星』。「翼を持った使者」との副題があるが、両翼に翼を授かったお陰で、広い宇宙を右へ左へと飛び回っている。各楽器の掛け合いの面白さは折り紙付きだ。有名な『木星』でも、あの美旋律が左右いっぱいに広がりを持って奏でられるのだ。
そんなスペクタクルな音響を最新のリマスターによる高音質で聴けるのだから、文句なしの星5つ!
|
|
|
初演指揮者の矜持!
この《惑星》を世界初演したボールト本人による、鮮烈極まるステレオ録音!
それ以上に、両翼配置の採用がオーケストレーションの面白さを再現しつくしていることを、声を大にして言いたい。
例えば『水星』。「翼を持った使者」との副題があるが、両翼に翼を授かったお陰で、広い宇宙を右へ左へと飛び回っている。各楽器の掛け合いの面白さは折り紙付きだ。有名な『木星』でも、あの美旋律が左右いっぱいに広がりを持って奏でられるのだ。
そんなスペクタクルな音響を最新のリマスターによる高音質で聴けるのだから、文句なしの星5つ!
|
|
|
曲本来の性格を歪めてまで「ピュアトーン」を押し通したいのか?!
ワーグナーを演奏するにあたり、ノリントンはオケに「ドイツらしさの排除」を求めたらしい。そんな莫迦な!
喩えるなら、麦芽もホップも使わずにビールを造れと言っているようなものだ。
テンポも拙速に過ぎる。もっとも両翼配置を採用し、対位法の面白さが手に取るように分かるという利点はあるが、ただそれだけである。両翼配置ならクレンペラーやボールトの名盤があるが、彼らのどしりと構えた演奏を聴いたあとでは、余りにも軽すぎる。百歩譲って、その軽さこそがノリントンらしさなのかも知れないが、ドイツ魂を剥奪された腑抜けたワーグナーなんか聴きたくない。
メインのエルガーであるが、20世紀の作品にまでノン・ビブラートを強いる理由がどこにあるのか。自作自演など、ビブラートやポルタメントが頻出しているが、それすらも否定してまで、いわゆる「ピリオド・アプローチ」をしたいのか。
曲本来の性格を歪めてまで「ピュアトーン」を無理強いする姿勢には、星0をつけたい。
|
|
|
作曲者ゆかりの老舗オケの矜持!
かつてはメンデルスゾーンその人が楽長を務め、また、交響曲第1番及び第3番の世界初演まで担当しているという老舗オケこそ、ゲヴァントハウス管弦楽団である。十八番の中の十八番をデジタル録音で聴けるセットがコレだ。
マズアとしては1971〜72年にも全集を録音しており、音質としては何故かこの旧録音の方がよいようだ。というのも、当再録音盤は残響過多の恨みがあり、このオケの特徴たる燻し銀のサウンドを充分に捉えきれていないところがあるからだ。
しかし、旧録音はRCAからもEurodiscからも廃盤の憂き目に遭っており、恒常的に手に入るのはこの再録音盤ということで、ちょっと残念である。
また、《スコットランド》に関して、同オケにはコンヴィチュニー盤という歴史的名盤もある。マズア盤も大変優れた演奏ではあるが、コンヴィチュニー盤はマズア盤より一層渋く重厚であり、終楽章コーダの悠揚迫らぬテンポで高らかに歌われるさまも見事である。メンデルスゾーンの演奏史を語る上で避けては通れない1枚であり、マズア盤との聴き比べも面白いところである。
とはいえ、これ程の水準の全集を廉価で聴けるのだし、若書きの《弦楽のための交響曲》も入っているのだから、星4つとしておこう。
|
|
|
作曲者ゆかりの老舗オケの矜持!
かつてはメンデルスゾーンその人が楽長を務め、また《スコットランド》の世界初演まで担当しているという老舗オケこそ、ゲヴァントハウス管弦楽団である。十八番の中の十八番をデジタル録音で聴ける1枚がコレだ。
マズアとしては1971〜72年にも録音しており、音質としては何故かこの旧録音の方がよいようだ。というのも、当再録音盤は残響過多の恨みがあり、このオケの特徴たる燻し銀のサウンドを充分に捉えきれていないところがあるからだ。
しかし、旧録音はRCAからもEurodiscからも廃盤の憂き目に遭っており、恒常的に手に入るのはこの再録音盤ということで、ちょっと残念である。
また、《スコットランド》に関して、同オケにはコンヴィチュニー盤という歴史的名盤もある。マズア盤も大変優れた演奏ではあるが、コンヴィチュニー盤はマズア盤より一層渋く重厚であり、終楽章コーダの悠揚迫らぬテンポで高らかに歌われるさまも見事である。メンデルスゾーンの演奏史を語る上で避けては通れない1枚であり、マズア盤との聴き比べも面白いところである。
|
|
|
シュターツカペレ・ドレスデンの美音全開!
チャイコフスキーの5番の名演は、例えばロシア勢のように不運を力づくで捻じ伏せるような演奏や、あるいはヨーロッパ勢のように甘美なメロディを殊の外強調するような演奏が多いと思う。
ではこのクルツ盤はどうかと言えば、力で攻めることもなければ甘く媚びることもない。ならば個性的でないかと言えば全く違っていて、とにかくオケの美質がこれでもかと言わんばかりに発揮されている。
重心は低いのに重怠くならず、温もりがある。分厚い弦やふくよかな管は円やかでコクがある。音の運び自体、デフォルメを避けてあくまでシンフォニックだ。
各奏者の名技も光る。第2楽章のペーター・ダムと思しきホルンの何と美しいことか! また、要所要所でペーター・ゾンダーマンのティンパニが尽くバシバシ決まるさまも快感ですらある。こうした名技性が、単なる技巧の御披露目にならず、曲想にいちいち嵌まるから凄い。
チャイコフスキーを通じて、オケの素晴らしさに酔い痴れたい人には、この上ない名盤となるだろう。文句なしの星5つ!
|
|
|
ドイツ風のビゼー!
ビゼーの名曲集と言えば、クリュイタンスやデュトワに代表されるような、フランス語圏のオケの独擅場である。パリッと乾いた軽快な響きが特徴的だ。
一方このレーグナーはどうか。一言で言えば純ドイツ風である。重厚感たっぷりであり、フランス系のオケからすると一段も二段も色彩のトーンが暗い。
ところが、それでいて野暮ったさとは無縁である。むしろ、フランス系のオケにはないコシの強さや内声部の豊かさが独特のコクを生み出し、実に味わい深いのだ。時折、交響曲やオペラのワンシーンを思わせるような濃厚な表現も見られ、とかく通俗的に扱われがちなビゼーから、深みのある味わいを引き出すことに成功している。
大推薦の星5つ!
|
|
|
純ドイツ風のグリーグ!
グリーグの名盤としては、やはり北欧系のオケの独擅場と言えるだろう。それらは概して透明感に溢れており、ひんやりとした質感を持っている。
では、ここに聴くスウィトナーはどうか。一言で言えば、純ドイツ風なのだ。即ち、低弦が土台を作り、渋い弦や野太い管が乗るという具合だ。透明感よりも重厚感が勝り、冷たさよりも人肌の温もりを感じさせる。《ホルベルク組曲》など、カラヤンに代表されるような流麗な演奏が多い中、ゴリゴリと力瘤が入ったマッチョな演奏になっており、異彩を放っている。
ところが野暮ったさとは無縁で、どこまでも血の通った、ヒューマンな演奏である。宇野功芳氏が激賞したのも宜なるかなの、立派な演奏だ。大推薦の星5つ!
|
|
|
初演団体による貴重な《グレート》!
シューマンの進言により、メンデルスゾーンの指揮で日の目を見た《グレート》。由緒あるゲヴァントハウス管の録音としては、近年ではブロムシュテットのDG盤が知られているが、このマズア盤も忘れてはならない。
旧東独時代のゲヴァントハウス管の響きは、後のシャイー時代には完全に失われたものだ。低弦がキッチリと土台となり、分厚い弦は渋くも艶があり、管も独特、その上、ここぞというときの打楽器が決まっているという具合だ。マズアはそこに、コンヴィチュニー時代にはなかった現代性を加味しており、実に魅力的な演奏に仕上げている。
PHILIPS(現DECCA)レーベルだが、シャルプラッテンとの共同制作であり、エンジニアには名手シュトリューベン氏の名前がクレジットされている。従って音質の良さも魅力の一つだ。
演奏・録音ともに文句なしの星5つ!
|
|
|
燻し銀のブラームス!
昨今ではブラームスにもピリオド奏法の波が押し寄せ、どんどんスリムになっている。勿論、今まで聴き取れなかった微細な音が拾われるなど面白い点も無きにしもあらずだが、それが感動と結びつくかと言えば、必ずしもそうではないのではなかろうか。
ここに聴くコンヴィチュニーは、そんなスリムなブラームスの対極にある。恰幅が良くて、堂々としていて、堅牢で、どんな雨風にもビクともしないような逞しさがある。当時のゲヴァントハウスの音色がまたいい。後のシャイーが楽長を務めた頃には失われた、渋くてコクがあるものだ。低弦がガッチリと下支えして、そこに分厚い弦や円やかな木管や力強い金管が乗る。ここぞというときに打楽器がバシバシ決まるという具合。それが、当時としては優秀な録音で収まり、更に確かな復刻技術で蘇ったのだから、何とも贅沢である。
昨今のスリムなブラームスに物足りなさを覚える向きには、かけがえのない1枚となるだろう。
|
|
|
歴史の重みにひれ伏す!
ゲヴァントハウス管の歴史は古く、1743年に創業している。あのウィーン・フィルより100年ほど古いのだ。ここに聴くベートーヴェンの《皇帝》やメンデルスゾーンの2曲は、ゲヴァントハウス管が世界初演を担当した演目でもある。そうした楽団の矜持が、ここにもしっかりと刻まれている。
ここまで堂々とした風格を湛えた《皇帝》も珍しい。まるで横綱相撲のようだ。メンデルスゾーンも、ヴァイオリン協奏曲におけるポルタメントを多用した節回しが、何ともロマンティックだ。
やはり、低弦に下支えされた重厚な音はドイツ・ロマン派音楽にこそ最も似つかわしく、ボンガルツのブルックナーなどでは迫力の金管もあって雄渾の極み。一方、ノイマンによるスメタナも、後のチェコ・フィル以上のボルテージを感じさせ、まるでライヴさながらの超熱演である。ムソルグスキーは、ラヴェル編曲からイメージされるフランス的な音は鳴りを潜め、どこまでも渋く仄暗い異色の出来。ガーシュウィンも、アメリカのオケのような楽天的な響きではなく、あくまで手堅くシンフォニックに料理されているのが面白い。
総じて、旧東独時代のこの楽団の特徴を様々な曲目を通して知れる、面白いBOXと言えよう。
|
|
|
ライヴ顔負けの超熱演!
ノイマンといえばチェコ・フィルとセットで語られるが、ここではゲヴァントハウス管を振っている。チェコ・フィルより一段と渋くコクのある響きが出せ、更にここぞというときの熱のこもり方にも特徴があるオケだ。そんなオケの美質が最大限に活かされたのが、ここに聴く《我が祖国》である。
冒頭のハープからして美しく、有名な《ヴルタヴァ》の滔々とした流れは、渋くも艶やかな弦楽セクションの成せる業だろう。何と言っても感動的なのは《ブラニーク》のラストの主題回帰のシーンで、ここをこんなにも高らかに力強く奏でられた録音が他にあるだろうか。クーベリックを始め他のチェコの指揮者が束になっても敵わないかも知れない。
気になる音質だが、従来のCDでは目立っていた音割れも軽減し、高音域の抜けが格段に良くなった。全体的に音が立つようになり、力感も増したように思える。従来盤に御不満の方も、是非手に取られたら如何だろうか。
|
|
|
ピアノの詩人ショパンを抒情的に演奏!
オーソドックスなルービンシュタイン、奔放なアルゲリッチ、技巧派のポリーニ、個性的なブーニンなど、ショパンの名盤はそれぞれにキャラクターが異なる。ではこのフランソワ盤はというと、一言でいえば抒情的である。感興の赴くままに、強弱緩急から音色のコントラストまで変幻自在に移ろい、ショパンのロマンを掬い上げる。メロディーラインが曲線的な繋がりをもって奏でられ、どの曲にもカンタービレの精神が込められている。それでいて情緒に溺れる手前で踏み止まっており、決して下品にならないところが凄い。
なお、マズルカ、バラード、スケルツォ、エチュード、即興曲はモノラル録音であるが、フランソワは有名曲をステレオで別に録音している。それらはTOCE-14004(国内盤)や7243 8 26690 2 9(仏盤)などで聴くことが出来る。もしモノラルの音質に御不満なら、これらに当たってみるのも良いだろう。
|
|
|
全集とは別録音が多数収録!
廉価盤10CDではモノラルだったマズルカやエチュード、バラードなどもステレオで収録されており、全集の音質に御不満の方には有難い1枚になっている。また、国内盤の『ショパン:ピアノ名曲集』とも別の音源が収録されており、聴き比べの楽しみもある。
フランソワの抒情的な演奏は、ピアノの詩人ことショパンに似つかわしい。独特の洒落っ気や外連味があり、しかも決して下品にならない。天性がキラリと光る名演揃い。テクニック一辺倒の演奏からは決して得られない霊感に満ちた演奏は、今日でこそ学ぶべきものが多いだろう。
ファン必携の1枚と言えよう。
|
|
|
ロシアのショパン、開陳!
年を追うごとに神秘主義のアブナイ方向にイッちゃったスクリャービンであるが、若い頃はラフマニノフと覇を競うほどのコテコテのロマン派だった。このことがよく窺えるのがこの1枚。
大柄でオクターヴを鷲掴みしてしまうラフマニノフに対して、スクリャービンは小柄な身体つきだった。しかしその分、細やかな指遣いで陶酔的な音楽を紡いでいったのである。
ショパンやラフマニノフがお好きな人、《法悦の詩》や《プロメテウス》なんかで拒否反応を示してしまった人、スクリャービンのロマンティシストな一面を知ることが出来ますよ。
|
|
|
ラフマニノフの盟友、ロマンと技巧の融合!
メトネルはラフマニノフの盟友として知られ、作風もよく似ている。つまり溢れんばかりのロマンを超絶技巧に落とし込むという具合だ。
特に第2番が聴き物。競合盤としてはアムランやトーザーが知られているが、彼らより速いテンポでキレッキレのテクニックを見せてくれるのが、このデミジェンコだ。
ラフマニノフ好きの人ならハマること請け合い。同シリーズのボルトキエヴィチ共々、心から推薦したい。
|
|
|
忘れられたロマンが蘇る!
アレンスキーもさることながら、ボルトキエヴィチが秀逸。大体、無名な作品というのは、キャッチーなメロディを作れなかったり、仮に作れたとしても構成がグデグデで冗長だったりするものだ。だがボルトキエヴィチは、ラフマニノフもかくやと言わんばかりのロマンティックなメロディを惜しげもなく紡ぎ、しかも主題の展開や回帰などをして構成的にもしっかりした作品を書いているではないですか。
特に第1楽章第2主題が究極の美メロ! これが回帰するところなどロマンの極み。第3楽章にもちゃんと関連付けをして、抜かりがないところも憎い。
演奏、録音も申し分ない。ボルトキエヴィチにご興味の方は、交響曲第1番に赴かれると吉。チャイコフスキーの交響曲第4番に酷似した構成と、ラストの《神よツァーリを護り給え》に狂喜すること必定!
|
|
|
父子鷹の競演!
レニングラード・フィルと言えば当然ムラヴィンスキーの名が挙がるが、彼の来日公演盤の多くは、「歪む、割れる、揺れる」の三拍子揃った低音質、おまけに彼方此方でゴホゴホと咳払いが混入するという代物であった。
当BOXのうち、父君アルヴィド氏の方は1970年の録音ということで、音質に一抹の不安があったが、聴いてみてビックリ。中々の高音質である。
ところが、レニングラード・フィルにしては珍しく、何故か低弦右側の通常配置なのだ。ムラヴィンスキーは、有名なDG盤のチャイコフスキー:後期三大交響曲を除いて、ほぼ両翼配置(対向配置)を採用していたはずである。
演奏自体は申し分なく、金管が突き刺すように響く辺りは流石と言える。もっとも、チャイ5の第3楽章でclが盛大にリードミスをお見舞いするところがあり、ズッコケそうになったが…。
対するマリスの方は両翼配置。ただしチャイ4のカッティング・レベルがかなり低く、第3楽章のピチカートなど、ぐんと音量を上げないと音が飛び込んでこない。
だが演奏自体は燃焼度が高く、終楽章ラストなどスヴェトラーノフと互角の畳み掛けを施す。白眉は《幻想交響曲》で、両翼配置の面目躍如たる音響と、ヒンヤリとした狂気が入り混じった怪演である。こちらは音質も良好。
総じて、本番一発撮りの故の瑕疵も無きにしも非ずだし、録音やオケの配置に多少の不満もある。だが、燃焼度の高い演奏が披瀝されているという点を加味して、星4つとしておこう。
|
|
|
N響、ロシアのオケに化ける!
良くも悪くも優等生的と言われるNHK交響楽団だが、良い指揮者との出逢いで豹変する強みもある。
スヴェトラーノフの場合もその好例。まるでロシアのオケに様変わりする。金管や低弦がパワーアップ。一方で、スヴェトラーノフならではのカンタービレの精神も聴かれ、殊に緩徐楽章が甘美濃厚である。
《雪片のワルツ》に見る天使の歌声にうっとりし、チャイ4の怒濤のクライマックスに胸を熱くし、ラフマニノフの連綿たる歌に酔い痴れること請け合いだ。
1つ注文をつけるとすれば、収録曲。グリンカが被っている上に、ロシア物とは言えないモツ34番が入っている。個人的には、これらの代わりに、カリンニコフの1番とチャイ5を入れて欲しかった。特に後者は、第2楽章がダイアナ妃の追悼として奏でられた名演だ。それと《スラヴ行進曲》があれば言う事なしである。
その分減点しても良いのだが、演奏の魅力が有り余っており、総合評価で星5つ!
|
|
|
歌心に溢れたマーラー!
オケ配置は通常配置ながら、Pentatoneの優秀な録音ゆえか分離が良く、音の見通しが素晴らしい。
それ以上に、オケの質感がいい。シルキーで艶がある。その美質は、例えば第4楽章の阿鼻叫喚でさえ、決して下品にならないところからも窺い知れよう。勿論迫力にも事欠かないのだが、迫力だけで押してくる演奏とは明らかに一線を画している。
何より、「マーラーってこんなにも歌心があるんだ」ということに改めて気付かされる。もっとも、よくよく考えれば、《巨人》は《さすらう若人の歌》と密接な関わりがあり、それゆえ曲にカンタービレの精神が根付くのは当然と言えば当然なのだが、このことをここまで如実に意識させられる演奏もそう多くないのではないか。
時折、蠱惑的とも言うべきポルタメントや、息を呑むほどのピアニシモも聴かれ、一音一音を慈しむかのようである。
憑依型とも分析型とも、まして時代考証型とも異なる、充実したマーラーを聴けた。
よって文句なしの星5つ!
|
|
|
狂気の両翼配置!
《幻想交響曲》は、やはりヴァイオリン両翼配置でやると2倍3倍に楽しめる。弦の掛け合いや揺れから、「阿片中毒に陥った青年芸術家」の心情や「固定楽想」の移ろいがよく分かるのだ。
このことは最近ではグザヴィエ・ロトも証明済だが、ここでのヤンソンスの演奏は「狂気」の面で一日の長がある。
勿論「狂気」のみを取るのならば、ミュンシュの1967年のライヴ盤にトドメを刺すだろうが、ヤンソンスも健闘している。なにより、ムラヴィンスキーからテミルカーノフへの移行期のレニングラード・フィルの音が良い。ひんやりと透明感のある弦、骨太の木管、切り裂くような金管、鉄槌のような打楽器、これらが、「狂気」を見事に表現している。
《マイスタージンガー》や《悲しきワルツ》も両翼配置の面目躍如たるものがある。対位法が見事に解されたり、死神と乙女の立ち位置がよく分かったりする。
音質もよく、拍手付きでライヴの臨場感もある。文句なしの星5つ!
|
|
|
これ、本当に「美音」なのか?
ヴィブラートがキツい上に、音が掠れたり裏返ったりする。時折、黒板を引っ掻いたような厭な音を出すという具合。
プログラム自体は魅力的で、ジャケットも美麗そのもの、ライナーノーツも充実しており、音質も言うことないのだが、肝心の演奏が頂けない。
よって星3つが妥当か。
このローラ・ボベスコという人のCD、中古市場だと稀にとんでもない値が付いている場合が見受けられるが、そこまでいい演奏なのだろうか?
|
|
|
「曲の持つ攻撃性は抑え目にし、一見穏やかな中に燃え盛る心を閉じ込める」という謳い文句のプロコフィエフだが、それでは正直つまらない。
例えばロジェストヴェンスキー辺りの、コテコテの旧ソ連的イケイケドンドンな演奏に慣れている耳からすると、何ともお行儀が良すぎ、ソフィスティケートされすぎな印象を受ける。
音が全体的に丸い。透明感はあるが覇気がない。テンポものんべんだらりとしている。聴き込むほどに何かあるのかと期待したが、退屈でしかなかった。
しかし、お祭り騒ぎな演奏では聴き取れない細やかな音を作り出すところに面白さを感じる向きもあるだろうから、間を取って星3つ!
|
|
|
トスカニーニこだわりの両翼配置をステレオで!
複雑な対位法が持ち味のワーグナーだからこそ、ヴァイオリンを両サイドに振り分けるのが正解だ。つまり、通常配置およびモノラル録音では、ちょっと物足りない。
その点、奇跡的にステレオで残されたこの盤は面白い。勿論、音響が人工的だとか違和感があるだとかいう意見も分からなくはない。だが、年代を考えてみれば、1954年の録音に今のスタンダードを求めるのは無理があるだろう。それよりも、途中記憶障害を起こしたトスカニーニの異常をいち早く察知し、ギリギリ持ち堪えたオケの底力を高く評価したい。何より、それをステレオで聴けることに、素直に喜びたい。
|
|
|
プログラムと顔触れこそ「そそられる」かも知れないが…。
フランチェスカッティも余り本調子ではないようで、時折黒板を引っ掻いたような嫌な音を出す。メインのベト7も、冒頭から何やら音程が狂っている。
ステレオだがヒスノイズが多く、音像の広がりも今一歩である。まあ、年代とライヴであることを鑑みれば無理もなかろう。
ただ、完成度こそ落ちるが、臨場感と伸びやかさに鑑みて星3つとしておこう。
|
|
|
両翼配置が活きたブラームスとエルガー!
注目はブラームス。EMIの全集盤も良い出来だったが、ここではライヴならではの熱さも込められている。とはいえ流石は英国紳士のボールト。フォルムはあくまできっちりとしている。
対するエルガーは、作品自体がやや冗長である。循環形式だということは分かるのだが、例えばフランクの交響曲のような引き締まった構成力を感じられない。とはいえ、時折ノーブルな、如何にもイギリス的な格調高さも聞かれなくないから、「これはスルメ的作品なんだ」と言い聞かせて聴いている。
録音は年代相応と言ったところで、ヒスノイズや分離の悪さも無きにしもあらずだが、老境のボールトの至芸を堪能するのに不足はないレベルだろう。
|
|
|
有名なEXTON盤をも超える奇跡的名演!
連綿と歌われる美しき旋律の波。スヴェトラーノフの息は長く、時に音楽が止まる寸前にまで溜めに溜める。一方でラストのように感情の限りを尽くして爆発することも厭わない。要はこれ以上ない情感の振幅があり、それがバシバシ決まる爽快感があるという具合だ。
EXTONの全集が、やや感情過多なイメージもあったが、ここでは客演先ということもあって、バランスがよいのもポイント。
ラフマニノフ・イヤーも間もなく千秋楽だが、ここでどうか聴いて欲しい。プレヴィンやアシュケナージ、マゼールなどが淡白に聞こえる程、濃厚なロマンと滾る情熱に打ちのめされること請け合いだ。
|
|
|
端正にして愉悦に満ちた名演!
流石はクリーヴランド管の黄金期。セルの棒はやはりタイトだ。そしてカサドシュもまた、端正な演奏スタイルを身上としている。セルからの信頼も厚かった。
この最高の組み合わせによるファリャとモーツァルトが、悪かろうはずはない。曲がファリャだろうが何だろうが、雰囲気に流されずキッチリ仕立てる。ピアノの粒立ちも煌めいている。モーツァルトも、ヒスノイズこそ多めながら、明確なフォルムを持っている。それでいてリラックスして聴けるところが不思議だ。
円安かつ物価高のこのご時世に、こんな廉価でいいんですかね?(笑)
|
|
|
シューベルトの哀しみが胸に迫る!
ブリテンが弾くピアノの前奏から引き込まれる。ふと間を置くところなど、まるで涙に濡れるシューベルトその人の心の襞に触れるかのようだ。そしてロストロポーヴィチのチェロが、これまた深い味わいで入ってくる。
これぞ、高い音楽性を持ち得る者同士だからこそ成し得た歴史的共演である。録音状態もよく、決定盤の1つに数えるのに吝かではないと思う。よって文句なしの星5つ!
|
|
|
ピリオド派の指揮者がモダンオケを振って成功した事例というのを余り知らない。アーノンクール然りノリントン然り。
さて、このガーディナーが丁と出るか半と出るか。
結果は、何とも中途半端に終わっている。いわゆるピリオド奏法でも両翼配置でもなく、モダンオケそのものの奏法であることに加え、例えば《ハンガリー舞曲》の緩急や間の取り方も、アッサリとし過ぎていて民俗的なニュアンスに欠ける。何より、選曲も地味である。もっとも《チェコ組曲》は『のだめカンタービレ』で少しは注目されたようであるが。
ただ、知名度の低い作品を敢えて取り上げる気概と、録音が比較的良好であることに鑑みて、星3つにしておこう。
|
|
|
フォーレの諸作品を網羅するBOX!
しかも演奏家はフランス勢で統一!
これだけ揃ってこの価格は有難い。但し、音質には少し不満あり。ピアノ曲や室内楽曲は年代相応ながら良好であるが、問題は管弦楽曲。どうも音場が狭苦しく、潤いに欠けた音なのである。一番酷いのが《レクイエム》。音圧レベルが蚊が鳴くように貧弱だし、ボリュームを上げればヒスノイズに苛まれるし、鑑賞に差し支える。
とはいえ、これだけの名曲を揃いに揃えた点や、ピアノ曲や室内楽曲で滋味溢れる演奏を聴ける点、またコスパの面を鑑みて、総合点で星4つ!
|
|
|
線の細すぎる神経質なヴァイオリンと、自由奔放すぎるピアノ。
有名アーティストの共演が、必ずしも同じ方向性で一つの音楽を作れるわけではないことを指し示した悪例。
それを「個性的」と捉える向きも一定数いるだろうから、星3つにしておく。
因みにこのカップリングなら、断然オイストラフ&オボーリン盤を薦めたい。
|
|
|
スペイン交響曲もさることながら、ツィガーヌが聴き物!
指揮者のロザンタールはラヴェルの薫陶を受けているし、ラムルー管弦楽団は《ボレロ》の初演団体でもある。つまり、ラヴェルを演奏するにはこの上ないコンビなのだ。
そこにソリストとして現れたグリュミオーは、美音をもって知られるヴァイオリニストである。重音奏法が頻出する高難度のこの曲を、美しい音色を保って弾き切る度量に感服させられる。
philipsのステレオも優秀である。
|
|
|
あっさり快速のラフマニノフ。
この曲を聴くならまずプレヴィン辺りから始めて、慣れてきたらスヴェトラーノフに酔い痴れるのが王道。
マゼールはどうも快速すぎて、もっと歌って欲しいところもあっさり通過。何をそんなに急いでいるのかね。
しかしながらベルリン・フィルの合奏能力が、ラフマニノフの濃厚なロマンの影に隠れがちな微細な音を拾いきり、細密さを感じさせる。だから決して拙速という訳ではない。
その辺りを買って、星3つにしておこう。
|
|
|
オイストラフのブラームスはこちらが正解!
後年、セル指揮クリーヴランド管弦楽団と再録音しているが、どうリマスタリングを変えても音割れや歪みが改善されることはないようである。
その点、この録音はステレオ初期ながら実に良い音で聴けるし、クレンペラーの指揮も万全。かつ、オイストラフの技巧もこちらの方に軍配が挙がる。
|
|
|
ヴァイオリンと音割れと歪みのための狂想曲!?
ハッキリ言ってクレンペラー盤の方が格段に音が良い。オイストラフのテクニックも充実している。
因みに当盤、あらゆるリマスタリングが試されているが、マスターテープそのものに瑕疵があるらしく、あちこちで音質の不満が囁かれている。
|
|
|
両翼配置のモダンオケでシューマンを聴くならこれだ!
勿論クレンペラーでもよいのだか、あれは些か重すぎる。
その点クーベリックは、時折思い切ったタメなどを見せることもあるが、テンポが中庸で聴きやすい。
何より両翼配置の採用が面白く、ヴァイオリンの掛け合うさまが実に見事。
音質も、アナログ後期の聴きやすいものだ。
|
|
|
あっさり快速のラフマニノフ。
この曲を聴くならまずプレヴィン辺りから始めて、慣れてきたらスヴェトラーノフに酔い痴れるのが王道。
マゼールはどうも快速すぎて、もっと歌って欲しいところもあっさり通過。何をそんなに急いでいるのかね。
しかしながらベルリン・フィルの合奏能力が、ラフマニノフの濃厚なロマンの影に隠れがちな微細な音を拾いきり、細密さを感じさせる。だから決して拙速という訳ではない。
その辺りを買って、星3つにしておこう。
|
|
|
ステレオとモノラルを継ぎ接ぎしたような変な録音。
いつものRCAの鮮烈極まるLiving Stereoからはちょっと想像がつかない。
演奏内容が良いだけに残念。
|
|
|
肝心要の《花のワルツ》にまさかのカットあり!
音質も演奏内容も頗る優秀であるが、なぜ余計なカットをしてくれたんだ?
|
|
|
歌心に溢れたマーラー!
マーラーに対するアプローチは実に様々である。苦悩する作曲家に寄り添うかのようなワルター、峻厳なクレンペラーから、憑依型のバーンスタインやテンシュテット、更には分析家タイプのブーレーズやジンマン、また最近ではピリオド奏法を取り入れたグザヴィエ=ロトなど、様々であり、それぞれに全く異なる作品像を見せてくれた。
それでバルビローリはというと、歌心溢れるアプローチである。曲の隅々にカンタービレの精神が息づいており、マーラーが歌曲を元に交響曲を書いていることを改めて思い起こさせてくれる。
確かに録音は古く、歴史的遺物と見做す気持ちも分からなくはない。が、もしこれが歴史的遺物なら、ワルターもクレンペラーもメンゲルベルクも尽く歴史的遺物になってしまうだろう。演奏を受け継いできた巨匠達への敬意を持って、価値を見出したいものである。
とはいえ、流石に1957年録音の《巨人》は音が悪い。この年代だと、DECCAはffrrを、RCAはLiving Stereoを採用し、目の覚めるような鮮烈なステレオ技術を持っていたことを考えると、当時のEMIは大きく水をあけられていたと言わざるを得ない。
勿論、一応は「ステレオ」ということにはなっているが、それはステレオと呼ぶより「疑似ステレオ」と呼ぶべきチープな音響であり、この名演の価値を大きく損ねている。他が素晴らしいだけに残念である。
《巨人》の分をマイナスして星4つ!
|
|
|
やはりチャイコフスキーとボロディンは、ボロディン弦楽四重奏団の専売特許であろう。
どうもこのドロルツ盤は、カラヤン時代のベルリン・フィルの悪いところ、即ちレガートたっぷり、ビブラートごってり、ピッチは上擦って、縦の線が微妙にずれるという悪癖を、ギュッとコンパクトに凝縮してしまっているようなところがある。それゆえ、落ち着いて聴いていられないのである。
やはりボロディン弦楽四重奏団の、極寒の冬景色を外に見ながらペチカの前で暖を取るかのような、柔らかであたたかな風合いが、この2曲には相応しい。
せいぜいが星3つだろう。
|
|
|
《春》と《クロイツェル》の決定盤の1つ!
オイストラフのヴァイオリンは、豊潤で厚みがあり、コクもある。ヴァイオリニストによっては、線が細くて神経質でキンキンいう音を出す人もいるが、オイストラフには全くそういうところがない。大らかで、温かみがあって、人間味がある。
勿論テクニックの素晴らしさも言わずもがなであるが、如何にも技巧をひけらかしているようには聞こえないところが、オイストラフの美しいところである。
オボーリンとの足並みもピタリと揃って、見事なアンサンブルを聴かせている。
音質も年代離れした良い音である。これは星5つだろう。
|
|
|
ハスキル盤の音質にご不満な方はこちらをどうぞ!
グリュミオーのモーツァルトといえばハスキルとの共演盤が有名であるが、ステレオとモノラルが混在している上に、肝心のステレオの方も、ヴァイオリンとピアノのバランスが悪い。勿論、演奏は非の打ち所が無いのだが、ハスキルのピアノが右前方からガンガン鳴り、グリュミオーのヴァイオリンが左後方からか細く聴こえるというような変な録音だった。
その点、このクリーン盤はデジタル録音ということもあり、ノイズにも苛まれることなく、楽器同士のバランスも良く録れている。グリュミオーのテクニックも衰え知らずであり、まさに円熟の極み。
文句なしの星5つだろう。
|
商品詳細へ戻る