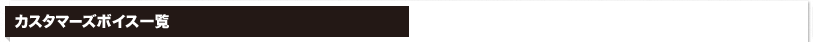
アローン・バット・ネヴァー・アローン / Larry Carlton
|
|
ジャズ、フュージョンを問わず、世のギターフリークたちに人気が高いのが、ラリー・カールトンだ。彼の代表作「夜の彷徨」の中の名曲「ルーム335」で披露された、流れるような美しいソロパートの演奏に、誰もが魅了されるのは無理もない。だが、それ以外のアルバムとなると、これがなかなか難しい。一長一短あり、競演ものなら、あれこれ候補が上がるが、単独作品となると、なぜか本命がない。だが地味な作品として位置付けられる、アコースティック・ギターを駆使した本作と、翌年の続編作「ディスカバリー」こそ、自信を持ってお勧めできる彼の代表作である。エレクトリックギターだけが、彼の売り物ではないことを再認識させてくれる。
カールトンは元々、ジャズ志向の青年でジョー・パスに師事していたくらいだ。またビッグバンドでもギターを担当していた。ザ・クルセイダーズに参加してから、交友関係と芸域を広げていったのであろう。一方で、彼はブルース音楽も非常に好んでおり、時折、旋律やアドリブにブルースのコードやメロディを垣間見せることもある。その後参加したフォープレイの創立メンバーの一人、リー・リトナーには以前から影響を受けていたという。本作も続編も、リトナーと良く似たギターフレーズが随所に聴き取れて、楽しくなる。
単なる聴きやすさを狙わずに、ちょっと捻った音階に進むのが彼のメロディー作りの特徴である。本作はスローとミディアムテンポの佳作ばかりで、数曲のソロも含む。ギターのパートではゆったりと時間をかけて難度の高い演奏をしている。一方で続編は、ドゥービーの名曲やサックスのカーク・ウェイラムをフィーチャーするなど、より万人受けする志向になっている。さらに両作品は、伴奏のアレンジがとても優れている点でも、特筆に値する。当時流行していたソフトアンドメローの路線を堅持しつつも、フュージョンの王道らしい、シンプル且つ高品質のパフォーマンスを展開しているので、名うてのミュージシャン達の職人芸に酔いしれるがいい。
おそらくカールトンは、人気が高まるにつれ、自身の将来の方向性に悩んでいたのではないか。それでアコースティックに挑戦し、図らずも全米で売れに売れてグラミー賞も獲得した。故に本作は、彼にとって真の金字塔であり、もっと再評価されるべきだと考える。
|
商品詳細へ戻る
ビリたきさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
活動50周年を迎え、デビュー当初からの三人のメンバーは殿堂入りも果たした。彼らは悠々自適の生活を送っているであろう。だが、私のようなシルバー世代のシカゴ・ファンは、かつて青春期にシカゴを聴いて、計り知れない感動を与えてくれた力強いブラスのアンサンブル・サウンドを、再び聴かせて欲しいと思っているはずだ。さて久しぶりに発売された38作目の本作は、その期待に応えてくれたであろうか?
残念ながら、それは望むべくもなかった。ブラスの録音が余り良くないせいもあるが、ブラスのアンサンブルを前面に出した豪快なサウンドは鳴りを潜め、ポップロックの聴きやすいメロディーに、ワンパターンのブラスの伴奏を被せた楽曲がほとんどで、クリエイティブかつサプライジングなアレンジを聴けなかったのは、寂しい限りだ。もう彼らに余計な期待をかけるのは、やめるべきなのだろうか。そう思って、しばらく本作を聴かないまま数ヶ月が過ぎた。
だが新年を迎え、ふとした拍子に改めて車を運転しながら、このアルバムを十数回聴いているうちに、割と良い曲が揃っていることに気づいた。リーダーのロバート・ラムは相変わらず優れたソングライターだった。名曲「サタデー・イン・ザ・バーク」に匹敵するような親しみやすい曲を、本作でも多数披露している。パンコウとラフネインのブラス・アレンジもワンパターンではあるものの、細部において従来にはない、意表を突いた粋なアンサンブルを聴かせてくれる。歳を重ねることで彼等が作曲とアレンジ面で大きな冒険をしなくなったのは仕方がない。でも、良い曲をファンに提供する努力は怠っていなかった。シングルカットすれば、そこそこヒットしそうな佳曲が盛り込まれているのが分かった。そんな三人をしっかりとサポートする七名のバックミュージシャンも素晴らしい。彼らのおかげで、今でもシカゴは欧米でライブを精力的にこなしているというから、恐れ入る。往年のファンにこそ、リラックスして聴いてほしいと思う。
|
|
|
フュージョンの評論家、金澤寿和氏の肝煎りで発売された執念の企画である。82年にLP化、89年にCD化、91年にCDボックス化、92年に4曲追加盤、という不思議な変遷を辿った「カジノ・ライツ」は、当時のワーナー専属アーテイストによるトゥー・ナイツ・フュージョン・ライブとして熱心なファンに愛聴されて来た。ところが日本未発売のボックス盤には未発表テイクを集めた番外盤が入っていたため、何とかこれを日本で発売しようと金沢氏が尽力して、今回の2枚組発売へと漕ぎ着けたのだ。
プロデューサーは著名なトミー・リピューマ。どうも彼の影響下にあるミュージシャンがレーベルを超えて特別参加しているようだ。また金澤氏によればホーンセクションなどを後からオーバーダビングしているという。調べるといくつも楽曲に謎が浮上するところに、本作の面白さあると言えよう。それゆえ、ライブならではのメンバーの組み合わせで演奏がなされているのは、誠に興味深い。
クロフォードとジャロウのボーカルの応酬、カールトンやフォード、ラーセン、サンボーン、ミラーがバック演奏に回るなんて信じられない。イエロージャケットとマイク・マイニエリのグループ演奏もとてもエキサイティングで聴き応えがある。
なぜか、チック・コリアが一曲だけ参加しているのも謎めいているし、カールトンの名曲「ルーム335」を敢えて追加盤に収録しているのも、不思議でならない。でもその分、長いアドリブが楽しめてお得感がある。ライナーノーツに、アーティスト別に詳細な参加曲のクレジットが載っているので、これを手がかりに、珍しい組み合わせによるパフォーマンスをじっくりと聴き込むのが楽しいだろう。
|
|
|
フュージョンの最盛期の名盤発掘に力を入れているタワーレコードだが、今回はメジャーレーベルのワーナーのアルバム群からセレクトされている。強力アーティストを多数揃えている会社だけあって、本作も魅力的なラインナップだ。ただ著作権をクリアできない事情なのだろう、同一アーティストで複数曲を収録しているのは、いささか興冷めであるのは否めない。とは言え、名曲、ヒット曲が多数入っているし、懐かしいアーティストの楽曲もある。購入して損は無いと思う。
本作を力強く牽引しているのは、やはりデイヴィッド・サンボーンとマーカス・ミラーだ。マーカス自身のアルバムは収録していないが、他のアーティストの楽曲に積極的に参加しており、当時の彼の影響力の凄さを物語っている。全盛期のサンボーンのサックスの音色とブローの美しさは絶品である。スタッフのヒット曲も改めて聴くと、やはり永遠の名曲だと思う。全く色褪せない。個人的には渡辺香津美とロベン・フォードの演奏に痺れた。渡辺は実にアグレッシブでアバンギャルドなギターソロを弾いてみせる。ロベンはブルージーながらロック・スピリットに満ちたご機嫌なソロを弾いて、とても印象に残る。アクースティックギターの名手、アール・クルーの美しいギターワークも忘れられない。女性ボーカルの歌声が魅力的な楽曲を披露しているヒロシマが、まだ現役で活躍しているというのも驚いた。
モントルーでジャズ・ライブが今も毎年開かれている。その歴史の中で一度だけフュージョンのスペシャルライブが開かれ、カジノ・ライツと呼ばれた。ファンの間では伝説のライブとして語り継がれている。今から40年前に発売された、そのライブの特別編集盤が先ごろタワーから新発売された。奇しくも本作のワーナー出身ミュージシャンが多数参加している。つまり、それだけワーナーは当時のジャズ界を牽引し、リードしていたのだ。ぜひそちらも聴いてみて欲しい。珍しい組み合わせのジャムセッションが楽しめる。
|
|
|
日本を代表するフュージョン・バンド、カシオペアは結成45周年を迎え、25年ぶりに新しいドラマーを正式に加入させた。今井義頼である。彼が今回レギュラー入りした価値はとてつもなく大きい。これまで神保彰という偉大な天才ドラマーが長年カシオペアを牽引して来たからである。しかし、ついに彼を超えるドラマーが出現したわけだ。確かに今井のドラミングは軽快、かつ精密な技巧派タイプだ。ただ神保よりパワフルなのが、起用の一因だろう。そしてバンドもP4という名を冠して新たに出発した。
私は初期から彼らの音源を聴いてきたが、正直言って第2期の途中から演奏も曲もマンネリ化して、次第にファンから脱落した。それ以来の購入であるから、大いに期待した。そしてその期待に違わず、彼らのサウンドは躍動しており、嬉しくなった。
第4期のP4は、本来のカシオペア・サウンドが帰ってきた印象で、とても溌剌としている。M1からM5まで怒涛の演奏が繰り広げられ、圧倒された。勿論、野呂節とも言える、歌謡曲っぽくて分かりやすいメロディラインも健在だから、従来のファンも満足だろう。本作ではリーダーの野呂が一歩退いて、他のメンバーに伸び伸びとプレーさせていることが功を奏したのだろう。さらに野呂はソングライティングに今回、重きを置いたとしか思えないくらい、気持ち良くノリのいいメロディを書いている。ベテランの鳴瀬もいつになく力強いベースラインを刻んでいる。とりわけキーボードの大髙のハモンド・オルガンの音色が素晴らしい。彼女はようやく才能を開花させた。また、各楽曲が似た曲調にならないよう、アレンジも工夫が施されているのが分かり、念入りにチェックがなされたに違いない。
たまたま同じ時期に、もう一つの日本フュージョンの双璧、ディメンションの新譜も発売された。こちらも早速聴いてみたが、残念ながらこの対戦はカシオペアに軍配を上げざるを得なかった。ディメンションはここ数年間、低迷している。カシオペアを見習い、大改革が必要であろう。
|
|
|
プログレッシブ・ロックの金字塔と称される半世紀前の名盤だが、イエスの作品の中でも、最高傑作として位置づけられ、今でも度々リマスター盤が出ては、その原音の高音質ぶりにファンはうれしい悲鳴を上げていた。本作もヘッドフォンで聴くと、その原音の良さに驚き、身体が震える。本作を聴きながら朝、散歩すると恍惚感を味わえると、あるカスタマーが書いていたが、あながち誇張ではあるまい。
私が最初に聴いた時は高校生でプログレ全盛の頃だったから、組曲風の大作が2曲も入っていることには驚かなかった。しかし、アンダーソンの透き通った高音域ボーカル、ハウの緻密なギターワークには度肝を抜かれた。さらに驚いたのは、スクワイアのハウリングを起こしたような図太いベース音とブラフォード独特の甲高いスネアのリムショット音であった。いずれの音も雷に打たれたような衝撃を受けた。キングクリムゾンもピンクフロイドも当時、あんな音は出せなかった。一方、ウェイクマンのキーボードはクラシック的な音階をまだ引き摺ってはいるものの、徐々に独創的なメロディを作り出していた。このメンバーの仕事は早くも、ジャンルを超えて音楽の粋を結集させた一大絵巻となり、未だ追随を許していない。
ただ歌詞については難解極まりない。発表当時のライナーノーツにある訳詞は意味不明な言葉で綴られており、形而上学的と評された。だが洋楽曲訳詞サイト「りりっくりすと」に掲載された「危機」の完璧な訳詞文を拝読して、やっと得心できた。アンダーソンは読書家であり、ヘッセのシッダールタに影響を受けたという。主人公が悟りの境地を開いたのが川で、彼も川に人生の安住の地を見出し、死の恐怖が消えたという。そうした苦悩から生まれた本作の音楽世界は、どこまでも深く広く、今後も聴く者に人生の新たな意味を考えさせるであろう。
|
|
|
ディスコ・ブームが最高潮に達していた1970年代後半。アースの人気は頂点に達していて、毎日メディアで「セプテンバー」など彼らのヒット曲が聞かれた。当時、大学生だった私は友人に誘われて、初めてディスコティックに出かけた。聴く方に一辺動だった自分がダンスをするとは考えもしなかったが、なんとなくその場の雰囲気に合わせ無難に乗り切ったことを覚えている。とにかく恥ずかしい一夜であった。
しかし、EW&Fはその頃からどんどん進化していった。ところがアルバム「太陽神」が出てピークに達した彼らは、なぜかその後、徐々に求心力を失ってヒットチャートから遠ざかっていく。実は、その遠因にリーダーのモーリス・ホワイトの病気が影響していたことは余り知られてはいない。どうも彼は元々丈夫ではなかったようだ。本作のライナーノーツを読むと、その辺りの事情が書かれており、興味深い。
いずれにせよアースは当時、無敵のバンドであった。それは本作のライブ音源を聴けば明らかである。聴衆の歓声と熱気は半端なく、演奏もそれに応えて完璧である。サックス・ソロなどの即興演奏が多いライブを聴くと、彼らのルーツはアフリカンであり、ジャズであることが明確に分かる。私はそのことに強い共感を覚える。しかしビジネスとして成功するには、ジャズだけでは難しい。きっと彼らも悩んでいたに違いない。だからこそ本作は、剥き出しになったアースの正体と本質が、思う存分味わえる。
スタートから怒涛のアフリカンリズムを前面に押し出し、聴衆を引きつけていく。そして私の大好きな曲「太陽の女神」ではファンキーなギターのカッティングに合わせて、重厚なホーンセクションとベイリーの高音ヴォイスが美しいハーモニーを奏でる。つまり彼らこそ、ソウル、ファンク、ポップ、ジャズをフュージョンさせた最高のエンターテインメント・バンドであった。事実、彼らを超えるようなトータルな演奏をするバンドは以後、現れていない。
|
|
|
カスタマーヴォイスで前回、タニア・マリアを取り上げた。となれば、男性のMBS(ブラジルで最も影響を与えたポピュラーシンガー)は誰なのか、と疑問が湧く。もちろん思い浮かぶのはイヴァン・リンスだ。1980年代になり、優しい歌声が主流だったブラジリアン音楽界に、彼は敢然とポルトガル語の力強いロック・ヴォーカルで、路線変更を試みた。すると、その斬新で説得力のある響きに、アメリカのマイナーレーベルが好反応して、本作は制作された。さらに彼の才能にいち早く気づいて、アメリカのフュージョン音楽界に引き入れたのが、ギターの大御所、リー・リトナーである。彼の名盤「ハーレクイン」の中で、リトナーはブラジリアン・サウンドを大胆に取り入れて、ヴォーカルに彼を起用した。私もこのアルバムで、イヴァンの凄さを知った。だが、そうした経緯を辿った故に、イヴァンにとってアメリカ進出は本意ではなかったかもしれない。それでも本作で披露される楽曲はいずれも、彼の新境地を感じさせるオリジナルな曲想に溢れ、親しみやすいメロディー、且つ英語の歌詞という戦略も相まって、大ヒットした。
私は当時、来日した彼のライブを、渋谷のクラブで観る幸運に恵まれた。会場は物凄い熱気で盛り上がり、皆が踊り興じていた。フュージョン音楽が隆盛した只中にあったから、彼のブラジリアン・サウンドも、日本の若者にはトレンドとして受け入れられたのだろう。
彼の歌声は、ジョージ・べンソンやダイアン・シューアなど名だたるミュージシャンにも強烈なインパクトを与えて、多数カバーされた。独特の旋律と唸るような節回しは、不思議な高揚感を与え、転調などの意外性もあり、世界中の人々を魅了した。惜しむらくは、ドラムマシンやシンセサイザーなど流行りの音に頼りすぎた単調なアレンジである。相当急いで制作されたとしか思えない。どれも良いメロディーラインを持っているだけに残念でならない。
|
|
|
タニア・マリアは、私が1980年代の頃に夢中になって聴いたアーティストだ。当時、斑尾高原スキー場の野外コンサートでも、彼女の生の歌声を聴きながら踊る幸運にも恵まれた。また先日、西友で買い物をしていたら、タニアの名曲「ドントゥ・ゴー」がBGMで流れて来て驚いたのだが、西友は最近、割と意識的に店内でフュージョン系音楽を流して、顧客をリラックスさせる戦略を採用していると聞き、嬉しくなった。
彼女の魅力は何と言っても、軽快なラテンリズムに載せてスキャットの歌声とエレピをユニゾンで即興演奏するという得意技である。これをライブで乗りに乗ってやれば、大受けするのは当然だろう。だが、アルバムとなると、なかなか難しい。ブラジル出身のジャズピアニストとしてフランスで着実に経験を積み、アメリカに進出して成功したのだが、それは同時に大衆にどれだけ歩み寄ってポップスやロック、ダンスミュージックの要素を取り入れるかという妥協の産物になるのが常だ。ゆえにアルバム全体の出来はどれも中途半端になってしまう。
そうした観点で80年代のアルバムを改めて聴き直してみた。すると、本作が最も肩の力が抜けて彼女らしさが出ていて、伸び伸びと歌っていることが分かり、楽曲自体もメロディアスで他より優れていた。とりわけインストルメンタル曲のM5におけるジャズ・パフォーマンスは、彼女のピアニストとしての才能が迸っており、聞き応え十分である。また冒頭から4曲目までのボーカル曲もそれぞれ印象的なメロディーとリリック、そしてスキャットを披露しながら聴き手を盛り上げていく。終盤のタイトル曲も、哀愁を帯びたチキチキ風の佳曲である。
バックの演奏もツボを心得た好ましいアレンジで、安心して聴いていられる。派手さがない分、リラックスして全員が演奏しているのが良く伝わってくる。フュージョンという枠組みで考えた時、ラテンリズム、ブラジリアン、ジャズ、ピアニスト、ボーカリストというマルチな要素をミックスさせた彼女の独創性は、もっと評価されていい。
|
|
|
ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズとは、血と汗と涙を意味するが、そもそもこの言葉は、イギリス首相のウィンストン・チャーチルが、第二次世界大戦の最中に英軍を鼓舞するために演説した文章から引かれたものだった。但しその言葉には、もう一つ「労苦」という単語が含まれていた。その後、血と汗の結晶とか、汗と涙の結晶という変形バージョンでも使用され、一般に知られるようになった。この由緒ある言葉を冠したアルバムこそ、ジャズロック、ブラスロックという当時の新ジャンルを語る上で、欠くことの出来ない。何故ならBS&Tの名を世界的に知らしめたあの名曲「スピニングホイール」を収録した記念碑的アルバムだからだ。当時、洋楽の洗礼を受けた私たちは「スピニングホイール」の冒頭で繰り出されるブラスのファンファーレに、雷に打たれたような衝撃を受けた。BS&Tは知らなくても、このファンファーレは誰もが聞き覚えがあろう。テレビやラジオ番組のジングルとして使われてきた。ジャズのフレーバーを漂わせたそのメロディーはとても新鮮で、フォークやサイケデリックなロックに飽きた若者達が飛び付いた。一方でプラスロックの雄、シカゴが遅れてデビューし、チェイスというトランペット部隊を前面にフィーチャーしたバンドも登場すると、ジャズロック、ブラスロックは最盛期を迎える。私は当時、テレビの歌番組で和田アキ子がチェイスの「黒い炎」を熱唱していたことを今でも覚えている。本作はセカンドアルバムだが、シングルカットされてヒットした曲が多い点でもBS&Tの傑作として位置付けられる。残念だが、デビューアルバムは凝りすぎて、テクニックに溺れた中途半端な内容になり、仲間割れを招いた。その後メンバーの再編が行われ、ヴォーカルに起用されたのがデヴィッド・クレイトン・トーマスであった。彼が先述の「スピニングホイール」を作曲した。そのしゃがれた声とシャウト唱法は、一度聴いたら忘れられないほど魅力的で、彼は後にBS&Tの牽引役になっていく。さらに本作は、トータルアルバムとして見ても完成度が高い。エリック・サティの有名なワルツを冒頭とラストで取り入れたり、カントリー調の楽曲やフリージャズ風の長いインスト曲を組み入れるなど随所に工夫が見られる。もちろんブラスによる高度なアンサンブルも聴き応え十分だ。吹奏楽をやる若者達にぜひ聴いて欲しい。
|
|
|
本作はカールトンのアコースティック・アルバムの傑作「アローン・バット・ネバー・アローン」の続編的作品だが、こちらの方が、ファンやフュージョン愛好家には馴染みがあるかもしれない。彼がにこやかに微笑んでいるジャケット写真も珍しいから、親しみ易さが増したであろう。そして曲調も、どちらかと言えばロックとポップス寄りのアレンジで制作されているので、彼は本作で知名度を上げたはずだ。ジャズ志向の「アローン」の大成功に味を占めたレコード会社が、おそらく二匹目のドジョウを狙って、企画されたであろうことは想像に難くない。
だが、その商売っ気は、本作では大いにプラスに作用しており、実に聴き応えのある内容になった。エディー・フロイドの往年のヒット曲「ノックオン・ウッド」やドゥービーブラザーズの名曲を挿入した辺りに、彼の遊び心が感じられる。冒頭の「ハロー・トゥモロー」は、カークウェイラムのサックスをフィーチャーした素晴らしい余韻が味わえる佳品である。彼はキーボードのボブ・ジェイムズとも組んで、優れたデュオアルバムを出しており、私はその才能を高く評価している。
5曲目はカールトンの代名詞でもある「ルーム335」を思わせるようなグルーヴ感溢れる楽曲で、思わずニヤリとする方々も多いはず。そして7曲目が「ミニット・バイ・ミニット」である。ここでのキーボードは作曲者のマイケル・マクドナルド本人であろう。コーラスやブラスの音も入っていて、とても豪華な仕上がりになっている。こうした馴染み深い曲を織り混ぜてアピールしている本作は、カールトンの人柄や音楽的嗜好が良く出ていて、彼のディスコグラフィーの中でも、メジャー志向の強い作品として異彩を放っている。是非とも「アローン」と聴き比べて楽しむことをお勧めしたい。
|
|
|
ジャズ、フュージョンを問わず、世のギターフリークたちに人気が高いのが、ラリー・カールトンだ。彼の代表作「夜の彷徨」の中の名曲「ルーム335」で披露された、流れるような美しいソロパートの演奏に、誰もが魅了されるのは無理もない。だが、それ以外のアルバムとなると、これがなかなか難しい。一長一短あり、競演ものなら、あれこれ候補が上がるが、単独作品となると、なぜか本命がない。だが地味な作品として位置付けられる、アコースティック・ギターを駆使した本作と、翌年の続編作「ディスカバリー」こそ、自信を持ってお勧めできる彼の代表作である。エレクトリックギターだけが、彼の売り物ではないことを再認識させてくれる。
カールトンは元々、ジャズ志向の青年でジョー・パスに師事していたくらいだ。またビッグバンドでもギターを担当していた。ザ・クルセイダーズに参加してから、交友関係と芸域を広げていったのであろう。一方で、彼はブルース音楽も非常に好んでおり、時折、旋律やアドリブにブルースのコードやメロディを垣間見せることもある。その後参加したフォープレイの創立メンバーの一人、リー・リトナーには以前から影響を受けていたという。本作も続編も、リトナーと良く似たギターフレーズが随所に聴き取れて、楽しくなる。
単なる聴きやすさを狙わずに、ちょっと捻った音階に進むのが彼のメロディー作りの特徴である。本作はスローとミディアムテンポの佳作ばかりで、数曲のソロも含む。ギターのパートではゆったりと時間をかけて難度の高い演奏をしている。一方で続編は、ドゥービーの名曲やサックスのカーク・ウェイラムをフィーチャーするなど、より万人受けする志向になっている。さらに両作品は、伴奏のアレンジがとても優れている点でも、特筆に値する。当時流行していたソフトアンドメローの路線を堅持しつつも、フュージョンの王道らしい、シンプル且つ高品質のパフォーマンスを展開しているので、名うてのミュージシャン達の職人芸に酔いしれるがいい。
おそらくカールトンは、人気が高まるにつれ、自身の将来の方向性に悩んでいたのではないか。それでアコースティックに挑戦し、図らずも全米で売れに売れてグラミー賞も獲得した。故に本作は、彼にとって真の金字塔であり、もっと再評価されるべきだと考える。
|
|
|
今から半世紀近くも前に繰り広げられた、ジャズ、フュージョン史上に残る西ハリウッドのクラブハウスでの名演である。当時はまだLPで発売されていたので、わずか40分しか演奏時間がない。しかも最後にはメンバー紹介のシーンまで記録されているから、実質的には35分ぐらいしかないだろう。それでも本作を、クルセイダーズの最高傑作として位置付けても文句は出るまい。普通、ライブ録音だと2枚、3枚組と長尺になるものだが、彼らは濃密な編集作業に挑み、クラブ内の熱気を再現しつつ、聴衆との掛け声なども再生させながら、白熱の演奏をあえて短い40分に凝縮させた。自信の程が窺える。
その熱気は冒頭のタイトル曲から溢れ出ている。リズム隊の力強いビートが観客の気持ちを鷲掴みにしていく。そこにサックスとトロンボーンの太い旋律がかぶさり、場内は早くも興奮の坩堝と化す。ビートルズの名曲「エリナー・リグビー」のカバー、「ハードタイムズ」と曲は進み、いよいよ場内は最高潮を迎える。ギターにラリー・カールトンが入った、当時の最高編成によって繰り広げられた名パフォーマンスだ。アメリカが誇るシンガー・ソングライター、キャロル・キングの定番を、美しいアレンジで蘇らせた「ソー・ファー・ラウェイ」が始まった。二管があの切ないメロディーをユニゾンで吹いていく。よくあんな繊細で哀しい旋律を管楽器に歌わせたものだと、聴く度にいつも思う。
カールトンの強弱を効かせたボリューム奏法が曲調にとてもマッチして、控えめなのが良い。短いソロが終わると、二管が静かな単音のロングトーンで盛り上げる。そろそろ終わるかなと思っていたら、まだ吹いている。1分はありそうな長い吹奏。そう、音を出しながら呼吸を続けるエキスパート奏法である。心配した観客がストップ!と声を発する。ようやく終わって、ギターの力強いソロパートに戻ると観客は安心したのか、やんやと喝采を送る。
そしてウェインによるメンバー紹介。これがまた場内の雰囲気を良く伝えており、臨場感は醒めることなく最終曲へと続いていく。どうやって40分に収めたのか、不思議でならないが、至福の時間はこうしてラストを迎える。
|
|
|
言わずと知れたフュージョン、あるいはAORの分野での超名盤である。あまりに売れたので、一種のトレンドとして当時の日本のメディア、特にラジオで頻繁に聴かれた。本作を当時LPで聴いた方は、この斬新なジャケットに衝撃を受けたに違いない。私も驚いた。こんな古めかしいDJの再現場面をあえてデザインしたからには、当時のフェイゲンには相当回顧的な思考があったのであろう。日本以上にラジオがメディアの重要な位置を占めていた1980年代のアメリカでは、若者たちにとって、今のネットのようにラジオが最新情報入手の最速手段であった。無論、日本の私たちの世代もラジオからトレンド情報を得た。テレビは中高年向けのダサいメディアだった。だから彼がそんな時代の、さらに前の50年60年代を懐かしんでいるのは、とても共感できる。人々はゆったりと自由に流行を楽しんでいた。40年以上前に彼は、現在のウェブ時代における個人が情報を無秩序に発信する危険性を察知していたのかもしれない。そう考えれば本作の価値は、いやが上でも増す。やがて到来するデジタル時代のアンチテーゼとして作られていたわけだ。
しかし一方で、本作は当時のデジタルサウンドの最先端を行く技術で録音されていた。そこに私はフェイゲンの生き方にある種の行き詰まり、やるせなさを感じてならない。彼は元々オタク的志向があり、部屋にこもって黙々と自分の音楽を極めていた。故にバンド活動に失敗して、一流ミュージシャン寄せ集めという手法で「エイジャ」という大傑作を作り上げた。ところがこれは金がかかり過ぎて、同じ手法は続かなかった。しかしソロ活動を成功させる上で、この手法はどうしても捨てられない。故に再び採用して成功した。
彼の策略はまんまと嵌った。若い音楽ファンが本作のノスタルジックなリズムとメロディに注目してくれた。それは彼にとって望外の反応であっただろう。ただ、その後が続かなかった。流石のフェイゲンも更なるアイディアは枯渇していたということか。
|
|
|
ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーが率いて人気を博したロックグループがスティーリー・ダンだが、1970年代、大学生だった私は、このバンド名はリーダーの個人名を冠したものだと勘違いしていた。ところが彼らが路線変更し、人気のジャズミュージシャンを多数起用して新作を発表したというから、これは大変だと急いで買って、聴きまくった覚えがある。そしてタイトル曲を聴いてみると、とんでもないドラムとサックスの掛け合いが演じられていた。私と同様、当時のフュージョンファンは度肝を抜かれたはずである。何故なら、ウェザーリポートのショーターとスタッフのガッドという超人気バンドの二大スターが、ロックバンドのアルバムで客演するなんて信じられなかったからである。そのくらい、本作はエポックメイキングな価値があり、今も名盤としても語り継がれているのも当然だろう。
たくさんのオタク的愛好家が本作を批評し、分析しているから、私がとやかくいう必要はない。ただウェブであれこれ調べてみると、いくつか貴重な指摘があったので、紹介しておくと、タイトル曲は元々、組曲を意識して作られたという。確かに転調の仕方とかリフの変化などにそれを予感させる。また英語の得意なシルバーサック氏は本作の全歌詞の翻訳を試みているが、これを読むと、エイジャは女性の名前とアジアの意味を掛けた意味深長な言葉であることが分かり、フェイゲンが当時、二胡が奏でる中国及び東南アジア音楽に夢中になっていたことも知った。
どの楽曲も旋律が素晴らしく、アレンジや構成、ソロパートのメロディに至るまで、練りに練られており、完璧な出来栄えである。どの楽器は誰が演奏しているのか、曲ごとのパーソネルを見ないで、推理して聴いてみるのも楽しい。だが、フェイゲンとベッカーは結局、本作以上の優れた作品を作り出すには至らなかった。そこが二人にとって、大いなる皮肉である。ベッカーは体を壊してしまい逝去、フェイゲンも個人活動に主軸を移し、名作「ナイトフライ」を産み出すも、以後は静かな活動にとどまっている。
|
|
|
ジャズ・クルセイダーズ時代の演奏を知っている方なら、おそらく私と同様、半世紀以上もフュージョン系音楽を聴き、愛してやまない、筋金入りのジャズファンであろう。そのクルセイダーズ結成時のピアニストこそがジョー・サンプルであり、その美しいメロディラインに魅せられたファンは、世代を超え、今も世界中で聴き継いでいるに違いない。
彼は2014年に亡くなっているが、試しにネットでサンプルのことを調べてみたら、多くの音楽ファンがブログに、彼の作品と演奏の素晴らしさを取り上げていて、とても嬉しくなった。そんなファンにとって、今回の名盤三部作をコンパイルした2枚組CDは、文字通りのお買い得品である。いずれも、LP時代の作品で曲数が少ない。しかしその分、中身は濃密で徹底的にアレンジを重ねている。どの楽曲も、聴く者の印象に強く残る、美しく清楚なメロディを持ち、無駄なアドリブや間奏もない。
サンプルのピアノソロ・パートは独特で、左手をあまり使わず、右手だけでシンプルに単音を刻んで、主旋律から少しづつアドリブで音を外していく。シンコペーションも余り使わない。それ故、クラシックのピアノソナタを聴いているような錯覚に陥ることがある。あえて抑制した弾き方を続けながら、彼はより綺麗なメロディラインを探究していたのかもしれない。
サンプルは、電子ピアノのフェンダー・ローズの名手であったことも有名だ。これを使う時はかなりジャズ的、ブルース的なメロディラインに変貌する。昔、クルセイダーズのライブ録音をラジオで聴いたことがあるが、観客と声を掛け合いながらフェンダー・ローズを巧みに操り、徐々に会場を盛り上げていくアドリブ奏法は見事であった。
レインボー・シーカーとカーメルは彼の最高傑作アルバムと言っていい。半世紀近く経つのに、全く色褪せていない。いずれもクルセイダーズの盟友、スティックス・フーパーがドラムで加わっており、リズムに切れと躍動感を出している。
ヴォイセズ・イン・ザ・レインは前二作と比べ、やや内省的な作風だ。しかし、この落ち着いた曲作りこそ、時流に阿ることなく彼がやりたかった作品世界のような気がする。
|
|
|
AORとFUSIONに精通している中田俊樹氏の選曲によるスムース・ジャズの企画盤は好調な売れ行きだそうで、今回が第三弾となり、さらに趣向が凝らされている。コンセプトは表題に示されている通り、朝、午前中で、この時間帯に聴きたい曲をセレクトしたという。でも聴いてみたが、別に午後や夜間に聴いても何ら支障はない。Disc1はインスト曲、disc2はボーカル曲という括りで、さらに80年代のアメリカのラジオ局でよくかかったことも選曲のポイントになっているという。全曲を聴き通して、意表をついた選曲もあり、なるほどと思った。
こうした企画盤の良さは、前にも書いたが、未知のアーティストや楽曲に出合える楽しみがあることだ。ウェイマン・ティスデイル、ジム・ホーン、リック・ブロウン、ヘザー・マレン、エリック・ベネイ、ケヴィン・レトー、ドリイ・カイミといったアーティストは今回初めて聴いて、いずれも興味深く、とても個性的な演奏や歌を披露してくれた。懐かしい曲もたくさんセレクトされており、往年のフュージョンファンには、若かりし頃の想い出が甦ってくることだろう。私の場合、ベンソンとクルーによるデュオ・ギター演奏のジャマイカ、ベンソンのボーカルが冴えるプリーズ・ドント・ウォーク・アウェイ、カーリー・サイモンの情熱的な歌唱が見事なブルー・オブ・ブルーなど、青春期の甘酸っぱい、苦い体験などが思い出されて、胸にグッと込み上げるものがあった。
中田氏には悪いが、本作はdisc1よりdisc2の方が、断然聞き応えがあった。たぶんボーカリスト達の力量と楽曲の良さが秀でているからで、偶然かつ望外の収穫と言えるだろう。それでもdisc1で、ラリー・カールトンの生ギター曲やキーボードのジェフ・ローバーとサックスのジョージ・ハワードのソロの掛け合いが楽しい曲をしっかり収録しているのは、中田氏のセンスの良さをつくづく感じてしまい、溜飲を下げた。
|
|
|
アランは、エレクトリック・ギターを演奏する皆さんにとっては神の如き存在かもしれない。その演奏スタイルは勿論、ギターの音色と周辺機材の研究、バンドの組み方、アレンジの仕方など、どれを採っても職人気質の塊だからだ、立て板に水のように16分音符や6連符をいとも簡単に奏でるギターソロは、全く他の奏者を寄せ付けないほどの風格が感じられる。ゆえに同じユニットで長続きしないのも当然だろう。その彼が2017年にあっけなく逝ってしまった。晩年は離婚による財産分与や体調不良、セッション相手に恵まれない、などの理由で経済的に困窮し、機材を売り払ったり、ヴァン・ヘイレンの援助を得たりして、食い繋いでいたという。何とも哀れだが、孤高のギタリストには相応しい生涯だったのかもしれない。本作は、彼が生前に自身のソロアルバムからセルフセレクトしたベスト盤で、死後さらにリマスターを施した高音質盤である。私はアランの熱心なファンではないが、彼が渡り歩いたバンドやアーティスト、例えばテンペスト、ソフトマシーン、トニー・ウィリアムズ、ジャンリュック・ポンティ、スタンリー・クラークなどのプログレ系、フュージョン系の音楽を好んで聴いてきたので、そのギターサウンドには以前から惚れ込んでいた。あの粘っこくもサラリとした博多ラーメンのようなソロパートのメロディは、一度聴いたらやめられない。本作は2001年から1982年までに発表された作品から公平にピックアップされており、いろんなタイプのアレンジとギターソロが楽しめる。律儀な彼らしい選曲である。車中でほぼ一ヶ月間、毎日のように聴きまくったが、ちっとも飽きなかった。どの曲もはっきりした楽曲構成にはなっていない。基本はドラムとベース、時に鍵盤も従えたモダンジャズ的なフリーフォームが多い。淡々とギターがAメロ、Bメロ、サビを弾いているので、一聴するとどれも同じ曲のように聴こえるが、聴き込んでくると、アランなりにうっすらと創意工夫と計算を施したメロディラインであることが分かり、心地よさが体に湧いてくる。彼のソロは連音重視のスタイルで、途中に印象的な旋律を敢えて入れないことが多く、ソロに切れ目が無いのが特徴だ。これこそ彼が求めたギターサウンドの境地か。無我の境地で、メロディを奏でている。指が速攻でフレーム上を自在に動き回るのだ。渓谷を流れる沢の水音を聴いているかのようである。
|
|
|
クインシーと言えば、マイケル・ジャクソンの「スリラー」のアレンジャーとして有名だが、我々シルバー世代にはテレビドラマ「警部アイアンサイド」のテーマ作曲者として印象が強い。ドラマ冒頭のブラスのファンファーレは実にカッコ良く、今でもテレビのジングルにしばしば使われている。しかし彼は元々、生粋のジャズミュージシャンであり、ビックバンドの名アレンジャーとして名を馳せた。そしてフュージョン全盛時代には、人気歌手や超一流ジャズマンを集めて独自のアレンジとプロデュースによる名盤を残した。それが本作である。チャカ・カーン、ルーサー・バンドロス、パティ・オースチン、マイケル・ブレッカー、スティーブ・ガッド、アンソニー・ジャクソン、リチャード・ティー、エリック・ゲイル等、枚挙にいとまがない。なぜ私がこのアルバムを取り上げたかと言うと、4曲目に凄いアレンジの演奏があるからだ。作曲はあのハービー・ハンコック。エレピを聴けば、いかにもハービーらしい優しい旋律が流れてくる。前半はメローなアレンジでゆったりと展開していくが、間奏に入ると、ハービーのピアノソロに合わせてヴァイオリンが同じ旋律を弾いていく。予めスコアに起こしてあるのだろう、二人の一矢乱れぬユニゾンソロは徐々に大胆な音符を刻むようになり、まるで男女の心の抑揚を、あるいは性的な営みの様子を、そのままメロディに置き換えているかのようで、激しさを増していく。「テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー」と名付けられたこの曲はフュージョン史に残る名演で、二人のユニゾンソロは実に3分以上も続く。その他の曲はボーカルを入れたものが多いが、どの曲も美しいメロディとコーラスやストリングスを使った凝ったアレンジで、クインシーの才能が迸っている。AORの名盤としてしも長く聴き継がれるべきであろう。
|
|
|
プログレッシブ・ロックの頂点に君臨するクリムゾンのアルバムを批評するには、相当の勇気を要する。世界中にフリークやコアなファンがいて、彼らは日頃、熱心に情報収集をしている。ゆえに下手なことは書けない。とは言っても、フュージョン的な視点で自由に述べることぐらいは許されるだろう。私は高校生の頃からクリムゾンの主要アルバムを愛聴してきた。第一作の「宮殿」には心底、衝撃を受けた。ロックでもない、クラシックでもない、フォークでもない、唯一無二で曼荼羅のようなサウンドはまさにフュージョンだ。イギリス音楽の全ての要素が詰まっていると思う。ロック・ミュージシャンからそうした楽曲が生まれたことに、クリムゾンの偉大さを感じざるを得ない。UK気質ともいうべき思索の深さと真実を追い求める姿勢はビートルズ以来、あの国の音楽家たちに脈々と受け継がれている。コロナ禍の時期に、奇しくもクリムゾンは結成50周年を迎えた。予定のツアーはキャンセルとなり、資金繰りにも相当苦労したらしい。それでもアメリカツアーが2021年に実現したのは、やはり熱心なファンがいたからだ。ライナーノーツの写真を見ると、客席の熱狂ぶりが伝わってくる。マスクをしたファンがスマホのカメラをステージに向けて撮影している。この貴重な瞬間を記録しておきたいのだろう。メンバーとスタッフは連日バスで全米を移動してライブをこなした。体力的にも相当辛かっただろう。しかし、ファンの熱狂に彼らは素晴らしいパフォーマンスで応えた。難解なリズムとメロディを絡ませた名曲の数々を、正確かつ力強い演奏で再現した。最新のメンバー達の高度なテクニックに酔いしれるがいい。フリップの楽曲の美しさと恐ろしさに身を任せるがいい。彼もすでに70代後半になり、もうライブは聴けないかもしれない。昨年の日本ツアーもとても評判が良かった。間近で観られたファンには、本作は間違いなく一生の宝物となるであろう。
|
|
|
普段は忙しいのに、たまたま半日ほど暇が出来て、フォープレイの作品の古い奴を聴き直したくなった。するとやはり、初期のアルバムの方が分かりやすくて、メロディも親しみ易く、アレンジも多彩なのが分かった。無論、最近作がダメという訳ではない。ただ30年ものキャリアをグループが積み重ねていけば、段々とマイナー志向になっていくのは世の常だ。最新作の「シルバー」にしても、演奏のクオリティーは高いが、楽曲に印象的な旋律が乏しいのは、否めない。換言すれば、内輪で仲良く楽しんでいる、ベテラン・ミュージシャン達の楽屋芸に陥っている気がしてならない。その点、第二作に当たる本作は実に心地良いメロディの曲が続いており、フォープレイのベストに選んでみても、ファンに異論は無いだろう。しっかりとした主旋律で聴く者を捕まえるという、大衆音楽の王道がこのアルバムに貫かれている。上品で優雅なメロディをどうやってフュージョンらしくアレンジするのか、ここに、キング・オブ・フュージョンとして君臨するフォープレイの真骨頂があり、ファンもそれを期待しているのだ。どうかこの姿勢を忘れずに演奏して欲しい。ギターのリトナーはこの後去っていき、ラリー・カールトンに変わる。しかし、ジャズ志向のサウンドに、ロック寄りのラリーは最後まで馴染めないままグループを去り、後釜のチャック・ローブが引き継いだが、惜しくも病死して、現在活動停止の状態であるという。やはり王者のクオリティーを長年キープすることは難しいのか。しかし本作は、二作目だったからこそ、そうした懸念を慮ることもなく、大胆なアレンジやソロが盛り込まれている。どうかフォープレイが原点に立ち返り、そうしたアレンジの冒険と優れたメロディを前面に押し出すことで、2022年に復活すると願うばかりである。
|
|
|
前回のレヴューで、アン・サリーの歌声を褒めた。だから、彼女のデビューアルバムも紹介しておきたい。彼女は名古屋市出身の在日3世韓国人で、内科医と歌手を兼業している。これまで、あまり正面の顔写真を載せておらず、もしかしたらコンプレックスがあるのかもしれないが、デヴュー作となった本作のジャケット写真を、私は大層気に入っている。デビュー後、アメリカへ医学留学している時に本場のジャズを聴いて、歌唱に磨きがかかったというが、本作では、フュージョンの人気グループ、シーウィンドの名曲「ヒー・ラブズ・ユー」を選んでいた。私も大好きな曲だ。たぶんサリーも原曲のポーリン・ウィルソンの歌声が自分に似ているので、それに惹かれて歌ったのではないか。全く違和感なく、丁寧に情感込めて歌っている。それくらい彼女の歌声は魅力的である。一度聴いたら忘れられないほど、伸びやかさ、軽やかさ、涼やかさを併せ持つ美しい声質で、これはまさに天性の素質というべきだろう。本作は、いわゆるカヴァーアルバムで、ボサノバやポップス、映画音楽の名曲が収められている。ジョニ・ミッチェルの作品が二曲選ばれているのは、サリーがお気に入りのアーティストだからであろう。楽曲はいずれもメロディアスで、耳に心地良く、BGMにも最適だ。彼女の英語やポルトガル語の発音も小慣れており、洋楽アルバムに相応しいボーカリストとしての才能を備えていることが分かる。発表から、すでに20年経っているが、日本人プレーヤーによるバックの演奏も古びて聴こえることもなく、本作が新鮮さを保っているのも、特筆に値しよう。さらにトゥーツ・シールマンのハーモニカ、難波弘之のエレクトリックピアノが彩りを添えているのは、ジャズファンには懐かしくも嬉しい共演で、本作のようなフュージョンの名盤を聴くと、このジャンルの魅力と奥深さを、素直に実感出来る。是非とも多くの方に聴いてもらいたい。
|
|
|
タワーレコードがまた、素敵なフュージョンの企画盤を出してくれた。ジャズの音源を多数持っていたビデオアーツ社のレーベルから、タワーの馬場雅之氏が選曲している。かつてフュージョンの最先端アーティストを多数送り出した人気レーベル、イーストウィンドの名盤も収録されている。名ギタリスト川崎燎の曲もあり、懐かしさと共に嬉しくなった。一方で、リズム・ロジック、ジェナイ、ピラミッド、アル・マッケイ、ビル・マイヤーズなど、私には馴染みのない新しいアーティストの楽曲も含まれており、とても刺激を受けた。これこそコンピレーションアルバムの良さだと思う。本作は、フュージョンやポップス、ロックの人気曲をカバーしたdisc1とビデオアーツのアーティスト達のオリジナル曲を収めたdisc2という2部構成で、実に魅力的だ。とりわけカバー曲の選曲が心憎い。乗っけからヒー・ラブズ・ユー、アイ・ジー・ワイ、ヒューマン・ネイチャー、セプテンバーとヒット曲が続く。そのあと、スパイロジャイラとボブ・ジェームズの名曲が畳み掛けて来るのだから、堪らない。50代以上の洋楽ファンなら絶対に買いたくなるだろう。個人的には、アン・サリーの二つのカバー曲に聞き惚れた。彼女の軽やかで伸びやかで透き通った歌声は比類のないもので、ジャズシンガーの域を超えた万能感を感じさせる。m1でシーウィンドの名曲を彼女なりの解釈で歌い込んでおり、思わず唸ってしまった。カバー曲がオリジナルを上回る出来になることは、良くあることだが、サリーの歌声も決して例外ではない。ジェナイとリズム・ロジックのオリジナル曲も聞き応えがあり、もっと評価されていいと思う。ビル・マイヤーズのm3はEW&Fとの合作で、いかにもそれ風のサウンド作りだが、解説にある馬場氏のお店でのエピソードを、聴きながら追体験できるので、ぜひ楽しんでもらいたい。
|
|
|
サンタナの作品は、すでに何度かレコメンドしてきた。彼の官能的なメロディラインは、初期の頃から変わりなく、今も我々の心に突き刺さる。サンタナは、すでに70代半ばを過ぎるも、その創作意欲は全く衰えず、彼の活動は見事というしかない。しかも本作は人気ミュージシャンのフィーチャリングという流行の制作スタイルに挑んでいる。「スムース」の大ヒットで共演したロブ・トーマスをはじめ、スティーブ・ウィンウッド、チック・コリア、リック・ルービン、コリー・グローバー、カーク・ハメット、アリー・ブルック、ナラダ・マイケル・ウォルデンなど、その共演者たちは実に多彩だ。こうした面々と共演できた背景には、実はコロナウィルスのパンデミックの影響でスタジオ録音ができないため、リモートによる録音に頼らざるを得ないという特殊な事情があった。バックバンドも、妻や息子と娘、兄弟姉妹らファミリーの総出演でカバーしている。これもおそらくパンデミックの影響なのだろう。しかし、こうした苦労は一方で、思わぬ福音をもたらした。つまりアルバムタイトルにある「祝福と奇跡」とも呼ぶべき素晴らしい共演者たちとの共演を可能にして、予想を超えるパフォーマンスとなって結実したのだ。本作を聴いて驚いたのは、妻のシンディ・ブラックマン・サンタナのドラミングのうまさである。とても60代の女性ドラマーとは思えない、パワフルさである。サンタナの曲作りも巧みで、ラテンのリズムを基調に、バラードから激しいハードロックまで、聴く者を飽きさせることなく、共演者の魅力を引き出そうと努めている。まさにポピュラー界のレジェンドだからなし得た、快心の作品である。
|
|
|
マクラフリンは、1970年代から活躍しているベテランの超絶技巧派ギタリストだ。カルロスサンタナと白いスーツを纏って歩いている姿が印象的なアルバムも有名だが、なんと言っても彼を世に知らしめたのは「火の鳥」と題された組曲を収録した、彼の率いるマハビシュヌ・オーケストラの同名タイトル・アルバムである。いずれのメンバーも超絶技巧の持ち主で、各自の速弾き演奏が一体化して繰り広げられるパフォーマンスは圧巻の一語に尽きる。そういう彼が、新型コロナウィルスによる活動休止を余儀なくされる中で、気心の知れたメンバーたちと創作したのが本作である。彼は「休止中に溜め込んだスピリットを発露させたことで、メンバーとの絆も強くなった」と語っている。プロモーションビデオを見ると、リモートで本作は録音されたようで、メンバーの自宅にセットされた楽器を操る様子が映し出される。とてもリラックスした中で、久々のレコーディングを楽しんでいるのが見て取れる。どの楽曲も、そのリラックス感が良く出ており、マクラフリンのギターも、いつになく柔らかい速弾きメロディを奏でている。M3はロックダウン・ブルースというまさに休止中を意味するタイトルだ。スキャットとドラムのシンクロ演奏が楽しい。M4は珍しいマクラフリンのピアノ演奏。感染症の克服を願う、祈りのような曲だ。M5は完全なモダンジャズ演奏で、意表を突いた趣向。そして最後のタイトル曲は、マクラフリンの奔放なアドリブ演奏が満喫できる。全体的にロックビートをなるべく排除して、ノーマルなジャズ志向を心掛けたアレンジで、好感が持てる。彼が調子に乗ると陥りがちな、複雑で難解なメロディもほとんど無い。まさにリベレーションな雰囲気を体現した、コロナ禍中の逆転の発想から生まれた傑作でる。
|
|
|
久しぶりのレコメンド投稿である。私事で多忙を極め、書く余裕が無くなってしまい、半年近く休んでいた。そんな折に、ディメンションも久々に新譜を出した。いいタイミングだと思い、レコメンドを再開した。二人体制になって2枚目のアルバムである。前作をやや辛口に批評したが、今作は確実にレベルアップしている。20回以上は聴いたと思うが、それだけ長く聴けたということは五つ星を進呈して良いだろう。しかし、満足はしていない。新たな方向性が見えて来たことへのご褒美として、五つ星の評価をしたと考えて頂きたい。お得意の、複雑かつ無機質なメロディラインで奏でられるm1は、増崎&勝田コンビの健在ぶりを示している。しかし本作の最大の聴きどころは、m6とm7の二曲だろう。かなりジャズ寄りに傾いたアコースティック・ギターの旋律が楽しめるm6は、このユニットの新境地を感じさせる。私は以前から、彼らにもっとメインストリームのジャズに取り組むべきだと提言して来た。そんなささやかな要望がようやく少しだけ叶えられたのは、率直に喜びたい。m7は、そうしたジャズ志向をさらに深化させたチューンで、前衛的なアドリブの掛け合いが展開される。勝田はこのところ、かつてマイケルブレッカーが好んで吹いていたコード進行とは異なるスケールで、無機質なメロディを自在に操る奏法を究めようとしている。徹底的に究めるがいい。その果てにどんな新しいアドリブ奏法が生まれるか、楽しみである。若手ミュージシャンが多数参加しているが、まだキーボードやドラムスの工夫が足りない。もっとクリエイティブな音作りをしてバックアップすることで双頭コンビを支えて欲しい。パーカッションを加えてリズムに多彩さを出しても良いだろう。より大胆な変貌を期待したい。
|
|
|
このアルバムは15年ほど前に、たまたま仕事で渋谷に出かけた帰りに立ち寄ったタワーレコード渋谷店で、偶然見つけたものだ。確か店頭のPOPに、豪華ゲストミュージシャン参加で繰り広げられる斬新な音作りで、フュージョンファンにオススメ!というような売り文句が書いてあった。それで、衝動買いした記憶がある。しかし、このグループはもう一作出しただけで、消滅してしまったようだ。このオンラインでリストに挙げられているhemispheresのもう一つの作品は、全く別の同名グループであるから、注意されたい。ネットで検索すれば、Amazonとかdisc unionのサイトで、本作のジャケット写真が確認できる。チックコリアのバンドで活躍したデイブ・ウィックルやエリック・マリエンサル、その他、サックスのビル・エバンス、ボブ・シェパードなども参加しているから、確かに豪華だ。主軸メンバーはベースとドラムとキーボードの3人で、いずれもフランクギャンヴァル、スパイロジャイラ、イエロージャケットなどで活躍していた実力派である。素晴らしいのは、そのメロディとアレンジ、ソロパートのアドリブが渾然一体となって展開している点だ。チックコリアの「妖精」「マッドハンター」あたりのサウンドと彼のエレクトリックバンドのサウンドがミックスされた感じと言えば、想像がつくだろうか?エレピが入っているが、全体的にはアコースティックな音作りで、とりわけサックスのメロディが美しい。とても抒情的な曲が多く、聞き惚れてしまう。全曲パーフェクトな出来と評しても大袈裟でない。何故このバンドが消滅してしまったのか、誰かお分かりの方があれば、教えて頂きたい。まさにフュージョン界の隠れた名盤である。一人でも多く方に、本作の価値を共有できる日が来ることを祈るばかりだ。願わくば復刻されんことを。
|
|
|
フュージョン、AORファンにとって、本作はAORの名盤中の名盤として知られている。中でもM6のハート・トゥ・ハートは、フュージョン界の名打てのミュージシャンが多数参加し、名演を繰り広げているのだから、堪らない。特に、間奏で展開されるアルトサックスのサンボーンのアドリブは何にも代え難く、極め付きの泣き節を聴くことが出来る。マイケル・マクドナルドのフェンダーローズも実に美しい。この曲はデヴィッド・フォスターとの共作というが、ロギンスの作曲と歌唱の才能が迸っていることも、実感出来よう。本作の発表は1983年。AORもフュージョンもピークを迎えていた。ロギンスは元々、ポップ、カントリー、ロック系の歌手であり、ロギンス・アンド・メッシーナという美しいコーラスを聴かせるデュオグループのヒットで知られた人である。ところがその後、彼の歌声を世界的な人気に押し上げたのは、フットルース、トップガンという大ヒット映画の主題歌に起用されたことである。おそらく作曲の能力を買われたのだろう。そんな絶頂期にいた彼でも、当時のAORの大波は無視できず、デヴィッドをプロデューサーに迎えて本作制作に至ったのだから、音楽のトレンドというのは恐ろしい。そういう経緯があるため、楽曲もやや異色なものが多い。効果音を随所に入れたり、スティーブ・ペリーとのデュオがあったり、TOTOやDooBieを思わせるビートの効いたギターサウンドがあったり、しっとりしたバラードもきちんと収められている。特にロギンスの綺麗なハイトーン・ボイスを生かしたメロディラインの楽曲が多いのは、親友であるデヴィッドの手柄だろう。
|
|
|
今は亡き名キーボード奏者、ジョージ・デュークとの双頭スペシャルバンドが残した、貴重なライブである。デュークはヤン・ハマーと並ぶ、フュージョン界の傑出したキーボーディストだった。とにかく器用でどんなタイプ今は亡き名キーボード奏者、とにかく器用でどんなタイプの曲であれ、卒なく弾きこなす。テクニックが優れているだけでなく、ハートもきちんと表現できる男だ。しかも本作では、DJ風のナレーションまで披露して、観客を盛り上がる。その語りに、ビリーの超絶技巧のドラムが絡んでくるのだから、盛り上がらないはずはない。お洒落でカッコいいパフォーマンスを満喫出来る。ドラムをやっている人なら、ビリーの演奏に思わず拍手をしたくなるのは間違いない。ビリーのドラミングは、絶頂期の頃だから冴えに冴えている。こんな速叩きは誰にも出来まい。ライブならではのアドリブも披露され、聴く者を興奮の坩堝に落とし込んでしまう。彼のテクニックに付いて行けるのは、デュークだけだろう。だから、この双頭バンドが成立したのだ。バラードからアップテンポの曲まで、まるでサーカスでも観ているようなスリルを楽しむといい。
|
|
|
このアルバムを、とうとう書く時が来た。その思いは、お読み下さる方には何の関係もない。しかし、私には最重要アルバムの一つである。何故なら高校、大学時代に、私が最も傾倒したドラマーだからである。彼の舐めるような速叩きドラミングは今も、比類が無い。凄いのは、オリジナリティに溢れつつも、他のミュージシャンのアルバムでは、彼はその超絶技巧をひけらかすことを、決してしなかった。私はその奥ゆかしさに惚れ込んだ。ドラマーの役割を熟知しているから、出しゃ張ることは嫌った。80年代当時、そうした彼の卓越したテクニックを上回るドラマーはいなかったはずだ。否、今もいないであろう。故にフュージョンブームの頂点で制作された本作は、コブハムの出世作、さらに最高傑作と言っていい。前作の「スペクトラム」では、速叩きばかり注目されて気の毒だったが、本作は、満を持しての制作であることは、ブレッカー兄弟など豪華な共演者を見ても実感出来る。組曲風の展開で奏でられる冒頭の楽曲は、9拍子の複雑なテンポにもかかわらず、全く違和感を感じさせない。途中に挿入される3分に及ぶドラムソロは、圧巻の一語に尽きる。イフェクトを掛けているが、何の抵抗感もなく、嵐の過ぎ去る様を見事に表現している。後半は、ブレッカー兄弟とのアドリブの掛け合いが面白い。今は亡きマイケルの、わざと調子を外すような無機質なメロディは、その後のサキソフォン・アドリブのお手本になった。タイトル曲は、新進のギタリスト、ジョン・アバークロンビーのソロが面白い。私は某専門学校の文化祭で、この曲のドラムを演じた思い出がある。文化祭としては、かなりトンガった選曲だったかも知れない。でも、そのくらいフュージョンは当時、絶大な人気があった。本作はフュージョン全体を見渡しても、ミュージシャンの熱いスピリットが溢れ出ており、重要な役割を持つ名盤である。録音が素晴らしいことも、付け加えておく。
|
|
|
ベノアは、フュージョンの世界ではとても知られたピアニストだ。グラミー賞候補にも数回選ばれている。彼の存在が特異なのは、モダンジャズの奏法ではなく、クラシックの手法でジャズにアプローチしてきた点で、それが彼の持ち味である。若い頃、ビル・エヴァンスに傾倒したと聞くが、その後GRPレーベルのデイブ・グルーシンと、本作の制作をきっかけに出会ったことで、彼の奏法やアレンジにも、グルーシンからかなり影響を受けたようだ。ベノアの美しいメロディラインが、エヴァンスとグルーシン由来であるなら、至極納得がいく。フュージョンがピークを迎えていた80年代半ば、本作タイトル曲を聴いた時は少なからず衝撃を受けた。ソフト・アンド・メロー、あるいは複雑化した旋律と超絶技巧を競うという二極化したフュージョン・シーンに飽きてきたファンに、彼の溌溂としたクラシカルなピアノ奏法と右手の単音だけで弾く美しいメロディは、心を洗われるような新鮮さをもたらした。旋律はまるでイージーリスニングのようだが、伴奏のアレンジは上質のジャズがベースになっており、時にストリングスや琴、パンフルートを加えるなど、かなり凝った音作りになっている。それら聴けば、グルーシンの肝入りによりGRPが強力に彼をプッシュしていたことが分かる。本作は彼にとって実質的なデビュー作であり、出世作でもある。前後して出た「ディスサイドアップ」「サマー」も傑作だから、ぜひ併せて聴いてほしい。正直、晩年の彼はクラシカル路線から脱皮できずに、向かうべき方向を見出せていない。どうか原点に立ち返り、独特の力強くて美しいメロディを、フュージョンのリズムに乗せて奏でてくれたら、と願う。
|
|
|
本作は、残念ながらすでに絶版となり、中古を除いて入手困難なアルバムである。しかし、92年発表の本作はフュージョン界にとって、知る人ぞ知るプレミア付きの名盤であり、私にとっても秘蔵のアルバムと言っていい。レコード業界関係者の方々に、もし拙稿が目に留まったのであれば、是非とも名盤の復活としてご検討いただきたい。とは言ってもファットバーガー自体もかなり激しい変遷を辿っており、サウンドも変容している。後半は単なるダンスミュージックに堕落してしまい、現在は活動していない。私が熱愛しているのは、ギターのスティーブ・ローリーが在籍していた頃の1980-90年にかけての、ソフト&メロウのフュージョンが大流行した時代のサウンドである。時流に逆らった彼の古風なオクターブ奏法は、ウェス・モンゴメリーやジョージ・ベンソンに全く引けを取らないテクニックで、エレガントでエモーショナルだが、時に切なく悲しい音色も放つ。その彼とキーボードのカール・エバンスjr.が双頭となって活動した80年代が、ファットバーガーの絶頂期だったと確信する。エバンスの流麗なアドリブ・ラインも、ローリー負けず劣らず美しい。ローリーをフューチャーしたアルバムは「グッド・ニュース」と「リヴィング・イン・パラダイス」「タイム・ウィル・テル」の3作で、それらから選曲されたのが、このベスト盤である。全曲が、当時のフュージョンが目指した、最高に心地良いベクトルのサウンドを、ほぼ完璧に奏でている。メインの旋律といい、アドリブのメロディといい、リズム隊の工夫といい、実に情感豊かで身を任せられる。凡百のヤワな、流行をなぞった当時の人気アーティストの楽曲とは全くちがう、上質なインストルメンタルの世界が展開する。極力イフェクトを通さない、生の音色で勝負するローリーのギターは、聴く者の胸にじわじわと染み入って来る。ぜひ若いジャズファンも、彼のオクターブ奏法の美しさを、心往くまで堪能して欲しい。
|
|
|
若い洋楽リスナーが一体、ピンクフロイドのことをどれだけ知っているだろうか。ここ10年くらいは活動休止状態だったから、知らないと言われても仕方がない。だが、我々シルバー世代はこのバンドの存在は忘れることはできない。中学生の頃に聴いた「吹けよ風、呼べよ嵐」「マネー」という大ヒット曲は、海外ロックの底知れぬ多様性と奥深さを少年たちに知らしめた。そして本作のライブ会場となったネプワースも当時、参加したバンドにはかなり思い入れの深い、因縁めいた場所だったらしい。音楽学校設立というチャリティー目的の二日間のライブだったが、イギリスの大衆音楽の発展に貢献したバンドが選ばれて出演したというから、それなりのプライドと責任を担ったパフォーマンスを、25万人に及ぶ大聴衆は求めたに違いない。そして、その要請にアーティストも真摯に応えた。オアシスなどもかなり緊張と興奮をしたことを後日語っているし、フロイドのメンバーも同様の発言をしている。前置きが長くなったが、ロックミュージックの過渡期、曲がり角にぶち当たっていた1990年という時期に、このライブが開催されたのは、必然だったのかもしれない。過渡期なのはフロイドにとっても同じ。にもかかわらず、デイブ、ニック、リチャードの3人がそれぞれ元気にプレーし、コラボしている姿を完全再現しているのだから、悪いはずがない。プログレシッブロックという20世紀の財産を頑なに守り続けた意地が見事に開花している。意外に音源は高音質だし、演奏にも手抜きは全く見られない。名盤「鬱」の発表直前だったいうタイミングも貴重だろう。30年の時を経て、完全CD化されたことを素直に喜びたい。
|
|
|
本作は、2007年のエモーショナリー・ブルーに続くジャズ色が強いアルバムだ。ダンサブルで親しみやすいメロディが特徴の、シャカタクお得意のポップ・チューンは数曲しかない。ライナーノーツによれば、本作はとりわけメンバーたちの嗜好が反映されているという。プロデューサー任せの音作りが排除されて、個性的なナンバーが並んでいる。個人的にはM7からM12までの曲構成がとても気に入っている。前半はシャカタク定番の軽快なリズムに乗せたポップな曲が多い。M1とM2はジルの作詞と思われるが、前者は息子を励ますような人生の応援歌であり、後者はタイトル曲だが、エロティックに男女の燃え上がる性愛を歌っている。ビルの憂いに満ちたメロディをインストルメンタルで演奏し、サビの部分で一気にボーカルやコーラスを絡めて盛り上げていく手法が、これまでのシャカタクの最大の魅力であった。しかし最近はこの手法を採用せず、導入部からボーカルを挿入する方法が増えている。それだけリリック重視の志向に傾いているわけだ。M9もジルのナンバーで、男に魅了されていく女の切ない姿を、滝の流れのように落ちていくと歌っている。こうしたセクシーな曲が聴けるのは、ベテランの技らしくて嬉しい。M8はサックスとギターをフィーチャーした完全ジャズナンバー。M10とM11はいずれもベースのジョージのナンバーで、タワーオブパワーを思わせるファンキーな乗りで異色だ。本作以降、彼らは再びポップな路線を意識し、原点回帰していく。
|
|
|
日本のフュージョンファンにとって、シャカタクは、もはやレジェンドと評されるべき存在だ。愛すべき宝物と称してもいい。40年以上も支持されている実績は何者にも代え難い。私も80年代から聴き続けているから間違いない。彼らが弛まぬ努力をしているから、こちらも聴き続ける。そんな暗黙の了解がある。日本人が何かに精進する姿勢に、彼らのサウンドがフィットしているからなのか。ともかく非常に相性の良さを感じる。テレビ朝日の深夜のお色気番組「トゥナイト」のテーマソングで知られるようになった彼らだが、決め手になったのはビル・シャープのシンプルで印象的なピアノだ。お色気とは異質の、爽やかで親しみやすいメロディに、若者たちが魅せられた。洋楽の斬新なグルーブ感に、新たなエンタテインメントの方向を見出し、ディスコ全盛時代に強烈な一撃を与えた。最近のシャカタクはメンバーが歳を重ねたせいか、ジャズ志向をより強めている。やむを得ないが、それなりに切磋琢磨を続けている。本作はその長い過程で、一つの頂点を極めた名盤である。クルマの中で何度聴いたことか。盤面は傷だらけで、ケースもほとんど壊れている。それでも運転に疲れてくると、このCDを取り出してしまう。静かなアレンジに乗せた、ビルのピアノの美しい響きとジルの優しい歌声には、何度聴いても魅せられてしまう。初期のビートの効いたサウンドはもはやない。逆に抑え気味のベースとドラムの音が妙にハートに迫る。大都会に住む現代人のアンニュイな気分が見事に表現している。個人的にはM1-6,M10-12の曲の流れがとりわけ心に沁みる。もしあなたが彼らの出世曲、ナイトバーズしか知らないなら、それは一生の不幸である。レジェンドの偉業を、ぜひ本作で味わうといい。
|
|
|
フュージョン界では、比較的マイナーな位置にいるダン・シーゲルだが、きっと日本でも熱心なファンが密かに存在する、そう私は確信している、頗る素敵なキーボーディストだ。入手できるアルバムはほぼ全て聴いているが、いずれも期待を裏切らない。真面目で良心的なアーティストと言っていい。同系列のピアニストにディヴィッド・ベノアがいるが、彼はメジャーになってからジャズ路線から外れてしまい、つまらなくなってしまった。が、シーゲルはスタンスを崩さず、マイペースでジャズを楽しんでいる。そこが気に入っている。本作は1989年の作品だが今、聴き直してみても、極上のスムース・ジャズである。全く出しゃ張らないサウンドが、実に好ましい。仕事をしながら、聴いても全く気にならないだろう。それほどの心地よさだ。それでいて、どこか記憶に残る美しいメロディ。アコースティックな音を基調にしながら、さりげなく電子音も加えて作るアレンジは、見事という他ない。抒情的な展開を見せる楽曲は、少しメランコリーで、時にはエンカリッジな気分になる。最近のシーゲルは、ベースのブライアン・ブロンバーグと意気が合って、ほぼモダンジャズ・スタイルのトリオ演奏を基軸にしている。ナチュラルな志向を目指す彼であれば当然だと思うが、やや内向的になり過ぎて、メロディの親しみ易さが無くなった。ここで、もう一度、原点回帰の演奏に立ち返ることを期待している。
|
|
|
ジャズのフュージョンと言えば、スタッフを思い浮かべる世代は、恐らく私と同じ60代前後のリスナーだろう。それくらい、80年代当時の日本で、もてはやされたバンドだ。メンバーのいずれもが、名うてのスタジオ・ミュージシャンかセッション・ミュージシャンだったから無理もない。当時、私は大学の合コンで、他の女子大生たちとスタッフのライブを後楽園ホールで楽しんだ思い出がある。それほどの大人気だった。ジャズとは縁もゆかりもない女子大生がジャズを聴いてくれたことに、ひどく感激したものだ。そんな懐かしい記憶も呼び起こす彼等は、こうしたコンピレーションアルバムを聴くと、やはりレジェンドであることに、改めて気付く。その完璧なパフォーマンスは全く古さを感じさせない。本作はタワーレコードのオリジナル編集だが、その選曲には相当苦心した跡が窺え、ファンとしては嬉しい限りだ。disc1はほぼ予想された内容だが、disc2は意表をつく選曲でセンスの良さを見せている。というのも、メンバーが他のアーティストのアルバムに多数共演していることは周知な事なのに、それらの楽曲をレーベルの制約を超えて編集するという試みは、これまでなかったからだ。この点は解説の金澤氏の言う通り、特筆すべき事であろう。本作の最大の売りと言っていい。disc1はライブ音源が多数あるのが魅力だ。現在、休眠状態になっていて、すでに物故者が何人かいることも考え合わせると貴重な記録である。リチャードの温かなキーボードの音色が最大の魅力だが、ゲイルとデュプリーのギターソロ合戦も聴き逃せない。そこにゴードンの力強いベースとガットの性格無比のドラミングが絡む職人芸的な演奏は、まさに彼らだから醸し出せる極上の一体感である。
|
|
|
前回のボイスに続いてスペシャルEFXを取り上げる。何故なら若い人たちに知って欲しいからだ。上質なフュージョンとは彼等のようなサウンドであることを、分かってもらいたいのだ。本作は、相棒のジョージ・ジンダが亡くなり、彼の遺志を継いでキエリ・ミヌッチが作ったアルバム群の中でも、とりわけ優れた出来栄えと言えよう。クルマの中でよく聴いていたのだが、改めて家のスピーカーで聴くと、その凝った音作りが再確認出来て、やはり本作はフュージョンの傑作だと思う。打楽器を控えめながら効果的に入れているのは、ジンダへの畏敬であろうことに間違いない。しかもミヌッチは心地良いサウンドに甘んじることなく、かなりドラマティックな構成で曲を書いている。これは従来のEFXには見られないコンセプトである。まるで美術館で様々な絵画を鑑賞しているような楽しい心持ちになる。天国のジンダも、この斬新な展開には驚き、きっと拍手を送っていることだろう。パットメセニーもウェザーリポートもなし得ない、ライト感覚のフュージョンで綴った物語世界が、目の前に広がって来る。そうした視覚的なサウンドでありながら、ドライブの邪魔にならない辺りが、彼等の控えめの曲作りの魅力である。入手困難なようだが、ぜひ探して聴いてみて欲しい。
|
|
|
このグループを知っているフュージョン・ファンは、日本では少ないだろう。90年代にGRPレーベルから出したアルバムは、そこそこ売れたはずだが、その後リーダーの一人、ジョージ・ジンダが難病に冒されるというアクシデントから、活動が思うに任せず、ずっとコンビを組んでいたキエリ・ミヌッチが後を継ぎ、ジンダの遺志を守っていくという、何とも不運な道を歩んでいくこととなり、彼らの革新的なフュージョンサウンドは熟成を果たさないまま今日に至っている。だが、このグループのオリジナリティは、30年の歳月を経た今も薄れることはない。二人のハイセンスな演奏はフュージョンの目指す高嶺をしっかりと表現しており、心地良い刺激と感動を聴く者にもたらす。パーカショニストとギタリストという意外な組み合わせのグループであった。だからこそ、そこにサウンドとしての革新性があったと言っていい。一聴すると、BGMのような耳に馴染みやすいメロディとリズムが展開していると錯覚するだろう。だが、よく耳を澄ますと、周到に考えられた音楽構成であることに気づくに違いない。ソフトでメロウな当時のフュージョン界に静かな抵抗を試みたわけだ。ソロ・パートのアドリブとアンサンブルの美しさを、控えめなアレンジで見事に融合させている。全くうるさくないサウンドこそが、彼らの真骨頂だ。そこに私は、彼等の革新性を見いだすのである。ジンダの控えめの打楽器音に、うっとりするような色気を感じられるならば、私があながち誇張した批評をしていないことが分かって頂けるだろうか。
|
|
|
正直言って、最近のパットは、明らかに行き詰まっている。最新作では、現代クラシック界の活況に進路を見出そうとしている。試聴してないので、余計な詮索は避けたいが、ジャズの手法をやり尽くしたと考えているのは確かだ。アドリブ重視のフリーな音楽追求に限界を感じて、クラシカルな手法を極めてみようと考えたのか。前作でも指摘したが、映画音楽のようなドラマティックな世界を求めた先に、クラシックの持つ正統音楽への再評価に気づいたのかもしれない。いずれにせよ彼は迷い続けている。そして、まだ出口は見えていない。そんなことを考えた時に、本作の存在を知った。メセニーグループの絶頂期のライブだ。デビュー以降、明るくライトなメロディーに、奔放でカントリー臭いアドリブはとても斬新で、若者達のハートを掴んだ。文字通りジャズ界に新風を巻き起こした。しかしその後、内省的な志向に変化し、現代が抱える大都会生活の不毛や国家間の対立に嫌気が差したのか、田舎や農村を思わせる曲調が目立ち、家族や友人などの絆を重視したタイトルが続くようになる。ファースト・サークル、スティル・ライフ、レター・フロム・ホームの三作がそれである。ライル・メイルズとの合奏による美しいメロディーラインを基調に、ギターシンセサイザーを取り入れてアドリブに強さを出した。さらにボーカリストを三名加えて、ボイスとギターのユニゾン奏法という驚愕のアレンジを開発し、厚みを加えた。チックコリアも同様の手法を試みたが、やはりパットの方がクリエイティブで感動的だ。こうした数々のチャレンジが結実して、ライブに於いても寸分の狂いなく再現されているのが本作である。フュージョン音楽の極致として位置づけても良いだろう。一曲目から最終曲まで臨場感に溢れた録音が聴かれ、完璧主義者のパットらしい、オリジナルに忠実な熱演には、唸る他ない。
|
|
|
たまたま80年代の名盤を物色していて、出合ったのが本作だ。こうした偶然の喜びがあるから、レコード収集は止められない。ライブ演奏で得られない、密かな愉悦と言って良い。アンディがポリス、ソフトマシーンに在籍したことは正直、忘れていたが、参加ミュージシャンが、イエロージャケットなどフュージョン系グループのアーティストに入っていることで、触手が動いた。早速聴いてみたが、期待に違わず素晴らしいインスト・アルバムであった。彼のギターワークは世評で言われる通り、技を極めたものであろう。過度の装飾を避け、出来得る限り余計なメロディを削ぎ落とした、究極のギター・アンサンブル作品であることは、一聴して容易に想像出来る。クルマで何度も聴いているうちに、彼の目指したサウンドはもしかしたら、最上にして最高峰の環境音楽だったのではないかと思った。何故なら、コンビを組んだキーボードのディヴィッド・ヘンツェルとの創造性豊かな、且つ美しいアンサンブルは、本当に見事であるからだ。抒情性と物語性を織り込んだ曲構成は、私にはピンクフロイドとキングクリムゾンの音楽世界を想起させた。無論、両者よりもっとポップな部分を目指して、アンディは取り組んだに違いない。でも抑制されたソロパートの中で、彼はどれだけ自身の感情を表現すべきか、そんな作業に腐心したことであろう。そして、その困難な目論見はほぼ達成されたと言っていい。まるで映画音楽を聴いているようなドラマティックな心地になる。現代人の心の不毛を描くマイナー調なサウンドは確かに、暗くどこまでも切ない。だが、ギターワークだけでなく、アルバム全体が目指す崇高なコンセプトを、リスナーが虚心に受け止めてくれるならば、その楽曲に込められた真摯な姿勢とクオリティは、誰もが感動を以って受け入れるであろうから、本作は永遠に聴き継がれていくはずだ。
|
|
|
1969年発表のシカゴのデビューアルバムが、半世紀ぶりにリミックスされた。これはファンにとって画期的なことである。買わないと人生の損失となろう。ポニさんがボイスで書かれている通り、再生音がオリジナルとは全く違う。定番曲「イントロダクション」を、イヤフォーンではなく、大音量のスピーカーで聴いてみると良い。その違いがはっきりと分かる。オリジナルはブラスセクション位置が左右に寄ってしまっていたが、本作では音像の中央に、三管がバランス良くに定位して、ど迫力のアンサンブルが蘇った。特にパンコウのトロンボーンとパラザイダーのサックスが聴き分けられるのが嬉しい。全曲を通して聴くと、テリーのギターとピーターのベースも、音域が広がって輪郭が明瞭になり、一音一音がきれいに聴き取れる。セラフィンのドラムも高音域のシンバルワークで迫力が増している。そしてボビーの抑制の効いた歌声が手に取るように聴こえるのが何より嬉しい。彼の説得力ある歌詞とヴォイスが初めて、本作で蘇ったと言って良い。一番驚いたのは、テリー・キャスの即興ソロ演奏である「フリーフォームギター」だ。これはリミックスならではの再現であろう。オリジナルを聴いた時は正直、ただメチャクチャに弾いているだけで何が良いのか、分からなかった。高校生だったから無理もないが。ところが本作では、立派なフリー・ジャズ風の、創造性あふれた大胆な楽曲として蘇った。様々なイフェクトを駆使してギターの音色を変え、落雷のような爆音のような、或いは機械音のような洪水で、聴く者を奈落の底に転落させる。
|
|
|
ルカサーが久々のソロアルバムを出した。盟友、ジョセフ・ウィリアムズも同じ時期に同じレーベルからアルバムを出していることを考えると、いずれも、今秋から再活動するTOTOに向けたデモンストレーションなのだろう。本サイトに掲載された宣伝資料に詳しい制作経緯とエピソードが書かれているので、それらを読んだ上で納得したなら、本作を買うと良い。何故なら、ルカサーはほとんど新しい挑戦をしていないからだ。むしろ時代に逆行して、サウンドは70年代80年代の匂いがぷんぷん漂っている。ということは、かなりプライヴェートな立ち位置で、本作は制作されたに違いない。おそらくルカサーは、再活動を前にして原点へ還りたかったのであろう。気心の知れたメンバーを集めて自由に楽曲を創り、意外かつ新鮮な印象のカバー曲を選んでいる。何しろあのリンゴ・スターがドラムを叩いているのだ。昔に還ることで、未来の方向性を見出したかったのかも知れない。タイトル曲の歌詞にはその思いが色濃く滲んでいる。聴きどころはM3,M4,M6,M8におけるギターソロだ。ほぼ一発録りに近いパフォーマンスながら実に美しい、気持ちの籠ったソロ演奏を堪能できる。ソロ・パートだけは本気でやっているから聴き逃すなよ、と語っているかのようだ。こう言ったら、本人には怒られるかも知れないが。
|
|
|
昨年40周年を迎えたTOTOが今秋から活動を再開するという。それに先行して出されたのが本作である。同時にルカサーもソロアルバムを発表しているから、何やらキナ臭い感じもするが、当分この二人の動向からは目が離せない。TOTOのボーカリストとして活躍したウィリアムズが久々に放ったこの新作は、実に素晴らしい出来栄えだった。オリジナリティに溢れた、親しみやすいメロディと気心の知れたメンバーによる演奏は、完璧と言っていい。どの曲も美しいコーラスラインとハーモニーを基調としており、コンポーザーであり、ボーカリストであるウィリアムズの面目躍如といった感がある。相当アレンジをやり直しているのが聴いていると分かる。ボーカルの処理や楽器の使い方に細心の工夫と意匠が施され、全く隙がない。聴きどころは後半以降だろう。オープニングはブルージーなミディアムテンポの曲で幕を開け、TOTO風の軽快なリズムと親しみやすいメロディの曲で、聴く者を引っ張っていく。しかし、Pガブリエルのカバー曲を、娘のハンナ・リュイクが囁くように歌い上げるM6から様相が変わり、ワルツの曲やケルト風の曲が現れたり、ビートルズの名曲、イフ・アイ・フェルが歌われたりする。ラストは世界の破滅を暗示するような歌詞で締め括られる。変化に富んだ曲構成に圧倒されながら聴き入るばかりであった。今年屈指のアルバムであると、断言出来る。
|
|
|
メゾフォルテのベストアルバムはどれか、と尋ねられれば、ファンはサプライズ・サプライズと答えるだろう。もちろん、それは至極妥当なのだが、実はデビュー以降、本作までの一連の作品はどれも、甲乙つけ難いほどクォリティが高く、いずれもお薦めできる。しかし、89年の本作で、主要メンバーが繰り広げるパフォーマンスは頂点に達し、メロディやリズム、アレンジには余裕が感じられ、向こう受けを狙うような、派手な曲構成や演奏テクニックを見せつけることも無くなった。だから本作を、私はベストアルバムとして選びたいと思う。今もクルマの中で愛聴している所以である。格好良く言えば、フュージョンの王道を歩み続ける円熟味を増した演奏である。グナーソンの想像力あふれた素晴らしい鍵盤の音色と、カールソンのエモーショナルな泣きを抑えたギターワークが冴え渡っている。余計なワードを足さないシンプルなタイトルも一貫していて、そこから、敢えてインスト一本で勝負する姿勢が感じられる。こうした彼らの禁欲的な姿勢に惚れ込んだ日本のフュージョン・ファンは多いはずだ。ひょっとしたら、アイスランドという厳しい土地で育った彼らは、同じ島国の日本人とどこか感性が似ているのかもしれない。
|
|
|
フュージョン・シーンを振り返る時、メゾフォルテの存在を忘れることはできない。本作は日本でも異例のヒットとなり、その後のフュージョンブームを牽引した。収録された各曲は40年を経た今でも、テレビのバラエティ番組のBGMやラジオ番組のブレイク曲などに使われている。それくらい彼らのサウンドは耳に心地良く、映像にしっくり溶け込むメロディラインを有している。これはジャズの楽曲としては稀有なことで、それは、彼らのオリジナリティが永遠の魅力を持っている証でもある。小難しい解説をいきなり書いたが、楽曲は難しくない。未知な方は、とにかく本作を入手して聴いてみるがいい。ダンサブルで親しみやすく、映画のワンシーンを見ているような抒情的な高揚感と緊張感もあって、全く聴き飽きることがない。キーボードのグナーソンとギターのカールソンが中心メンバーだが、二人の作曲編曲の能力は有名フュージョンバンドと比べても桁違いにすごい。飛行機に乗っているようなスピード感、辺境の地に舞い降りたような孤独感と焦燥感、宇宙旅行を想起させる浪漫的な雰囲気などが、次々に聴く者の脳裏を掠めていく。
|
|
|
ジャズピアニストの巨星、チック・コリアが亡くなった。彼の弔いに何か拙文を謹呈したいと考えたが、余りにも作品が多すぎて、Wikipediaで調べても、選びようがない。ただディスコグラフィをじっくり眺めて、私とは最も親和性が深いリターン・トゥ・フォーエヴァーから選べそうなことは分かった。このバンドの革新性は群を抜いていた。保守的なジャズファンの度肝を抜き、骨抜きにする程の圧倒的な力を持っていた。当時高校生の私がジャズにのめり込んだのも、チックのおかげである。リターンの楽曲はハードロックやラテン、フリージャズ、クラシック、プログレッシブロックなどを取り入れて、まさに自由奔放にジャズのフィールドを駆け回っていた。この行動にこそチックの音楽性の全てがある。音楽の枠を打ち破ることに心血を注ぎ、新たなジャズの地平を築いたのである。そんなリターンの最終到達点が本作だと思う。物語形式の組曲が好きなチックは、宇宙への憧れをリターン前期で表現したが、それに飽き足らず本作では、中世の歴史世界に理想を求めた。まるで映画のサウンドトラックを聴いているような絵巻が、最高のメンバーのサポートを得て繰り広げられる。目まぐるしく変わるメロディとリズムは一糸乱れることなく、完璧のパフォーマンスを見せつけて圧巻である。それ以降もチックは、独自の編成で幻想的な歴史世界を描くことに腐心する。中でもスペインへの憧憬は自らの血筋がもたらしたのであろう。傑作アルバム、マイ・スパニッシュ・ハートで結実する。
|
|
|
迂闊にも、私は彼の存在を見逃していた。ただ前作のタイトル曲、ウォーキン・オン・エアは、元シカゴのボーカリスト、ジェイソン・シェフの新作にも収録されており、聴いていて気に入っていた。金澤寿和氏の解説によれば、熱心なAORファンに、彼の才能は早くから注目されていたというから、本作は文字通り待望の、そして渾身のアルバムであろう。これまで20回は聴いただろう、才気あふれるキーボーディストであることは疑いない。ただ批判を恐れずに言えば、どの曲もデジャヴー、既視感があることは否めない。「うーん、このメロディやフレーズ、どこかで聞いたことがあるな」と感じること頻りである。フュージョンやAOR、スムーズ・ジャズの人気アーティスト達の、あのメロディに似たものが、次々と登場する。継ぎ接ぎというのではない。彼らをリスペクトしているが故に、自分なりに消化したいという意気込みの表れからなのだろう。だから殊更、否定すべきではないのだが、やはり彼の豊かな才能を考慮すれば、そこは厳しく指摘しておきたい。前作を試聴サイトで確認したが、楽曲の出来は雲泥の差で本作の方が良い。つまり、彼も充分、今回はオリジナリティを意識していたはずだ。その点では本作は率直に評価したい。相当な準備を費やして本作が制作されたことは疑いなく、研究熱心なアーティストであることが窺える。聴きどころは、m1とm15だと断言できる。大方の曲はAOR系の佳品だから、とても心地良いが、デジャヴーは否めない。それを割引くと、この2曲はオリジナリティを感じさせる。クインシー・ジョーンズを意識しつつも独自のサウンドを展開している。さらにプログレッシブロックの細かく複雑なマイナーメロディが好きなのだろう。それを下敷きにした独創的な展開も感じさせる。どちらも大いに磨いて欲しい。その苦闘から本流のAOR路線でもオリジナルな楽曲が生まれるに違いない。
|
|
|
私が高校一年生の時のアルバムだが、その頃の私は、まだ洋楽の習いたてで、ドゥービーの知識もほとんどなかった。しかし、ロング・トレイン・ラニングの冒頭を聴いた時の衝撃は忘れられない。あのリズムギターのカッティングは、当時としては画期的だった。コードをリズミカルに奏で、かつリフレイン的に変化させて刻む奏法は、まだ確立していなかったからだ。その斬新さがあったからこそ、幾つかの大ヒット曲が本作から生まれたのだ。ジェフ.・バクスターが加入して、サウンドに厚みが増したことも大きい。ドゥービー前半の黄金期のアルバムと称されるの当然であろう。本作はトム・ジョンストンの作による曲が多いが、やはり彼のソング・ライティングの才能はずば抜けていた、と改めて思う。単純明快ながら飽きの来ない旋律に、しっかりとビートを効かせて、曲のグルーブ感を持続させていく展開は、まさに独壇場とも言えよう。さらにハーモニーの歌声も加えることで優雅さと抒情性を生み出しているのは、プロデューサーのテッド・テンプルマンの技だろう。ハードロック、カントリー、ブルース、フォークロアなど、様々なジャンルの音楽を巧妙に取り入れて、懐の深さを感じさせているのも、ドゥービーならではの魅力だ。この前半期のバンドは、シンプルな曲作りに見えるが、聴けば聴くほど色々な発見が出来る。後期のマイケル版ドゥービーとは対照的な魅力を持っていると思う。ぜひ聴き比べて頂きたい。
|
|
|
現在、50代以上の方々にとって、ドゥービーは青春期の忘れられないロックバンドであろう。とりわけ、本作収録のグラミー賞ナンバー、ファット・ア・フール・ビリーブスはテレビCMなどにも使われたから、馴染み深い。私が社会人になって初めてアパートを借りた時、部屋のラジカセから流れたイントロのピアノの連打は、何故かとても哀愁を帯びていて、今も耳に残っている。マイケル・マクドナルドの加入は、ファンの間でも賛否両論ある。結成当時の、力強いギターのリードでぐいぐいと聴く者を引っ張るストレートなサウンドは、トム・ジョンストンの伸びのあるダミ声と共に、ファンの心を圧倒した。それを潰したのはマイケルの仕業だというわけだ。もっともだと思うが、よく聞き込めば、前期のカントリー・ロック色は失われたのではなく、ソフィスティケードされたに過ぎない。本作の後半のチューンは、いずれもカントリーテイストの軽快なサウンドが奏でられ、伝統のドゥービーらしさが出ていてリラックスできる。聴きどころは何と言ってもm1からm5まで。マイケルを中心としたメロディアスな曲の連続だ。それらは、発売当時のLPならA面に収められたわけで、心憎いばかりの演出である。半世紀近く経た今でも、彼らのサウンドは美しく切なく、時に心躍らせる。
|
|
|
メリカン・ロックの雄、ドゥービーの貴重なライブだ。解散前の1982年に、前期と後期のメンバーがライブで一堂に会するのはこのアルバムしかない。ゆえにドゥービーの入門用には、打って付けのアルバムである。たくさんあるベストアルバムより、私はこちらをお勧めしたい。会場の雰囲気も和やかで、解散を惜しむ観客の思いがリアルに伝わってくる。オリジナルとは違うアレンジが随所に見られるのもファンには嬉しい趣向だ。同じバンドながら前期と後期でこうも違うサウンドになるのも珍しい。カントリー志向の田舎臭いロックを聴かせたトム・ジョンストンの力強いボーカルは、やはりアメリカそのものだ。ツイン・ドラムズという画期的なリズム隊が実にぴったりとハマる。トムが抜けて、バンドはマイケル・マクドナルドのワンマンバンドになったが、サウンド的には、ここから格段に広がりを見せた。当時流行り出したAOR路線を前面に打ち出したのである。名曲ファット・ア・フール・ビリーブズは、今聴いても素晴らしいメロディとリリックだ。とは言え、やはりライブ後半は前期の大ヒット曲で盛り上がりを見せる。この絶妙なバランスこそが、彼らの偉大さなのだろう。その後何度か再結成がなされたものの、もはや往時の輝きは残念ながらない。故に、こうしたレジェンド・アルバムが若い人たちにも聴き継がれることを切に願う。
|
商品詳細へ戻る