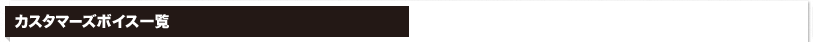
スウェーデン放送所蔵音源によるバイロイトの第9 / ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、他
|
|
長年聴き慣れたゲネプロと比較し、本番の演奏は、第1楽章のテンションが低く、不完全燃焼のまま終わる。ところが第2楽章で突如、火を噴くような凄絶な表現となり、少々、唐突の感がある。第3楽章では、フルトヴェングラーの表現にやや不自然なしつこさがあり、ゲネプロでの崇高な感情は、ここでは聴けない。終楽章もゲネプロでの極大なスケール感や神懸り的な高揚感には遠く及ばない。フルトヴェングラー未亡人が演奏の質から言って、1954年のルツェルンの第9こそ最高の演奏だったと回想したと伝えられているが、そのことが頷ける演奏内容である。
|
商品詳細へ戻る
侃々諤々喧々囂々さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
「くるみ割り人形」は1934~5年の録音とは思えないような非常に鮮やかな音質で、驚かされる。演奏もまた素晴らしい! 「アラビアの踊り」にしても「花のワルツ」にしても、これほど味の濃い演奏をした指揮者がかつていただろうか。30代半ばにしてベルリン・フィルを振って、これほどの演奏を成し遂げるとは本当に見事な才能の持ち主だったのだろう。敗戦直後のベルリンで米兵に射殺されたというのは痛恨の極みである。その殺害の直前の演奏では、「ロミオとジュリエット」が強烈だ。終結部の凄絶さは、かつて聴いたことのないものだ。
|
|
|
ワルターの数多い録音の中でトップを争う名演であると同時に、名盤の多い「ドン・ジョヴァンニ」の中でも断トツの名演である。1942年のライブでありながら、音質は良く非常に聴きやすい。2012年発売の輸入盤(WHRA-6045)も音質は良かったが、今回の国内盤の方が、より自然で落ち着いた響きになっている。さて、肝心の演奏についてであるが、これほど指揮者&オケがモノを言っているオペラ演奏は少ないのではないかと思われる。ワルター/メトロポリタン歌劇場管弦楽団は、強い集中力と推進力が一瞬たりとも途切れることがなく、その充実した響きの上で、題名役のピンツァをはじめとする歌手たちが実に伸び伸びと名唱&名演技を示している。本作品は、しばしば「デモーニッシュ」と言われ、そうした特性を最も良く表しているのがフルトヴェングラー盤とされるが、とんでもない!! フルトヴェングラー盤は、最晩年期の非常に落ち着いた演奏であって、このワルター盤こそが、本作品の全CDの中での唯一無二のデモーニッシュな演奏と言うべきである(デビュー当時のハーディングも良かったがワルターには及ばない)。そのデモーニッシュな演奏ぶりは序曲から既に明らかではあるが、地獄落ちまで聴けば誰もが納得するのではないか。3時間を優に超える長い作品であるにもかかわらず、本演奏を聴いてしまうと、また何度も繰り返し聴きたくなってしまう(良い意味での)”中毒性”があることも、本演奏の大きな特徴だ。これが「ドン・ジョヴァンニの毒」なのかもしれないが、それを味あわせてくれる唯一の演奏である。
|
|
|
本盤のフランクは、フルトヴェングラー(スタジオ録音)や、モントゥー、パレーと並ぶ名演として著名なもの。しかし、個人的には、ダンディの演奏を、より傑出したものと評価する。デュトワ=モントリオールが紡ぎ出す、この上なく透明で清涼な空気感は、本作品の魅力を最大限に引き出しており、非常に感銘深い。
|
|
|
陰鬱極まりない2作品だが、音楽的な美しさに溢れており、「単なる暗い楽曲」で終わっていない点が素晴らしい。とりわけ、ピアノと管弦楽のための交響的協奏曲は、楽曲・演奏ともに抜きん出ており、一聴の価値は大いにある。
|
|
|
ドイツの敗戦後13年、フルトヴェングラー死後4年という時期に録音された本盤は、「魔弾の射手」の演奏のひとつの規範となり得るもの。ドイツの民俗的な情趣が色濃く刻印され、当時のドイツの土臭くローカルな雰囲気が横溢している点が大きな特徴だ。そうした傾向が特に強く感じられるのは独唱陣である。プライのヒューマンな魅力も良いが、圧倒的に素晴らしいのは、アガーテ役のグリュンマーである。素朴で初々しい声と表現は、アガーテ役にぴったりであり、どの歌唱もよく感情が乗っていて聴く者の心を動かさずにはいられない。一方、本盤における個々の場面での演奏に関しては、特に「狩人の合唱」が聴きものである。当時のベルリン・フィルのホルンが、コクのある深い響きを聴かせており、コーラスもまた、世の中に数多ある「狩人の合唱」の中でも最高水準のものといってよい。ただ、「狼谷の場面」だけは、全体に迫力不足の感を否めない。とはいえ、全曲を聴いた後の充足感は非常に深いものがあり、名盤の名に恥じない優れた演奏だと言える。
|
|
|
ドイツの敗戦後13年、フルトヴェングラー死後4年という時期に録音された本盤は、「魔弾の射手」の演奏のひとつの規範となり得るもの。ドイツの民俗的な情趣が色濃く刻印され、当時のドイツの土臭くローカルな雰囲気が横溢している点が大きな特徴だ。そうした傾向が特に強く感じられるのは独唱陣である。プライのヒューマンな魅力も良いが、圧倒的に素晴らしいのは、アガーテ役のグリュンマーである。素朴で初々しい声と表現は、アガーテ役にぴったりであり、どの歌唱もよく感情が乗っていて聴く者の心を動かさずにはいられない。一方、本盤における個々の場面での演奏に関しては、特に「狩人の合唱」が聴きものである。当時のベルリン・フィルのホルンが、コクのある深い響きを聴かせており、コーラスもまた、世の中に数多ある「狩人の合唱」の中でも最高水準のものといってよい。ただ、「狼谷の場面」だけは、全体に迫力不足の感を否めない。とはいえ、全曲を聴いた後の充足感は非常に深いものがあり、名盤の名に恥じない優れた演奏だと言える。
|
|
|
シューリヒト最晩年期の素晴らしい記録。録音状態も良い。「ハフナー」は、はち切れんばかりの生命力に溢れた輝かしい演奏。しかし、それ以上に見事なのがレーガーだ。ロマン的な情感が楽曲の隅々に至るまで滲みわたっており、聴きこめば聴きこむほど、味わいが増すという何とも魅力的な名演である。この作品には、クナッパーツブッシュやベームの名演もあるが、シューリヒトの本演奏こそ、最高の名演と称えたい。ブラームス第2も、ロマン的な情緒が横溢しているが、終楽章に関しては、流石にもう少々の推進力が欲しいところだ。
|
|
|
セール価格(900円)になったので購入。受け止め方は人それぞれだと思うが、個人的には、正直、感心しない。感情移入が豊かで個性的な演奏ではあるが、では、それが聴き手の感動を喚起するかと言うと、どうもそういうわけでもない。指揮者本人にとっては必然性があるのかもしれないが、不自然で、時に芝居がかった表現が耳につき、感銘は薄い。ゴロワノフの演奏が多数900円になったので、この機に、いろいろ購入しようかと思っていたが、やめておこうと思う。
|
|
|
貧相な音質であることに加え、音量レベルが著しく低くマックスに近いボリュームで聴いても物足りない。1990年代に発売されたGolden MelodramのCDよりも、はるかに音が悪く、特にオーケストラ部分は壊滅的と評すべきレベル。そのため、たとえば、噎せかえるようなウィーン情緒を醸し出すクナならではの「銀の薔薇の献呈シーン」も、まったく活きていない。唯一の救いは、独唱者の声が明快に聴こえることで、オックス男爵を演じるクルト・ベーメの演技巧者ぶりに思わず微笑んでしまうほど。とはいえ、オーケストラの音質の貧相さはいかんとも為し難く、本盤は全体を通じ、この演奏の素晴らしさをほとんど伝え得ていない。現時点において入手可能な唯一のクナ=ウィーンの「薔薇の騎士」という点を評価して★2としておくが、近い将来、上記のGolden Melodram盤レベルのしっかりとした音質のCDが発売されることを期待したい。
|
|
|
残念ながら音が悪い。このレーベルのCDは、以前から音質の問題が指摘されていたが、本セットもそうした事例のひとつ。特に1940年代の録音は、極めてデッドで含みのない乾いた硬い響きに閉口させられる。1950年代から60年代初頭の録音も、ザラザラとした感触で、色艶のない干乾びた響きのものが多い。デッカのステレオ(スタジオ)録音はさすがにそこまでひどくはないが、音の鮮度はもうひとつだ。結局、音質面でのこうした状況ゆえに、往時のウィーン・フィルの典雅で時に甘美な音色的な魅力はほぼ味わうことができない。選曲面でも、「トリスタンとイゾルデ」の「前奏曲」が入っているのに「愛の死」は入っていないなど疑問が残る。このセットに何らかの良さがあるとすれば、入手が難しくなった音源も含まれていることだろう。その点をプラス評価して★2としたい。
|
|
|
3番が圧倒的な名演! ユジャワンは、リストやブラームスなどの19世紀ものも良いが、やはり、ガーシュイン、ラヴェル、ラフマニノフ、プロコフィエフなどの20世紀ものが特に素晴らしい。コンチェルトにおける指揮者との相性でいえばドゥダメルが抜群。それゆえ、約10年前にライブ録音されたドゥダメルとのラフマニノフのピアノ協奏曲第3番とプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番は、本当に素晴らしかった。そんなユジャワン&ドゥダメル・コンビが、満を持してラフマニノフのピアノ協奏曲全集を録音したというのだから、聴く前から結果は明らかだったと言えるが、やはり、非常に素晴らしい演奏である。3番を旧盤と比較すると、特に次の3点が顕著だ。1つ目は、ユジャワンの演奏は、陰翳が濃くなった。結果、演奏内容の奥行き、深みが一段と増している。2つ目は、ドゥダメルとのコンビネーションが格段に良くなっている。10年前も「相性抜群」と感じさせた見事な連携であったが、このたびの全集では、一切の隙がない、極めて緊密でスムーズな音楽づくりができており、その結果、楽曲解釈の整合性・統一感を含め、演奏の説得力が著しく高まっている。3つ目は、スタジオ録音でありながら、ライブ録音でもなかなかこうはいかないというレベルの凄まじい高揚感に満ち溢れている。楽曲全体を通じてハイテンションだが、特に3楽章終盤は、手に汗を握るほどの高揚を示していて感動的である。3番以外では、2番も印象的だ。前回のアバドとの録音では、アバドの非常にしみじみとした楽曲解釈に引きずられた印象のあったユジャワンだが、今回は、ドゥダメルとともに自己を解放しており、非常に吹っ切れた演奏になっている。結果、ロシア的な憂愁は希薄となっており、リヒテル&ヴィスウォツキ=ワルシャワ・フィルの演奏などを好ましく感じる方々も多いのではないかと推察する。1番や4番、パガニーニ狂詩曲も、上記と同傾向である。個人的には、やはりユジャワンのオハコである3番こそが本全集の白眉だ!
|
|
|
メインは武満徹の「ギターのための12の歌」であり、鈴木大介にとっては3度目の録音。四半世紀前の初回録音では、早いテンポで走り抜けていきつつ、千変万化するニュアンスが魅力的であった。それに対して、今回は、全体に遅めのテンポで、時にロマンチックに歌うのが特徴だ。「ギターのための12の歌」はビートルズ作品が3分の1を占める点がよく話題になるが、個人的には、革命歌(労働歌)「インターナショナル」がトリを務めている点が興味深い。19世紀以来、世界各国で歌われ、トスカニーニも、ヴェルディ「諸国民の賛歌」の中にこの「インターナショナル」を組み込んだトスカニーニ版を戦時中のアメリカで演奏していた。日本では労働争議や学生紛争などで頻繁に歌われたものだ。武満徹の編曲は、そうした原曲における、地の底から湧き上がるような力強さや高揚感からは一線を画した編曲となっており、鈴木大介の演奏がそれを助長する。それはあたかも遠い日の追憶のようですらある。「昭和は遠くなりにけり…」といった風情で感慨深い。
|
|
|
2007年6月のウィーン・ライブである。ポリーニは、同じくウィーン・フィルを弾き振りして、2005年5月に17番と21番をライブ録音しているが、本盤における12番と24番の演奏は、一段と素晴らしい! ウィーン・フィルとのコンビネーションもいっそう緊密なものとなり間然とするところがない。表現に関しては、両作品とも、春の陽射しのような暖かな幸福感があふれ出ているのが特徴だ。24番は、特に第1楽章など、得てして悲愴感を表に出す演奏が多いが、本盤では、哀感は微笑みの中に隠され、ふとした瞬間に顔を出す、という趣である。モーツァルトを聴く歓びに浸れる充実の一枚だ。
|
|
|
エルガーの交響曲第1番のあまりの素晴らしさゆえに5つ☆とする。同作品に関して、これまで十数種類の演奏を聴いてきたが、本盤こそ圧倒的な名演奏である。バルビローリもボールトも、そしてもちろんショルティなども遠く及ばない。全篇に漲る覇気と推進力、そして抒情的な部分で奏でられる情感漲る歌! 本作品は、「大英帝国の黄昏(あるいは残照、落日)」などと評されることが多いが、第1楽章冒頭で現われる循環主題が、第4楽章で再現される時に、コリン・デイヴィスが描出する力強い高揚感は、単なる“黄昏”や“落日”などではなく、逆に“陽はまた昇る”という確信に満ち溢れているかのようですらある。他の作品の演奏については敢えて触れないが、このエルガー1曲のためだけに購入する価値のあるセットである。
|
|
|
随所に録音年代相応の窮屈な部分があることは認めつつ、しかし、それでも、全体として、非常に生々しい音になっている点が特筆される。ドレスデン国立歌劇場の「魔弾の射手」といえば1973年録音のカルロス・クライバー盤が有名だ。クライバー盤が出たときは、その瑞々しい感性と、ドライブの効いたスリリングな音楽作りが圧倒的な評価を獲得する一方、重厚さに欠ける点を批判する声も多くあった。ところが興味深いことに、その22年前、1951年録音の本盤もまた、決して重厚と評せる演奏ではなく、やや軽めで見通しの良い演奏になっている。ケンペの指揮は、序曲における夢幻的な雰囲気豊かな表現で聴き手を一気に惹きつけるものの、幕が上がると、手堅い表現に終始しイマイチ…! ところが、見せ場の第2幕終盤の「狼谷」のシーンで、突然別人の如く燃え上がり、場を大いに盛り上げる。第3幕の「狩人の合唱」も、軽めながら早めのテンポで生命力あふれる演奏を示しお見事! 歌手陣に関しては、女性では、アガーテ役のトレッチェルとエンヒェン役のバイルケが好演を示しているが、クライバー盤のヤノヴィッツ&マティスには及ばない(特にバイルケ)。男性陣では、マックス役のアルデンホフと、カスパール役のクルト・ベーメが流石の歌唱を見せている。
|
|
|
演奏は☆5、CDの音質は☆3で、全体として☆4としておきたい。「目の覚めるような音質の良さ」を売りにしている本シリーズの中にあって、このCDは音が悪い。ワーグナーの管弦楽曲集で驚かせてくれた音の素晴らしさは、ここにはない。全体にくぐもったような鈍い音であり、近年、各社のCDにおいて、フルトヴェングラーの演奏が比較的良好な音質で楽しめるようになっていることを思うと、いささか残念な状況であると言わざるを得ない。たとえば、フルトヴェングラー最晩年の1954年に録音されたリスト「前奏曲」など、もっとクリアな音質のハズだが…(拙宅の再生装置が安物だから低音質なのだろうか!?)正直に言って、わざわざ買うほどのものではなかった(もっと良い音質のCDを保有しているので)。
|
|
|
ブラームス第4は、シューリヒトが遺した同作品の7つの音源の中でもっとも古いものだが、音質は明澄であり、たいへん聴きやすい。演奏は、明晰で見通しのよい表現に特徴があり、中庸なテンポでよく流れ、活力や推進力に事欠かない。しかも、ふとした瞬間に黄昏の情感が漂うのもシューリヒトらしいところだ。一方、バッハの管弦楽組曲第2番は、既出盤(1961年のフランクフルト放送響との演奏)より6年前のものだが、音質・演奏ともに、本CDの方が良い。ブラームス同様、明晰かつ活力・推進力に溢れた演奏だが、全篇に古雅な風情が漂い、非常に感銘深い。首席フルート奏者ペパンの妙技も聞きものだ。
|
|
|
モントゥーがベルリン・フィルを振った稀少な記録というに留まらず、モントゥー屈指の名演という意味でも価値が高い一枚。最初の「レオノーレ」序曲第3番からして、内部から放射される生命力の強烈さはその比を見ず、ライブならではの推進力と相俟って一気に聴かせる。しかし、それにもまして素晴らしいのは「ペトルーシュカ」で、モントゥーの放射するエネルギーとベルリン・フィルの名技性が相乗効果を発揮して、まさに光彩陸離たる名演奏に仕上がっている。それに対して、サンサーンスのヴァイオリン協奏曲第3番は、シュヴァルベが健闘しているが、巨匠・名匠たちの融通無碍な妙技を聴き慣れた耳には、いささか窮屈に聴こえる。
|
|
|
モントゥーがベルリン・フィルを振った稀少な記録というに留まらず、モントゥー屈指の名演という意味でも価値が高い一枚。最初の「レオノーレ」序曲第3番からして、内部から放射される生命力の強烈さはその比を見ず、ライブならではの推進力と相俟って一気に聴かせる。しかし、それにもまして素晴らしいのは「ペトルーシュカ」で、モントゥーの放射するエネルギーとベルリン・フィルの名技性が相乗効果を発揮して、まさに光彩陸離たる名演奏に仕上がっている。それに対して、サンサーンスのヴァイオリン協奏曲第3番は、シュヴァルベが健闘しているが、巨匠・名匠たちの融通無碍な妙技を聴き慣れた耳には、いささか窮屈に聴こえる。
|
|
|
フェリアーによる戴冠式頌歌 Op.44より 「希望と栄光の国」が、本盤の最大の聴きどころだ。ところが、フェリアーによる歌唱は、思いのほか淡々としたもので、少なくとも愛国的・感動的なものからは程遠い。他の作品の演奏については、今更言うまでもない著名なものなので、そうなると、わざわざ購入した意味は、いささか乏しいと言わざるを得ない。
|
|
|
2004年10月のミュンヘン・ライブだが、ティーレマンのブルックナー演奏の素晴らしさを知らしめる一枚となっている。堂々たる造型と、重心の低い骨太な響きをベースに、推進力に満ちた進行を見せる。特に感銘深いのが最初の2つの楽章で、たとえば、第2楽章の第2主題を歌う弦楽器群の輝かしくも意味深い響きは、かつて聴いたことのないものだ。全体を通じて、2021年3月録音のウィーン・フィルとの新盤を大きく凌駕する出来栄えと言っても過言ではない。
|
|
|
ティーレマンによるブルックナー第5といえば、2004年10月のミュンヘン・フィルとのライブ録音が、現役のCDとして購入可能であり、かつ、ティーレマンのブルックナーの素晴らしさを知らしめる名演奏であった。したがって、今回のウィーン・フィルとの演奏は大いに注目されるところだ。ミュンヘン盤では、全体に推進力が強く、時に動的な点に特徴があったが、今回のウィーン盤では、梃子でも動かない堅牢さが見られるようになっており、全体に独特の静けさが漂っている点が印象的だ。なかでも、第2楽章に関しては、とにかく丁寧にゆったりと情感豊かに歌い上げる姿勢が顕著で、時として、それが音楽の流れに停滞感をもたらしている点が惜しまれる。音楽がもたれてしまっているのだ。ミュンヘン盤との比較でいえば、総じて、第3楽章まではミュンヘン盤の方がより魅力的である。ウィーン盤では、第4楽章に至ってようやく調子が上がってきた感があり、同楽章に見られる生気が第1楽章から湧き上がっていれば…との思いを禁じ得ない。
|
|
|
ティーレマンによるブルックナー第5といえば、2004年10月のミュンヘン・フィルとのライブ録音が、現役のCDとして購入可能であり、かつ、ティーレマンのブルックナーの素晴らしさを知らしめる名演奏であった。したがって、今回のウィーン・フィルとの演奏は大いに注目されるところだ。ミュンヘン盤では、全体に推進力が強く、時に動的な点に特徴があったが、今回のウィーン盤では、梃子でも動かない堅牢さが見られるようになっており、全体に独特の静けさが漂っている点が印象的だ。なかでも、第2楽章に関しては、とにかく丁寧にゆったりと情感豊かに歌い上げる姿勢が顕著で、時として、それが音楽の流れに停滞感をもたらしている点が惜しまれる。音楽がもたれてしまっているのだ。ミュンヘン盤との比較でいえば、総じて、第3楽章まではミュンヘン盤の方がより魅力的である。ウィーン盤では、第4楽章に至ってようやく調子が上がってきた感があり、同楽章に見られる生気が第1楽章から湧き上がっていれば…との思いを禁じ得ない。
|
|
|
作業用BGMとして最高の2枚組。それぞれ短時間ずつではあるが、聴き慣れた作品の数々を、極上の録音で、そして、概ね質の高い演奏で聞き流すことができる。まとまった感銘を受けることがないので3つ星とするが、ありがたい存在だ。
|
|
|
アルプス交響曲は、シュターツカペレ・ドレスデンの音色の魅力を堪能できるという意味で、1970年代のケンペの同曲の名演を彷彿とさせる。1990年代以降、徐々に薄れていった同オーケストラの個性的な響きをここまで引き出してみせたルイージの手腕は本当に素晴らしい。ただし、楽曲解釈という点では、「その作品自体に語らせる」という趣きで、特段の個性は感じられない。それでも、「嵐」の迫力は特筆すべきで、ここでひとつの山場を築いている。一方、「4つの最後の歌」が始まると、ルイージ&シュターツカペレ・ドレスデンの演奏は俄かに雄弁となり、ソプラノのアニャ・ハルテロスともども、時にドラマチックな演奏を繰り広げる。オペラ的な表現とも言えるが、果たして、この作品の解釈として妥当なのだろうかと、個人的には違和感もある。
|
|
|
8番と3番で名演奏を示したティーレマンだったが、4番ではやや常識的な演奏に陥り、今回の2番では、いささか「熱量の低い」演奏に終始してしまった。2番には、楽曲の魅力を嫌というほど思い知らせてくれるヨッフム&ドレスデンという圧倒的な名演奏が存在するほか、孤独感や寂寥感が漂うティントナーの味わい深い演奏もある。それに対して、ティーレマンは、何を訴求したいのか明確なビジョンを示してはくれない。他の方もおっしゃっているように、全集録音の一環として、とりあえず取り上げたということか。ウィーン・フィルならではの美しい響きもあって、魅力的な部分はもちろんあるものの、まとまった感銘には至らないのが残念。ティーレマンなら、もっとできるはずと思わざるを得ない。
|
|
|
8番と3番で名演奏を示したティーレマンだったが、4番ではやや常識的な演奏に陥り、今回の2番では、いささか「熱量の低い」演奏に終始してしまった。2番には、楽曲の魅力を嫌というほど思い知らせてくれるヨッフム&ドレスデンという圧倒的な名演奏が存在するほか、孤独感や寂寥感が漂うティントナーの味わい深い演奏もある。それに対して、ティーレマンは、何を訴求したいのか明確なビジョンを示してはくれない。他の方もおっしゃっているように、全集録音の一環として、とりあえず取り上げたということか。ウィーン・フィルならではの美しい響きもあって、魅力的な部分はもちろんあるものの、まとまった感銘には至らないのが残念。ティーレマンなら、もっとできるはずと思わざるを得ない。
|
|
|
オケは生硬、ソロは貧相…で、どの楽曲も開始早々は、「どうなることやら…」と先行きへの不安を感じさせる。しかし、演奏が進むにつれて、オケも次第に落ち着き、こちらの耳も徐々に慣れてきて(?)、そんなことはあまり気にならなくなる。むしろ、「晩年のフルトヴェングラー(最晩年の衰えを痛感させる演奏ではなく、その直前期の演奏)」だからこそなし得た深さ・巨大さに圧倒されていく。「田園」におけるしみじみとした感慨深い表情、「運命」における深沈とした佇まいなど格別だ。「英雄」は第1楽章が圧巻である。フルトヴェングラーの他の「英雄」と比較しても、その仰ぎ見るようなスケール感において比肩するものがない。第2楽章以降はやや小型になるが、それでも、フルトヴェングラーの「英雄」の中でも屈指の名演奏であることは異論の余地がないだろう。
|
|
|
コストパフォーマンスが良くないので3つ星とする。本セットはショスタコーヴィチ第5だけで3種類の演奏が入っているなど、選曲に偏りがあり、寄せ集め感が強いが、実際、全部聴いてみても、玉石混交の感は否めない。コンヴィチュニー指揮のマーラー第5は、冒頭のトランペットが止まりそうになるなど、オケの技量が何とも頼りない。一方、クリュイタンスの「幻想」は、流石の貫禄を見せるが、ホールのひどくデッドな音響に足を引っ張られている。全部の演奏に関して書いているとキリがないので、やめておくが、音質と演奏の両面から満足できたのは、デルヴォーとマルティノンのみ。特に素晴らしいのはマルティノン、それも「春の祭典」だ。半世紀ほど前、日本の高名な音楽評論家が「マルティノンの春の祭典は涼しい」と評していたのがずっと記憶に残っていたのだが、実際に「涼しい」かどうかはともかく、圧倒的な名演だ。これまで数十種類の「春の祭典」を聴いてきたが、これほどまでに、イキイキと躍動する演奏は初めてだ。もちろん、マルティノン指揮フランス国立放送管弦楽団ならではの気品高い音色と洒脱な表現も存分に味わえる。あくまでも個人的な感想だが、マルティノンの全演奏の中でもトップレベル、「春の祭典」の全CDの中でもトップレベルと言えるのではないか。だが、この1曲のためだけに定価15,590円を
支払おうと考える人は、流石に少ないのではないだろうか?
|
|
|
廃盤で入手難が続いていたが、ウラニアが復刻してくれ本当にありがたい。しかも、音質は良く、音量レベルも高い。本演奏こそは、1942年の「ドン・ジョヴァンニ」メトロポリタン歌劇場ライブとともに、ワルターの全演奏の中でも特筆大書すべき名演奏である。オペラの演奏において、歌手ではなく指揮者がここまで雄弁にモノを言っているケースは稀有であろう。楽曲の隅々までワルターの血が通い、あらゆる箇所が意味をもって聴き手に語りかけてくる。ワルターは曲想を徹底的に抉り抜き、生気に満ち推進力に富んだ、しかも味の濃い、人間味豊かな「魔笛」像を提示してくれる。個人的には、ベーム&ウィーン・フィルのデッカ盤における澄み渡るような高純度の美演をひとつの理想形としてはいるものの、「魔笛」という作品を心から楽しんで一気呵成に聴き通すという意味では、このワルター盤こそ断トツであることを認めないわけにはいかない。大歌手が出演していない代わりに、歌手もコーラスもオーケストラも完全にワルターの手足となって、ワルターの目指す「魔笛」像を描き切っていると痛感される。どのアリアがどう良いとかいった次元を超えて、聴いている間も、そして聴後も、圧倒的な深い充足感に包まれる盤である。
|
|
|
小澤征爾の若き日の名演だ。前衛が熱かったあの時代にあって、同時代の音楽を何としてでも世の中に伝えようとする強烈な使命感がひしひしと伝わってくる。ヒリヒリするような火照りが漲っている点が、後年の演奏とはまったく違う点だ。とりわけ「ノヴェンバー・ステップス」は、切込みの鋭さ、音楽の深奥に迫る抉りの強さという点で群を抜いている。メシアンの「トゥーランガリラ交響曲」と並ぶトロント時代の代表的演奏と称してよいだろう。
|
|
|
1930年代のヨーロッパでは絶大な人気を誇っていたワルターが、ナチスに追われてアメリカに渡って以降、以前のような人気や評価を同地で得ることなく終わったのは残念なことであった。ニューヨーク・フィルの団員からは「ワルターに学ぶことなど何もない」という声もあったと記した書籍に触れたこともある。しかし、現代においてCDで聴くワルターのニューヨーク時代の記録には素晴らしいものが少なくない。本盤もそのひとつだ。気品に満ち柔和で時に甘美な「戦前期ウィーン・スタイル」とは一線を画した、奔流のように押し寄せる力強い表現と豊麗極まりない歌に満ちた演奏を、我々は聴くことができる。特に素晴らしいのは、世評通り、25番、35番、38番。29番は早いテンポで時に輝かしい表現を聴かせているが、曲想との間に若干の距離がある。また、5曲全部を通して聴くと、どうしても当時のニューヨーク・フィルの艶に欠ける音色に物足りなさを感じるのも事実で、(ウィーン・フィルではない以上、それはないものねだりであることは重々承知の上で、)☆1つ減としたい。
|
|
|
ベートーヴェンとモーツァルトに関しては、2016年にキングインターナショナルから発売された盤と、音質面で大差はない。あえて言えば、2016年盤の方が、音がパリッと冴え、響きが力強かった。それに対して今回の盤は、ややこもったような音色で全体に落ち着いたトーンになっている。もちろん、今回の方がよりナチュラルな音色と感じる人もいるだろうが、その微妙な差異のために定価4690円も支払う必要は感じない。2016年盤には含まれていなかったリヒャルト・シュトラウスの「ティル」をどうしても聴きたいという人向けか。
|
|
|
2005年5月のウィーン・ライブ。17番の傑出した演奏ゆえに5つ星としたい。ピアノ、オケいずれもが、澄み渡ったような美しい透明感を湛え、非常に純度の高い表現を成し遂げている。しかも、時として、愛くるしいチャーミングな表情を見せ、また、時に、ウィーン・フィルならではの気品高く優美な表現を聴かせる。さらには、推進力の強い覇気あふれる音楽進行を示す。結果、「17番って、こんなにも魅力的な楽曲だったのか」という驚きと楽曲再発見の歓びを味わうことになる。この17番と比べると、21番は、名演奏ではあるものの、そこまでの驚きや感動はなく、特に第1楽章などは、やや常識的である。それでも、第2楽章の美しさなどは、かつて聴いたこともないレベルであり、同作品における第2楽章の最高の名演奏であると称して差し支えないだろう(グルダ&アバドVPOより上に置きたい)。
|
|
|
2007年6月のウィーン・ライブである。ポリーニは、同じくウィーン・フィルを弾き振りして、2005年5月に17番と21番をライブ録音しているが、本盤における12番と24番の演奏は、一段と素晴らしい! ウィーン・フィルとのコンビネーションもいっそう緊密なものとなり間然とするところがない。表現に関しては、両作品とも、春の陽射しのような暖かな幸福感があふれ出ているのが特徴だ。24番は、特に第1楽章など、得てして悲愴感を表に出す演奏が多いが、本盤では、哀感は微笑みの中に隠され、ふとした瞬間に顔を出す、という趣である。モーツァルトを聴く歓びに浸れる充実の一枚だ。
|
|
|
2007年6月のウィーン・ライブである。ポリーニは、同じくウィーン・フィルを弾き振りして、2005年5月に17番と21番をライブ録音しているが、本盤における12番と24番の演奏は、一段と素晴らしい! ウィーン・フィルとのコンビネーションもいっそう緊密なものとなり間然とするところがない。表現に関しては、両作品とも、春の陽射しのような暖かな幸福感があふれ出ているのが特徴だ。24番は、特に第1楽章など、得てして悲愴感を表に出す演奏が多いが、本盤では、哀感は微笑みの中に隠され、ふとした瞬間に顔を出す、という趣である。モーツァルトを聴く歓びに浸れる充実の一枚だ。
|
|
|
「オーパス蔵」など他レーベルの復刻CDと比較して、非常に自然で、抜けの良い素晴らしい音質だ。ブルーノ・ワルターのピアノは、ピアノの巨匠たちのような超絶技巧はないかもしれないが、それでも、粒立ちの良い美しい音色は魅力的であり、気品に満ちた優美な表現が聴く者の心に滲みる。ウィーン・フィルの演奏も、戦前期のウィーン・スタイルそのものと言ってよいもので、スタイリッシュかつ時に甘美だ!この演奏の良さを存分に満喫できるCD-Rということで、本番の価値はとても高い。
|
|
|
「英雄」が衝撃的である! 冒頭より、ただならぬ緊張感が場を支配し、異様な集中力と緊迫感の中、早めのテンポ設定を基調にした、切っ先鋭く、推進力の強い音楽が一気に奏でられる。ムラヴィンスキーの他のあらゆるライブ演奏と比較しても、”攻撃性”の強さという点では他に類例を見ず、随所で見せる怒涛の寄り身には圧倒される。第4楽章におけるティンパニーの轟きも凄まじい。それだけに、表現の幅が逆に狭まり、”アグレッシブ一方”ゆえの単調さを感じる人もいるに違いない。その点でマイナス1☆としたい。ただ、ムラビンスキーの「英雄」としてはこれが一番の演奏だろう。ショスタコーヴィチの第5も、同傾向の凄絶な演奏だが、完成度という点では、後年のウィーン楽友協会ライブには及ばない。
|
商品詳細へ戻る