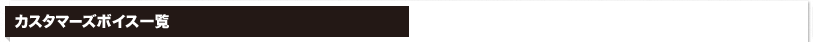
商品詳細へ戻る
原始霧さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
コルネリア・ヴァシレのヴァイオリンで、ニコロ・パガニーニの作品を聴く。演目はハインツ・ヴァルベルクの指揮する北ドイツ放送交響楽団の伴奏による協奏曲No.2と、カプリース集からのセレクション(No.1,4,5,9,11,13&24)。前者は1969年11月20日から翌日にかけて、後者は1970年1月21日という録音の日付がある。どちらもハンブルクの北ドイツ放送の第10スタジオで収録されたもので、スタジオ・ライヴと書かれているが、演奏終了後の拍手はない。協奏曲ではわずかにオーケストラと息の合っていないところを認めるが、カプリースの抜粋共々、大きな瑕疵はない。
ヴァシレは、ドイツ・グラモフォンから50年以上前にデビュー・レコードをリリースしたことがあり、国内盤が出た時には「コルネリア・ヴァジーレ」と呼ばれ「ヴァイオリンのアルゲリッチ」というキャッチフレーズがつけられていた。このデビュー・レコードではウジェーヌ・イザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタNo.2とパガニーニのカプリースの抜粋(No.5,7,9,11,13,15,19,22,23&24)を採りあげていた。このデビュー録音のカプリース集は、パガニーニ直系の弟子という触れ込みで現れたジュゼッペ・ガセッタという老人の若かりし頃の録音として、ノイズ加工されて21世紀初頭にリリースされていたことがある。捏造の発覚でヴァシレに脚光が当たるかと思いきや、ガセッタ翁は真実を語らぬまま2008年に急死し、2年後にはヴァシレもミュンヘンで亡くなってしまったことで、再評価の波を作ることが出来なかったようだ。ヴァシレは1970年代に故国ルーマニアのエレクトレコードで、パガニーニのカプリースの全曲を録音してリリースしており、こちらは2001年に一度CD化もされたそうだが、早々に廃盤になっている。
ヴァシレの演奏は、賛辞を送ったイヴリー・ギトリスの芸風とはまるで違う。技巧を誇示して拍手を貰いたいような俗物根性の演奏ではなく、ひたすら鍛錬の成果があるかどうかを自問自答しているような演奏である。興奮させたり、爽快な気分にさせるような演奏ではないのだが、そのひたむきさに、ただただ聴き入ってしまう。
この録音が呼び水となって、エレクトレコードの録音が、ドイツ・グラモフォンの録音と共に、再度リリースされることを望む。他の作曲家の解釈も聴いてみたい。
|
|
|
清水高師の独奏とグジェゴシュ・ノヴァークの指揮するロンドン交響楽団の伴奏でヘンリク・ヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲No.1とカミーユ・サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲No.3を聴くアルバム。ヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲は、18歳の時に発表したNo.1と、27歳の時に発表したNo.2とがあるが、楽想の扱いに創意工夫の見られるNo.2のほうが演奏頻度が高い。No.1の方も、作曲者なりに演奏家として身につけた効果の高い超絶技巧をふんだんに盛り込んだ意欲作なのだが、力作の第一楽章で力を使い果たし、第二楽章以下のオーケストレーションが粗略になっているところに、未熟さを指摘する向きがあるらしい。年長のベルギー人ヴァイオリニストのアンリ・ヴュータンが技巧的かつシンフォニックな協奏曲を書いていたから、なおさら伴奏が手抜きっぽく見えるのだろう。そうした言いがかりを黙らせるには、手抜かりのない伴奏と、ニコロ・パガニーニもかくやと思わせる独奏の冴えが必要だ。清水も、自らの技巧で作品の魅力を底上げすることを狙って、敢えて挑戦したのだろうが、盤石の演奏とは言い難く、二重把弦が混むと音程が甘くなるところがある。Naxosのマラト・ビゼンガリエフの演奏と比べると、まだまだ華奢で、技巧的な余裕がない。ノヴァークが丁寧に伴奏をつけているだけに、その丁寧さに十分応じきれない表現の詰めの甘さが、ロン=ティボーやチャイコフスキー、エリザベート王妃などの国際音楽コンクールで首位を逃す壁となったのだろう。サン=サーンスの作品は、ヴィエニャフスキのように貪欲に超絶技巧を詰め込むようなことをせず、被献呈者のパブロ・デ・サラサーテの技が映えるように整理されている分、ヴィエニャフスキの作品よりも攻略しやすかったのだろう。ブックレットの解説にある長谷川武久の「果敢に難所を乗り越える部分も技術的に余裕がある」という清水評は、サン=サーンスの作品の演奏にこそ相応しい。ただ、超絶技巧を華麗に決めてドヤ顔をするような独奏者としての厚かましき自己主張が弱く、彼の芸風は室内楽向きなのではないかと思える。サン=サーンス作品におけるノヴァークの伴奏は、ヴィエニャフスキ作品の伴奏ほどに熱心ではないが、その一歩引いた解釈が却って、サン=サーンスの作品の理性的な作風に合致している。
|
|
|
アメリカ人ヴァイオリニストのルッジェーロ・リッチが、ジャン・フルネの指揮するオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団(バック・インレイなどの表記ではオランダ放送管弦楽団)の伴奏を得て録音した、フェリックス・メンデルスゾーンのホ短調とピョートル・チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲のカップリング。このカップリングは、その筋では「メンチャイ」と呼ばれた定番のカップリングだった。両曲とも1975年7月21日に録音されたとのこと。アンコール的トラックとして、リッチの独奏とピエロ・ガンバの指揮するロンドン交響楽団の伴奏によるパブロ・デ・サラサーテのツィゴイネルワイゼンがつく。こちらは1959年9月の録音。
リッチのメンデルスゾーンの協奏曲は、既にガンバ&ロンドン交響楽団と録音しているし、そちらのほうがリッチの技巧面でのモチベーションが高い。
チャイコフスキーの協奏曲もマルコム・サージェントの伴奏指揮で2回録音していて、どちらも終楽章にレオポルト・アウアー流のカットが入っているのだが、このフルネとの共演では、さらにあちこち鋏を入れている。
ツィゴイネルワイゼンの演奏でノリノリなリッチの演奏が聴ける分、「メンチャイ」でのやる気のなさが際立つ。フルネもやっつけ仕事のお手伝いの域を出ない。やる気満々で力の入った演奏が暑苦しくて嫌だという人には、ダラダラ流す分には合うかもしれない。しかし、超絶技巧の無伴奏曲を嬉々として弾いていた往年のリッチの凄みは、このアルバムではあまり味わえない。
|
|
|
2021年4月に神奈川県相模湖交流センターで収録されたヨハン・ゼバスティアン・バッハのゴルトベルク変奏曲。演奏は福田ひかり。CDのバックインレイにベヒシュタインのマークがあるように、ベヒシュタインのピアノが使用されている。C4=256Hz(A4≒430.5Hz)のピッチで中全律音ベースの調律が施されていて、調律したのはベヒシュタインジャパン社長でトーンマイスターの加藤正人。一般的なホール備付のピアノはA4=440Hz以上なので、ピッチを下げて特殊な調律を施すとなると、元の調律に戻した時に元通りの響きに戻る保証がないので、ホール側がピアノの貸し出しを渋るだろう。なので、ベヒシュタインジャパンの持ち出しで、この企画を遂行したと思われる。尤も、モダン・ピアノの一般的な調律である12均等平均律を別の調律に直して弾くケースに前例がないわけではないが、ピアノ・メーカーの重役が自らサポートを買って出るというのは珍しい。
福田は岡山県津山市出身のピアニストで、東京藝術大学では音楽学の修士号を取得している。この時の修士論文のテーマがゴルドベルク変奏曲であった。1998年からJ.S.バッハの作品を自分のレパートリーの中心に据えて活動しており、ブックレット記載の紹介では「『"難しい"というイメージが先行しがちなバロック音楽に親しみを感じ楽しく弾こう』というコンセプト」で指導者向けのセミナーも行っているという。音律や古楽器の研究にも取り組んでいるそうで、現代のピアノと古楽器の接点を探る人材であればこそ、ベヒシュタインが全面的なバックアップをして録音したのだろう。これが福田の初レコーディングとなるが、活動歴はベテランの域である。こうして自身の研究を踏まえ、良い環境で初めての録音を行えたことは、本当に幸福なことではなかろうか。
演奏については、主題回帰でグレン・グールド流の逆アルペジオが顔を覗かせる程度で、特に奇を衒ったところはない。リピートは第13,15,25と主題回帰でのみ省いているようだ。しかし、何か特別なことをしている風ではないのに、音楽が生き生きと息づいている。往々にして、この曲を腕試しのように弾くピアニストは少なくないのだが、そうした腕試しの演奏とは毛並みが違う。J.S.バッハの居る健全で楽しい日常の一コマとしてこの演奏が録られているような、程よく脱力した自然な佇まいが心地よい。
|
|
|
アントニオ・ヴィヴァルディの《和声と創意の試み》全曲をドイツはベルリン出身のユリアン・オレフスキーのヴァイオリン独奏で聴くアルバム。1954年頃の録音で、伴奏はヘルマン・シェルヘンの指揮によるウィーン国立歌劇場管弦楽団(実態はウィーン在住の音楽家を集めた混成メンバー)の弦楽合奏。オレフスキーは1926年にベルリンで生まれたヴァイオリニスト。10歳でアルゼンチンに移住し、当地でアレクサンドル・ペチュニコフの薫陶を受けた。1947年にアメリカに演奏旅行に出て以降はアメリカを本拠とし、1951年にアメリカ市民権を獲得しており、ドイツのヴァイオリニストとして紹介するのには違和感を残す。ウェストミンスター・レーベルに少なからぬ数の録音を残したが、本家レーベルの復刻では、この《和声と創意の試み》から〈四季〉の部分が切り取られて復刻された程度に留まる。このDoremiレーベルが積極的に彼の録音を復刻してくれたことで、オレフスキーの録音へのアクセスが容易になった。技巧的に堅実で、解釈面でも奇を衒わぬながら芯の通った良い演奏をする。指揮をするシェルヘンも、オレフスキーと同じベルリン出身の人だが、オレフスキーよりも35歳くらい年上だ。自分の後輩世代の作曲家の作品を精力的に紹介し、電子音楽にも親しむ進取の気質の持ち主という印象が強いが、余り演奏されない古の作品の発掘と紹介にも積極的に取り組む音楽学者的なところもあった。ここに聴くヴィヴァルディ作品の録音は、そんなシェルヘンの音楽学者的な興味を感じさせる演奏である。無論、その演奏様式は、例えばファビオ・ビオンディ等の演奏と比べると、随分と厳めしい。しかし、通奏低音に曲がりなりにもチェンバロを使っている点は、1950年代の演奏としては見識のある方か。ただ、勝手気ままに弾きそうな団員達を監視するかのようなシェルヘンの縦割りのテンポの取り方は、ヴィヴァルディの音楽に流麗さを求める向きには抵抗があろう。オレフスキーの独奏は、フレキシブルでスマートな美しさを志向しているのだが、ゴツゴツしたシェルヘンの伴奏の所作に引きずられており、お世辞にも主導権がオレフスキーにあるとは言えない。私自身は、この演奏を面白いと思うが、説明調のシェルヘンのアプローチに疲れるという人もいるのではないか。万人には薦め難い。
|
|
|
浦川宜也のヴァイオリン独奏と、林千尋の指揮するスロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団の伴奏で聴く、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのニ長調、フェリックス・メンデルスゾーンのホ短調、ヨハネス・ブラームス、ピョートル・チャイコフスキーの各ヴァイオリン協奏曲全4曲。録音は1995年3月25-29日&4月4-6日の日程でスロヴァキア・フィルハーモニー・ホールで行われたとのこと。収録されている4曲は、オーケストラのコンサートでヴァイオリン協奏曲を選曲する時の鉄板ネタだ。ヴァイオリニストにとっても避けて通れないベーシック・レパートリーなのだが、それは誰でも簡単に攻略できて演奏効果の上がる便利な曲というわけではない。日本ヴァイオリン界の重鎮である浦川は、都合8日間の強行的な日程で、この4曲を録音し終えたわけだが、これらの曲の決定盤と言われるほどの存在感は示し得ていない。伴奏のオーケストラは、アンサンブル自体に乱れはないが、独奏に積極的に働きかける類のものではなく、お付き合い程度の立ち位置に安住している。浦川の独奏自体も、念入りに準備しなかったのか、所々でたどたどしく、音程も甘めだ。これら4曲は、人気曲ではあるが、8日間の日程で集中的に演奏してどうにかなる類の音楽ではない。浦川の演奏は、それを身をもって証明してくれた好例ではあるのだが、このようなやっつけ仕事のような録音を企画した企画者の見識は疑われてしかるべきだ。
|
|
|
アメリカのヴァイオリニスト、アルバート・スポールディングが演奏活動からの引退を宣言した後にレミントン・レーベルに録音したルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(ニ長調)と、ヨハネス・ブラームスのヴァイオリン協奏曲のカップリング。
どちらもヴィルヘルム・ロイブナーの指揮するオーストリア交響楽団(実態はどうやらウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団らしい)が伴奏を務める。
ベートーヴェン作品はかつてケン・レコード社のWING DISCというレーベルからCDとして復刻されていたことがあり、ブラームス作品の方は、イギリスのパールという復刻専門レーベルからCDが出ていた。
演奏自体は、独奏に関して言えば、活動晩期のスポールディングの演奏として、どちらの曲も低空飛行気味ながら善戦しているといえる。作曲家でもあった彼独自のカデンツァも貴重であろう。
伴奏は、もう少しシャキッとしたところが欲しいが、NHK交響楽団に来演した時も温厚だったといわれる彼の人柄が滲み出ているのか、その柔和さに慣れれば、なるほど納得の演奏。
ただ、この復刻CDで許せないのは、ベートーヴェン作品の第一楽章冒頭のティンパニの音が欠落していることである。いや、原盤であるレミントン・レーベルのレコードが録音を制作した時点でミスをして欠落していたというのであれば、修正不可能な瑕疵ということで、歴史的録音を愛好するものは涙を呑んで受け入れるだろう。しかし、先のケン・レコード社の復刻では、ティンパニ音の欠落はなかったし、レミントン・レーベルのレコードを所有している人に確かめてもらっても、そのような欠落はないという。
この復刻CDを制作したグリーンドア音楽出版社は、この音の欠落について、原盤に起因する問題として片づけており、復刻態度として誠実とは言えない。音源の復刻は、復刻を監修する人の責任において、最良のコンディションの音源を調べて探し出し、それをリマスタリングせねばならないだろう。この復刻盤の制作者は、先行の復刻盤について、どう考えるのだろうか。これは再度復刻作業を、調査からやり直すべき、問題のある復刻盤である。
|
|
|
ルイス・デ・モウラ・カストロのピアノ独奏と、エドゥアルド・チバスの指揮するベネズエラ交響楽団の伴奏で、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのピアノ協奏曲全5曲を演奏した記録。全てライヴ録音らしく、演奏終了後に拍手が入る。
このCDセットの販売元は、「現代のフルトヴェングラー」というキャッチコピーでチバスを売り出したいようだが、本家のフルトヴェングラーとチバスの間には芸歴からも芸風からも関連や共通点は見いだせない。
ピアノ独奏を務めるカストロについても、クラウディオ・アラウの名前をちらつかせて、購買層への興味を掻き立てようとしている。しかし、これを聴いてみて、アラウを思わせる芸風の持ち主とは思えなかった。
総体的な演奏の印象は、必ずしも好印象とはいえない。カストロのピアノは無難の域に留まるのだが、チバスの指揮するオーケストラのアンサンブルが何とも荒く、カストロとのコンビネーションも噛み合っていない。アラウやフルトヴェングラーといった往年の名演奏形の名前を宣伝文句に使うのであれば、もう少し演奏の精度を上げてほしいと思う。南米の演奏家によるベートーヴェンのピアノ協奏曲全集という条件にこだわりたければ、ホルヘ・フェデリコ・オソリオの独奏と、エレーラ・デ・ラ・フエンテの指揮するメキシコ・シティ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を探して買った方が良い。
|
|
|
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団のかつての首席ヴィオラ奏者で、ヴラフ四重奏団のヴィオラ奏者も務めていたヤロスラフ・モトリーク。そのモトリークが独奏を務めた録音を集めたもの。
一番新しいブラームスのヴィオラ・ソナタNo.1は、No.2の演奏もあればと思わせる程の出来栄え。クヴィエタ・ノヴォトナーのピアノの凛とした響きと、モトリークのしっとりとした語り口の中にそこはかとなく哀感を滲ませる芸風がうまく合わさり、気品のある演奏に仕上がっている。
ラディスラフ・ヴィツパーレクの無伴奏組曲とイーゴリ・ストラヴィンスキーの悲歌も、モトリークの卓越した芸風を味わうのに不足がない。
ボフスラフ・マルティヌーの狂詩的協奏曲は、ズデニェク・コシュラーの指揮するチェコ・フィルハーモニー管弦楽団との共演で、モトリーク壮年期の演奏で、演奏後に拍手が入る。かつてスプラフォン・レーベルから国内盤でもリリースされた、定評ある演奏。コシュラーのキビキビとしたオーケストラ・コントロールの上で朗々と歌うモトリークのヴィオラがとても魅力的だ。
|
|
|
精緻に作られた、ドリフターズのコントのような味わい。往年のアンサンブルのような第一ヴァイオリンの一人勝ちではなく、第二ヴァイオリン以下が隙あらば艶のある所作で聴き手を惑わせる。
どんな曲だろうと、彼らの流儀で面白く聴かせるのだが、それがパターンに陥るのではなく、常に生き生きとしたやり取りとして奏でられるのが魅力。このボックスに収められている演奏は、職人芸的アンサンブルの一つの完成形だ。
|
|
|
ウジェーヌ・イザイをして「我が最高の弟子」と言わしめたというイタリア人ヴァイオリニスト、アルド・フェラレージの録音集成。数年前にイタリアでローカル・リリースされていたCD9枚組に未CD化だった録音を加えて18枚分もの音源を集めた販売レーベルのコレクター魂に頭が下がる。
音質はさすがにばらつきがあるものの、豪放にして明快なフェラレージの芸風は掴むことが出来るだろう。
|
|
|
ジェラール・プーレ門下のフランス人ヴァイオリニスト、マリー・シューブレのデビュー・アルバム。ジェイムズ・デプリーストの指揮するモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団の伴奏を得て、ドミトリー・ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲2曲を演奏する。中々の健闘だが、やはり旧ソ連の名手たちと比べると、散漫な演奏に終始。伴奏は好演。
|
|
|
先般亡くなったオーストリア出身のピアニスト、イェルク・デムスの協奏曲の名演集。モーツァルトのピアノ協奏曲No.22は、ちょっとねっとりとしたピアノの歌いまわしが、陰影に富んだ音楽に合致している。ハイドンのハンガリー風ロンド付きの協奏曲は輸入盤で復刻されていたものだが、こちらはオーケストラのきびきびとした音楽運びが生きている。ベートーヴェンの合唱幻想曲もダイナミックで良い。
|
|
|
2003年に東京藝術大学教授を退官したバス歌手の高橋大海の退官記念演奏会の演奏。高橋は指揮を受け持ち、教え子や音楽仲間たちが集って演奏したのをライヴ録音したようだ。プロフェッショナルの指揮者であればきちっと合わせるアインザッツが揃わなかったり、慎重すぎて音楽の流れがもたもたしたりする。カットも比較的多め。
|
|
|
音楽評論家であった宇野功芳の最晩年の指揮の記録で、仙台フィルハーモニー管弦楽団との共演。前半のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲では、宇野のお気に入りであった佐藤久成が独奏を務める。チャイコフスキー作品は独奏も指揮も伸縮自在のデフォルメでドラマティックに攻略するが、要所要所の執着を強く出しすぎて末端肥大的。後半のベートーヴェンの交響曲No.7は、オーソドックスな振りをしながら結局我が道を行く。
|
|
|
セゴビアの独奏とエンリケ・ホルダの指揮する元NBC交響楽団との共演。ロドリーゴの《貴紳のための幻想曲》は初演間もないころの録音だ。ポンセの《南の協奏曲》も、セゴビアが頼み込んで作った作品なので、演奏史的に外せない録音。ただし、ねっとり歌うセゴビア節は、今日的には諄いか。カサドのボッケリーニ編曲もちょっと野暮ったい。
|
|
|
イタリアのヴァイオリン教師で作曲家のアルベルト・クルチのヴァイオリン協奏曲集。実家が有力な音楽出版社だったので、自分の趣味全開の曲を書いて出版できたのだろう。この録音も、その実家の出版社がプロデュースしたそうで、人選もなかなか豪華だ。歌謡性と名技性をかけ合わせた、19世紀ロマンティークの香りがする。
|
|
|
ダイアナ湯川の2枚目のアルバムだったもの。数あるこの曲の録音の中では、演奏自体に特筆すべきところはない。練習したとおりに演奏できている印象はあるが、オーケストラと対話するまでには至っていない。クラシック音楽のアーティストとしてやっていくには力不足か。その後、彼女はクロスオーヴァーの方面に去ってしまった。
|
|
|
カタルーニャの雄、パブロ・カザルスことパウ・カザルスの渾身の演奏。まるでベートーヴェンの交響曲を演奏するかのようにモーツァルトの交響曲を演奏する。上流階級の音楽という先入見を捨てて、フレーズの一つ一つにカザルスならではのドラマティックなニュアンスが込められているのだが、決して行き当たりばったりにデフォルメしているのではなく、彼なりのロジックが働いている。だから訴求力があるのだろう。
|
|
|
マルコフのヴァイオリンはフランコ=ベルギー奏派の雰囲気をなぞるのではなく、パガニーニを弾くかのようなアプローチで独自のヴュータン像を作り上げようとしている。ただし、ヴュータンはオーケストラ伴奏もしっかり作りこんでいるため、ヴァイオリン独奏が名人芸を披露するだけでは聴き手に充分な満足感を与えられない。レーヌの伴奏が従属的なのに救われてはいるが、これではヴュータンが小心者のようだ。
|
|
|
ヤッシャ・ハイフェッツの後継者として期待されたエリック・フリードマン。日本での人気はあまりパッとしなかった。このRCAに遺した録音の網羅的なBoxを聴いて、彼の芸風を色んな角度から眺めることが出来る。技巧的に緻密なのはさすがハイフェッツの弟子といったところ。彼のウリは、特にパガニーニの協奏曲で聴かせる抜群の安定感にあると見る。ただ、少々生真面目に過ぎるとの感想を持つかもしれない。
|
|
|
高音質を気にする人には全く向かない、いわゆる歴史的音源の典型的なもの。クーレンカンプの演奏するシューマンのヴァイオリン協奏曲は、後のスタジオ録音と比べてオーケストラ伴奏のカットはない。復刻はノイズ・リダクションに苦労の跡が見える。サシュコ・ガブリロフ演奏のチェロ協奏曲のヴァイオリン盤は膝上録音ということで1980年代の音質にあらず。余白では、ヨアヒムの音源復刻が中々のもの。
|
|
|
齢70半ばの頃のルッジェーロ・リッチによるパガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番。堤俊作の指揮する東京ニューフィルハーモニック管弦楽団の伴奏で矍鑠とした演奏を披露する。リッチのヴァイオリンは音がかすれたり、小さくなくなったりするものの、飛帛体の書のような趣があって興味深い。アンコールのクライスラーのレチタティーヴォとスケルツォやパガニーニのカプリース第13番も、音楽のフォルムは崩れていない。
|
|
|
マリピエロらの校訂したヴィヴァルディの協奏曲は、今となっては貴重な資料だろう。スタジオ・ミュージシャンをかき集めたであろう伴奏のアンサンブルがまったり気味。ミルシテインの独奏はキリッとしているが、その語り口はカンタービレを基調とする。カルミニョーラやポッジャーのようなパルラント的な語り口とは、そもそも発想が違うのだろう。
|
|
|
苦悩から歓喜へというコンセプトに基づくロマンティックで主観的な解釈が主流だった時代から、古楽器奏法が主流化する時代の橋渡しとなる演奏。ネヴィル・マリナーの解釈は、確かに演奏法は古楽器のそれではないが、シリアスで偉大なベートーヴェンという当時のオーソドックスな像とは違った像を切り結ぼうとしている。軽やかで洒落っ気のある演奏は、マリナーが没した今でも十分インパクトがある。
|
|
|
ロシア・ナショナル管弦楽団をムスティスラフ・ロストロポーヴィチが指揮し、このオーケストラの創立者ミハイル・プレトニョフがピアノを弾く。ラフマニノフ&プロコフィエフ(二人ともファーストネームがセルゲイ)のそれぞれの作ったピアノ協奏曲No.3を、プレトニョフはスラスラと弾きこなす。オーケストラともども、劇的な演出に頼らないクールな仕上がり。21世紀のこの曲の解釈の新基準といえる演奏ではなかろうか。
|
|
|
札幌交響楽団が、札幌市民交響楽団として旗揚げした時の、最初の演奏会の記録。全体的に厳つく、まるで軍事教練のような気合の入れ方だ。物凄く練習を積んだ大学のオーケストラの演奏を聴いている感じ。今の札幌交響楽団と格段の差があるものの、その甘えのない真剣な音を「下手」の一言で切って捨てるのを躊躇わせる。札幌交響楽団は、ここから始まったのだ。
|
|
|
ベートーヴェンの交響曲の解釈は、時代考証が進み、よりスリムな響きで小気味よく演奏するアプローチが常態化してきた。そうした今日において、メンゲルベルクのロマンティックな演奏は、時代遅れというよりは、新鮮に感じられる。歴史研究の成果を担保にした「正しさ」よりも、自分の信じるベートーヴェン像を掘り下げたメンゲルベルクの在り方は、羨ましいくらいに清々しい。
|
|
|
ビーチャムはヘンデルの作品をこよなく愛した。それはカップリングの《忠実な羊飼い》からの組曲の演奏でも感じられるが、《メサイア》の録音は生涯3回に渡って録音した点も証左となる。カット込みの最初の録音、ノーカットの2回めの録音を経て、この録音ではグーセンスに依頼した特別な編曲版で演奏している。傾奇者の遊び納めのような華やかさは、鬱憤ばらしにもってこいだ。
|
|
|
モーツァルトの交響曲No.35にベートーヴェンの交響曲No.1&No.2を詰め合わせるというのは、中々出来ることではない。2枚目のCDでもベートーヴェンの交響曲No.6&No.7をカップリングという、なかなか出来ないことがあっさり実現している。無論、個々の曲の所要時間の短さは記録的だが、その音楽には人を急かしたようなところがない。名演奏だ。
|
|
|
ホセ・カレーラスが表題役を歌う、エルマンノ・ヴォルフ=フェラーリの歌劇《スライ》全曲盤。2000年のバルセロナでのライヴ録音で、相手役はベルギーの若手イザベル・カバトゥだ。指揮をするカレーラスの甥っ子はやや平凡だが、カレーラスが頑張っているので、演奏全体の印象は底上げされている。
|
|
|
ウィルヘルミ版のパガニーニのヴァイオリン協奏曲No.1とサン=サーンスの序奏とロンド・カプリチオーソは、繊細ながら達者なブスタボの芸風を楽しめる。
ブラームスの協奏曲は、オーケストラ共々、スケール感豊かに聴かせるには力量不足の感があるが、かえってブスタボのキャラクターを考えさせる材料になりそう。第一楽章終盤に音飛びがあるのは残念。
|
|
|
ダルレ&フレスティエによるサン=サーンスのピアノ協奏曲全集の録音は、この曲集の古典的名盤として知られたもの。条理を尽くしていないようでいて隙のないダルレの独奏も恰好良いが、フレスティエの雑然としていながら締めるところは締める融通無碍な伴奏も魅力的だ。
カップリングの七重奏曲もパスカル四重奏団の怜悧さとデルモットの華やかなトランペットの音色の組み合わせが心地よい。
|
|
|
ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団の歴代の指揮者の録音の集成という企画自体は素晴らしい。しかし、色々詰め込み過ぎて、ダイジェスト盤のような体裁に陥ってしまった。例えば、元祖神童のフェレロとトロヴァヨーリのコンビでは、ガーシュウィンのピアノ協奏曲も録音していたし、フェレロの他のガーシュウィンの録音を合わせれば、それだけでCD1枚構成出来た筈だ。各指揮者の業績に着目した丁寧な復刻を望みたい。
|
|
|
往年のルイス・カウフマンの至芸を味わう録音。テレマンの協奏作品2曲とモーツァルトの偽作を収録。古いコンサート・ホール・レーベルの板起こし復刻らしく、音質は鮮明とまでは行かないが、カウフマンの美音を堪能するには問題ない。
伴奏のオーケストラは、テレマンにしろ偽モーツァルトにしろ、少々野暮ったいが、1950年の録音で、おそらく寄せ集めの臨時編成オーケストラらしいことを勘案すれば、充分健闘している。
|
|
|
このスレンチェンスカ女史のピアニズムが凄いと、友人に言われたので、買って聴いてみた。
御年80を優に超える老ピアニストの演奏とのことだが、80歳で全く淀みなくブラームスの小品(実際はかなりの大作)を平らげていく様は圧巻。
デビューしたてのピアニストほどの切れ味はないものの、その紡ぎだされる音楽の存在感の大きさを前にすると、もはや黙るしかない。
|
|
|
半世紀経っても未だに売れる録音。
ドイツの名匠が、その長いキャリアに渡って弾き続けてきたレパートリーだけに、よくこなれた演奏になっている。
ベートーヴェンの大曲を征服しようという気負いは感じられず、とても自然体。
|
商品詳細へ戻る