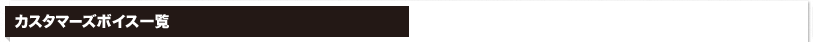
商品詳細へ戻る
colourmeisterさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
長谷川由輝子のデビューCDということだが、技術も音楽性も第一級だ。もう一つ特筆すべき点は、音色の美しさ。濁りがないのはフォルテピアノのよう、しかしスケール感や力強さはモダンピアノ。フーガの線がクリアーに見える。解説書を見ると、「クリス・マーネ制作のピアノで平行弦」とあり、バレンボイム・モデルかその改良型なのだろう。長谷川由輝子はこの特性を活かし、見事に使いこなしていると思う。ベートーヴェンの第3楽章変イ長調3声のフーガが、お団子にならずにクリアーにほぐれる。ベートーヴェンの頭の中で鳴っていたのはこういう音楽なのだろう。
|
|
|
ドイツグラモフォンは粋ないたずらをします。ベトルーシュカを気持ちよく聴き終わり、春の祭典の10秒ぐらいのところで「音程が低い。プレーヤーが故障?」と、ストロボをチェックしましたが異常なし。レコードラベルを見ると「45」とあります。ベトルーシュカは33回転、春の祭典は45回転なのです。ジャケットには何の説明もありません。こういうジョークのような真面目な商品は最近少ないので、ニコニコしてしまいました。演奏も音質もすばらしいです。
|
|
|
「バソンとピアノのためのフランス音楽」ということで、19-21世紀の名作が演奏されている。ローラのバソンは美しく、ロジェ・ブトリがピアノを弾いているのも嬉しい。各曲の細部までよく光を当てて描き出し、アンサンブルも見事。録音はレンジの広さ、音色、安定感など優秀。両方の楽器の音をはっきりくっきり録るタイプ。
|
|
|
第一級の奏者たちが、曲に共感を持って演奏している。特に感心したのはヴィオラで、必要なところでフッと主張し、チェロとヴァイオリンの間にスッと入ってバランスの良い響きを奏でるところが名人芸。モーツァルトの2曲の爽やかさとドヴォルザークの芳醇な味がすばらしい。録音も優秀。音像が明確で音場も自然。ホールの豊かな反射音もよくとらえられている。機材は表記されていないが、質感からするとマイクはDPAかな。
|
|
|
演奏は従来から定評のあるもので、指揮・ソリスト・オーケストラともドヴォルザークの最高の理解者。音質もすばらしい。ノーマルCD(スプラフォン・DENONのBluespecCD)と比較すると、SACDは柔らかく、音場も広く深い。明らかに良い感じに聞こえる。しかし、この録音は4チャンネル収録されていると思うので、なぜマルチチャンネルで発売しなかったのだろうか?
|
|
|
「おとぎ話」がコンセプトのアルバムだろう。演奏者自身の作品に挟まれて、チャイコフスキーやラヴェルのおとぎ話が綴られる。演奏はエンターテインメント性の高いもの。ショパンの「雨だれ」はどしゃ降りのよう。音質はディズニーホールのオルガンの迫力をよく伝えている。名前はロビンと表記されているが、フランス人なのでロバンの方が適切。演奏はオリヴィエ・ラトリーの流れ、作曲はダルバヴィの流れを感じさせる。
|
|
|
テンシュテット指揮のマーラーは、EMIのシングルレイヤーやエソテリックのハイブリッドも出ているが、このSACDが1番洗練されていると思う。エソテリック盤はシカゴ響で、ダイナミクスは優れているが、細部のクォリティはこのロンドンフィルの方が良い。とくに奥行き感、空間の広がり感はすばらしい。交響曲第1番はジェームズ・ジャッド/フロリダフィル盤に一歩及ばないが、テンシュテット盤もよく録れていると思う。
|
|
|
絵画の展覧会を見て回るように、音色が変化するのがすばらしい。ロト/ル・シエクルの演奏は和音に透明感があり、管楽器の音色がこれまでと異なり、ラヴェルの意図した響きが再現されていると思う。キエフの大門は堂々として迫力がある。録音も良く、精緻に切れ込み、奥行き感も深く、ライブのハンディを感じさせない。「展覧会の絵」のベスト盤だと思う。
|
|
|
よく考えられた演奏で好感が持てるが、デュティユーもすでに40種類近い録音があり、ジョワ、ガンツ、岡本愛子、ル・ゲ、レヴィン、岡田博美など優れた演奏があるところに録音する場合、新しい主張が必要と思うが、「何か変わったもの」は感じられなかった。録音は高音質録音狙いと思うが、ピアノの中に頭を突っ込んでいるように感じられる。自然なプレゼンスやピアノ全体の形を感じる録音がこれらの曲にはふさわしいと思う。
|
|
|
田中カレンのピアノ曲は、仲道郁代の演奏で聴くことが多かったが、今回は仲道祐子。どちらも優しく明快な演奏だが、敢えて比較するなら今回の演奏はややクールで張り詰めた空気感がある。曲は三善晃の系譜を感じさせる美しい旋律と和声を持ち、こういう曲が子どもたちに弾かれるのはすばらしいことだと思う。録音もわざとらしさがなく、高音でキャンキャンすることもなく、聴きやすいと思う。
|
|
|
ハープのための作品や、良くできた編曲が集められている。自主レーベルだから、レコード会社の商売とは無関係に、良い作品を優れた演奏で聴けるのが魅力。もう一つの魅力は音質の良さ。軽井沢コルネの自然な音で、それぞれの曲のイメージを活かす録りかた。UHQCDで、SACDを凌駕する音質。立ち上がりの良さ、楽器の音のリアルさ、反射音の粒立ち、どれをとっても最高。
|
|
|
国内盤は高価で買えなかったが、輸入盤が発売されてようやく聴くことができた。P.ヤルヴィの指揮はバルトークの音楽の構造や音色を適確に表現していてすばらしい。録音もfレンジが広くて良いが、時々旋律を演奏する楽器が大きく聞こえすぎるところがある。ピアニシモはもっと小さい方が良いと思う(たぶん実演はもっと強弱の差があるのだと思うが)
|
|
|
100mをノンブレスで泳ぐような演奏。どんどん突き進み、そのうち息が詰まる。ピアノはアンドレ・ワッツのベヒシュタイン(1985年)を古典調律したということで、たしかに独特の響きがある。音質は優秀。プロデューサーとエンジニアは小坂浩徳。ジャケットは呉 逸寒の絵をディスプレイした写真を使って上品なイメージを出している。
|
|
|
プロコフィエフとデュティユー以外は初めて聴く曲だが、どれも洗練された曲で美しい。演奏はフルートもピアノも繊細で丁寧で節度のある表現。録音も優秀。フルートとピアノの音色が融け合う。P:ピエール-イヴ・ラスカル、E:ニコラオス.サマルタノス。24bit44.1KHz、マイクはノイマンCMV563、ショップスCMC3(MK2-Sとの組み合わせ)。
|
|
|
隅々まで適切な光と陰影で描き出し、一気呵成のクレッシェンドが心地よい。CBSOからこれだけの音楽を引き出した功績は大きい。ただ、声楽を伴う作品の演奏クォリティは今日のそれに及ばない。フォーレのレクィエムはエラート盤の方が良い。音質は概ね優秀、特にマスネの「ル・シッド」、サンサーンスの交響曲第3番、シャブリエの「スペイン」等は圧巻。音場が三次元に散乱する。SACDマルチチャンネル化できないだろうか?
|
|
|
第1楽章はテンポを頻繁に変えるので落ち着かない。木管楽器やティンパニーの音程に疑問なところがある。第3楽章以降は悪くない。ディスクの盤面は傷と汚れが多く、品質管理は良くない。音質は優秀。音場の広がりや奥行き、各楽器の質感がよくとらえられている。フォルテでも混濁せず、騒々しくならない。P:J.Maarse、E:Mark Donahue,John Newtonである。
|
|
|
吉野直子は独奏曲のCDはそれほど多くなかったが、自身のレーベルからリリースされるのは朗報。このCDに収録されているのは難しい技巧を要求される曲が多いが、難渋さを感じさせない伸びやかな演奏は見事。録音は中軽井沢のコルネというオルガンホール。ケール感、質感をよくとらえ、切妻屋根の空間イメージもリアル。情報量が多く、音場がよく広がる超優秀録音。前作よりアタックがシャープ。P:吉野直子、E:峰尾昌男。
|
|
|
ダルバヴィの協奏曲で鮮烈な印象を与えてくれた千々岩が、こんどはフランスの親しみやすい曲を録音。どの曲も良いが、とくにフォーレがすばらしい。バイオリンとピアノのアンサンブルが良く、洗練の極み。録音も楽器の音を明確にとらえながら間接音も適度にとりいれて、広がり、奥行、低域の深みを感じさせる。高域の伸びや艶感が加わるといっそう良くなるのだが。P:平井宏、E:江崎友淑。
|
|
|
CD規格の高音質盤では、ガラスとXRCDが良いが、値段が高い。UHQCDは普及価格でそのレベルに迫っている。何より、実在感が感じられるようになったのは大きな進歩だ。アナログに近い感触の音質である。サンプラー収録曲では、マーラーの5番、ノヴェンバー・ステップス、子供の領分、ドヴォルザークの弦楽セレナードが良い。ブルックナーの7番と5番はXRCDと比較しても遜色ない。新譜のUHQCDも楽しみだ。
|
|
|
パユのフルートはもちろん、ピノック指揮カンマーアカデミー・ポツダムの演奏もすばらしい。とくにニ短調の第3楽章は、超高速だが全く破綻がないのは見事。まさにシュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)だ。メンバーには笠井友紀(Vn)の名前もある。録音は優秀。フルート独奏と弦楽合奏のバランスが絶妙。プロデューサーはスティーブン・ジョーンズ、エンジニアはフィリップ・ホッブズ。
|
|
|
10人の作曲家による共作「ジャンヌの扇」がおもしろい。バレエ音楽という枠はあるものの、それぞれが個性を活かした曲で楽しい。P.O.フェルー、ロマン=マニュエル、マルセル・ドラノワの曲は初めて聴くが、けっこうよくできている。録音は切れ味鋭くダイナミック。超優秀録音と言って良いが、わずかにブーンという電気的ノイズがあるのが惜しい。プロデューサーはダニエル・ザレイ、エンジニアはユーグ・デショーである。
|
|
|
柔らかく、スムーズな美音で、耳に心地よい演奏。今井信子のビオラとアウリン・クァルテットとの融け合いもすばらしい。モーツァルトの音楽はもう少しとんがったところもあると思うが、疲れているときはこういう演奏も良いかも。録音は美しい。楽器の音はリアルでアナログ的な温かさがある。間接音も豊かにとりこまれているが濁りはない。プロデューサー & エンジニアはAndreas Spreer。
|
|
|
C.P.Eバッハの音楽は「バロックと古典派の架け橋」という形容も頷ける。1772年頃の作曲という点から見ると、転調やリズムの変化が大変独創的で斬新だと思う。トレヴァー・ピノックとイングリッシュ・コンサートの演奏は、明快で颯爽としていて美しい。音質は優秀。とくに4チャンネルで聴く音は間接音が豊かで、ヘンリーウッドホールの響きをそっくり届けてくれているようだ。
|
|
|
イポリートとアリシーを幻想交響曲と関連づけるのは新鮮なアイデアだと思う。幻想交響曲の第3楽章ではコーラングレと舞台裏のオーボエのかけ合いが物語へ誘う。マルシュは堂々としたテンポで始まるが、そのままインテンポで進めて欲しかった。録音は大変優秀。全体はクリアーで軽いトーンだが、低域はズシンとくるし、フォルティシモは炸裂する。ディレクターはマルティン・ザウアー、エンジニアはトビアス・レーマンらによる。
|
|
|
プレートルの音楽は、アゴーギクとディナーミクの変化を大きくとるが、それが嫌みにならないのが個性。「イタリアのハロルド」はヴィオラ独奏がワルター・トランプラーというのも魅力。「ツァラトゥストラはかく語りき」はうねりの大きさなどで、ニーチェが語ろうとした紆余曲折と永劫回帰を表現している。音質は総じて良好。特にデジタル録音の「ツァラトゥストラ」は迫力がある。アナログ録音の中ではシベリウスの3曲が優秀。
|
|
|
第13番「ロザムンデ」はノーマルCDでも聴いていたが、悲観的な情感とやさしく平和な部分を併せ持つ曲で、その対比を見事に表現している。ペンタトーンのSACDは音質がより鮮明で、かなりオンマイクだが間接音も豊かに取り込まれている。イタリアSQの第10番はこのSACDで初めて聴く。美しく歌心あふれる曲で、生き生きした強さと穏やかな表情を描き分ける。
|
|
|
バーバーの「弦楽のためのアダージョ」は、作曲者が言うように葬送音楽ではないので、重くなりすぎない表現が適切。その意味でこの演奏はちょうど良い重さで演奏されている。音質は良いが、フェーダーで音量を操作しているのを感じてしまうところが何カ所かある。バーバーよりもブルックナーの方が音場のイメージが自然。プロデューサーはフィリップ・ネーデル、エンジニアはマルティン・キストナーである。
|
|
|
エネルギッシュで燃える演奏だが、粗野ではなく、アンサンブルは緻密。動と静のバランスが見事だ。「だったん人の踊り」は、合唱とオーケストラの僅かなずれが惜しい。録音は1977年、優秀録音である。CDの解説書にはスタッフは書かれていないが、プロデューサーはCharles Gerhardt、エンジニアはMartin Atkinsonで、Kenneth Wilkinsonも参加していたようである。
|
|
|
以前はストコフスキーの音楽を敬遠していた。派手な演奏効果で大衆受けを狙う指揮者というイメージが強かったからだ。しかし、今は楽しんで聴いている。このCDは91歳とは思えないエネルギーだ。彼は聴衆を喜ばせることと、曲の本質を強調することに熱心なのだと思う。少なくとも、勢いとダイナミクスで感動を強要する演奏よりずっと素直に聴ける。録音は多くのマイクを使っていると思うが、不自然さはなく、音の洪水に浸れる。
|
|
|
ブレンデルのピアノは、よくコントロールされたタッチで、濁りがなく、完璧なモーツアルトの美学を表現している。このピュアでピースフルな表現は他の盤からは聴けない。ネヴィル・マリナー指揮ASMFとのアンサンブルも生き生きして絶妙。音質は優秀。繊細・優美。LP(蘭Ph 6542 438)と比較すると一長一短。LPの方が実在感、空間のつながりが良く、SACDの方が奥行き感と広がりに優る。続編に期待。
|
|
|
バッハは当時のイージーなトレンドに立腹していたようだ。ヒューイットは怒りを優しさで包み込むような音で表現するが、重みは他のJ.S.バッハの全ての曲以上かもしれない。「満を持しての録音」ということなのだろう。録音は優秀。プロデューサーはリュドガー・ベッケンホフ、エンジニアはサイモン・ベリー、ファツィオーリの音色とイエスキリスト教会の空間をよくとらえている。
|
|
|
「アルペジョーネ・ソナタ」は、ハイモヴィッツの個性を前面に押し出した演奏。流れが滞るが、意図してそうしたのかも。録音はドライな音質で感心しない。「弦楽五重奏曲」はミロ・クァルテットのペースでロマンティックな音楽作り。こちらは優秀録音。潤いがあり、音場も広く拡散する。プロデューサーはLuna Pearl Woolf、「弦楽五重奏曲」のエンジニアはDa−Hong Seeto(司徒 达宏)である。
|
|
|
パリ四重奏曲は、テレマンの曲の中ではかなり複雑で難しく書かれているが、4人の奏者はそれを感じさせず、爽やかで楽しい雰囲気が伝わってくる。録音も優秀。良い意味で柔らかく、自然な広がりと奥行き・高さが感じられる。デルフトのOud-kathorieke 教会。エンジニアはOlaf Mielke。彼はCoviello ClassicsやNEOSで質の高い録音をしている。演奏も録音もこの曲のベストワン。
|
|
|
坂本龍右の2枚目のソロアルバム。ルネサンス期のリュート作品の歴史的変化や、タブラチュア譜などをよく研究して構成され、演奏は丁寧で洗練されている。録音も極めて優秀。バインヴィルというスイスにある教会での録音。SN比も響きもすばらしい。エンジニアはヨナス・ニーダーシュタット。彼はCarpe Diem Recordsの主催者で、最近の佐藤豊彦のディスクも手がけている。繰り返し聴くと味わいが増すディスク。
|
|
|
ルーセルの「バッカスとアリアーヌ」は、賑やかでデモ効果抜群。曲の完成度や演奏のクォリティはプーランクの「牝鹿」が秀逸。山田和樹は、ダイナミックでスピード感のある表現と、しっとりした繊細なディテールを両立させている。録音は現代の最高水準。レンジが広く、音場空間も三次元に展開する。ただ、ところどころ編集の跡が見える。プロデューサーはJob Maarse、バランスエンジニアはErdo Grootである。
|
|
|
「悲嘆」というタイトルで、情感たっぷりの演奏。フレーズの最後はチョチョギレそうに掠れ、音程が不安定。どの曲も同質の表現なのでboringだ。師匠のアーロン・ロザンドはワンパターンではなかった。オリジナルはドリアンレーベル。音質は生々しく、スケール感があり、ピアノの低音は深く沈み込む。プロデューサーはアンマリー・ベイカー・シュウォーツ、エンジニアはクレイグ・D・ドリーである。録音は☆☆☆☆☆。
|
|
|
ハープ版もオーケストラの譜面はギター版とほとんど同じだと思う。演奏はとてもうまいが、聴き慣れたギター版と比べるとアランフェスの第1楽章のオーケストラが騒々しい。個々の楽器の音質は悪くないが、ハープ以外の楽器のソロが強調されすぎだと思う。第2楽章以降は気にならない。ドビュッシーとトゥリーナはとても素敵で、素直に音楽に浸れる。プロデューサー&エンジニアはケン吉田 & リトル・トライベッカ。
|
|
|
丹念に音を紡ぐ演奏で、「こぶし」も「ため」もなく、美しさを引き出している。ロンドン響のブルックナー交響曲第5番は初体験。とても洗練された良い演奏と思う。録音も優秀。普通のボリューム位置だと少し音量が小さいので、一割ほど上げて聴いた。艶や滑らかさは今ひとつ不足だが、ステージのプレゼンスがうまくとらえられ、S席で聴く感覚。プロデューサーはティム・ハンドリー、エンジニアはフィル・ロウランズである。
|
|
|
近現代曲のコンサートというイメージのプログラム。超絶技巧の部分はギドン・クレーメルと吉野直子でなければ演奏できないのではないだろうか。中でも高橋悠治の「Insomnia」がめっぽうおもしろい。箜篌が使われて効果をあげている。正倉院に保存されている楽器をもとに復元したものという。音質は大変良い。プロデューサーとバランスエンジニアはウィルヘルム・ヘルヴェク、エンジニアは福井末憲と櫻井卓である。
|
|
|
ソナタ第5番「春」は、グリュミオーの甘美な弦とアラウの堅実なタッチがうまく調和して、独特の世界を醸し出している。それに比べてソナタ第1番は真面目で普通。気張らずにリラックスして演奏しているとも言える。シェリング/ヘブラー盤のような躍動感はなく、ファウスト/メルニコフ盤のような創造性も感じられない。音質は艶やかで広がりがあり、LPやノーマルCDより優れている。
|
|
|
ハルモニアムンディは1980年前後も宝の山で、復刻されるのは嬉しい。このディスクはレザールフロリサン設立3年目の収録である。オーケストラ、独唱、合唱ともうまい。録音は優秀だが、LP[HM1083]と比較すると、CDは間接音がよく聞こえ、楽器や声はややさっぱりしている。LPの方が濃密でトロリとした印象。プロデューサーはロビナ・ヤング、エンジニアはジャン・フランソワ・ポンテフラクトである。
|
|
|
シェレンベルガーが25歳の頃の録音だが、すでに超一流の技術を持っている。4曲の中ではシューマンとプーランクの演奏が良いと思う。もっと成熟した音楽性を求めるなら、カンパネラムジカ盤がベター。オーボエの音質は悪くないが、チェンバロはやや刺激的で音量が大きすぎ、ピアノはドロンとして鈍い。プロデューサーはフランツ・クリスティアン・ヴルフ、バランスエンジニアはカール・アウグスト・ネーグラーである。
|
|
|
10月2日にネヴィル・マリナーの訃報を受けた。多くの優れた遺産を残した指揮者だった。中でも「カルメン組曲」や「アルルの女組曲」は好演である。「アルルの女組曲」は1992年にASMFと再録音しているが、このロンドン響との演奏が良いと思う。録音は優秀。マルチチャンネルは、広がり・奥行きがあり、ディテールの描写も繊細である。LPは長岡鉄男A級セレクションの1枚である。
|
|
|
78年から79年に、4回に分けて収録されているが、たぶん初めから全曲の予定だったのだろう。通して聴いたときに、作曲上の変遷が見えるように演奏されていると思う。たとえば初期の3曲は溌剌として積極的で、特に1番はグリュミオー/アラウ盤と比較すると一聴瞭然だ。「クロイツェル」から第10番が作曲された間に約9年のブランクがあったことも、演奏から感じられる。録音も優秀。ラ・ショードフォンの響きを伝えている。
|
|
|
LP時代から何度も聴いた名演で、今でも色あせない。録音もたいへん鮮明。音場感、実在感、音色は最近の録音に優る部分もある。テープノイズはあるが鑑賞の妨げになるほどではない。ラヴェルはPRAGAからSACDが出ている。これは米ロンドンのマスターではないだろうか。音色が温かくディテールがよく聞こえる。キングのスーパーアナログは低域がややファット。タワレコ盤は英DECCA盤の音質に似てクールでシャープ。
|
|
|
モーツァルトのピアノ四重奏曲はこの2曲で全て。曲としては第1番の方に魅力があると思う。イングリット・ヘブラーとベルリンフィルのトップ奏者の演奏は、初めのうちはオーソドックスで可もなく不可もなくという印象だが、じわじわとその凄さが湧き出す。この曲はヴィオラの旋律が特徴的に書かれているが、ジュスト・カッポーネがそれを見事に表現している。録音は水準以上。スタッフは不明。
|
|
|
「高雅にして感傷的なワルツ」は、シューベルトのワルツにならって作られた曲だが、ラヴェルのシューベルトを尊敬する思いと、古きよきウィーンへの憧憬を随所に感じさせるアバドの表現も見事である。録音は優秀。音場が広く、奥行きも充分あり、ソロ楽器が明解に浮かび上がる。プロデューサーはクリストファー・オールダー、バランスエンジニアはクラウス・ヒーマン、エンジニアはハンス・ルドルフ・ミュラーである。
|
|
|
アバドが37〜38歳頃の録音。彼はドビュッシーの「ノクチュルヌ」が好きなのだろう。曲に対する熱意と共感が感じられる。ラヴェルは綿雲の上を浮遊するような弱音部が絶品。録音は1970年〜71年で、もちろんアナログだが、音質は良い。ホルンは天井まで立ち上り、音場は真横まで広がる。プロデューサーはカール・ファウスト、ディレクターはライナー・ブロック、エンジニアはギュンター・ヘルマンスである。
|
|
|
弦楽四重奏曲第15番は長大な力作である。転調やトレモロ、ユニゾンなどを駆使し、意外性の連続で聴き応えがある。ミハル・カニュカが編曲したアルペジョーネソナタは、とくにアダージョがピアノ伴奏版よりしっとりした味わいで優美。演奏は超一級。録音もすばらしい。マルチマイクと思うが、各楽器の潤いのある音色がよく融け合い、豊かな空間を醸し出す。ディレクターは小島裕、エンジニアは瀬口晃平である。
|
|
|
シベリアで捕虜になった父が「ロシア人は数人集まるとすぐハモる」と言っていた。「バビ・ヤール」はそんな雰囲気を伝える。幸い父は虐殺されず無事帰国した。プレヴィン盤の演奏がベスト。ペトコフのバスと合唱団がうまい。音質も超A級である。声楽とオーケストラのバランス、壮大なスケール感とディテールの描写が両立している。プロデューサーはスヴィ・ラジ・グラッブ、エンジニアはクリストファー・パーカーである。
|
商品詳細へ戻る