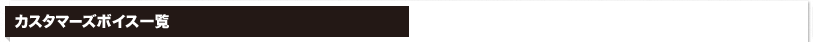
商品詳細へ戻る
Cranさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
何度CD化されたかわからないウラニアの「エロイカ」。わたしも何度購入したのか覚えていない。さて世の中にはフルトヴェングラーの演奏の何がいいのかわからない人もがいるようだ。それは当然だろう。音楽を数値で「データ」で捉えるのなら理解できなくて当然だと思う。「スペシャル」な存在はともかく、標準的なプレイヤーのレベルは間違いなく現代は向上している。オーケストラの技術レベルも上だろう。かつてのベルリンフィルやウイーンフィルより例えばアンサンブル、縦の線をそろえることなどは精度は上がっている。だけど音楽というのは何だろう?音は生じた次の瞬間には消えていくものである。しょせんそこにあるのは「不完全な」追憶でしかない。その「不完全な」状態でやるべきなのは音楽が「何を伝えるか」ではなかろうか。かつての演奏家たちはそれにすべてをかけた。その中でフルトヴェングラーは音楽が「何を伝えようとしているか」をわたし達にそのまま「提示して」くれた。あいまいな言い方しかできないけれどフルトヴェングラーの音楽は「向こうから」やってくる。きわめて「切実な」ものとして、顔を背けるような「あいまいさ」を許さないものとして。当然こういうやり方は他人に教えようがない。フルトヴェングラーの指揮が残っていない理由の一つだろう。このCDのウイーンフィルより現代のウイーンフィルのほうが「技術的」には上手いのであろう。だが何を伝えているのかは別である。フルトヴェングラーの実演を聞けた人がものすごくうらやましい。再生音の状態は極上である。
|
|
|
わたしにとってグスタフ・マーラーの交響曲第9番は非常に重要な曲である。わたしは交響曲の最高傑作だとさえ思っている。幸いにして、わたしは数多の優れた実演を聴くことが出来た。若杉/都響の数々の公演。そしてあの若杉/ミュンヘンフィルの公演…。いろいろな録音にも接することが出来た。バーンスタインだけでもイスラエルフィル、アムステルダムコンセルトヘボウ、ベルリンフィルにニューヨークフィル。バロビローリやジュリーニ/シカゴ交響楽団等々。最近もシュタイネッカーによる優れた演奏を聞いたばかりである。だが実はわたしにはマーラーの交響曲第9番は長い間わからなかった。マーラーの交響曲第9番は、マーラー自身の交響曲第2番や第8番のようにエネルギーの燃焼が「外」ではなく「内面」に向いているから。それをわたしに教えてくれたのは柴田南男の「グスタフ・マーラー」である。さてブルーノ・ワルター/コロンビア交響楽団のマーラー交響曲第9番はわたしが初めて聞いたマラーの交響曲第9番である。聞いて「これは何なの?」と思った。レコード評もいろいろ読んでみたけれど、まるでわからなかった。だが今は、第1楽章展開部を聞いてコロンビア交響楽団が編成が小さいとか技術が稚拙だとかはどうしても思えないし、何よりワルターの燃焼の激しさ!恩師の最高傑作を音にするという「特別なこと」にかけた情熱!そしてそれに対するコロンビア交響楽団の「歓喜」!まったく素晴らしい。第1楽章の夢、そして第4楽章の澄み切った叙情…。録音状態は極上。再生状態は「こんな音まで録音されていたのか」と驚くばかりである。
|
|
|
わたしがこの演奏を始めて聴いたのは、1980年代の初めだったと思う。バッハはなんとなく「謹厳実直」だと思っていたので、初めはびっくりした。だけど何回か聴いていくうちに「これは」と思うようになった。もっとも、今思えば「スポーツ的快感」に酔っていたのではないかと思うが。当時はまだバッハは「厳格な」冗談も言わないようなイメージがあったのかな。でもその後、むしろバッハは「破天荒な」むしろ「情熱あふれる」人だったらしいということになり改めてこのゴールドベルク変奏曲のグレン・グールドの旧録音の「凄さ」にきずかされた。その後グールド自身も新しく録音し、もちろんそれも注目すべき演奏であるが、今改めてこのCDを聞いて思うのはグールドの「ファンタジー」そして何よりグールドのピアノの音の「美しさ」。その「美しい音」によってグールドは果てしなく広いバッハの世界を「自由に」飛び回る…本当に素晴らしい演奏だと思う。録音状態は「最高」。かつてのCDとは全然違う。これほどの音が録音されていたなんて、まさに「驚天動地」である。
|
|
|
わたしは普段CDに録音されているすべての曲を聞いてから、そのCDの評価を書く。これは多くの人が同じだろう。しかしこのCDにはその禁を破ろうと思う。そのCDは「レオ・ボルヒャルトの芸術」。戦後ベルリンフィルに米兵に射殺された指揮者がいたことは聞いていた。なかなかいい指揮者だったらしい、と。それでこのCDを手に入れ、聴いてみた。今、ウエーバーのオベロン序曲まで聴いたところである。聴いてみて思った。「もしボルヒャルトが死なず、戦後のベルリンフィルを率いていたらベルリンフィルはカラヤン時代の様な音色になっていただろうか?と。わたしの耳にはボルヒャルトの指揮は極めて的確、理知的でありながら盛り上げる「ポイント」も外さないように聞こえる。フルトヴェングラーとは個性が違いながら、音楽に対しての「接し方」は、少なくともカラヤンよりは共通点が多いように思える。果たしてボルヒャルトが指揮していたらベルリンフィルの音はどうなっていたのだろうか。歴史にifはあり得ないからそれは永遠にわからない。しかしわたしはそう考えずにはいられない。ぜひその音を聞いてみたかった。さてこれから「ロメオとジュリエット」と「ステンカラージン」を聴くのが楽しみだ。
|
|
|
素晴らしい。気迫も技術も十分。何より自分が音楽を「演奏する」ということを理解しているのがいい。今どきの意味も分からず、ただ人よりうまく弾けるから弾いているだけの「演奏屋」とは違う。いやびっくりした。やはり自らの人生をかけた人の音楽は美しい。オーケストラも見事。フィルハーモニアフンガリカは確かドラティのハイドン交響曲全集のオーケストラだと思うが、指揮者のウリ・セガㇽと共に落ち着いた演奏を行っている。
|
|
|
「現代の棒振り機械に敢然と挑む存在」。この言葉に言い尽くされているのではないか。まさにテンシュテットは「指揮者とはどういう存在か」「なぜ指揮者が必要なのか」。それを「全身全霊で表現する」存在だったと思う。しかもこの現代という時間の中で。わたしは必ずしもテンシュテットのすべてを肯定はしない。しかしその「在り方」には無視できないものがあると考えている。現代においてもいまだこういう考え方をする人がいるということを(テンシュテットは1998年に死んでしまったけれど)、わたしは大事に思う。ボストン交響楽団はさすがの性能の良さ。だけどあのホールはどうなのだろう?やはり音楽にとって、楽譜に書かれているすべての音符を音にすることにさして意味はないように思われるが。
|
|
|
ジャニーヌ・ヤンセンが素晴らしい!勢いで引き飛ばすのではなく、丁寧に音を奏でる、というか音楽に「語らせている」。とにかく素晴らしい。ヤンセンは初めて聞くけれど、あまりの独奏の素晴らしさにあっけにとられた。オスロフィルの性能にも驚かされた。失礼ながらyoutubeなどで耳にした限りではこれほどいいオーケストラだとは思わなかった。そしてクラウス・マケラ。マケラはやはり頭のいい指揮者だと思う。若さゆえの反射神経の反応の良さだけではなく、音楽の「意味」を「理解して」指揮をしているようにわたしには聴こえる。彼もまた勢いに任せて音楽を演奏することはしない。聞けばシカゴ交響委楽団のシェフも務めるらしい。いまだ30歳にもなっていないのに。やはり逸材と言っていいのではないだろうか。
|
|
|
自称シベリウス好き「シベリウスのCDは…」(わたしはこういう言い方は好まないが)、そんな人に言いたい。これはこのCDは、かつて日本に渡邊暁雄という素晴らしいシベリウス指揮者がいたという何よりの証拠である、と。渡邊暁雄のシベリウス交響曲全集は新旧共に持っているし、新しい全集は新譜で発売されたときに購入している。だから実はタワーレコードで復刻された当初は購入に二の足を踏んだ。だがやはり渡邊暁雄のシベリウスが復刻された以上は購入するべきだろうと思い、手に取った。聴いてみて驚いた。この演奏の自然さ、テンポの自然な揺れ、アレグロ等の速度…。すべてが「泰然自若」でありその演奏の美しさに。日本フィルも「最高」とは言わないが、まことに心のこもったいい演奏をしていると思う。音の状態は初発売時に比べると格段に向上している。このCDはシベリウスに興味のある人にとって「必須」のCDである。今わたしはこのCDに夢中である。
|
|
|
音というものは発せられた瞬間に消えていくものである。だからこそ美しいものでもあるのだが。
ウイルヘルム・ケンプのライヴ・コンサート・エディションを聴いた。これはケンプ、いやピアノ音楽に興味がある人にとっては必聴なのではないか。少なくともわたしはこれを聴いて初めてケンプがどういう音楽家だったのか分かった。なんでブレンデルが「ケンプはエオリアンハープを奏でるように演奏する」といったのか理解した。確かにケンプは唯一無二そして調子の良し悪しに左右される演奏家だったであろう。しかし興が乗ったときは得もいわれぬ、極上の「移ろい」を聴かせてくれる演奏家だったのだろうと。ユジャ・ワン等の現代の演奏家ははるかに「精密な」演奏を聴かせてくれるだろう。現代は「細密化」の時代なのだから。しかして「移ろいゆく」美に対してすべての音符を音にすることに何の意味があろう。はかない「移ろいゆく」美に対して、すべてを明らかにすることは意味があるのだろうか?
|
|
|
サー=エイドリアン・ボールトという名前をわたしが知ったのは、わりと以前からである。「惑星」とかヴォーン・ウイリアムスの指揮者として。だがタワーレコードの復刻でブラームスの交響曲を聴いたときその印象が変わった。なんという美しさ、いわばその「栄養素」の高さに驚いた。「年齢」を重ねることの「美しさ」に感動した。ボールトは派手ではないかもしれない。ボールトは決して急がない。表面的な効果も求めない。しかし奏でているその「音楽」にはたっぷりと「滋養」が含まれている。そんなボールトが演奏するベートーヴェンの「英雄」とシューベルトの「ザ・グレート」。しかもライヴ。幸福な時間を過ごせることだろう。
|
|
|
オスモ・ヴァンスカはパーヴォ・ベルグルンド亡き今最も注目すべきシベリウス指揮者かもしれない。今年ヴァンスカは都響とシベリウスの交響曲第5・6・7番を演奏した。あれは素晴らしい演奏会だった。都響のシベリウスは絶対いいと思っていたし、何よりヴァンスカに興味があった。演奏は想像以上に素晴らしかった。おそらくヴァンスカの演奏はオーケストラを選ぶ。ヴァンスカの演奏をリスペクトするオーケストラでないと彼の演奏は魅力的にはならないのではないか。どちらかというとほの暗い渋めの音で曲想の変化に敏感でないとヴァンスカの演奏の魅力は伝わらない。ミネソタ管弦楽団はヴァンスカに非常によく寄り添っている。そしてその音は紛れもなくシベリウスの「音」である。このCDはシベリウスを愛する者にとってかけがえのない贈り物である。
|
|
|
まずジャック・マルスとミシュリーヌ・グランシェは大変立派。賞賛すべき出来だと思う。そして何と言ってもカミーユ・モラーヌ!素晴らしい!こんな難しいオペラをこんなに立派に歌いきるなんて。特筆すべき出来だといっていいだろう。だが一番すごいのはアンゲルブレシュトだろう。なんというかぐわしさ!そしてなんという楽器、いやコントロールの素晴らしさ!これが曲を「演奏する」ということだと思う。「演奏」というのが音符をなべて「音」にすることだけではないその最良の証左だろう。録音については何も言うことはない。シャルランがこれを残してくれたことにただ感謝しかない。
|
|
|
どこで読んだのだったか。「バッハは海である。」と聞いたことがある。無伴奏チェロ組曲にせよ無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータにせよ、たった一丁の楽器からこんな宇宙を感じさせるなんて、バッハというのは本当に偉大な存在だと思う。この録音が発売された当時「女性らしい繊細さはあるがバッハの雄渾さは感じられない。」と評され、第3巻は発売すらされなかったと聞く。わたしには信じられない。これほど鮮烈で雄渾な、強烈に鮮やかに響く演奏を特筆しないなどと。ここには現代では失った、「人間の」演奏する「行為」の.そのほとんど最上のものが刻まれている。マルツィは決して走らない、楽譜を落ち着いて音化する。そこから生まれるのは落ち着きと思慮、そしてその音楽はこの上なく鮮やかに響く…。これは素晴らしい録音だと思う。しかもこの時マルツィは30,31才。すごいとしか言いようがない。録音は極上。鑑賞するのに不満はない。
|
|
|
現在の、若いクラシックファン、あるいはクラシックを聞き始めたばかりの人には、クラウディオ・アバド/BPOのベートーヴェン交響曲全集といえばローマで録音した交響曲第1~8番と2000年5月にベルリンで録音した交響曲第9番のものになるのだろうか。だがあえて言う。アバドのベートーヴェン交響曲全集でより聞くべきなのは、アバドがベルリンで全ての交響曲を録音した「全集」であると。それどころかあの「旧」全集は極めて高い「意味」を持つ「全集」であると。フルトヴェングラーの死後、BPOはカラヤンを首席指揮者に選んだ。それどころか確か「終身音楽監督」とまでした。結果的にはそれは成功だったと思う。BPOはカラヤンの下世界一のオケとなり経済的にも大いに潤った。カラヤンの後を襲ったアバドはベートーヴェンを「マス」ではなく「透明な」「鮮烈な」音でベートーヴェンを表現した。それはとてつもなく「鮮やかに」ものすごく興味深い「全集」となった。これを「軽い」と聞く人がいるのはわかる。一見これはすごく「聞きやすい」から。だが注意深く聞くとアバドは驚くべきことをやっている。「マス」ではないのにもかかわらずこの「全集」はとても激しく「演奏して」いる。アバドとBPOは非常な集中力を持ってこの録音に臨んでいる。この全集の交響曲第9番のアバドのジャケット写真。それまでのアバドらしからぬ不敵な表情。それが全てを語っているような気がしてならない。
|
|
|
録音状態は極上‼だまされたと思って聞いてほしい。これが1926年の録音だなんて誰が信じる。そしてクライスラーは当時51歳。技術的にも最高の状態ではないか。あの頃はレコードを録音するにも再生するにもおそらく今ほど「手軽」ではない。それこそひょっとしたら「一期一会」かもしれないのだ。それほどの覚悟で聞いたであろう当時の人々。現代のわれわれが忘れているかもしれない覚悟。それが演奏にも表れているのかもしれない。この頃の演奏に聴ける「味」や「歌」。楽譜にある「音符」をすべて音にするだけでは足りない何か。時代の進化とはいったい何だろう?
|
|
|
わたしはショパンが苦手である。ショパンの曲は、わたしには「よくしゃべる」ように聞こえる。けして「詩情豊かな」「ロマンティックな」ものには聴こえない。いやある意味これはものすごく「ロマンティック」なのだが。演奏は時代の移り行くと共に演奏スタイルも変わってゆく。フー・ツオンのショパンの演奏スタイルはもしかしたら現代のものとは違うのかもしれない。なにしろこれは真の意味での「情緒纏綿な」「思いのたけをむき出しにした」演奏なのだから。昔わたしは「夜想曲」だけを持っていた。それを初めて聴いたとき「うわぁ」と思った。ここにあるのは上辺ではない真実の意味での「望郷」だから。
|
|
|
ジャン・フルネは巨匠である。フルネは東京都交響楽団に盛んに客演してくれた。一時は首席指揮者さえ務めてくれた。わたしが東京都交響楽団の年間会員になったのが1985年なので数多くのフルネの実演に接することができた。それはとても幸せな時間だった。特にフルネが都響と演奏するフランス音楽はまさに「天下一品」だった。そのジャン・フルネ、あのアンゲルブレシュトから「ペレアスとメリザンド」の初演を託されたジャン・フルネのフォーレの「レクイエム」。聴かないという選択肢はわたしにはない。
|
|
|
これはあくまでホロヴィッツを聴くべきCDだと思う。世の中に数多いるピアニスト。「ヴィルトゥオーソ」という言葉を聞く機会も多い。しかし少し待ってほしい。真に「芸術的」いや「音楽的」な「ヴィルトゥオーソ」というのは、わたしはピアニストでは何人かしかいないと考える。その一人がウラジミール・ホロヴィッツである。ホロヴィッツのピアノは「歌う」。彼のピアノの美しいこと!彼のピアノは「人間が」弾いている。ヴィルトゥオーソが単なる指の回転速度ではなく、そこにはあくまで「音楽」がなければならない。彼のような古き良き「グランドマナー」を持っているピアニストをわたしはまた聞くことが出来るだろうか?ワルターについてはわたしには言うべきことはない。
|
|
|
堀辰雄の聞いたフォーレの「レクイエム」。わたしが初めて聴いたフォーレの「レクイエム」はコルボの一回目の録音だった。それに感動したわたしは様々な指揮者のものを聴いた。コルボの新しい録音や幸運にも数多くの実演に接することのできたジャン=フルネ(この人が都響でやったフランス音楽は絶品だった!)、そしてアンドレ=クリュイタンス。だがわたしが聴いたのはクリュイタンスの旧盤のほうだ。クリュイタンスの旧盤はサントユスタシュ合唱団及び管弦楽団。マルタ・アンジェリン(ソプラノ)、ルイ・ノゲラ(バリトン)。わたしはこれにすごく感動した。たしかにフィッシャー=ディースカウやロス=アンヘルスのような「華のある」歌手ではない。しかしそれのどこが悪かろう?フォーレの「レクイエム」は技巧を必要とする曲だろうか?華やかさが必要な曲だろうか?横道にそれた。ここに聴くフォーレの「レクイエム」は美しく、そして素朴である。余計な化粧は一切なくそして「敬虔さ」を見る。そこには現代がひょっとしたら見落としている「正直さ」をわたしは見る。わたしはこの演奏を愛する。
|
|
|
大演奏である。かなりテンポは揺れるし(特に終楽章のコーダ!)、聴いたことがないような音色等、かなりユニークな(少なくともわたしにとって)マーラー。わたしにとってマーラーはものすごく大事な作曲家であり、だからこそなるべく多くのマーラーを聴くのは喜びである。そして今またヤッシャ・ホーレンシュタインという新たな指揮者のマーラーが聴けた。なんというか、ホーレンシュタインは「覚悟が決まっている」。彼は歌うべきところではためらわずに、そして重要だからこそ焦点を「当てる」。素晴らしいマーラー指揮者だと思う。ヤッシャ・ホーレンシュタインにあって今の時代には無いもの。それは重要なもののはずだ。
|
|
|
わたしはシベリウスのヴァイオリン協奏曲を「偏愛」している。そう、まさしく特別に「愛して」いる。理屈ではなく「肌に」馴染むのだ。この演奏については昔から知っていた。CDだって何枚か所持している。だがいつ聞いてもそれほど素晴らしいとは思えなかった。なんというか「隔靴掻痒」今一つ届かない感じだった。ところがこのシリーズでベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(クライスラーの旧録音)を聴いてそのヴァイオリンの音に驚いて、ぜひヌヴーのシベリウスを聴いてみたいと思ったのだが…。驚いた。このCDはぜひ聞くべきだ。まずワルター・ジェスキントがいい。大変立派な伴奏だと思う。そして何よりジネット・ヌヴー。絶品だという以外言葉が見つからない。わたしにはハイフェッツよりはるかに好ましく聞こえる。こういう演奏を聴くと「現代の演奏は進化しているのか」とつくづく感じる。この演奏に足りないものなどごくわずかなものしかありえないのではないかと。本当にいい意味で驚かされたCDである。
|
|
|
何度も買いなおしたCD。ブルックナーは最初はわからなかった。なんかどろどろしてどこに焦点を当てて理解すればいいのかまるで分らなかった。だからわかるまで繰り返し聞いた。本を読んだ。ある日ふと気ずいた。「もしかしてこれが意味があるものだったら?」。そこからブルックナーの交響曲が面白くなった。年齢を重ねるごとにますます興味を惹かれるようになった。この演奏においてクナッパーツブッシュは、版の問題・アンサンブルの精度やフォルムの精確さなどにはこだわっていないと思う。クナッパーツブッシュにとって大切なのは「この音楽は何を訴えているのか」でありそれ以外のものは枝葉末節でしかないのだから。現代は「細密化」の時代である。細かい部分を拡大して見ようとする時代である。しかし不思議なことに物事の本質は何も変わっていない。今なぜクナッパーツブッシュやフルトヴェングラーがいないのか、わたしたちには何が足りないのか。この演奏を聴いて考えてみるのも一興ではないだろうか?
|
|
|
EMIからチェリビダッケ/MPOのブルックナーの交響曲が発売されたとき、わたしはためらわず購入した。ちょうどそのころチェリビダッケ/MPOのサントリーホールでのブルックナーを聴き、非常な感銘を受けた後であり、購入しない選択肢はなかった。そのころ「これはブルックナーではない」、「ブルックナーの演奏としてはシュツットガルト放送交響楽団との演奏のほうが優れている」というような評が盛んにいわれていたように記憶している。わたしはこのような意見に戸惑うばかりであった。あれは、あれこそはこの上なく「形而上的な」演奏であり、チェリビダッケが、いかに大きな知識を持ちMPOがそれを音にすることができる技術を持ち、そしてそれをチェリビダッケがオーケストラに伝えることができる。それがはっきりわかる演奏だったから。率直に言えば哲学者ならあの演奏にビンビン感じなければ噓だろう、そういう演奏だった。そしてわたしには当然衝撃的な演奏だった。それ以来チェリビダッケは、わたしには当然のように特別な名前になった。
もしかしてここではこういうことを書くべきではないのかもしれない。今わたしが書いているのは「わかる人だけわかればいい」ということだから。チェリビダッケの演奏について一言いうならば、彼の演奏はわたしのレゾンデートルにつながるものである。それ以外言えない。
|
|
|
聴いた瞬間、まず頭に浮かんだのは「ワルターはこの響きと離れたくなかったんだ」。現在の精妙な演奏、汎個性的な響きからすると、おそらく様々な瑕瑾を指摘する人はいるだろう。だがここには夢見るような響きが、あこがれを追い求める「音」がある…。わたしにとってグスタフ・マーラーはとても大切な作曲家だが、今現在のわたしにとってブルーノ・ワルターのマーラーは必ずしも最上のマーラーとは考えていない。ワルターのマーラーにはわたしがためらう「何か」、「演奏」を考えるときにどうしても無視できない「何か」がある。だがこの演奏の「夢見るような」響きは必須なものに思う。ブルーノ・ワルターそしてウイーンフィルにとってもこの演奏には思うものがあっただろう。わたしにはそれが音楽を聴くうえでものすごく大切なものに思える。
|
|
|
3番から聴き始めたのだが、聴いた瞬間涙が出そうになった。この演奏についてはライナーノーツに書かれていることがすべてだと思う。そう、かつてはこういう丁寧な仕事をする指揮者がいたんだ、と。運動神経や反射神経だけでなく、楽曲の隅々まで目を通し、細かく演奏を作り上げる決して単なる合奏のまとめ役ではない「本当の」仕事ができる「職人的な」指揮者がいて、そしてわれわれはそれを親しく聞ける環境にいたのだ、と。現在の演奏がすべてだめだとは言わない。クラウス・マケラなどはわたしも好んで聴いている。しかしかつてはこの音を、こういう指揮者を聞いていたんだと思うと涙が出そうになる。わたしはなんてすばらしい環境にいたのだろう。交響曲の何番がいいなどとは言えるはずがない。このCDはとても大切なCDである。
|
|
|
「サロネンってこんな熱い指揮者だっけ?」…、それが聴いた後まず感じたことだった。同時にサロネンのとてつもない「情報の処理能力」に舌を巻いた。サロネンの「情報を扱う能力」それをオーケストラに伝える能力は群を抜いている。そしてそれは彼が自分を理解している証拠でもある。こういう人が指揮者をやっていてMTT以後のサンフランシスコ交響楽団を振っていることが、うれしくてたまらない。これほど演奏を聴いて考えさせられた経験はそうあることではない。ロスアンジェルス交響楽団のうまさにも驚いた。これは素晴らしいCDだ。
|
|
|
このCDは何というべきか…、とりあえずこんなとがった演奏をして、こんな面白いCDを作るピアニストは今はいないだろう。この5人の女性作曲家(たぶんあまりいい呼び方ではない)の作品はそれぞれ興味深い。耳を傾けるとそれぞれのやり方で音を「紡いで」いるし、ピアニストはそれを注意深く「奏でて」いる。なかでもやはりウストヴォリスカヤのピアノソナタ第6番は圧倒的だと思う。その演奏はあまりに「鮮烈に」響く。いま向井山朋子はさらに活動スペースを広げているという。わたしも行ってみたくなった。いまこんな「とがった」CDでデビューする「女流」ピアニストはいないだろう。これはリマスターするにふさわしいCDだろう。
|
|
|
ラファエル・クーベリックが大指揮者であることは誰もが知っていることだと思う。一方、クーベリックが録音面においては、いささか恵まれてはいないことも広く知られていることだろう。ブラームスやベートーヴェン(!)、マーラーの交響曲全集、そして何より「わが祖国」はあっても肝心のブルックナーの交響曲全集はない。ベートーヴェンの交響曲全集は素晴らしかった。非常に面白い交響曲全集だった。まさにクーベリックにふさわしい画期的な全集だった。マーラーもよかった。一見自然の息吹にあふれている演奏だけどそれだけでなく内声部をえぐりにえぐっているかなり「カロリー」の高い演奏だった。ブルックナーはどう考えてもクーベリックに似合っているのに、ベルリンフィル等の暗い響きでなく、あのバイエルン放送交響楽団の明るい響きとクーベリックが演奏するブルックナーは絶対に素晴らしいものになるのにそれはついに実現しなかった。まさに痛恨の極みである。確かに交響曲やオーケストラの録音は多大な費用が掛かる。またクーベリックの一般な知名度も問題になったのかもしれない。わたしはあくまで一般の音楽ファンに過ぎないのでその点はわからない。繰り返すがクーベリックのブルックナーの交響曲全集がないのは残念無念である。CBSソニーの録音は素晴らしい。これは非常に価値ある商品だ。
|
|
|
わたしには二人の尊敬するピアニストがいる。ソロモンとウラジミール・ホロヴィッツ。ソロモンは何よりベートーヴェンのピアノソナタで。そしてそれ以外のピアノ、「音楽」としてのピアノとそれを奏でる「ピアニスト」としてのホロヴィッツの二人である。ホロヴィッツは前世紀の大家の「グランドマナー」それを伝えるほとんど最後のピアニストだったのでではないかと思う。単に技巧がどうとかではなく、その音色の「ブリリアントさ」「コクのある音色」それを伝える最後のピアニストだったと。ホロヴィッツ以降も数多の才ある若手、優秀なピアニストがデビューしたが、結局この「音」を今聞くことはできない。「唄」は絶えてしまった。ホロヴィッツは世のピアニストが「わたしはピアニストです」と言うのが不思議で仕方なかったらしい。さもありなんと思う。ホロヴィッツとその他のピアニストの違い。そこには「ピアノ音楽とは何か」という極めて大きな問いが隠されている。かえすがえすもホロヴィッツの生の「音」を聞いてみたかった。ラフマニノフにおいてメータはホロヴィッツによくついている。これは完全にホロヴィッツを聴くための映像である。
|
|
|
このCDは帯に書いてある通りこの演奏に対する評価を改めさせる可能性がある。クナッパーツブッシュもカーゾンも彼らのベストとは言わないまでも、十分に優れた演奏を行っているし(少なくとも彼らにとって不名誉な出来ではない)、ウイーンフィルも相変わらずいい音色を奏でている。このCDの解説には初出時のこの演奏に対する評価が載っているのだが、カーゾンはクナッパーツブッシュに押しまくられてはいないし、カーゾンが不調でキレが悪くもないし指揮者の人選のミスとも思えない。いったい昔の評論家は何を聴いていたのだろう。この演奏が「皇帝」の理想の演奏とまでは思わないが、繰り返すが彼らにとって「不名誉」となる出来ではない。少なくともわたしはこの演奏に感心した。
|
|
|
チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第1番」とドヴォルザークの「新世界」は「朝飯を食いながら」聴く曲と言われているそうだ。あいにくとわたしは大好きだが。閑話休題。このCDはある意味「手に汗握り、そしてあっけにとられる」いわば「一大スペクタクル」である。腕っこき集団であり悍馬のようなウイーンフィル、日の出の勢いの指揮者ががっぷりよつに組んだ「完成度」より「きらめき」のような録音だと思う。まさにこれは人が一生に一度しか録音できない(それを録音できない人も多いが)CDである。いやあ確かにこれは聞くべき録音だ。
|
|
|
このCDには心底驚いた。ジークフリートの葬送行進曲を聴き始めた途端「え、これがワーグナー?」、わたしはバイロイトには行ったことはないが、これでもクラシックを聴き始めてから半世紀近くになる。そんなわたしが聴いたことのないワーグナー。ムラヴィンスキーは完全に自分の目でスコアを読み込んでいる。慣習ではなく。ムラヴィンスキーは自分が読み取った通りに曲を演奏する。もちろんオーケストラは超高性能。ムラヴィンスキーの読み取った通りに曲を演奏する。これではワーグナーの序曲の演奏で一晩の演奏会を開催するどころか、独唱者、合唱一切なしでワーグナーの楽劇を上演してもいいとさえ思う。もしその演奏会を聴けたら興奮のあまり死んでしまうのではないか。恥も外聞もなくムラヴィンスキーこそ世界最高のワーグナー指揮者であるといいたくなる。まさかワーグナーの序曲の演奏でこんなに胸躍る日が来るとは。ムラヴィンスキーは恐るべき演奏家である。これはムラヴィンスキーの演奏を語るうえで非常に重要なCDだと思う。。
|
|
|
このCDは完璧!フィルハーモニア管弦楽団のべらぼうな上手さ!独唱陣の見事なこと!そして何より、ムーティに称賛を!この時ムーティは40歳にもなっていないが、オーケストラを見事にコントロール。勢いに任せて駆け抜けることなど薬にしたくもない。いやあ、このCDを聴くのは初めてだが、あっけにとられた。素晴らしい演奏だと思う。独唱陣の歌も聴きとれる。なお録音は超優秀。すべてのディテールが聴こえる。まったく見事なCDだ。
|
|
|
J・S・バッハは偉大である。マタイ受難曲、ヨハネ受難曲、ミサ曲ロ短調、管弦楽組曲、ブランデンブルク協奏曲、無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ、無伴奏チェロ組曲そして数々のカンタータ…。これほどの名曲を残した作曲家をわたしは知らない。そしてバッハの世界は「広い」途方もなく「広い」。無伴奏チェロ組曲はチェリストならば一度は録音を残したい曲であろう。数々の録音が存在するがなぜか名チェリストと呼ばれる人の録音は50代後半や60代に録音したものが多いようである。あの世界は「若さ」だけではどうにもならないのであろうか。このCDはヨーヨーマが20代半ばで録音したものである。ヨーヨーマはここでチェロを「歌わせ」「飛翔し」自由にこの世界を旅している。彼はテクニックはもちろん、しっとり演奏すべきところもおろそかにはしない。ヨーヨーマは「自由」だ。そしてその姿勢は実に「美しい」。マはやはり稀有なチェリストであろう。わたしは、実はヨーヨーマの演奏を聴くのを避けていた。カザルスやロストロポーヴィチの演奏を好んでいた。カザルスやロストロポーヴィチにも優れた無伴奏チェロ組曲の録音がある。だが今回この録音を聴いて心底驚いた。この「若さ」に。ヨーヨーマにはこれ以降2度の無伴奏チェロ組曲の録音がある。それを聴くのが非常に楽しみだ。
|
|
|
いわずと知れた名盤。録音状態も極上。まったく、今のファンはうらやましい。この音で「始められる」のだから。このCDを聴いて思った。「これがフルトヴェングラーの音だ」と。何回も言うが、フルトヴェングラーは「伝達者」だ。他のソリスト・演奏家が「音を出す」のに比べ、フルトヴェングラーの「音」は「こちらに」迫ってくる。もちろん録音状態が良ければより分かりやすいけれど、一度気づけば録音があまり良くなくともそれを聴きとるのは難しくはない。ただし、これを他人に伝える・「言語化」するのは非常に難しい。フルトヴェングラーが後継者も、同じことをやろうとする者もいないゆえんである。少なくともわたしは知らない。このCDはその「音」がすごくよく聞こえる。平林さんはまことにいい仕事をしてくれたと思う。出来たら多くの人がこのCDを聴いてくれればいいいのにと思う。
|
|
|
トスカニーニのローマ三部作。いわずと知れた、名演。名CD。わたしはトスカニーニが苦手である。だから見当はずれなことを書くかもしれないが。
このCDを聴いて気づいた。「あ、これ現代の演奏と同じだ」と。なんていうか「音の出し方」?「音の語り口」?あるいは「音の進行の仕方」?アルトゥール・トスカニーニとヴィルヘルム・フルトヴェングラーは20世紀前半の指揮会の二大巨頭だが、後世の指揮界に影響を与えたのはアルトゥール・トスカニーニだ。なぜか?以前も書いたがトスカニーニの演奏は「言語化」あるいは「記号化」ができるから。この時代にこの演奏ができるならそれは「素晴らしい」としか言いようがないだろう。現にわたしも「ローマ三部作」の演奏としてはこれ以外は考えられないと思う。そしてそれは「伝える」ことができるから結果として現代の指揮界に大きな「足跡」を刻む。対してフルトヴェングラーの指揮は、極論すれば「伝達者」であり「言語化」や「記号化」を目指したものではない。どちらが伝えやすいかは論を待たないであろう。わたしはこのCDは素晴らしいと思う。一つの究極の形でさえあると思う。にも関わらず相変わらずわたしはフルトヴェングラーを聴き続けるだろう。あの「音」を聴きたいから。このCDの録音状態は極上。これ以上は望むべくもない。
|
|
|
チャイコフスキーの交響曲は独特である。ベートーヴェンやブラームスといった、いわゆるドイツ本流の交響曲に対し、まるで抒情詩のような独特な交響曲である。ムラヴィンスキーもまた「自分の目」でスコアを読み込む指揮者である。ムラヴィンスキーにはチャイコフスキーのような、いわばロシア音楽の神髄のような曲でも「伝統」に従うだけの演奏は許し難い。ここでのレニングラードフィルいやムラヴィンスキーの下でのレニングラードフィルもいつものように「鮮烈な」演奏を行っている。これだけの規模なのに音色や演奏が揃っているとかのレベルではない。「音楽を」奏でている。そしてそれを統率しているのはムラヴィンスキー。確かにこれはチャイコフスキー演奏の一つの「究極」であると思う。ムラヴィンスキーはやはり「独特な」指揮者である。
|
|
|
これは大変素晴らしいCDである。なぜか。「フルトヴェングラーの音がよくわかるから」。録音状態は良くない。ただし1970・80年代にフルトヴェングラーのCDやLPを聞いた人間には問題にならないレベル。あの時なら「音がいい」というレベル。さすがに現在のレベルなら音がいいとはお世辞にも言えないが。ではなぜ「フルトヴェングラーの音がよくわかる」のか。フルトヴェングラーは誤解を恐れずに言うならばいわば「仲介者」あるいは「伝達者」だと思う。普通指揮者であれソリストであれ、自らが音を出す。当たり前だ。自分が演奏しているのだから。だがフルトヴェングラーは違う。彼の演奏は音が「向こうからやってくる」。彼はそれをオーケストラに伝えて音を出させる。内田光子が言うように残された映像からはそれがはっきりわかる。トスカニーニとフルトヴェングラー。いずれも20世紀前半の二大巨頭と言っていいだろう。だが現在の指揮界により大きな影響を及ぼしているのはトスカニーニだろう。なぜか。以前にも書いたがトスカニーニのほうが「記号化」できるから。フルトヴェングラーは自己を見つめいわば「才能」で指揮をした。音を「出させる」のではなく「向こうからやってくる音を伝える」。これをどう伝えるのか。それを実行したのが過去・現在を問わず、わたしが知る限りフルトヴェングラーだけだ。それが、この「不完全な」録音状態からもよく聞き取れる。だからわたしはこのCDは素晴らしいと評価した。この意見は賛否両論いや否定的な意見が多いであろうか。
|
|
|
ウイーンでウエーバー、シューベルト、ブラームスを演奏するのは覚悟がいる。ほかの土地とは違う。「ウイーン」は「本場」だから。オーケストラも聴衆も強い自負を持っているだろうと思う。このCDはいわばムラヴィンスキー/レニングラードフィルが「本場」にガチンコで勝負を挑んだいわば「本気」のCDである。ウイーンの聴衆は驚嘆したと思う。ウエーバーやシューベルト、とにかくドイツではこういう演奏をする、それとの感覚の違いというかムラヴィンスキーの解釈、そしてレニングラードフィルの異次元とさえ思える性能。恐らくほとんどの聴衆にとってこんな「情報量のある」含蓄の豊かな演奏は初めて聞くものであったと思う。わたしは残念ながらムラヴィンスキーの実演に触れることはできなかった。わたしがクラシック音楽を聴くようになったのはムラヴィンスキー最後の来日の少しあとである。そのころは「ムラヴィンスキー」の名は全く知らなかった。その後は多くの人と同じようにあのチャイコフスキーなどの道をたどって惹かれて今に至るわけだが。現在はムラヴィンスキーはチェリヴィダッケと並んで「今世紀最大の天才指揮者」であると考えている。そしてそれは次々に発売されるCDを聞いても全く変わらない。ムラヴィンスキーは自分が確信を持てる限られた曲を磨き続けた人であると思うが、その結果が余人の追随を許さない「結果」を出せた人だと思う。このCDは非常に「含蓄のある」CDだと思う。
|
|
|
ソロモン…新しいリスナーには聞かない名だろうし、前から聞いているクラシックのリスナーにとっても決して親しい名ではないだろう。日本に来日したこともあるのに評判は良くなかったと聞いている。わたしがソロモンの名を聞いたのは例にもれず吉田秀和の著書によってである。聞いて驚いた。決して走らないテンポ、濁らない音。余裕のあるコントロール。こんなベートーヴェンがこの時期に奏でられていたなんて。かつての評論家そして好楽家たちは何を聴いていたのだろう。こんな素晴らしいベートーヴェンを見逃すとは。そして今や若いファンは聞くすべがない。これほど悲しいことはないだろう。これなに「美しい」音楽を聴けないなんて。
|
|
|
今回の20数年ぶりの、バーンスタインのマーラー新録音体験はどうしても「復活」で終わりたかった。「復活」にはどうしても思い入れがあるし、何よりわたしにとってとても大切な曲だから。わたしはベルティーニ/東京都交響楽団のマーラー・チクルスを埼玉会館で聴いている。その後親友に言ったことがある。「復活」ってマーラーの「春の祭典」なんだと。それに対して親友はこう言った。「第一楽章ね」と。あのマーラー・チクルスはとてもためになった演奏会だが、何より親友のこの言葉がうれしかった。そしてもうひとつ、恐らくマーラーは終楽章においてクロップシュトックの「蘇るだろう」を聴くまでこの曲をどう終わらせたらいいのか途方に暮れていただろうこと。わたしにはそれほど大事な曲である。さてバーンスタインの「復活」の新録音について。ライナーノートにあるようにこれほど切実で広々と、深い演奏をわたしは知らない。いまやマーラーは人気作曲家であり様々な指揮者が録音している。それぞれ見るべきところはありわたし自身も新しい録音を聴いて感心することがある。しかしそれでも結局バーンスタインのマーラーに帰ってくる。バーンスタインはむしろ「冷静に」客観的に距離を取ってマーラーを眺めている。そのうえでバーンスタインは「感動」を感情を無にしない。素晴らしいマーラーだと思う。将来これ以上の演奏が出現するとしたらヤクブ・フルシャが録音したときだろう。これは聴かなければいけない演奏である。この文章が今は亡き親友を辱めないことを願う。
|
|
|
わたしはシベリウスのヴァイオリン協奏曲を偏愛している。そう一番愛しているヴァイオリン協奏曲である。初めてこの曲を聴いた時のことを覚えている。曲が始まった瞬間、文字通り「肌に」馴染んだ。なぜか日本人女性に合うと思った。その後様々な演奏を聴き今では少し聴き方が変わってきたけれど。ユーハン・ダーレネはむしろ線が細すぎず、しっとりと落ち着いて曲を演奏している。この部分、旋律は何を表しているのか、そのためにはどう弾いたらいいのか、それをわかったうえでダーレネは演奏しているように聞こえる。そしてそれはわたしが大変好んでいるこの曲の弾き方である。ダーレネは素晴らしいヴァイオリン奏者だ。ヨン・ストゥールゴールズもロイヤルストックホルムフィルも大変見事。これは素晴らしいCDだ。
|
|
|
グスタフ・マーラーの交響曲第3番は面白い交響曲だと思う。まず規模がとても大きい。来日するオーケストラがこの交響曲を演奏するのは賭けに等しい(直近ではわたしの大好きなヤクブ・フルシャのバンベルク響来日公演か)。何せ第1楽章だけで30分を超える。30分あればモーツァルトの交響曲が1曲聞ける。だからたとえCDでも演奏を聴くのは覚悟がいる。そう気軽に聞ける音楽ではない。しかしマーラーのブルーノ・ワルターにあてた手紙にあるように「マーラーの曲を楽しめる人にはこの交響曲が示した道をたどると無上の喜びが約束される」そういう曲でもある。特に第1楽章は長さもたっぷりあり、曲の美しさも大変素晴らしい。第2楽章、第3楽章の美しさ、第4、第5楽章の独唱や自動合唱の素晴らしさ。そして第6楽章の「大きさ」。まったくすごい曲だと思う。グスタフ・マーラーの交響曲第3番がいかに素晴らしい曲であるか、その意味が初めてわかった演奏だとさえ思う。これは素晴らしい演奏である。やはりバーンスタインのマーラーは要注目である。
|
|
|
グスタフ・マーラーの交響曲第8番は「異形」の交響曲である。大きくは二部に別れテーマ的にも巨大な「交響カンタータ」である。そして「神」を「人生」を讃える…。完全な「ハレ」の交響曲である。まるでマーラーらしくない。マーラーの人生はご存じのようにこれ以降難しい方向に向かってゆく。愛する娘の死、アンナの不倫…。作曲家としてもR・シュトラウスばかり認められマーラーの作曲は揶揄され…。とにかくそのマーラーの最後の(少なくとも大々的には)肯定的な交響曲である。バーンスタインはむしろ俯瞰的に、冷静に指揮していると思う。客観的に眺めたうえで主観的に事象を眺めるのは最初から主観的に眺めるのとは違う。バーンスタインのマーラーはその一つの優れた例だと思う。歌手陣もそれぞれベストの出来だと思う。かえすがえすもこれが二度目のマーラー全集としての録音でないのが残念である。
|
|
|
タワーレコードに希望したい。ソロモンのベートーヴェンのピアノソナタ。多分ほとんどの人が知らないだろうし、セールスも期待はできないだろう。だけどソロモンのベートーヴェンは…「高貴」である。言葉の本当の意味で。あのベートーヴェンはあまりに「尊い」。ベートーヴェンのピアノソナタを語るのなら、ソロモンを聞かなければ意味はない。是非ソロモンのベートーヴェンを出してくれないだろうか?強く強く希望する。
|
|
|
わたしにはブラームスのピアノ協奏曲にはふたつ聞きたい録音があった。ひとつはゲルバーの第1番。これは吉田秀和氏の本で知った。吉田秀和氏の評を呼んで聞きたくて聞きたくてたまらなくなり散々探し回ったが、幸いにもCDが手に入りあまつさえ、タワーレコードがリメイクしてくれた。期待にたがわず素晴らしい演奏でADF大賞にふさわしい演奏である。これがデビュー盤とはまさに「ゲルバー恐るべし」だった。一方もうひとつはアンネローゼ・シュミットの第2番。何かで読んでこれまた聞きたくなった。それがかなったわけだが、さて何と言おうか。いい演奏とは最初の一音で引き付ける。まさにこの演奏がそうだしシュミットは実に深くて落ち着いたいい演奏をしている。効果狙いではない音楽「そのもの」に語らせた演奏といえようか。ケーゲルの伴奏も見事。これまた落ち着いた地に足のつぃた演奏である。タワーレコードのセンスは実に見事。
|
|
|
マーラーの交響曲第6番は従来からの古典的形態を、マーラーの交響曲の中では一番保っているように見える。またこれはバーンスタインのマーラーの交響曲全曲を聞き終わってから書く積もりでつもりでいたけれど、20数年ぶりに聞いてみるとバーンスタインが意外と「形」を保つことに意識を割く人だと驚いているので余計そう感じる。考えてみればバーンスタインは作曲家でもあるので当然ではあるが。この迫真力というか迫ってくる感じは只者ではないだろう。それはバーンスタインもウイーンフィルもある種の「真実」をつかんでいるからのように、わたしには聞こえる。わたしにはこの交響曲第6番は「この上なく」切実なものとして聞こえた。これはバーンスタインがかつて録音してから「正しい」道を歩んできたからだと思う。わたしはこのCDを愛する。
|
|
|
グスタフ・マーラーの交響曲第5番というとルキノ・ヴィスコンティの「ヴェニスに死す」。第4楽章のアダージェットと多くの人は言うだろうが、わたしにとってはカラヤンがその録音時に冒頭のトランペットを少年、その柔らかい唇が奏でる音色を求めたという印象を持つ。このCDのライナーノートに書かれているように、まさにこれはウイーンフィルそしてバーンスタインにしかなしえない演奏だと思う。かなり遅いテンポでありながらこの実在感、自分に迫ってくるというかむしろ自分に突き付けられているような迫真力。まったくこの演奏は名演というよりむしろ異常とも思える。バーンスタインのマーラーはつくづく素晴らしい。
|
|
|
グスタフ・マーラーの交響曲第4番は非常に色彩豊かな曲である。まるで真っ白なキャンバスに描かれた極彩色な絵のような。一方他のマーラーの交響曲に比べれば編成も小さく演奏時間も短い、事実マーラーの交響曲の中では比較的早い時期から親たまれた(?)曲なのであろうか。バーンスタインは1度目のマーラー全集を4番の録音から始めたのではなかったか。この録音時バーンスタインは旧録音時とは比較にならないであろう演奏経験と指揮技術を獲得していたであろう。バーンスタインは一見かなり自由にテンポを歌わせロイヤルコンセルトヘボウはそれに余裕をもってついていく…。終楽章のソプラノ独唱は旧録音ではレリ・グリストが素晴らしい独唱を聞かせ新録音ではボーイソプラノに歌わせている。確かこの選択には否定的な意見が多かったように記憶している。20数年ぶりに聞いてみるとこの独唱はやはりなかなかいい。少なくともわたしには全然「アリ」だと感じた。確かに女性に比べ多少「固いかな」とは思ったがそれでもわたしは「いいんじゃない」と感じた。バーンスタインもロイヤルコンセルトヘボウもいわば「大人の遊び・自由さ」をもってこの曲を演奏している。やはりこれは特筆すべきCDであろう。
|
|
|
グスタフ・マーラーの交響曲第7番は不思議な交響曲である。19世紀ドイツロマン派の文脈の中での理解では(一見)理解するのが困難なように見える。そう、「一見」。しかしいったん落ち着いて考えてみるとあることに気づく。響きのコラージュ。比類なく豊かな音色のパレット。そうそこにあるのはきらめくような音色のキャンバス、色彩豊かな音の変化。そしてそれはドイツロマン派のもともと目指したものではないか。だからこそマーラーはシューマンの交響曲を編曲したのではないだろうか。このCDを聴くとそんなことを考えさせられる。やはりバーンスタインは不世出のマーラー指揮者であった。
|
商品詳細へ戻る