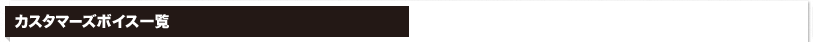
ベートーヴェン: 交響曲第9番「合唱」 / カール・ベーム、他
|
|
伝説的な公演が聴ける貴重な記録。ベームは情熱と冷静さのバランスがよく(ライヴ録音の中には、このバランスが崩れてしまっているものもある)、見事な出来。第3楽章の豊かさとフィナーレの高揚感は十二分に満足のいくものだ。オーケストラもよい。
|
商品詳細へ戻る
DASFさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
星の数は四つと三つの間です。以前に出たベルリン盤の方が聴きやすいという印象です。カットを見直すなどの変化もあって興味深いのは事実ですが、やや大味に感じられます。演奏自体は、きっと客席で聴けたなら、もっと感銘深いものであったでしょう。
|
|
|
ドヴォルザークのチェロ協奏曲では、ヘルシャーの独奏が登場から輝かしく、強烈な説得力を示します。シューマンは濃密な響きが素晴らしいのと、テンポが速い部分でのスピード感によって高揚感を味わえます。二曲のチャイコフスキーでは、やはり「悲愴」が面白く、たいへん個性的ですが、後半の二つの楽章は見事だと思います。
|
|
|
全てがよいというわけではないので、星四つにしました。岩城とのショパンの1番の協奏曲は名演だと思います。他方、ノイマンとの2番の協奏曲は今一つ。これはノイマンとの相性の問題ではないでしょうか。この一枚目のディスクにはモーツァルトのソナタが入っていますが、これがまた見事な出来です。
二枚目のディスクはブダペストでのリサイタルですが、音がちょっと。大曲を四つ並べたプログラムは圧倒的です。
|
|
|
モーラン、いいです。ピアノ三重奏曲と、チェロとピアノのための前奏曲は、しみじみとさせられます。演奏も申し分ありません。
|
|
|
星五つでもよいのですが、シマノフスキの曲に馴染みがなく、評価をためらってしまうので、四つにしておきます。
フランクのソナタは繊細な美しさで、他の代表的な演奏の厚みのある音や表現に慣れているだけに新鮮に響きます。ショーソンの詩曲も、素晴らしい美しさと言えるでしょう。
|
|
|
デュトワとのチャイコフスキーはモノラルで、存在価値は乏しいように思います。ノイマンとのシューマンはステレオですが、ノイマンが少々真面目過ぎる感じで、アルゲリッチとの相性に問題があるようです。他方、東京でのリサイタルは音も演奏も優れています。
|
|
|
ブルックナーに絞って書くと、悪くはないが、物足りなさも残す。管楽器が比較的前に出てきているのは悪くないし、演奏もうまいのだが、弦楽器が渋すぎ、ブルックナーらしい浄福感・恍惚感が出ていないところに欠点がある。この欠点は、この曲の要であるアダージョで大きな問題となる。他の楽章では、そこまでの違和感はないので、残念だ。
|
|
|
スターンのブラームスは星3つ。シェリングのメンデルスゾーンに星5つ。後者は甘さはないけれども、表情がうまく、情熱的である。スターンは、立派に、切れ味もよく弾き切っているとは思うものの、もう少し味わい深さがないと、名演の多い中では存在価値が乏しい。あるいは、録音のせいかもしれない。
|
|
|
どちらも名演です。曲の好みで言えば、郷愁の漂う第5ですが、第二次世界大戦で作曲家が心に受けた衝撃と悲しみを描いているかのような第6も優れています。演奏・録音も万全です。
|
|
|
これは絶好調のベームが聴ける一枚。この時期の彼のライヴでは、ときに焦り過ぎと感じさせられることもあるが、ここにはそのようなことは見られない。気迫と響きの充実感には文句なしである。ブラームスでは、さらに味わい深い独奏陣が加わって楽しめる。この作品のCDの中では上位に位置づけられるのではないか。
|
|
|
シューマンはよいと思いますが、ベートーヴェンはシューマンに比べて音が悪い(圭角がとれている)ように感じました。結果として、感銘度は低くなりました。同じ日のライヴなのに、理解に苦しみます。
|
|
|
「エロイカ」は初めの内は直截な進め方なのだが、途中から大きく動き出す。ここからの動きにうまくついて行ければ、とても楽しめる。モーツァルトはメヌエットが奇妙に速い他は安定したテンポ。ところどころで個性的な表情が聴かれる。ベートーヴェンの第7は、主題と、主題間を結ぶ経過部分とのテンポの差が大きい(主題は遅め、経過部分はかなり速い)。フィナーレに至っては、速めの主題のテンポから、さらに速いテンポに一気に飛び込んでしまう。なんと大胆な。
|
|
|
特にラヴェルに関しては、この音ではつらい。演奏自体は悪くないように思うのだが。ショパンは第一楽章の管弦楽のみの提示部に伝統的なカットを施した版での演奏。第二楽章が味わい深いが、両端楽章は、あまりスケールの大きさが感じられない。
|
|
|
高評価を得ているCDだが、それほどとは思えなかった。よい表情がついているところもあるのだけれども、散発的で説得力が弱い。ワルターやアバド、セル(旧盤)やケルテスを押しのけるほどのものではない。また、私の装置では少しうるさく聴こえる場面もある。(余談ながら、ティンパニの音は、とてもよい。)
|
|
|
ミルシテインならではのキビキビとした進め方で、技巧の冴えも見事という他ない。それでいて、微妙な表情の変化が織り込まれているところが嬉しい。クリーンのピアノも、さすがの出来である。
|
|
|
星四つと五つの間というのが正直なところ。尾高は、かつては、ところどころに勝負所を設けて、深い感銘を与える演奏をしていたが、近年は、より自然体になった(やや寂しくもある)。これは、共感に富んだ演奏で、迫力よりは味を楽しむものになっている。
|
|
|
音の状態がよく、楽しめる。ライヴならではと言えるのが、特に終盤での高揚感である。グールドにも、こういう面があったのだと思わされた。
|
|
|
個人的には、同じ組み合わせによる第8よりも、こちらの方が上ではないかと思う。音色も表現も違和感なく受け入れられる。この曲のCDとして最初に入手するのもよいだろう。ただ、名盤が目白押しな状態で、その中から抜け出せるほどのものではない。
|
|
|
圭角のある響き、テンポの変化の巧みさ、歌の豊かさ、そしてヴァイオリン独奏のうまさによって、「シェエラザード」のCDの中でも上位に置かれてよい演奏です。
|
|
|
トリオの方が特に名演と言ってよいように思います。有名な五重奏曲の陰に隠れがちな作品ではありますが、こちらの方が曲に生命力と肯定感があって、個人的には好きです。ソナタも好演です。時にピアノが、ややうるさく聴こえる場面があります。
|
|
|
シベリウスについては、作曲者の孤高の境地や内面が厳しさを伴って描き出された好演だと言えるでしょう。ディーリアスは、第3楽章の「去りゆく燕」を除いて初めて聴きましたが、悪くないと思います。チェロ・ソナタも短い曲ではありますが、楽しめます。
|
|
|
どちらも名演です。ブルックナーは細部にまで神経の行き届いた演奏で、豪快さには欠けるものの、アダージョの美しさは特筆に値します。シューマンは緻密であり、かつ迫力も備えた素晴らしい出来栄えです。フィナーレのコーダのさらに最後のところだけ、ちょっとテンポが速すぎたような気はしますが、これだけの演奏は、なかなかディスクでも実演でも聴けないでしょう。
|
|
|
録音が、やや大味です。演奏は、後半はばずまずですが、この曲の要である前半は、あまり面白くありません。
|
|
|
ティーレマンのブルックナーには、ミュンヘン・フィルとの来日公演(8番)で違和感を持ち、敬遠していましたが、これは悪くない出来だと思います。ただ、弱音を強調し過ぎなこと、流れの悪くなる場面があるのがマイナスです。細部の強調も新鮮なところもあれば、意味不明に感じられるところもあり、説得力は今一つというところでしょうか。第一楽章は、とてもよいと思います。
|
|
|
ヘスのピアノはスケールも大きく、聴き応えがある。それでいて「皇帝」の第2楽章での主題の弾き方はエレガントそのもの。ベイヌムの協演も推進力のある、充実したもの。シューマンは第1楽章でのアンダンテの部分の陶酔感が素晴らしい。これほどロマンティックな演奏は、他にあっただろうか。リパッティの死の年のライヴと並んで大切にしたい。
|
|
|
復刻を歓迎したい。マタチッチの指揮は音楽に勢いがあってよい。トニオ役のゴッビが素晴らしく、プロローグを始め、これだけのものは滅多に聴けない。コレッリはデル・モナコと比べられてはつらいかもしれないが、十分によい。アマーラは初めの内、声が重く感じられたが、後になるほどよいように思う。
|
|
|
優秀な録音とファウストの腕前が魅力の一枚。ただ、特にベルクに関しては、ファウストはうま過ぎると思う。特に第2楽章の死の苦しみや断末魔など、うまさゆえに怖さが伝わってこない。全体としても、少し綺麗過ぎるのではないか。
|
|
|
この時期のカラヤンの気迫・勢いには目を瞠らせられる。両曲共、緩徐楽章の味わいに丁寧なリハーサルの裏づけを感じさせられる。音質は、この時代のものとしては、並みのレヴェルではないか。
|
|
|
音質のよいパルティータ5番が、一番の聴きもの。イタリア協奏曲はよいけれど(フィナーレは圧巻)、やや金属的に聴こえるので、音量を絞り気味に楽しむのがよいかと思う。技巧の鮮やかさと抒情の味の濃さはグールドならでは。
|
|
|
店頭で何となく気になって購入してみた。よく整ってはいるが、圭角に乏しいのがブルックナー演奏としては大きなマイナス。
|
|
|
宇野氏の評論には、たいへんお世話になったのだが、演奏に関しては抵抗感が拭えないできた。これもそう。協奏曲は期待したほどに説得力のある演奏ではなかった。ベートーヴェンは崩れ・乱れが気になる。もう少し、合奏の精度を上げてから暴れるのがよいのではないか。
|
|
|
テンポの遅さは周知のとおりだが、意外と最後まで飽きずに聴き聞き通せた。日頃から愛聴する、というものではないけれど、これを聴く機会を逃すのは、あまりにももったいないと思う。
|
|
|
スクロヴァチェフスキの到達点を示す、たいへんな名演奏。ザールブリュッゲンのオーケストラとの来日公演のときは違和感だらけで全く感心しなかったのだけれども、この演奏は最初から最後まで文句のつけようがない。アダージョが特に気に入っている。
|
|
|
賛否が分かれている演奏らしいけれども、私は支持する。
似たようなタイプの演奏は、今日、少なくないが、これは、かなりの高水準だと思う。
|
|
|
バティアシュヴィリは好きなヴァイオリニストであり、従って、大きな期待をして聴いてみたが、これは大ハズレだと思った。バレンボイムが全くよくない。退屈の一言。それに足を引っ張られたのか、バティアシュヴィリも冴えない。このコンビのディスクがこれだけ(だと思うが)なのも頷ける。
|
|
|
ブロムシュテットには、実演で納得させられたことがないのだけれど、ディスクには、いくつか優れたものがある。これも、そうした一枚で、特にドヴォルザークが素晴らしい。
|
|
|
ほぼ原典版による演奏。マタチッチの5番ではNHK交響楽団との一枚が、マタチッチらしい豪快さの塊ではあるものの、より完成された演奏はこちらだろう。
|
|
|
ワルツもよいのだけれど、ボーナストラックのノクターンが素晴らしい、いや、とんでもないほどの名演奏。
|
|
|
熱狂的な支持者もいるケーゲルだけれど、私とは相性が悪いのかもしれない。これらのベートーヴェンの体温の低さには、どうしても拒否反応が起こってしまう。
|
|
|
アバドに対しては、申し訳ないが、あまり高い評価をしてこなかった。しかし、このアルバムは名演である。これほどまでに生気に溢れた演奏がアバドから聴けるとは思わなかった。もちろん、多少の出来不出来はあるし、特に第9は今一つとは思うが、一聴の価値は十二分にある。
|
|
|
このアルバムでのベストは、ドビュッシーだと思う。これほどまでに情感の豊かな「牧神の午後」は聴いたことがない。
|
|
|
どうも、この指揮者とは相性が悪いようで、今回も説得されませんでした。古典奏法も意識しながら、また、優秀な録音の助けも借りながら、いろいろな工夫をしているのはわかりますが、皮相に聞こえてしまうのです。録音の新しい「運命」なら、バッティストーニ盤を押します。
|
|
|
89歳のパレーだが、衰えは全く感じられない。フランスのオーケストラなだけに、デトロイト盤よりも音に味わいがある。強烈な推進力の「ボレロ」は圧巻。ドビュッシーも曲の構造がよくわかる演奏。フランクも、重苦しさを排した好演である。
|
|
|
私が音楽を聴き始めた頃は、アンセルメと言えば、フランス音楽とストラヴィンスキー、さらにはバレエ音楽の専門家と見なされていて、そのドイツ物の評価は低かったものでしたが、今回きちんと聴いてみて、びっくりです。素晴らしい。ベートーヴェンを聴く喜びが味わえます。4番のみ、少々音が硬いです。
|
|
|
ネルソンズは期待していた人なのですが、実演でもCDでも、感銘を受けたことはありません。このブルックナーも、私には退屈でしかありませんでした。
|
|
|
敢えて所有するほどの価値があるセットであるかどうか、疑わしいと思います。悪いわけではないのですが、ブルックナーを聴く満足は得られません。3番だけはよいと思いました。
|
|
|
美演ではあります。しかし、ブーレーズの演奏は、どこか静止画像を見ているような感じにさせられるところがあり、マーラーが必死に死を超える希望を見出そうとしていることが伝わってきません。
|
|
|
音もよいですし、ファウストのテクニックも申し分ありません。しかし、バルトークにしては冷静さが勝ちすぎているように感じます。曲に肉薄する凄さがバルトークの演奏には欠かせないのではないでしょうか。
|
商品詳細へ戻る