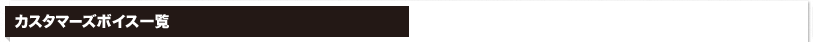
モーツァルト: 交響曲第38番「プラハ」、第36番「リンツ」(2025年ORTマスタリング)<タワーレコード限定> / オトマール・スウィトナー、他
|
|
本盤は日本コロムビアのベテラン技師、林正夫による優秀録音であり、私たちオールド世代が小・中学生時代に慣れ親しんだ昭和の市民ホールの響きを、指揮者が指揮台で聴いていたであろう原寸大サイズでリスニングルームに届けてくれる。またディテール表現も特筆すべきものであり、当時のN響トーンが手を伸ばせば触れることができそうなほどリアルに収録されているのも魅力だ。スウィトナーの指揮も結構手を抜いているので、随所に聞かれる演奏ミスや、リズム・アンサンブルの乱れは放置されていて、良く言えばライブを彷彿とさせる勢いに満ちている。使用されたデジタル録音機は、日本コロムビアが1977年に改良したPCM録音機DN-034R(14bit 47.25kHz)と思われ、83年の初出CDや99年の再発CDは、デジタルマスターからアナログ変換した信号をアナログコンソールでマスタリングし、それをCDフォーマットでデジタル化したものと推測するが、そこはデジタル録音のパイオニアの仕事であり、従来CDでも音質的な不満は全く感じられなかった。さて今回の新マスタリングについてタワーの解説では「鮮やかな音質」「間接音や倍音の豊かさ」を目指したとあるが、若干音像が前に出て、弦の密度が上がったように聞こえるが、これは音質が劇的に改善されたというより、機材の性能アップとマスタリングの方針の違いに過ぎず、それだけ元の録音や従来CDの仕上がりが良かったことの証明でもある。ちなみに個人的には、薄っぺらでシャラついた弦の響きをより忠実に再現してくれる従来CDの方が好みだが、再生装置によっても印象が異なるはずなので、他のリスナーのご意見も気になるところだ。
1
|
商品詳細へ戻る
mejiさんが書いたメンバーズレビュー
|
|
手持ちCD(HS2088)と比較すると、録音会場の残響成分が明瞭に聞こえるし、スタインウェイを特徴付けるフレームと響板間の共鳴音において不自然さが払拭されたし、フェルマータでの減衰の様子も極めてナチュラルになったことから、本ディスクのマスターは、アビーロードスタジオで、オリジナルのマルチトラックアナログマスターテープから新たに2CHにミックスダウンされたものだと思われる。とはいえネヴィル・ボイリングによる録音自体が良くないので、優秀録音へと激変したわけではないが、ミケランジェリのピアニズムがDG録音(こちらも褒められた出来ではないが)並にわかるようなったことは大いに評価したい。最後に道化抜粋は、モノラルでヒスノイズも歪も酷く、「72年セッション録音」というのは全く納得できないが、音も演奏も素晴らしい73年日本ライブで十分事が足りるのでここでは言及しない。
2
|
|
|
本盤は日本コロムビアのベテラン技師、林正夫による優秀録音であり、私たちオールド世代が小・中学生時代に慣れ親しんだ昭和の市民ホールの響きを、指揮者が指揮台で聴いていたであろう原寸大サイズでリスニングルームに届けてくれる。またディテール表現も特筆すべきものであり、当時のN響トーンが手を伸ばせば触れることができそうなほどリアルに収録されているのも魅力だ。スウィトナーの指揮も結構手を抜いているので、随所に聞かれる演奏ミスや、リズム・アンサンブルの乱れは放置されていて、良く言えばライブを彷彿とさせる勢いに満ちている。使用されたデジタル録音機は、日本コロムビアが1977年に改良したPCM録音機DN-034R(14bit 47.25kHz)と思われ、83年の初出CDや99年の再発CDは、デジタルマスターからアナログ変換した信号をアナログコンソールでマスタリングし、それをCDフォーマットでデジタル化したものと推測するが、そこはデジタル録音のパイオニアの仕事であり、従来CDでも音質的な不満は全く感じられなかった。さて今回の新マスタリングについてタワーの解説では「鮮やかな音質」「間接音や倍音の豊かさ」を目指したとあるが、若干音像が前に出て、弦の密度が上がったように聞こえるが、これは音質が劇的に改善されたというより、機材の性能アップとマスタリングの方針の違いに過ぎず、それだけ元の録音や従来CDの仕上がりが良かったことの証明でもある。ちなみに個人的には、薄っぺらでシャラついた弦の響きをより忠実に再現してくれる従来CDの方が好みだが、再生装置によっても印象が異なるはずなので、他のリスナーのご意見も気になるところだ。
1
|
|
|
従来CDやダットンのハイブリッドでは、キングスウェイホールでの収録とは思えない平面的な音響に「あのウィルキンソンがしくじったのか?」という疑問を拭うことはできなかった。しかしその理由は本盤のリマスターを行ったキストナーによる解説である程度分かったし、なによりスピーカーから聞こえてきた「DECCAサウンド」は、元の録音は決して悪くはなかったことを証明してくれた。ちなみにキストナーの解説で解せないのは「オケはマイク2本でしか収録されておらず…」の一節だ。解説書の表紙を飾っている録音風景写真には、ピアノに向けられた2本のMIDマイクが見え(この画角ではピアノのハンマーエリアを狙った近接マイクは見えない)、両サイドの高い位置にアウトリッガスマイク(アンビエンス)も見えるので、ここまではキストナーの言う通りであるが、ピアノの前にはデッカトゥリー(マイク3本)と思しきスタンドが置かれていて、弦楽器群の中央と右に2本のマイクも見えることから、「オケはマイク2本のみ」との記述と矛盾する。また本盤で聴かれるオケ全体のパースペクティブをややオフ気味に捉えたサウンドはデッカトゥリー特有のものであるが、ホルンとティンパニはいつものウィルキンソン録音に比べて弱い。で当方の推測は次のとおりである。① RCAからの4CH再生を前提にしたマイクセッティング(弦楽器群の2本以外の配置は不明)指示に従って、2CHのオケトラックが収録されたが、当然ながらこれはウィルキンソンの意図するサウンドとはかけ離れたものであった。② 一方で、DECCAの基本マイク(DECCAトゥリー+アウトリッガス)とピアノのサブマイクの信号は、LP用マスターとしてウィルキンソンによってその場で2CHにミックスダウンされ、演奏者とプロデューサーによって承認された。しかし本録音はRCA委託録音だったので、DECCA独自のサブマイク配置は採用されなかった。これならオケパートに①のマスターが用いられた従来CDやダットンハイブリッドのサウンドが残念な出来であったことや、本盤がウィルキンソン自身のミキシングであるにも関わらず、同時期の他録音と比べてやや聴き劣りすることのことの合理的な説明がつきそうだ。とはいえ、録音後半世紀を経て、この歴史的名演奏が本来あるべきサウンドで蘇ったことは快挙でありタワーレコードには心より感謝申し上げたい。
3
|
|
|
LP時代から、国内初出CD①、海外盤OIBP②と聴き込んできた愛聴盤の待ちに待ったSACD化③であったが、首を傾げざるを得ない出来だ。まず①はLPカッティング用のマスターを用いていたと思われ、LPに馴染んだ耳にも違和感の無い自然なサウンドが特徴だ。その後②が出ると、ディテールの解像度は向上したものの、耳障りなまでにハイ上がりなイコライジングに加えて、終楽章の鐘は別物にすり替わっていて打音タイミングまでずれまくるというとんでもないシロモノであった。しかしながら、このことから②は、①のミキシングに用いたマスターにまで遡ってのリマスタリングだったが推測される。さて今回の③だが、サウンドはほぼ①そのままでブラインドで聴いてもSACDの優位性は感じられない。鐘も①と同じだが、一か所編集ミスがあり、練習番号68から鳴らされる2度目の打音がずれている。つまり使用マスターは①と同じものにも思えるが、鐘のずれを考慮すると②のマスターにオリジナルの鐘トラックをミキシングし、①を参考にイコライジングしたのかもしれない。それならば、全体の解像度はもっと増すはずだが、①と変わらないとはどういうわけか?とにかく謎だらけのリマスターだ。かかる高付加価値ディスクを購入するユーザーは、昔からこの演奏を愛し、かつ相応のグレードの再生装置を持っていて、これまでより少しでも良い音で演奏を聴きたいという熱心なリスナーのはずだ。そして皆が知りたい情報は、オリジナルマスターテープがどんな状態で、何トラックあって、それを誰が、何を基準に、どんなポリシーを持ってミキシングしイコライジングしたのか?といった、リマスタリングに関する技術的な詳細情報である。しかるにブックレットに掲載された情報は、学生の感想文レベルの書下ろしと、昔のCDに掲載した楽曲解説の再掲載という体たらくだ。ユニバーサルジャパンには、かかるユーザーのニーズを適切に把握し、製品の情報開示を積極的に行うことを強く望む。
3
|
|
|
私の時代、復活といえばメータ&VPOでありLPも持ってはいたが、曲を覚えたのはスイトナー&N響による79年のエアチェックであった。演奏も録音もメリハリの利いたメータと比較すると、スイトナーは非常に呼吸が自然で、牧歌的でもあり、まるで別の曲に聞えたものであった。これまで、この理由は当時のN響の技量とNHKの録音技術の稚拙さによるところが大きいと思っていたが、今回のSACDを聴いて、スイトナーの解釈が一寸もブレていないことに驚くとともに、オケの技量と録音が良いと、これほどまでに感動の度合いが増すことを改めて思い知らされた。5番についても、スイトナーの解釈は一貫しており、一、二楽章はモーツァルトのレクィエムを、三~終楽章はR・シュトラウスの晩年の作品を聴いているかのような錯覚を感じさせるほど、優しく、静謐な音楽だ。現代における一般的なマーラー解釈とは全く異なるが、歴史的な名演だと思う。
1
|
|
|
コンヴィチュニーのブルックナーは、4番を73年の国内LP以来愛聴しており、今なお私にとって本曲のベストだと思っている。5番はうかつにもノーマークであったが、ppにあっても豊かに楽器を響かせ、随所で木管ソロを浮き立たたせ、盛り上がりではトランペットやティンパニを強奏させ、しかし全体の響きは開放ではなく凝縮に向かう、コンヴィチュニーならではのサウンドが聴かれ、軽い興奮を覚えながら全曲を一気に聴き通した。5番といえば、最近ではマタチッチにしか手が伸びなくなっていたが、これからは原典版を聴きたいときにはコンヴィチュニーという選択肢が増えて嬉しい。
0
|
|
|
早速「春祭」を手持ちCD(ブリリアントクラシックス)と比較したが、冒頭からCDでは聞えないホールの暗騒音が聞えてきただけで、今回のリマスターが十分信頼に値することを確信した。ブックレット解説もマスター音源の詳細(仮面舞踏会に関してではあるが)にまで及んでおり、だんまりのE社と比べても、これだけで信頼足りえる。次なるお願いは、この流れで「ペトルーシカ」と「火の鳥」のSACDを!
0
|
|
|
ヒスノイズの除去に加え、現代の同曲録音における周波数スペクトルに近づけるようなイコライジングによって、60年以上前の録音とは思えないようなフレッシュなサウンドに生まれ変わっている。通常、ここまで音がつくり込まれると、始終大きな違和感に苛まれるはずが、意外にもすんなりと聴けてしまう原因は、伝説的なエンジニア、ロイ・ウォーレスがこだわった3本マイクのみのデッカツリーがもたらすナチュラルなコンサートプレゼンスによるものだと思われる。そうなると、どうしてもマスターテープの素の音も聴いてみたくなるのがコアなファンの性である。そこでタワーレコードさんへのお願いだが、SACDレイヤーでは収録時間がたっぷりと余っているのだから、次回からはマスタリング前の音も併せてディスクに収録して頂くよう強く希望する。
0
|
|
|
このショパンアルバムは「奇跡」である。フー・ツォンの演奏は、強靭なダイナミズムに裏打ちされた極めて逞しい外観をまとっているが、内部には絶望的な寂寥感とそれを達観視するかのような慈愛が色濃く漂う、まさに唯一無二のショパンである。その特徴はマズルカに最も良く表れている。ほとんどのピアニストは、背中と指を丸めて、鍵盤を羽毛で撫でるようなタッチで、柔らかにこじんまりと弾くが、フー・ツォンは大曲同様に、まるでポロネーズのように堂々と演奏する。しかも、感情が溢れ出さんばかりの歌心にも満ちており、作曲家の強い愛国心と祖国への郷愁を誰よりも強く聴き手に伝える。フー・ツォンは、アシュケナージが2位になった55年のショパンコンクールで3位に入っているが、その際審査員のミケランジェリが、ハラシェビチを優勝させた審査結果に異議を唱えて退場したエピソードがあまりにも有名だ。ミケランジェリが演奏も(マスクも)「甘い」だけのハラシェビチを支持しなかったことは当然だとして、常識的で優等生のアシュケナージを評価した理由がこれまでどうしてもわからなかったが、このCDを聴きながら思い浮かんだのは「ミケランジェリはフー・ツォンを支持したのではないか?」ということである。当時の風潮・文化として、極東の後進国出身の無名の若者が、伝統ある西洋のコンクールの覇者になるなどあってはならないことであり、さすがのミケランジェリも正直に主張できなかったのではなかろうか。そして聴き進むにつれて、フー・ツォンが作曲者同様に祖国を失い、さらには両親も悲劇的な死を遂げるという過酷な人生を経験している事実、さらにはアルゲリッチがショパンコンクールに臨むに当たって「フー・ツォンの演奏に影響を受けたこと」を独白した事実、また彼女が別府音楽祭に度々フー・ツォンを招聘していた事実を知ると、この考えが確信に変わっていった。そしてアルバムの最後に置かれた絶筆のマズルカの和音(冒頭の幻想曲と調性が同じなのは意図されたものなのか?!)がフーっと消えた瞬間、「この演奏こそ史上最高のショパンだ」との確信に至った。「完全限定版」につき、既にオンライショップでの取扱いが終了しているのは極めて残念だが、このショパンは全ての人に聴かれなければならない。
0
|
|
|
まず4番から手元の2004年のハイブリッド盤と比較した。アナログ再生用のテープデッキの性能は当時から変わっていないと思われるため、今回のリマスターとの音質差は、「16年の経過による磁気テープの劣化」「ADコンバーターの機能向上」「マスタリングツールの技術的進化」及び「マスタリングポリシーの変化」によるものとなる。今回のリマスターも、音場を左右一杯に広げ、音のコントラストと分離、解像感を高めた、いわば「今風のサウンド」を目指した音づくりとなっている一方で、弦やトランペットなどの高域がややヒステリックに響くことから、オリジナルテープの劣化はそれなりに進んでいると考えられ、2004年リマスターの方がよりアナログライクで好ましい音だと感じた。続いて3番は、オリジナルテープの劣化によるハンディは4番と同じか、それ以上であるはずだが、結果的にこちらの方が違和感なく楽しめた。もっともこの原因はもともとのサウンドの傾向が異なることに他ならない。3番はショルティのリング以来、ゾフィエンザールでの録音経験が豊富で、この会場の音響を知り尽くしたゴードン・パリーによるものだ。パリーのサウンドは、マッシブで筋肉質なフルボディサウンドが特徴で、本録音でもその特徴が際立っている。一方の4番はコリン・ムーアフット。ムーアフットも1965年以来、ゾフィエンザールでのセッション経験があるが、そのサウンドは、師であるK・ウィルキンソン譲りの、広大なパースペクティブと高解像度を併せ持つスペクタキュラーさが特徴だ。このように3番も4番もいずれも優秀録音ではあるが、音そのものがかなり異なっており、今回の最新リマスターでは、たまたま前者との相性の方が良かったということだと思われる。最後に、オリジナルの磁気テープの劣化は、今後も徐々に進行していくわけで、その時代時代で、最高の技術を用いて高密度のデジタル化を行うことは極めて重要であり、こうした意味でタワーの独自企画を強く支持するものである。しかし前のレビューにもあるとおり、ヒスノイズや演奏ノイズなどを過剰に除去するのは決して褒められたものではなく、SACD層は容量が十分あるのだから、今後は「ノイズ除去及びイコライジング無し」のオリジナルデータも一緒に収録することを強く要望する。
1
|
|
|
火の鳥の優秀録音を、ステレオ初期から年代別に挙げると、50年代はマーキュリーのドラティ(59年 W.コザート)、60年代はデッカのアンセルメ(68年 K.ウィルキンソン)が不動の王座を占めていて、70年代では本盤(75年 B.グラハム)が真っ先に頭に思い浮かぶ。そしてこの後には、デッカのデュトワ(84年 J.ダンカーリー)、リファレンスの大植(96年 K.O.ジョンソン)と再び定番が続く。このように録音史に名を刻む偉大な名エンジニアの中にあってグラハムは正直無名であるが、それでも本録音の仕上がりが少しも見劣りしないのは見過ごせない事実だ。本録音の最初の聴き所は、冒頭から訪れる。ここでは、グランカッサによるピアニッシッモのトレモロをバックに、弱音器をつけたチェロとコントラバスとが最低音域でのアルコでユニゾンを奏でる中、2台のコントラバスだけがピチカートで同じ音を弾く。そして、この微細な超低域成分を、マイクがどこまで克明に捉えられるかによって、聴き手が感じる薄気味悪さの印象は大きく変わってくる。ここでグラハムは、マンハッタンセンターの空調ノイズや、演奏ノイズを克明にとらえることで、楽員達が息をひそめて自らの出番を待つ気配すら伝えてくれる。もう一か所挙げると「夜明け」の冒頭だ。ここでは舞台裏の3本のトランペットとステージ上の1本のトランペットとが、薄明りの森の中を飛び交う怪鳥の奇声を表わしている。スコアでは、このトランペットの動機は、舞台裏の3番奏者→2番奏者→1番奏者→ステージ上のソロ奏者→舞台裏の1番奏者→2番奏者→3番奏者と、順番が指定され、強弱記号も舞台裏はフォルテ、ステージ上はメゾフォルテと書かれている。つまり作曲者はここで4台のトランペットそれぞれに等価のパワーを持たせた上で、ファンタジー映画のようなスペクタキュラーな遠近感とサラウンド効果を狙っているわけだが、作曲者の意図を最も効果的に表現しているのが本録音なのである。最後にSACDへのリマスターだが、過度なノイズカットはもちろん、最近流行りの音のリフレッシュ化を目的とした不自然なイコライジングも行われておらず、良心的な仕事ぶりが評価できる。
0
|
|
|
誰もが気になるXRCDとの比較であるが、こちらはブルックナー4&5番以上に音は異なるがどちらも優れたリマスターだ。XRCDにおける故杉本氏の音づくりは、基本的にオリジナルLPのバランスを目指したもので、過去にRCAリヴィングステレオがXRCD(杉本氏)とSACD(サウンドミラー社)で相次いでリマスターされたときも、世間の評価は前者が「オリジナルLPと遜色ない鮮烈な音」と評されたの対して後者は「最新録音のようにリフレッシュされた現代的な音」であったことからも伺い知ることができる。そして誤解を恐れずに言えばBASF音源のブラームス全集XRCDも、RCAリヴィングステレオ的な音づくりだ。つまり、ステレオの中抜けを嫌い左右の広がりを抑えた音場(当時のRCAの3マイクセッティングのポリシー)、マイクの特性上の高音域のピークをイコライジングで矯めないマスタリング(当時のRCA録音のポリシー)、そして中低音の分厚いパワー感(ウェストレックス社のカッティングマシン固有の癖)だ。これに対してAltusの齋藤氏は、現代の最新録音のようなフラットな周波数特性とナチュラルな音色の再現を目指しており、左右の音場も録音会場の広さが実感できるよう大きく広げている。一方で両者に共通して言えることは、過剰なノイズリダクションを行っていないので、録音時の雰囲気・臨場感が削がれず、過剰なイコライジンングを行っていないので、元のレーベル固有のサウンドカラーが保たれていることである。我々ユーザーは、優劣や好き嫌いを議論するのではなく、その日の体調や気分に応じて聴きたい方を選択すれば良い。
1
|
|
|
誰もが気になるXRCDとの比較であるが、ドロップアウトの箇所が異なるのでXRCDはBASFから日本に送られたコピーマスター、タワー盤は独Profil社が保有するか、或いは探しあてたコピ-マスターを使用しているものと思われる。マスターテープの違いに加えて再生機材も異なるだろうし、CDとSACDという器自体が違うし、さらには故杉本氏と斎藤氏とのリマスタリングに当たってのマスターテープ音質に対する解釈の違いもあって、音質の傾向はかなり異なるが、どちらも過剰なノイズ除去は行っておらず、ディテールの情報量も豊かなので、単純に両者の優劣はつけられない。全体的な傾向としては、XRCDがパワーとメリハリ重視の凝縮した音づくりなのに対して、Altusは高域の硬調感を和らげ、グラディエーションと空間の再現性を重視していると言える。後者の超高域倍音付加は、既にヨーロッパで歴史的録音に対して実験的に行われている技術であるが、ここでは高弦や金管楽器の強奏時の耳障りな硬直感が軽減され、XRCDよりも生っぽく聞こえる。いずれにせよ両者ともに高品質リマスターディスク再生の奥深さを堪能できる優れたディスクだ。
0
|
|
|
肝心な音質については広島の放蕩息子さんに全面的に同意するものである。1番の冒頭で聴こえる演奏ノイズ一つ取ってもE社はただ聴こえるだけなのに対し、タワーでは演奏者の存在を感じとれるし、弦楽器の弓の擦過音の生々しさはE社では決して聞くことができない。恐らくE社はタワーより1世代下流のマスターテープを掴まされていると思われる。本盤は何種類もディスクを持っており、今回も正直購入を躊躇したが文句無しのマストバイだ
1
|
|
|
PENTATONEのSACDが肝心のエロイカだけが未だに発売されない状態で、こちらを買わせようする業界ぐるみの陰謀が感じられる上、特にDG録音は過剰なポストプロダクションのせいでSACD化による音質向上の恩恵が少ないことも購入を躊躇させる大きな原因だ。
0
|
|
|
単曲でハイレゾ配信されるなら77CDボックスを買うのだが、ポゴレリチの新盤がハイレゾ配信されていないので過度な期待は禁物だ。ハイレゾが出ないことを見届けたうえでSACDに手を出した場合、限定生産で完売という最悪のシナリオも考えられる。新リマスターの音質を見届けてから判断した方がよさそうだ。皆さんレビューをお待ちしてます。
0
|
|
|
RCA盤ではあるが、デッカのK・ウィルキンソンによる本拠地キングスウェイホールでの録音であり、モトは優秀録音であるはずだが、RCAによりSQ4チャンネル用にミキシングされたテープがマスターとして用いられていると思われ、今回のSACDでも目立った音質改善は叶わなかった。明瞭なピアノに対して不自然な残響が付加されたオーケストラパートがいかにも異質で、バレンボイム指揮のバックの出来が良いだけに残念だ。
0
|
|
|
92年EMIリマスターの外盤CDと比較するとテープヒスは過剰に取り除かれ、ピーキーな高域は丸められ、左右のセパレーションも「自然に聴こえるよう」恣意的に操作され、現代風のサウンドに仕立てられている。本国から送られてきた96-24データを国内でいじっているようだが、なぜこのような余計なことをするのか?ぜひSACD層には何もいじらない音を、CD層に好きなようにリマスターした音を入れて頂くよう強く望む。
0
|
|
|
77年のN響定期以来の名演。17年後もテンポや解釈の変化は無いがオケが優秀な分ギーレンの意図が明確に分かる。SWRとのセッションの方が指揮者の指示がより正確に反映されているとは思うが、客演ならではのオケの自由さ・緩さと、ライブならではでの緊張感とが程よく融合して、大曲を一気に聴かせてしまう。録音もDG系のトーンマイスターによる作為的な箱庭音場とは異なりナチュラルで好ましい。夜の歌ファン必聴の1枚。
0
|
|
|
デッカレジェンズのCDとの差はほとんど無い。レジェンズもヒスノイズの除去をはじめとし、かなり化粧が施されていたので、同じ96-24データを用いている可能性もある。ソフトと機材の進化からか、より耳当たりの良い音になってはいるが、肝心な情報量はレジェンズと比べて全く増えていない。オリジナルのマスターテープには盛大なヒスノイズとともに、大量の演奏ノイズやホールの暗騒音が含まれているはずだが・・・
1
|
|
|
今度のSACDはテープヒスの除去はもちろんのこと、薄気味悪いほどリアルに収録されていた演奏ノイズも取り除かれ、ピーキーな高域成分は丸くイコライジングされた所謂現代風のサウンドへと厚く化粧が施されている。キングレコード時代の国内盤CD盤のいじくられていない音に馴染んだ耳には別の曲に聴こえる。ユニバーサルのSACDでも化粧は気になったがここまでひどくはなかった。今後はこのようなことはやめて頂きたい。
0
|
|
|
オリジナルマスターに遡っての初のDSDリマスターは、バックハウスの無骨なタッチにレスポンス良く反応するベーゼンドルファーの古風な音色をこれまで以上に際立たせると共に、録音エンジニア毎のサウンドクオリティーの差を露呈させる結果となった。中でもウォーレスとウィルキンソンは別格であり、リスニングルームが瞬時にビクトリアホールの空間へと置き換わり、スピーカーの中央にはバックハウスの姿がはっきりと見える。
1
|
|
|
マンフレッドが飛び切りの優秀録音だ。アルプスの城郭を舞台とした劇詩にふさわしい洞窟状のサウンドステージをアビーロードスタジオ録音で成しえたパーカーの鮮やかな手腕には驚きを禁じ得ない。一方キングスウェイホールで収録された1812年は、まるでデッカのフェイズ4録音のように不自然な失敗作だ。SQ4チャンネルを意識し過ぎた恣意的なミキシングの結果だと思われるが弘法も筆の誤りだ。演奏はどれも素晴らしい。
0
|
|
|
シュトリーベンによるアナログ末期の録音は、過剰なマルチマイクと恣意的なミキシングによりサウンドステージは箱庭的で、いたる所で一部の楽器が異様にクローズアップされたり、曲によって楽器のバランスが異なる等かなり不自然だ。LP時代は気にならなかったので、それだけディテールの解像度が高まったということだろう。ただし本SACDは2015年の国内版CDより残響の消え方が自然で違和感はより少ない。
0
|
|
|
硬派のショスタコファンからは生ぬるいと酷評されがちな本シリーズだが、ショーン・マーフィによる録音は相変わらず素晴らしく、録音を含めたパッケージ全体としての魅力には抗しがたいものがある。しかもCDで腰を抜かした方には、次はハイレゾで現実と非現実との境界へワープするという異次元の楽しみが待ち構えている。本盤も必聴だ。なおロンドンでの録音は誤記であり、従来同様ボストンシンフォニーでのライブ収録である。
0
|
|
|
2012年のSACDシングルレイヤーを買い損ねた人にとっては朗報だが、既に所有している人々のためにも、是非協奏曲編を分売して頂きたいものである。
0
|
|
|
タワーレコードのこのシリーズはとにかく解説書の内容が充実しており素晴らしい。今回もリマスタリングエンジニアのレポート付きで、当事者しか知りえない貴重な情報が満載だ。ヒスノイズには手をつけないオリジナルマスターに忠実な仕事ぶりも大賛成である。
0
|
|
|
ショーン・マーフィによる恐るべき優秀録音だ。1905年冒頭の鳥肌が立つような低弦のppを耳にしただけでこの録音のポテンシャルがわかるが、一斉射撃の場面におけるバスドラムの獰猛さとスネアドラムの無常さは聴く者全てを一瞬にして100年前のサンクトペテルブルグにワープさせる。しかもこのCDサウンドにノックアウトされたリスナーには、本物のタイムマシンを体感できるハイレゾの切符も用意されている。
0
|
|
|
このところセル&クリーヴランドの新しいリマスターが相次いでSACDで発売されているが、購入する度に彼らの「本当の凄み」を痛感させられる。このキージェ中尉も、ライナー&シカゴの名盤以上に音程、リズム、アーティキュレーション全てが正確で、どんなに音量が増しても響きは拡散せず却って凝縮していく。これらを余すところ無く捉えた録音も優秀で、当時のエピック録音がこれほどのポテンシャルを有していたとは驚きだ。
0
|
|
|
協奏曲はヘルマンスが録音したDG伝統のマルチマイクによる平面的なサウンドだが、ヴィルトハーゲンが録ったパガニーニアーナの方は録音会場の空気感を良く伝える優秀録音であり、その結果メインの協奏曲より小品集の方がミルシテインの演奏の凄みを伝えてくれる。ただし同じくヴィルトハーゲンが録ったポリーニのショパン練習曲と同様にサウンドの傾向は硬質なので、再生では若干バスを持ち上げハイを下げることをお薦めする。
0
|
|
|
ウィルキンソンがキングスウェイホールで収録した伝説的な優秀録音のひとつである。手持ちCD(クラシックサウンドシリーズ外盤)と比べ再生情報量の増加は明らかであり、冒頭の管楽器の点滅やハープを聴くだけでプレゼンス、レゾリューション共に大きく改善していることが分かる。リハーサルの対訳がついているのも嬉しくタワーレコードはパッケージメディアに求められる消費者ニーズを良く把握していると思う。マストバイだ!
0
|
|
|
経年を考慮すると確かに鮮烈なサウンドだが音場はスカスカの印象だ。この当時、最終的な音決めはLPカッティングで行われておりマスターテープは単なる素材であった。しかもステレオ録音は実験段階であり、クラシックサウンズ社のエンジニアが何を目標サウンドにマスタリングしたのか知りたいところだ。「本国のリマスター音源使用」の場合の常で、このあたりの解説がいつも無いが、今後の企画では是非検討をお願いしたい。
0
|
|
|
このアルバムの白眉は何と言ってもウィルキンソンが録音した7番だ。5番、6番を受け持ったG・パリーは初めてのシカゴ録音で相当手こずった痕跡があり、録り慣れたゾフィエンザール録音と比較するとサウンドステージやディテールの再現性に違和感を残す。一方、御大ウィルキンソンによる7番ではエンジニアとしての技量の差、格の差を実感させられる。その理由は冒頭のバスドラムの振動を聴けば十分だろう。
0
|
|
|
既にハイレゾ配信されている千人では音質差は無かったが、大地の歌は嬉しいプレゼントだ。デッカのシカゴ録音としてはメディナテンプルへ録音会場を戻す前、クラナートセンターでの最終セッションの一つだが、巨大なサウンドステージの表出とマッシブでパワフルなオーケストラの再現性には思わず息を呑む。ウィルキンソンによるショルティ&シカゴ録音では、幻想交響曲やベートーベン全集もSACD化やハイレゾ配信を期待したい。
1
|
|
|
この当時のDG録音は過剰なマルチマイクと過剰なポストプロダクションの影響で、当時のLPと最新リマスターとの音質差が少ないのが常である。本SACDにおいても劇的な音質改善こそ見られないが、高域の硬直感とレゾナンスの開放感は向上している。クーベリックの第9は、スコアを深く読み込んだ結果としての独自のテンポ設定やディテール表現が随所に聴かれる隠れた名演だが、楽天的なオフマンのテノールが玉に瑕だ。
0
|
|
|
本家がワルキューレとウィーンの休日を高価なSACD-SHMで出したっきり鳴りを潜めていたところへ思いもかけないタワーからのプレゼントである。しかもサウンドは同品質で1,200円も安く・・・。従来CDの欠点だったダンゴ状の響きが開放されたことで、悪名高い改訂版ですらその必然性を感じさせてくれる。この勢いで、残りのワーグナー、くるみ割り、大学祝典序曲等のSACD化を是非お願いしたい。
1
|
|
|
パーカー&ビショップによるアナログ末期の優秀録音である。2番はテスタメントのリマスターは満足できる出来栄えだったが、9番のCDはどれも響きが開放されないもどかしさに悩まされ続けており、今回のSACDで長年蓄積していたフラストレーションがようやく解消された。特に9番はリファレンスレコーディングスのスクロバチェフスキー盤を例外として優秀録音に恵まれない曲だったので、ブルックナー録音史上も貴重だ。
1
|
|
|
冒頭から聞こえるヒスノイズを聞いただけでオリジナルマスターテープに最大限の敬意を払った忠実なリマスターであることが分かるし、聞き終えた後は、より良い音質を求めて同じ演奏をもう買い換える必要が無いことへの安心感にも満たされる。微視的なディテール再現の向上も目覚しく、8番第2楽章でセルがこの遅いテンポをとった理由も初めて解明された思いだ。この素晴らしい仕事に対しタワーレコードには心より感謝したい。
0
|
|
|
アナログ末期にジェイムズ・ロックがゾフィエンザールで収録した優秀録音の待ちに待ったハイビットリマスターは期待通りの素晴らしさだ。深々とした低弦、張りのあるティンパニ、コクのあるウィンナホルン、メロウな木管、シルキーな高弦と、ウィーンフィルの魅力が全開だ。唯一残念なのはSACDで発売してくれなかったこと。
0
|
|
|
ブックレットの最後に掲載されているアンドレアス・マイヤーによるマスタリングレポートの内容が素晴らしい。過去の名録音の最新リマスターに求められるのはかかる情報開示と、マスタリング方針と合致した結果(サウンド)だ。RCA交響楽団に関する詳細なレポートにも眼からウロコだ。肝心なサウンドもこれまでのどの再発ディスクをも凌ぎ、パッケージ共々コストパフォーマンスは最高だ。
0
|
|
|
冒頭から盛大に聴こえるヒスノイズを聴いただけでこのリマスターの素性の良さが分かるが、その後のDレンジの大きさや、強奏時の混濁の無さ、さらには個々楽器の定位の明確さと3D的な立体感には思わず息を呑む。K・ウィルキンソンのステレオ黎明期の名録音を素晴らしいリマスターでSACD化してくれたタワーレコードには心から感謝したい。
1
|
|
|
アナログ録音全盛期にC・パーカーと並ぶEMIの名エンジニアS・エルザムが、ホールの空間ごと切り取ってきたかのようなフルボディサウンドを届けてくれる超優秀録音の待ちに待ったSACD化である。特にアビーロードスタジオとキングスウェイホールで収録されたナンバーのスペキュタクラーな響きが素晴らしい。壮年期のベルグルンドの指揮もパワフルかつ濃厚でシベリウスサウンドをとことん堪能させてくれる。
0
|
|
|
本ディスクの評価の分かれ目はE社のSACDとの音質差に尽きると思われる。本SACDは、最初こそオケは薄く左右への広がりも少なく、ピアノは後ろに引っ込み、おとなしいサウンドに聴こえるが、これを聴いた後にE社のSACDを聴くとその厚化粧に驚かされることになる。かかる良心的な商品企画を次々と繰り出すタワーレコードには心より感謝すると共に、同様の企画を強く応援するものである。
1
|
商品詳細へ戻る