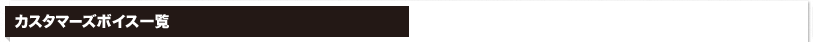
商品詳細へ戻る
T.KANAIさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
実にバラエティ豊かな16枚組。何しろ《ワルキューレ》第3幕を中心としたワーグナー二重唱曲集(CD10、11)からトワイライト・コンサートという小品集まで。ブラームスやチャイコフスキーの交響曲も。ラフマニノフの交響曲で短縮版使用や小品集に大曲の一部を断片的に収録するなど、LP初期という時代も感じさせるが、演奏そのものは至ってまっとう。特に印象に残ったのは、プロコフィエフ《交響曲第5番》、シベリウス《交響曲第4番》、コープランド《リンカーン・ポートレイト》(CD8所収。「ゲチスバーグの演説」がナレーションで入る)、《ウィリアム・テル》序曲(CD12所収。こんな劇画的で格好いいロッシーニは初めて)等である。
|
|
|
全45枚について詳述出来る筈もないし、ストラヴィンスキーやフランスものなどCD化されてから一定の評価を得ているものもあるので、ここではLP時以降、全く記憶から欠落していたベートーヴェンの交響曲(何故か1番、8番が入っていない)について述べる。全体が若々しく金管の強奏も目立つが、音が暖かい。絶叫型のベートーヴェンとは対極にある。《田園》《4番》などが特に素晴らしいが、《エロイカ》がこんないい演奏とは思わなかった。スクリベンダムの常として、実に優れた音質。
|
|
|
73年録音のEMI盤の前年のライヴ。音質が良いのに驚く。マルティノンは66歳という、まさに円熟期に他界したため、こうした音源のCD化は大歓迎だ。スタジオ録音には見られない即興性・熱気が感じられるのはライヴならでは。EMI盤ではコルネット入りの版を使っていたが、ここでは通常のヴァージョンに依っている。《ローマの謝肉祭》も理想的と形容したい演奏。
|
|
|
フェドセーエフはムラヴィンスキー同様、自分でもこの曲を何百回指揮したか憶えてはいないだろう。しかしこの演奏にはルーティンワークのかけらもなく、新鮮でかつこの曲はこう演奏するものだ、という確信が溢れている。どこをどう評価出来る、という性格のものではない。小細工だらけで中身スカスカのクルレンティスとは格が違う。金子先生何かコメントは?
|
|
|
私は彼女たちが暑い日も寒い日も、フェスティバルホールやザ・シンフォニーホールの前で自分たちのコンサートのチラシを配っていたのを憶えているし、実際に演奏を聴いて各人の技量の高さ、アンサンブルとしての纏まりの良さに驚いたのも記憶に新しい。このCDではアンサンブルの精度に一層磨きがかかり、もはや言うことはない。これからはバンドネオンの三浦一馬氏等と同様にピアソラの魅力を国内外に広めていってくれることであろう。
|
|
|
《第1番》の冒頭や《第2番》の第3,4楽章などその部分だけを取り出せばかなりテンポが速いが、全曲を聴いた後ではそういう感覚はなく、充実した音楽に浸った満足感を味わえる。この指揮者のテンポ・ルバートは天才的と言えよう。《第4番》が変にセンチメンタルに流れないのもいいし、《ハイドン・ヴァリエーション》も名演と思う。音質面での限界はあるが、ブラームスファン必携のアルバム。
|
|
|
3曲共後年のこのコンビからは想像のつかないプログラム。ボロディンの《第2番》は、私が聴いた同曲録音中最も堂々とした演奏。これならコンサートプログラムの後半にメインとして置けるだろう。フランクは元々独墺系のオケのレパートリーとも言える(ジュリーニがウィーン・フィルとベルリン・フィルで2回正規録音を残している)。やはり風格豊かな音楽。《中央アジア》はもう少し軽い感じの演奏が主流だろうが、こういうスタイルも悪くない。
|
|
|
マルティノン×N響が2枚、フルネ×N響が1枚、同時発売された。➀著作権の期限をクリア、②テープの修復技術の進歩、があろう。プロコフィエフの《第5番》は今では日本でもポピュラーになっているが、当時はまだ珍しい部類だった筈。見事に決まっている。ルーセルの《第3番》は今でもあまり演奏されない(私は実演で聴いた記憶がない)が、さすがに作曲者直伝のマルティノンの棒は確信に満ちている。両曲共聴いていて、フランス語の「エスプリ」という言葉が頭に浮かんだ。
|
|
|
後年のフルネは専ら都響を振っていたが、彼が日本を頻繁に訪れるきっかけになったのは、N響の招聘によるものだった。ディスク冒頭のドビュッシー、ラヴェルはまさに手中の作品。《牧神》のフルート奏者の名は記すべきだったかもしれない。フォーレの《レクイエム》は私の所属する合唱団も取り上げたことがあるが、団員数は多い目の方が向いているように思う。ここでも音から判断して、小編成ではなさそうだ。清澄ないい演奏。バリトンがモルナールとは驚き。無難にこなしている。ソプラノは十全。
|
|
|
「カラヤンにはふりまわされただけという楽員が、ストラヴィンスキーの3部作に20回も費やした思い出を今も熱っぽく語っている。楽員の強い要望でマルティノンは、10年後再びN響の指揮台に立った」(元N響プロデューサー・中野吉郎氏『レコ芸』別冊1981)その時の音源が残っていたとは!1963年という年代を考えれば、N響がこれ程こなれたストラヴィンスキーを演奏したのは驚異だし、それを可能にしたマルティノンも凄いと思う。解説文によると、この時も無茶苦茶な練習量を取ったらしい。練習は原則3日、という現在では不可能かもしれない。日本オーケストラ史上の貴重なドキュメントである。
|
|
|
これも2021年に初めて店頭で目にした。シューベルトの《交響曲第5番》第1楽章の指定はアレグロで、2分の2拍子。実際にはワルターのように遅めのテンポを採る指揮者も多い。その方がこの曲のインティメイトな雰囲気が醸し出される、ということか。カラヤンのような速めのテンポ(それが正解なのだが)では素っ気ない感じもしよう。山田はやや速めのテンポで、それでピタッと決まっている。テンポ設定に限らず、この指揮者の設計の巧みさには舌を巻く。だから実演でも録音でも当たり外れがない。アザラシヴィリの《無言歌》(元はピアノ曲)は懐かしさを感じさせる音楽。
|
|
|
《第1番》でのレヴィットのピアノは高級なクリスタルガラスを見る感。一音一音の輪郭が明確で、音が澄んでいる。ワン・シャオハンの弾く《第2番》はレヴィットのような鋭利さと対照的に、暖かい音色が楽しめる。オケの響きはもっと厚みのある方が個人的には好みだが、これも悪くはない。
|
|
|
2014年の生産のようだが、私は2021.3月にタワーレコード本店で初めて見た。市販されていなかったのかもしれない。それはともかく、奇を衒ったところのない、気力充実した素晴らしいベートーヴェン。この作品にはこれくらいの生命力が欲しい。リピートの省略も好ましい。《第5》1曲のみ。その代わり低価格。いい意味で初心者向けとも言える。最後の拍手は少し長く入れすぎかも。
|
|
|
《ドン・ジョヴァンニ》の作曲者は?モーツァルト?《ラ・ボエーム》の作曲者は?プッチーニ?前者にはガッツァニーガ、後者にはレオンカヴァッロも曲を付けている。この10枚からなるアルバムにはそれらも含め、不運にも今日殆ど上演されなくなった6曲のオペラを収録。すべてを聴いての感想は、駄作は一つもない、ということだ。制作者もそれをよく知っており、キャスティングを見ても、ビゼー《ジャミレ》の表題役はルチア・ポップ、マスネ《テレーズ》のそれはアグネス・バルツァ、他にも名歌手が綺羅星の如く。指揮者も読響の常任を務めていたアルブレヒト、カンブルラン、しばしばN響を振っていたワルベルクなど一流揃い。上演を伴わなくても、音楽だけでも十分楽しめる、オペラファン必携のアルバム。デモーニッシュでない《ドン・ジョヴァンニ》もいいものだ。価格も良心的。
|
|
|
マゼールのベートーヴェンは、かつてクリーヴランド管を振ったものがあんまりあんまり…だったので、一抹の不安もあった。ところがオケが「待った」をかけた?せいか、個性的な部分もあるにせよ、ここではオーソドックスで気迫漲る音楽が鳴っている。録音もライヴとしてはまず文句ないところで、価格も考えると大変なお買い得。《第9》の独唱・合唱も優秀と思う(私は合唱団の一員として、この曲何十回も歌っている)。
|
|
|
これが1928,9年の録音とは!エンジニアの方は人間国宝に指定してもいいくらい。《スコットランド》は私の大好きな曲だが、ペーター・マークの4種の録音以外は満足感を得られなかった。ワインガルトナーは溢れんばかりの共感を持って曲を再現、聴いていて涙が出そうになった。ウェーバー《舞踏への勧誘》(原曲はピアノ曲)のワインガルトナー編曲版は初耳。従来のベルリオーズ編曲版ではチェロと管楽器の掛け合いで始まる出だしのところは、弦楽器のユニゾンで演奏。全体的に派手やか。他の2曲は立派かつ模範的と言っていい演奏。
|
|
|
聴く前から名演揃いであることが予想出来る4枚組。注目すべきは、珍しくもクリュイタンスが振った1枚。はじめの2曲はウィーン・フィルのレパートリー。《ハフナー》は生気溢れる。次の《ドン・ファン》もそうだが、ここでは音のバランスに独特のところも。《マ・メール・ロワ》《ダフニスとクロエ》はクリュイタンス自家薬籠中の曲。ウィーン・フィルがこうした響きを出すのは驚異と言えるが、指揮者の果たす役割がいかに大きいかの証左となろう。他もいい演奏ばかりだが、録音に少し…という面もある。
|
|
|
ロイ・ハリスは1945生のニュージーランドの作曲家で、両曲ともヴィンセント・オサリバン(ハリスより8歳年長)の詩をテキストとしている。強烈なメッセージ性に満ちてはいるが、聴後感は悪くない。外盤にしては珍しく、詩が全文掲載されている。《最後の手紙》は尋常ならざる死を遂げた母親がテーマ。詳細は原詩を読まれたい。《フェイス》は第一次大戦で顔を負傷した兵士のトラウマを描く。「顎の輪郭が消し飛んでも、(それが誰かは)正確に特定出来る」といった記述が続出。ところでNaxosは日本では馴染みのない作曲家の作品を次々とリリースしており、その作品・演奏評については結局リスナー次第だが、「理解出来る」作品を出しているのは事実。何年か前「現代曲部門」でアカデミー賞を取ったCDを3千円あまりで買ったはいいものの、5分でギブアップ。まるで拷問。このレーベルは安価だから、仮に「ハズレ」であっても、特段気にならない。
|
|
|
ハープの吉野直子さんに続いてオルガニストの大木さんが自主レーベルを立ち上げた。吉野さんと同様、これから第2弾、第3弾が出てくるだろう。従来、特にピアノやヴァイオリンは単に「弾けます」というレベルの人がルックスだけを売りにCDを出すケースもあった。当然売れる筈もなく…国際的に評価されるこの2人については、そんな心配はゼロ。このCDはメルヘンチックなパッヘルベル作品に始まり、ポジティフ・オルガンならではの親しみやすい佳曲が並ぶ。伊左治直(1968-)、ダンクザックミュラー(1969-)は初耳。名前を伏せたら、現代の中堅作曲家の作とはわからないだろう。もちろんアルバム全体の中にピタリと収まっている。
|
|
|
いずれも21世紀に入ってからの作。《交響曲第5番》は単一楽章形式、ただし急ー緩ー急という流れにはなっている。出だしはティンパニが大活躍。金管も含め、何かサスペンス映画を観る感。最後は派手に格好良く終わる。《サプリカ》は静かな曲想。《管弦楽のための協奏曲》はバルトークの名作を思わせる部分も。日本のオケにも挑戦して欲しい。3曲ともアメリカン・リアリズムと称したい音楽で、私個人は気に入っている。
|
|
|
私は名古屋フィルハーモニーの演奏を聴きに、しばしば名古屋に行ってはいるものの、この室内オケの存在は知らなかった。録音のメンバーは13人。これ以上になると音が厚くなり過ぎ、少ないと逆に痩せてしまうことを納得させる。それにしても何という精緻なアンサンブルであろうか。モーツァルトの魅力が巧まずして立ち現れる。解説の一部を担当している山本直人氏は元名古屋フィルの首席オーボエ奏者で、大変な名手であることは、実演を聴いて知っている。下手な評論家よりこういう方の推薦文の方が説得力がある。
|
|
|
この3曲、初演に立ち会った聴衆は度肝を抜かれたろう。《告別》の第1楽章ではピアニシモで終わるアダージョの序奏部からアレグロの主部への移行が唐突だし、《ハンマークラヴィーア》では斬新で奇抜なアイディアが続出する。緩徐楽章だけで180小節を超えるピアノソナタなんて人々には初耳だった筈―何でわかりきったようなことを書くか。河村さんの演奏を聴くと、いつも初めて作品に接するような感動に襲われる。既成概念にとらわれず、虚心に楽譜を読み込んでいるからであろう。得がたいピアニストである。
|
|
|
2020年はフローラン・シュミットの生誕150年でもあったのだが、ベートーヴェンの陰に隠れてしまい、めぼしいCDがこれ1枚というのは残念だった。シュミットはフランスでは大作曲家と見做されており、私もマルティノン等の演奏で親しんできた。《サロメの悲劇》は交響詩としては珍しい2部構成。印象主義的な作風だが第2部では劇性も際立ち、女声合唱によるヴォカリーズも効果的。他の3曲も大変聴き応えがある。ファレッタの棒捌きはいつものことながら、実に鮮やか。
|
|
|
カムラン・インスは1960年生まれのトルコ出身の中堅作曲家。この交響曲第5番《ガラタサライ》は同名の、トルコの誇るサッカーチームの創立100周年を祝って作曲された…と言うけれど、私の耳には宗教音楽のように聴こえた。会場で流したら観客がどんな顔をするか。それはともかく、他の曲も含め作品としては良く出来ている、と個人的には思う。イスラーム圏出身の作曲家だな、と感じさせる旋律も多く、興味尽きないアルバムである。
|
|
|
レオー・ヴァイネルはバルトークやコダーイと同世代のハンガリーの作曲家であるが、教員活動が主体であったために作品数も少なく、等閑視されてきたようだ。ハンガリーの民俗音楽を蒐集し、作品に活かす―ということではバルトークがよく知られているが、このCDはヴァイネルが民俗音楽を用いた作品がメインに構成されている。バルトークより率直・素直な印象を受ける。チャーミングな旋律、優美な旋律が散見されるのは、上記2人にはない特徴であろう(ちなみに指揮のチャーニは女性)。ヴァイネルの作品は他にもディスクがあるようなので、もっと聴いてみたい。
|
|
|
ブラガ・サントス(1924-1988)はパッケージに「ポルトガル最大の管弦楽作曲家」とあるので、同国では著名らしい。ごく近年の人なのでもっと前衛的な作風かと思ったら、そうではない。CD中最も現代音楽的なのはピアノ協奏曲で、アクロバティックな妙技は聴きもの。実演でも聴きたい。他はもう少し穏健な曲が並ぶ。こういう「現代音楽」なら歓迎したい。
|
|
|
アルフレート・ブリュノー(1857-1934)はフランスの作曲家で、オペラ畑の人だったらしい。〈フランス風〉でも〈印象派風〉でもない、独自の作風を貫いたようで、パッケージのタイトルとつき合わせてみると、表題音楽的な感じが強く、親しみやすい。最後の、歌劇《メスィドール》第3幕第1場ー黄金伝説、は力作というに相応しい、聴き応えのある音楽である。
|
|
|
《ブル8》は、カラヤンの主要レパートリーの中では、比較的遅めのテンポを採る(ヨッフムやメータはCD1枚に収まるテンポ設定)。この大曲を一瞬の緩みもなく最後まで聴き手を惹き付ける手腕には感嘆するのみ。これはスタジオ録音ではないが、この後のカラヤンのブルックナーには指揮者が全面に出過ぎて、豪壮過ぎるという批判もあったし、また晩年には弛緩するところも出てくる。演奏家と録音のタイミング、という問題を考えさせられる1枚でもある。音質はこの時期としては標準的か。
|
|
|
音質はまずまず。カイルベルトのベートーヴェンはテレフンケン×タワーで出ていた(オケはバンベルク響他)が、第9のみ未収録だったので、このCDの登場は嬉しい。何の変哲もない表現ながら、聴き手に迫ってくるエネルギーは凄まじい。モーツァルトは3曲を収録。いずれも丁寧、誠実な演奏で飽きが来ない。全4枚を通して、この名指揮者の多面性、奥深さを実感出来る。なおオビにある演奏紹介文、的外れと思う。
|
|
|
フェラスはカラヤンが好んで用いたヴァイオリニストで、やや線は細いものの、音の美しいことでは争えない。フォルムの整った立派な演奏である。個人的には、このコンビによるチャイコフスキーとブラームスは今なお同曲のベストである。併録のバッハはこの時が初出だったと思う。モダンオケによる、折り目正しい演奏。
|
|
|
アバドの旧盤。彼はその後デル・マー(デル・マール)による校訂版をベルリン・フィルと再録音し、アバドらしいのはそちらかもしれないが、抵抗感があるのも事実。一般にお薦めできるのは断然こちらである。《第5》の冒頭主題など変にゴツゴツしていないし、《田園》の出だしなど、ベートーヴェンの作品のノーブルな側面を聴く思いがする。もちろん《第9》その他、随所で迫力ある音楽を堪能出来る。律儀なアバドらしく、基本的にリピートは実行。主要な序曲すべてと、案外録音の少ない《合唱幻想曲》なども素晴らしい演奏で収録し、7枚組で何とこの価格!
|
|
|
「舞曲」をテーマにしたCD。よく知られた音楽をチェロ用に編曲する場合、➀たまたま自分がチェリストだから、という比較的軽い気持ちでトライするのと、②原曲とは異なる魅力を醸成しようという意志を持って演奏するのとでは、雲泥の差がある。新倉さんはもちろん後者。この拙文を書いている時点で4,5回は聴いており、そのたびに新しい発見がある。
|
|
|
定評ある名演の素晴らしい音質による復刻。最近のフルトヴェングラーの復刻盤を聴くと、この巨匠が案外モダンな感じの演奏をしていることに気づく。これもそうで、《ブラ1》は基本的にインテンポでリピートはすべて省略、第4楽章の例の有名な主題は、カラヤンより速い位(ベームもここは速めのテンポを取っていた)。ただしコーダの壮絶な追い込みは、やはりフルトヴェングラーの面目躍如。
|
|
|
岡城さんのデビューアルバム。彼女はその後ややマニアックとも取れる路線にシフトし、アメリカを拠点にしたせいかしばらく新譜も途切れ、今は坂本龍一氏の作品の紹介に寄与している(坂本氏の子息のピアノ教師をした関係らしい)。しかし今年再発されたこのCDを聴くと、何と若々しく、感受性豊かな音楽が溢れ出ていることだろう。シューマンの《アラベスク》など絶品である。一音楽ファンとしては、こういう正統的なピアノ曲もこれから取り上げて貰えたら…と思う。
|
|
|
《グノシエンヌ》や《ジムノペディ》だけがサティの代表作ではありませんよ、魅力的な作品は他にも山ほどありますよ、と言っているような内容のCD。演奏者は日本におけるサティ受容の立役者。《子供の音楽集》ではピアニスト自身の朗読が入る。日本語。特にストーリーはないし、音楽もウィットに富み、子供が喜びそうな作品である。
|
|
|
一番感銘深かったのは《未完成》。指揮者の芸風と曲の本質がピタリ一致している。ベートーヴェンは、「作品をして語らせしむ」といった感。ただし最終楽章は大変迫力がある。シューベルトの3番はウィーン・フィルのような典雅な音色ではないが、もちろん立派な演奏である。ノイマンのファンには殊に喜ばれようが、エキセントリックな演奏に辟易した私には一服の清涼剤だった。
|
|
|
私たちの世代にとって、ミュンヒンガーは大指揮者。昔某雑誌で「未完成」のベストレコードとして、彼がウィーン・フィルを振ったものが紹介されていた。如何なる理由か、デッカはケルテス/ウィーン・フィルでシューベルト交響曲全集を録音することになったため、中途半端な形で終了したのは残念である。《ロザムンデ》序曲1曲を聴いただけでも、ミュンヒンガーの凄さがわかるだろう。堂々とした序奏部から軽やかでチャーミングな主部への鮮やかな推移!もちろん交響曲も全て名演揃いである。
|
|
|
足かけ7年に亘る、このコンビのプロコフィエフ交響曲全集完結編。構成が特殊で摑み所がない《第2番》、長いだけであまり聴き易くもない《第3番》を、リットンはメカニックとも言えるアプローチで巧みに切り抜けている。最新録音ということも加味すれば、現時点での最も優れた全集と言えるだろう。
|
|
|
初めにギターのPR。➀6~7万程度のもので、一応まともな音が出る。②フレットを押さえれば一応狂った音は出ない。③音量が小さいから、あまり防音に神経質にならなくても良い。ただしその後は…ギターの場合、リサイタルにせよCDにせよ、プログラム・ビルディングに一工夫いる。どうしても単調に流れる恐れがあるからだ。その点、これは最初のバッハ《無伴奏チェロ組曲》の編曲版から、最後のグラナドス《アンダルシア》まで一気に聴かせる。演奏者は指導者にも恵まれ、コンクール歴も凄い逸材。実演を聴いてみたい。
|
|
|
このコンビによる交響曲全集の完結編で、前3曲と同様に、実に立派な演奏。作曲者が自身の持つ技法の全てを注ぎ込んだ傑作ということを、これほど見事に明示した演奏も稀ではないか。確かにブラームスはとっくの昔に消えた筈のパッサカリアなど用いているが、それあくまで手段であって、別に「晩年の諦観」とやらを表すためではない(この後作曲した《ヴァイオリンとチェロのための協奏曲》がもともとは第5シンフォニーとして構想されていたことは、周知の通り)。《悲劇的序曲》は私の大好きな曲で、専らバルビローリを聴いていたが、これからは尾高盤か。《大学祝典序曲》も堂々たる演奏で、聴き映えがする。
|
|
|
テンポ、アーティキュレーション、音色など昨今流行りのものとは異なる。バッハ時代の楽譜は絵画で言えば大まかなデッサンのようなもので、おまけにこの2曲は自筆譜も残っていない。あとはシェフ=指揮者の味付け次第。こんなに美しく、流麗なバッハは他で聴けるものではない。カールハインツ・ツェラーのフルートの技巧に唖然とする。
|
|
|
今や世界的に見ても女流指揮者は珍しくもなく、重要なポストに就いている人も多い。ただ「女流指揮者でなければ制作不可能」というディスクとなると、直ぐには思いつかない。その意味で、大変興味深く聴いた。最初のノーノ作品はソプラノ歌手でもあるハンニガンが一人で歌った小品。沈痛な叫び。現代における〈受難〉とはこういうものか。アタッカでハイドンの《受難》に入る。第1楽章こそ寂しげな雰囲気があるものの、第2楽章以下は快活なハイドン。ルートヴィヒ管弦楽団がモダンオケなのも、嬉しい。しばらく間を置いて、メインのグリゼの作品。ここでもハンニガンが歌いながら指揮をする。ノーノとは違う意味でやはり悲痛な表情の曲。ただ救いがない、ということもなく、強いメッセージ性を感じる。現代音楽が人気がないのは、意味不明の音の羅列が多く、メッセージ性に欠けるからではないか、と再度認識した。
|
|
|
何で今更ワーグナーの管弦楽曲集?と聴く前は思わないでもなかった(手許にはカラヤン、テンシュテット、モノラルのフルトヴェングラーなどがある)。ところが最初の《さまよえるオランダ人》序曲から圧倒され、それが最後まで続いた。選曲、演奏に加え、極めて優秀な録音がプラスに作用している。
|
|
|
このコンビの演奏は読響大阪定期(2020.2. フェスティバルホール)で聴いて感心した。第2楽章など実に爽やかに流れ、第3楽章も変にグロテスクにならない。纏まりに欠ける第4楽章でも、圧倒的なクライマックスに持って行く手腕が見事。全体のバランスとしてはティンパニを強調気味。別に違和感はない。それにしても読響は上手い。
|
|
|
オーマンディの最大の功績は、カラヤンが録音しなかった通俗名曲の数々を、極上のサウンドで遺しておいてくれたこと(カラヤンの振る「剣の舞」って想像出来ます?)と思う。このCDは「ロシアもの」で統一してある点が好ましい。イワーノフ(正確な発音不知)の《コーカサスの風景》からの「酋長の行進」は、私が子供の頃、某音楽放送のテーマ曲として使われていた。
|
|
|
冒頭の《エグモント》はテンションが高い。メインの《田園》、テンシュテットとこんなに相性がいい曲とは思わなかった。気がついたら第2楽章、安心して聴き惚れていた。第4楽章「嵐」ではティンパニを相当強打させ、第5楽章「牧歌」の幸福感を際立たせて全曲を締めくくる。
|
|
|
スポーツでもドラマでも、スターばかりでは成り立たない。指揮者でも地域主体で活動する人もいる。デルヴォーもその一人。両曲とも勘所を押さえた、とてもいい演奏だ。《絵のような風景》終曲の出だしは、昔映画のニュース番組開始のテーマ音楽として使われたらしい。聴き覚えのある人も多かろう。とても親しみの持てる音楽である。
|
|
|
音質の良いのに驚く。復刻エンジニアの労力に敬意を表したい。《田園》もそれ程ハンディを感じなかった。詳述は避けるけれども、全9曲を聴くと、今古楽器使って小編成でチマチマやってる人たちが、いかに楽聖を矮小化しているか、わかろうというもの。
|
|
|
驚異の音源の出現である。バックハウス×ベームの《4番》はUNITELが映像化しており、そこでのオケはウィーン交響楽団。これがウィーン・フィルだったらという思いもあった。本盤ではここそこにウィーン・フィルならではの艶やかさがうかがえる。《3番》は少し音質に問題もある。トスカニーニの指揮はややザッハリッヒではあるものの、ベートーヴェンの意志力は十分に伝わる。ヘスのピアノも安定感があり、これも聴きものであろう。
|
|
|
イザイの《無伴奏》はバッハのそれと並ぶこのジャンルの傑作だが、録音の数は多いとは言えない。これは素晴らしい演奏だ。この作品に必要なのは、➀演奏者の強い共感、②最後まで聴き手を惹き付ける構成力、③演奏者と相性のいい名器(松田さんはここではガダニーニを使用)、さらにCDとなると、④演奏者が信頼を置く録音スタッフ、が揃うことが必要となる。それらを十分に満たす演奏。ヴァイオリンのシャープでクリアな音色が見事に伝わってくる。
|
商品詳細へ戻る