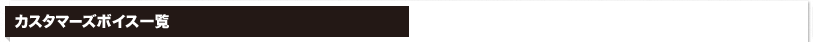
商品詳細へ戻る
NFJKさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
ピアノはアルド・チッコリーニです。データがバグってます。
|
|
|
これまで、スクリアビンの独奏ピアノ曲は専らロシアの大家たちの演奏を聴いてきました。ソフロニツキーとか、リヒテルです。ソフロニツキーは作曲者遺族公認の技量ですが、録音が古すぎます。ダイナミズムで比肩するものもないリヒテルと、気分転換でアシュケナージでしょうか。
今回のムストネンの演奏のタッチが美しいこと!とにかくどんな強音でも濁りません。スクリアビンの意図した美に触れられた思いがします。アシュケナージも良かったですが、よりムストネンに惹かれました。
|
|
|
ショスタコーヴィチの全集はコンドラシンやバルシャイのものがあるが、全集には至らないが個々の交響曲でベストな録音を残した指揮者を一人挙げるならムラヴィンスキーだと思う。5番や12番は圧倒的だった。ムラヴィンスキーは初期Noの録音は残さなかったし、15番は理解できなかったのでこのCDボックスに手を出した。
冷血非情なムラヴィンスキーより指揮ぶりは遥かに親しみやすく、とっつきやすいことは確かである。また、ロシア系指揮者によるロシア臭さのバイアスがない分、純音楽的学的に楽しめる。これは特に5番、7番、8番に当てはまる。
|
|
|
「さすらい人」よりも即興曲、CD最後の2番に惹かれた。まさしくシューベルトに成りきって、彼岸から奏でているような音色である。俗世を捨てて修道院に入ってしまった人であり、「厭離穢土 欣求浄土」がぴったりはまる。
この人のディスコグラフィは廃盤だらけで、ドビュッシーといい、本CDといい、アマゾンでの中古購入に1年かかった。なぜかディスクユニオンには出品されないのである。まともに入手できるのはメシアンくらいではないか。
|
|
|
評点が渋いのは、無調な現代音楽全般が個人的に好みでないからです。この作曲家の場合、交響曲や弦楽四重奏等は聞きとおすのがつらいものがありました。そんなものコメントするなと言われそうですが、「ハープ協奏曲」や「ヴィブラホンとマリンバ協奏曲」、ピアノ独奏曲で「春」や「秋」は極めて好みだったのです。非常な多作家だったそうですが、作品の傾向も色々です。
代表作は「屋根の上の牡牛」や「世界の創造」で、バーンスタインの名演で聞かれた方も多いでしょうが、それ以外となるとほぼ馴染みがないのではないでしょうか。全ての作品を好きにはなれないが、どこかにきっと好みの曲がみつかるセットだと思います。
|
|
|
モノラルライブとしては最大限の音質向上が図られていると思います。ネタがヴォーン・ウィリアムズというあたりがとてもマニアックですが。
RVWの曲はボールト卿の一連のCDで親しんでおりました。ステレオ録音も多く、バルビローリやプレヴィンの演奏と聞き比べてもボールト卿推しでした。特に3番、5番、8番が好きなのですが、今回のCDはあまり聞かない6番と9番です。これらはボールト卿の演奏でもいまいち気に入らなかったのですが、むしろ今回CDの方が琴線に触れました。ライブだけあってド迫力です。
|
|
|
クーベリックの指揮が十全に発揮された名演です。出だしからの沈鬱さはまさしくドイツ的で、イタリアの物語とは思えません。曲の根幹を成す主人公の悩み(作曲技法が伝統から外れること)が現代日本人としては浮世離れしていると感じられるので、曲が美しいのにどうも感情移入できません。過去の大作曲家の亡霊だの天使が現れるシーンでは、神意が下されるにしてももっとましなテーマがあるだろうとか思ってしまいます。かような罰当たりな小生を捕らえて最後まで聴かせるあたりがクーベリックの凄さです。
|
|
|
ブラームスの「雨の歌」は大好きな曲です。これまでベスト盤はシェリング&ルービンシュタインでしたが、気品と優雅さにおいて本盤は決して引けをとらないと思います。
|
|
|
期待以上の音質でした。中でも、ラストのブルックナー9番が一推しです。
カイルベルトはブルックナーは6番、9番を偏愛していたようで、どちらも数種類の録音がありますが、9番については本BOX収録の1960年ザルツブルグでのベルリンフィルとのライブ録音がベストに思われます。ブルックナーの交響曲の内容は等しく自然の賛美と神への賛歌だと言いますが、この曲は一歩踏み込んで神の諸相を描写しているように思えるのです。第一楽章はさしづめ審判の神、第二楽章は世界を舞台とした狂言作者としての神、第三楽章は万物の源としての神、そして未完の第四楽章は慈愛と救済の神が描かれるはずだったのではないかと愚考します。第四楽章の代わりにテ・デウムを演奏しろとのブルックナーの遺言とも平仄が合うのではないでしょうか。といったことをつらつら考えさせる演奏でした。
|
|
|
これは本当にステレオなのか?モノラルでももっと良い録音はあると思うが。
クリュイタンスの指揮については申し分ない。
|
|
|
ホーレンシュタインのCDは色々集めてきた。悪名高いVOXレーベルやフランス国立放送管のボックスを含めて。
CD帯にはステレオ録音もある、オケの音色が鄙びていい感じとか寝言が書いてあるが、録音状態はステレオ?含めて下の上、オケは下の中といったところかと思う。
これだけの大指揮者が指揮しているので、部分部分に素晴らしい部分も散見される。ローエングリンの前奏曲とか、ブル3は大きな破綻はない。ディスコグラフ上の売りと思われるメタモルフォーゼンとベト2はBBC響あたりで聞きたかったと思わずにいられない
|
|
|
このCDボックスは特価だったので購入した。長期ドライブのBGMとして聴き始めて余りの完成度の高さに驚愕した。
それまでチェンバロ音楽で感動したことはなかった。不明を恥じる。38歳で夭折されたことが悔やまれる。
|
|
|
バルビローリのステレオ録音です。
フィッシャー=ディースカウのイヤーゴを聞くために中古を探しました。「イヤーゴの信条」とか、期待通りの出来栄えです。ギネス・ジョーンズのデズデモナもいい感じです。絞殺される際の絶叫とか鳥肌ものです。
マクラッケンのオテロは余り高評価のコメントを見ないのですが、イヤーゴに手玉に取られる弱さが十二分に表現された結果、情けなく感じられるのでしょう。これはこれで名演なのではないかと思います。
バルビローリの指揮ですが、かの有名なフルトヴェングラーのザルツブルグ音楽祭公演をステレオで録ったらこんな感じになるんじゃないかと思いました。なんでこれが廃盤なのか理解しがたいです。
|
|
|
ヘンツェの管弦楽付き「トリスタン」がメインのアルバムなのだろうと思うが、ヘンツェ以外(リスト、マーラー、ワーグナー)は楽しめた。偏に小生に現代音楽への理解が足らないためだと思う。
|
|
|
グッドール卿のワーグナー及びブルックナーはどれも外れはないですが、トリスタン以外は入手困難なのが残念です。このマイスタージンガーも名演です。1968年のライブで、Chandosらしくクリアーな音質です。
配役は個人の好みの問題ですが、ザックス役が爺むさく、ワルター役は線が細く、そして何と言ってもベックメッサー役が嫌らしすぎます。ある意味理想のベックメッサーと言えます。むかつくことこの上ないのですが、第三幕で見事な?迷演を披露して笑いものになる場面の嘲笑や野次が酷いので一周回って気の毒になりました。終盤の盛り上がりは実に見事です。
|
|
|
このボックスはDisk Unionで中古で買った。一聴して驚愕。なんでこんな名盤を廃盤にしたのか・・・・
ポーランド人だし、ショパンコンクール入賞者と聞いてショパンがメインなのだろうと思っていたが、むしろ後半のチャイコフスキーやブラームスやベートーヴェンの方が良かった。特にフランクは晦渋極まりなく、フレージングが合わないと途端に曲の魅力が失われるのだが、実に見事だと思う。今までのベストのボレットを凌駕する。20枚組くらいに内容を拡充してリマスタリングし直して再発を望む
|
|
|
特にブルックナーが絶品である。是非7番や8番を聞いてみたい。
この人のディスコグラフィは壊滅的に少ないのだが、正規録音をほとんど残さなかったのなら放送局やライブの録音に望みをかけるしかない。どこかからか出てこないものか。
|
|
|
メーカー(Memories)はハイドン94番「驚愕」を堂々と94番「奇跡」と誤記し、輸入元は輸入元でシベリウスをスウェーデンの作曲家だなどと間違えています。音質も年代相当で良くありません。色々不満はありますが、ライブの臨場感、曲目の珍しさ(フルヴェンのエン・サガ!)、ハイドンとベートーヴェンの立派さは掛け替えのないものです。ジャケット等一新し、リマスターし直して欲しいと思います。
|
|
|
スターリン統治下のソ連にあって、体制を堂々と批判したにもかかわらず、スターリン自身が彼女のファンだったために投獄も処刑も免れた、とされる伝説のピアニストです。冷や飯食いが続いたので録音には全く期待していなかったのですが、意外にいい音なのでびっくりです!
この時期のソ連は、ショスタコーヴィチその人、リヒテル、ギレリス、ネイガウス父子、グリンベルク、ソフロニツキー、ヴェデルニコフ等天才ピアニストの見本市のようなものでしたが、バッハ(及びベートーヴェン)はユーディナがベストだと思います。
|
|
|
バイオリン協奏曲は1944年、交響曲は1943年の録音を鑑賞に堪えるまでにリマスターしているのは天晴です。バックスは日本では知名度が殆どないと思うのですが、ホームグラウンドの英国ではそこそこファンがいるために本ディスクが作られたのでしょう。それでもバックス音楽のコレクターアイテムなので、ブライデン・トムソン、リチャード・ヒコックス、ロイド・ジョーンズあたりの演奏に触れてから聴くことを推奨します。
|
|
|
5番はあたかもドン・ジョヴァンニのような禍々しさが良く出ている。未完成は出だしの超弱音がムラヴィンスキーなみ。曲そのものはカヒーゼにしては控えめに感じた。ザ・グレートは伸び伸びとしているが独特なフレージングがちょっと引っ掛かりました。
|
|
|
ロスバウトは現代音楽の擁護者として名高く、このセットにもシェーンベルクやウェーベルンやリゲティ、メシアン等の録音が含まれるが、小生が最も感銘を受けたのは古典音楽(ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン)だった。異論もあるだろうが、後期ロマン派の代表であるワーグナー、マーラー、ブルックナーより生気に満ち、素晴らしく思われた。特にベートーヴェンは、2番や8番に込められたユーモアの表現が素晴らしかった。表面上いかにも真面目くさっているからこそ表現されるユーモアが感じられ、この点はフルトヴェングラー(深刻一辺倒)やクナッパーツブッシュ(ひたすら豪快)より勝ると感じられた。
|
|
|
カバージャケットがダメなので減点1。ジゴロにしか見えません。
選曲がリストに偏りがちなのは、リストのスペシャリストとされていたのでしょうがないように思いますが、この人の真価はバッハやフランクやドビュッシーにあったように思います。伝説のカーネギーホールリサイタルはタワレコ盤をほぼ毎日のように聞いているくらい好きです。絢爛豪華なピアニズムより、弱音に深い深い感興を忍ばせた演奏が非常に好みなのです。
|
|
|
はじめに廉価版で購入し、後で買いなおしました。「無人島に流されてもこれさえあれば退屈しない」ベストオブベストの一枚です。その後、色んなピアニストのCDを買いましたが、バックハウスを超える30~32番はない、というのが結論です。
|
|
|
楽曲の内容を精確に把握できたとは言えないので星3つとした。思ったより現代音楽してなく、初期交響曲は後期ロマン派としてワーグナーの延長線にあるものとして聴ける。ダウスゴーの指揮は温かみがあり、かつクリアーで、他の指揮者であれば星は1~2減ったことと思う。
ランゴーは生前理解されず生涯不遇だったと聞く。当時ダウスゴーのような理解者がいて、指揮を引き受けていれば随分とマシだったのではないかと思う。交響曲1番がもっともとっつきやすいが、これを18歳で作曲したとは信じがたい。
|
|
|
コスパの良いボックスセットです。全てロシアものです。12枚に収めるためにチャイコフスキーは「悲愴」のみ、ショスタコーヴィチは「革命」のみ。とみせかけてミヤコフスキーのヴァイオリン協奏曲など馴染みが薄い曲を紹介してロシア音楽の裾野を広げる姿勢が良いと思います。個人的な一押しはボロディンです。
|
|
|
正しくはGoldenMelodramのGM10002を購入したのですが、正規音源であるOefeo版の方が音が良いはずです。さすがバイロイト、グリュンマーのエルザにコーンヤのタイトルロールが実に実に素晴らしいです。モノラルであることなど全く気になりません!
|
|
|
RVWの交響曲第五番は大変好きな曲です。これがピアノ用に編曲されたとのことで購入しました。第一楽章出だしから引き込まれます。いい出来だと思います。販促用?のタリスファンタジアピアノ版もいい感じです。
|
|
|
最初から最後まで爆演しています。春の祭典はマリインスキー管の演奏が余りに有名ですが、若い頃からこうだったのだと納得がゆきます。
ラストの現代音楽以外は楽しめました。小生があまり聞かないので耳が慣れていないだけで、これも名演なのだろうと思われます。
|
|
|
モノラル録音としても最悪に近い。1951年の筈が1920年代の録音に聞こえる。音がかすれるわ録音レベルは安定しないわ散々である。これに比べたらフルトヴェングラーのライブはデジタル録音に等しい。
くれぐれも最近の録音(バレンボイムでもカラヤンでもいいから)で曲に耳を慣らしてから聞けば、ある程度脳内補完できると思う。そうすると俄然面白くなると思う。
|
|
|
誠に残念なことながら、マーラー10番は第一楽章が欠けています。元からこうだったのか、録音が失われてこうなったのか不明ですが。
多重録音したといっても、この曲のやたら複雑なポリフォニーをピアノで再現することは無理です。なので、曲のエッセンスをとらえて再構築することが必要です。終楽章を聞く限り、あの寂滅な曲調、彼岸の雰囲気を良く出していると思います。
あと、ブゾーニのピアノ協奏曲が2種類はいっています。同じ曲の別の演奏でDisk5枚のうち2枚使う、コレクター魂にぐっとくる姿勢が割と好きです。
|
|
|
スヴェトラーノフは爆演型の指揮者だったが、本Boxで初めて演奏に接する方(そんなのいるかどうか不明だが)にはイロモノ扱いされると思われる。何せボックスのイラストがソ連軍だし、開封して目に付くDisc1(ブル8)の紙ジャケットが赤旗を掲げて勝ち誇るソ連兵だし。
実際に購入して視聴した小生としては、ゴロワノフ程「力isパワー」(これはこれでありだが)でもないし、楽しめたと申し上げたい。
故宇野先生はフルトヴェングラーの指揮したブルックナーを必要な資質の対極にあると批判したが、本Boxのブル8を聞いたら何と言っただろうか。それでも、干物のような演奏よりずっとマシだと思うのである。
あと、ラストDisc20のフランクとサン‣サーンスが良かった。フランス風エスプリなど欠片もないが、推して押して圧しまくるのがいっそ新鮮だった。廃盤なのが惜しまれる。
|
|
|
ブリテンに感銘を受けました。この人の曲で気に入るものはあまりないのですが、ピアノもオケも素晴らしいです。録音もブリテンがベストで、残念ながらライブ録音のカルミナ・ブラーナはいまいちです。いずれタワレコあたりがリマスターしてSACD化する可能性に期待したいと思います
|
|
|
弦楽合奏の曲は心に染みるのですが、合唱曲はちょっと怖いです。ホラー映画のサントラに使えそうです。
|
|
|
ステレオはファウスト、ヘンゼルとグレーテル、ボリス・ゴドゥノフで後は全てモノラルです。
フランスものはグノー、ビゼー、オッフェンバック、プーランクと押さえられていますが、それより半分を占めるはワーグナーがいい出来です。特にローエングリン(タイトルロールがシャーンドル。コーンヤ)が絶品です。マイスタージンガーはバイロイト公演が3種類あり、ハンス・ザックスをナイトリンガーが歌ったものがお気に入りです。
|
|
|
モノラルですが音質良好です。第一楽章の美しさ、第二楽章の滋味、第三楽章の巨大さ、第四楽章もクナならではのスケールで最高です。
|
|
|
カイルベルトのバイロイトの指輪全曲が実験的ステレオ録音として残っていたのは有名ですが、これも同じ経緯でしょう。まずは感謝を。モノラルっぽいステレオで、重心が低音側にある音質が曲想にぴったりです。歌手は勿論良いのですが、カイルベルトの指揮も曲の禍々しさを余すことなく表現しています。何といっても「水夫の合唱」が絶品です。
|
|
|
歴史的名盤である9番と同じBPOとの演奏ですが、音質は大分劣ります。2番と6番と異なり一応ステレオです。
音質は聞いているうちに気にならなくなると思います。
|
|
|
ビーチャム卿の為人は諸説ありますが、この演奏は名演です。だからこそ、LPやXRCDやSACDに手を変え品を変えてカタログに残り続けているのだと思います。リマスタリングで音質がどう向上しているのか知りませんが、小生にはこのCDで十分です。
ビーチャム卿はグリーグの音楽に思い入れが強かったとのことで、演奏からも曲への共感と愛情が見て取れます。
|
|
|
断片的な遺稿(というかスケッチ)を纏め上げた手腕には敬意を表するが、これじゃない感が強い。8番の威容はアルプスに例えられることが多いが、9番から受ける印象はCosmicであり、折角の第4楽章からはその印象が薄い。もっとも、完成していればブルックナーの最高傑作となっただろう作品であり、完成させるにはブルックナーと同等の才能が要るとすれば当たり前に思える。完成した9番でなく、4.5番とか6.5番としてなら充分及第点だと思う。
けなしてばかりだが、小生の聞き込みが足りないせいでもあると思う。もう少し聞きこんでから、完全版の改訂稿も聞き比べてみるつもりである。
|
|
|
ホルスト・シュタインはワーグナー等独墺音楽指揮者としての印象が強く、シベリウスもワーグナーっぽく聞こえます。選曲もドラマチックなものが多いこともその印象を強めています。小生はシベリウスのベストは交響曲第6番だと信じ、収録されていないのが残念ですが、これはこれで悪い演奏ではありません。曲想と良くマッチしていると思います。
|
|
|
1995年の録音で、ソングリストの1~9がRVWの「旅の歌」、10~14がフィンジの「花輪を捧げよう」、15~19と23~28がバターワース、20~22がアイランドの歌曲です。帯ではRVW推しですが、フィンジに最も惹かれました
|
|
|
モノラルですが名盤です。弦楽四重奏曲64番、67番、66番であって68番は含まれませんのでご注意
|
|
|
収録曲:①フィンランディア、②カレリア組曲、③カンツォネッタ、④ダンス・インテルメッツォ、⑤ポヒョラの娘、⑥悲しきワルツ、⑦トゥオネラの白鳥、⑧レミンカイネンの帰郷、⑨ラカスタヴァ第三楽章
|
|
|
とてつもない名演です。バッハは祈りというより懺悔のようです。何よりもラストのグラナドス「オリエンタル」!おそるべき無常感に呪縛されます。この曲のベストの演奏であることに疑いありません。
|
|
|
録音の仕方と個人の好みのせいでしょうが、ステレオのモリーニよりモノラルのシュナーダーハンの方が魅惑的に聞こえました。
|
|
|
録音がそれほど多いオペラではないので、お試しだったのですが、予想外に魅惑的な演奏でした。フランスのオケだけあって見事なラヴェルですし、それを統率するスラットキンもまた見事です。
|
|
|
まずCD1枚目ですが、1954年のライブとは信じがたい良い音です。難くせつけるとしたら、全強奏でマイクに入りきらずに音が潰れることですが、CD2枚目では大幅に改善されています。クナのモノラル録音は音質が貧弱だと思い込んでいる人に薦めたいアルバムです
|
|
|
若い頃はフルトヴェングラーのような、テンポを激しく動かして直截的な演奏が好きでした。セルの、完璧だが(フルヴェンに比べ)血が通ってないような演奏は敬遠していました。馬齢を重ね多少はニュアンスを感じ取れるようになり、まして本演奏はライブなので迫力も十分です。
|
|
|
エコーがかかって輪郭があいまいな音です。印象派絵画のようです。近年の流行である、流麗でありながら一音一音が粒立った演奏とは真逆なので好悪は分かれると思います。沈める寺はまさしく海底から響いてくる感じがします。
|
商品詳細へ戻る