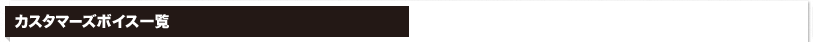
商品詳細へ戻る
もりちゃんさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
オケがビンビン鳴ってメリハリの強いブラームス。私は、気に入りました。ブラームスの内に秘めたパッションを、小澤の敏腕がうまく引き出したようです。いやぁ、見事みごと!各奏者もうまいですね。この音盤、パートやソロを聴く楽しみもありますよ。
|
|
|
その昔、キングレコードが1枚1,300円の廉価版“GT”シリーズで再発したとき、宣伝チラシに「火傷しそうな熱い演奏」と評されていたと記憶します。実際、初めて聞いて、その評を思い出したのです。要所要所で聞かせるエッジが強いので、慟哭の惜別という雰囲気です。レクイエムらしいかどうか、私には何とも言えませんが、古い年代のものにしては流石に音はシッカリしていて、幾度も聴きたくなるような説得力のある演奏だと思いました。
|
|
|
先日ドライブ中にNHK-FMで偶然聴いたのが大橋純子の特集。
“シルエット・ロマンス”しか知らなかったので、“鍵はかえして”“ペイパー・ムーン”を耳にしてビックリしましたよ。歌唱力の高さは知っていましたが、これほどだったとは!
70〜80年代を懐かしく思い出すメロディーと伸びのある大橋の歌唱に浸っています。
|
|
|
このシリーズ、演奏といい録音といい高水準なので、この先がとても楽しみです。当盤の3曲は、磨き上げた鋼のよう光輝な高音と安定して豊かな低音が、心に響きますねぇ。変に感情移入がないから、そうした音がダイレクトに響くからでしょうな。コルンゴルトのセレナードは、特に訴えかけの強い曲。1度実演で聴いてみたいと思いますよ。
|
|
|
商品紹介文にある“ベルリンフィルの極上の響き”、まさにそのとおりです。弦の美しさと艶、木管の晴朗、金管のふくよかさ、とベルリンフィルの美質がいかんなく発揮されていると思います。しかし、それを導いているのは、他ならぬケンペですよ。リズムが安定していて、強弱の表現を煽らない、落ち着いたリードですが、それによってベルリンフィルの奏者は思い切った自己表現ができているのだと思います。しかし、ケンペの表現は落ち着いているだけではない。極端にスローな第1楽章の後に、シッカリと三拍子を刻んだ第2楽章ワルツを聴くと、何と艶美な舞曲になることか。第3楽章の、強めのオーボエとコーラングレは恋の鞘当てのよう。そして、最終楽章の鐘。梵鐘のような低めの音は、まさに黄泉の国の響きであり、作曲者の注文どおりの響きではないか?と、いうことで、一挙に3度繰り返して聴いてしまいました。音質も、録音が古い割には、結構クリアで、教会特有の残響も程よく聴こえてきます。
|
|
|
素晴らしいラヴェルです。ラヴェルの曲には、国境は無いですね。“ㇻヴァルス”の素晴らしいこと。西仏両国の血が流れる男が、19世紀半ばのウィーンをイメージして成した曲を、英国人と英国のオケが、実に見事に奏でている。一寸、今までに聴いたことのないヴァルスですが、それは違和感ではなく、新たに見出した道筋です。マ・メール・ロワも、ボレロも同じ。録音も素晴らしい。
|
|
|
良いですねぇ。初見参の曲が多くて、しかも、“旋律家”弟ヨーゼフがふんだんに盛り込まれていて。録音も良い、ホール感があって。ヴェルザー=メストの解釈は、一寸凝りすぎな面もあるけど、それはオケがシッカリほぐしているように思えます。
|
|
|
前評判のとおり、ロウヴァリは優れた指揮者になると思います。全体を通じて感心したのは、余裕を感じる指揮又は曲づくりです。恐らく、曲の全てを手中に収めているからでしょう、テンポの変化、間のとり方、アクセントの付け方、ロウヴァリ流の味付けが分かるのですが、曲の流れに自然に乗っているように受け止められるのです。これこら、既出の盤も聴いてみようと思います。音質は、ライヴのアルペンとツァラは褒められたものではありませんが、奥行きと明晰さは感じられるので、まぁ良しとしましょう。
|
|
|
良い演奏でした。ドヴォでも書きましたが、セルが“冷たい”とは、一体誰の評論?縦線がピシッと決まっていて、それでも、管楽器はノビノビと吹いています。弦は、随所で目一杯美しく弾かれています。それが、セルの、ベートーヴェンの交響曲に対する思いでしょう。十分に熱い名演奏ばかりてすよ。録音も、高品質のイヤホンで聴くと、奥の深さ行きとホールトーンの美しさに一寸驚きます。
|
|
|
少々難しい作曲家ですね。環境音楽とするには仄暗いし、構えて聴くにはホンワカしている、と。エッシェンバッハの導きが優れているせいか、オケも、管のソロを始め良い響き。しかし、曲が胸に迫ってこない。幾度も、じっくりと聴き込めば、印象は変わるかもしれません。この時代の作曲家、本当に難しい。
|
|
|
“斬新珍奇”と言うと否定含みのようだか、ざっと曲目を眺めたときに浮かんだ言葉が、これ。しかし、さすがロト、聴かせてくれます、楽しませてくれます。まず冒頭、キャバレーワルツでガツンとやられます。そして、続くワルツやポルカも、現代のドラマや映画でも通用しそうな軽快さと美しさ。大半が谷間に咲いた可憐な花としておくには、勿体無い気もします。これも、ひとえにロトの知恵と技なのでしょう。このアルバムでは、“スケーターズワルツ”や“天国と地獄”のような人口に膾炙した名曲がスパイス役ですね。ただ、欲を言えば、録音にもう少し残響がほしかった。シエクルの音じたいが古雅なので、曲の特性に照らすと、もう少しゴージャスな雰囲気があっても良かったのではないかと。それを、録音でカバーしてもらいたかったと思うのです。
|
|
|
ロベルトの方は、とても良い共演だと思いました。ラナもネゼ・セガンも彫琢が丁寧で曲の襞までがハッキリわかるよう。ラナのピアノはかなりのマイペース、テンポや強弱は変幻自在で奔放。しかし、セガンのバックはしっかりとラナを支えている。それでいて、オケの存在感は全く薄れない。むしろ、ラナと対峙するような木管のソロなど、つい聴き惚れてしまう。素晴らしい名盤の誕生!録音も、音が近めながら、ホール感は失われていない。一方、クララの方は、文献的な価値に留まるという印象。ロベルトの曲とペアで幸せだったのか……。
|
|
|
ライナーノート記載のとおり、アントルモンへの誤解を解く熱演でした。若き小澤征爾のパッションのほとばしりも素晴らしい。買って良かったと思います。オケもピアノも音が近い録音で少しと驚きました。
|
|
|
Pカザルス指揮によるこのシリーズは、録音有史における至高の宝物だと思います。一級の演奏家又はその有力候補者たちが、カザルスを一点に見つめて、一心不乱にJSバッハを奏でる。各曲から、この直向きさや熱さが直につたわって来ます。音質も、恐らく十全の環境ではないにも関わらず、奥行きがあってみずみずしい響き。
|
|
|
想像したほど音質が向上していなかったので四ツ星。私には、この盤は、LPレコード時代からオイストラフの奇麗でコシのあるヴァイオリンを聴く演奏と認識しています。Oクレンペラーのバックが、思ったほど重量感が無いのと、スピーカーに貼り付くような音が難点と思っていましたが、音質面では、さほど改善されていませんでした。しかし、オイストラフのヴァイオリンはセル盤よりもノビノビとしているように感じられます。
|
|
|
とても良い演奏ですね。全ての奏者がPカザルスの姿だけを見て、一心不乱に弾いている、吹いている、叩いている。それでも、ベートーヴェンほど演奏が盛り上がってこないのは、WAモーツァルトが古典派だからでしょう。古典派の鋳型は、情熱や熱意だけでは、乗り越えることはできません。しかし、40番の熱い疾走、39番の我を忘れたような抉り、41番の大胆な奔放さは、眼前に迫ったロマン派を思わせる。指揮者も演奏者も“天晴”です。録音も、予想したほど悪くない。ライヴとは思えない奥行きがあります。
|
|
|
何れも中継を観ましたが、そのときは、さほど惹かれませんでした。なので、あの時の印象を確認しようと思いたち、音盤を購入し聴きました。結果は、同じです。Cクライバーは、“こうもり”は生き生きとして素晴らしいのに、私には、個別のワルツやポルカは味わいに乏しくて単調に聴こえるのです。ただ、会場の楽しそうな雰囲気は伝わってきますから3点献上しました。
|
|
|
モシュコフスキは旋律の美しい聴きやすい曲でした。大きく構えたところが無いので演奏機会に恵まれないのでしょうが、鑑賞には十分値する佳曲だと思います。一方、パデレフスキの方は第1楽章の途中で辛くなってしまいました。失礼な喩えですが、ウケない芸を一所懸命に続ける芸人を観ているようで…。しかも、フィナーレ近くで音飛びが発生!見ると、盤面にキズがありました。これ幸いと、先を聴くのをやめました。
|
|
|
“新世界”の素晴らしさに惹き込まれ、一挙に7番8番と聴き進めてしまいました。余白の?小品も含めて、全てが、素晴らしいの!一語に尽きる名演奏。「セルは冷たい」とは、いったい誰が言い始めたのか、少なくとも、このCDはセルとオケの思いが結晶した熱い演奏ばかりですよ。それでいて、アンサンブルは完璧ですからね。さらに特筆すべきは、セヴェランスホールの優れた音響を見事にとらえた録音の良さ。リマスターの効果もあるのでしょうが、原盤も、良かったのでょう。
また、解説書も、このシリーズは実に充実していますね。奏者まつわるの挿話、曲目解説、奏者のプロフィール、録音技術の説明など、買い手の期待を意識した内容です。拍手拍手👏
|
|
|
ピアノ協奏曲は初めて聴きましたが、曲想自体に華やかさが無く、独奏が大見得を切るような見せ場も無いのですが、全体に漲る幽玄性や寂寞感が何とも言えない味を出しています。版の問題もあるのかも知れませんが、もう少し、演奏されても良い曲だと思います。実は“パリ”も同じで、タイトルから想起するほど、都会の賑わいや喧騒が表出されているわけではありません。むしろ、大都市の抱える闇や悲哀のようなものに重心が置かれていると思います。それでも、曲としてはとても魅力的だと受け止めました。デイヴィスとスコティッシュのコンビは流石の名演。ディーリアスに求められる管の上手さも際立っています。
|
|
|
英国のライトクラシックは、とても馴染み易い。洒脱と厳粛、軽妙と厳格、下衆と貴賓、これらが絶妙の配分で融合しているのですね。エリック・コーツはその代表格。そして、ジョン・ウィルソンは、その特徴をしっかり捉えて表出しています。だから、居間で膝を揃えて聴いても、車を運転しながら聴いても、スンナリと耳に入ってきます。
|
|
|
アリス・沙羅・オットのピアノはFリストでも、やはり、明るく粒立ちが良いので、スンナリと耳に入ってきます。もちろん、軽い、あっさり、との評価もあるでしょう。でも、音自体の芯はしっかりしているので、聴き応えはあると思います。録音も、そうした特徴をしっかり捉えた優れたもの。
|
|
|
“アパラチア”は、曲想に照らすと新盤の方が好ましいと思いますが、壮年期のバーンスタインの勢いの良さやメリハリの強さは捨て難い。しかし、“ロデオ”はそれが魅力として活きています。録音は、やや平板な印象を受けます。
|
|
|
マーチは良いが、それ以外はダメです。今迄、この手のアルバムが無かった理由が分かりました。しかし、Kヤルヴィ指揮のRスコティッシュOの演奏は、シンフォニックで丁寧に感じ、好感が持てます。
|
|
|
このシリーズのお陰で、バーンスタインの魅力に気がつくことごできました。日本の専門家は、壮年期のバーンスタインに厳しい評価を下していますが、素人の耳には、どれもこれも魅力ある演奏に思えます。この盤も、そう。バーンスタインならではの、歯切れの良さ、嫌味の無いテンポの揺さぶり、そして、処々でハッとさせられる仕掛け(悪戯?)、と。これら人口に膾炙した名曲の、新たな魅力にも気付かせてくれます。もちろん、「ウィンナ・ワルツらしくない!」と言われれば、素直に「そのとおり」と返します。しかし、果たしてJシュトラウスらは、“ウィーンの”という思いで各曲をものしたのだろうか。その“らしさ”を意識して、三拍子や二拍子を刻んだのだろうか?バーンスタインの演奏を聴いていると、そんなことすら考えさせられるのです。
|
|
|
音質云々よりは、個別に所有していたCDが1冊にまとまる利便性に惹かれて購入しました。各音盤もともと優れた音質でしたが、今回のリマスターで、音に厚みが増したように思えました。ところで、LPレコードの時代は、米国オケを率いる大物指揮者の陰で、とても地味な売られ方をしていたと記憶します。それがために、買いそびれて聴き逃してしまった方々はたいへん残念だったと思います。フレイレの端正にして芯のしっかりしたピアノを含めて、どれも素晴らしい演奏ばかりですから。中でも、ロマン派の嚆矢という位置付けに徹した“グレート”と、華美にならずとても全体の見通しの良いチャイコのP協はイチオシですよ。
|
|
|
「一曲一曲にスウィトナーの“思い”がしっかりと込められている!」通しで聴き終えて、得た感想です。ベルリンシュターツカペレも良いオケですね。木管のソロなど、とても楽しい。録音も広告どおりの素晴らしさ。私はCDですが、会場の隅々にまで響き渡るような広がりと、各楽器の音を明瞭に捉えた粒立ちの良さ、見事な録音技術だと感心します。
ただ、解説書の内容が今ひとつ。21曲それぞれの解説が欲しいと思いました。
|
|
|
ルロイ・アンダーソンを聴くのであれば、この全集を1番に勧めたいと思います。演奏と録音の良さが高次元で整っていて、これだけの曲数が、“万”をはるかに下回る金額で聴けるのですから。LPレコードの時代、ことのほか冷遇されていたルロイ・アンダーソンを知る者としては、夢のような一巻ですよ。歌入りの「ブルータンゴ」と「舞踏会の美女」は洒落ているし、アンダーソンにピアノ協奏曲があったとは新鮮な驚き。そんな刺激もたまらない。Lスラットキンは、シナをつけたり揺さぶったりしないオーソドックスかつシンフォニックな解釈で、これまた好感が持てます。
これまでNAXOSには、さほど関心を寄せていませんでしたが、今後はしっかりと見ていきたいと思います。
|
|
|
スペイン協奏曲を聴いてファン・マネンに少々関心を持ったので、この音盤を購入しました。20世紀の人ですが、ロマン派の流れを汲んだ作曲家なので、この曲自体は複雑でも難解でもありません。しかし、構成力の問題でしょうか、両曲とも第1楽章の長さには辟易しました。第1楽章の長い協奏曲は、名曲と言われる曲でもありますが、いずれも20分前後。このVn協奏曲は約30分と、桁外れ。それだけなら、まだしも、というのが率直な感想です。Vnの心得も、読譜能力も無い小生は、辛抱強く耳を傾けるしかありませんでした。ただ、バルデラマのVnとバルセロナ交響楽団は、水準の高い技量を持っていると思いました。
|
|
|
カラヤンの“シェエラザード”は少し残念な結果。絢爛豪華で旋律の輪郭が明瞭な演奏を想像して購入したが、処々各楽器の旋律が混淆して団子状態になってい、期待の半分が満たされなかった。録音も、この時代のDGのカラヤン盤にしては、教会特有の奥深い響きに乏しく、これも残念。他の曲では、マゼールの狂詩曲とマルケヴィッチの“金鶏”が良かった。前者は、流石に才人、締まったアンサンブルと弾むようなリズムが素晴らしく、何より若者らしくて表現がストレート。後者は、初めて聴く曲ですが、旋律の輪郭が明瞭なのでスンナリと耳に入った。それにしても、ラムルーOは地味だけど、マルケヴィッチで聴くと結構優秀、これも流石。
しかしながら、このような企画モノは、買うのに躊躇してしまう。狙いが、分かるようで分からない。せめて演奏者が統一できるテーマに限るべきだとと思う。
|
|
|
個別に所有していたものが1冊にまとまったので、買い直しました。従って、全てを聴き終えたわけではありません。しかし、“悲愴”と“ロメオ”は音が少しクッキリと聴こえるようになったと思います。しかし、これらの音盤は、音質以上にミトロプーロスの指揮の凄さを聴くべきでしょう。フルトヴェングラーが、信頼を寄せた理由が分かります。“浄夜”“タリス”“悲愴”など、各曲で見せるうねりの大きさと細部への配慮の見事な両立はミトロプーロスならではと言えます。フルトヴェングラーがステレオで蘇ったら、と思わずにはいられません。ところで、解説が雑駁でになりがちな他社の高音質版のライナーノートに比べて、CBSのは、録音のきっかけを始めとても親切で丁寧。これも、音楽素人にはとてもありがたい。
|
|
|
ヤン・シベリウスのピアノ曲が、こんなにも魅力のあるものだとは思いもしませんでした。高山に咲く、可憐でも逞しい草花のような、優しさと強さをあわせ持った曲が多いように思えます。また、理性と感情のバランスがほど良いのでしょう、どの曲も、とても聴き易いのです。ヴィータサロの演奏も癖がなく、これらの曲には適役だと思います。
|
|
|
“スタン・ゲッツ”の第2楽章とパルティータには痺れました。20世紀の、特に戦後のクラシック音楽が、このような聴き易さに溢れていれば、どのような21世紀を迎えていただろう。セレナードも、十分に楽しめる一曲でした。ベネットには、交響曲でも、ロマンチシズムを発揮して欲しかったと思います。Jウィルソンは、オケをのせるのが上手いのでしょう。BBCスコティッシュの管楽ソロが、どれもこれも素晴らしい。
|
|
|
下野・広響による期待の第3弾。旋律に気を取られると、掴みどころの無い曲に聴こえるし、旋律を存分に歌わせないと、そもそもこの曲の魅力を発揮し得ない、何とも解釈の難しい交響曲だと思います。熱心なブルックナー党では無い小生に、第7は、しっくりくる盤が無いのは、この特徴のせいなのでしょう。第5と第4で“場外ホームラン”をかっ飛ばした下野・広響コンビも、この第7では、球は僅かにフェンスを越えられなかったという結果。それでも、長打ですから、満足度の高いブル7の演奏だと思いますし、「さて、次は何番か!?」と、期待を継続させるだけの高水準であることは確かです。
|
|
|
半世紀前の名著“交響曲名盤100”で諸井誠氏は、バーンスタインORFの幻想交響曲を評して「フランスになりきれない歯がゆさが…」と。このラヴェルでそれを実感。しかし、ヘタウマではありませんが、私には、これがレニーの何にも代え難い魅力だと思えます。まるで「パリのアメリカ人」を地で行くような。NYOとの演奏も同じです。中でも、ダフクロは、精一杯精緻に優雅に旋律を歌わせながらも、時おりレニー固有のダイナミズムが襲かかり、如何にもアメリカンな恰幅の良さに支配されてしまう。これは、私は、バーンスタインの至芸と受け止めます。ここまで大胆な芸当、今や誰ができましょうか。
|
|
|
今さら、とは思いました。しかし、来日時の第5の演奏が耳に残っていたので、漸く決断し購入しました。結果は◎です。何よりも素晴らしいのは、各曲に生命力が宿っているように聴こえること。一音一音に魂が込められていますね。タワレコには日本語解説付きで再発売してほしいと思います。
|
|
|
耽美的な曲が3曲(+1)続くと飽きそうなものですが、バティアシュヴィリの伸びのある美音は飽かずに聴かせてくれます。シマノフスキは初めて聴きました。渋くて掴みどころが無いような曲ですが、聴き込むうちに、押しては返す波のようなバティアシュヴィリの音響美に嵌りました。フランクのソナタと詩曲も、バティアシュヴィリの持ち味が発揮されていると思います。ただ、フランクは、少し線が細いような気がして、ピアノ伴奏も少々遠慮がちに聴こえるので、総点は四つ星にしました。
|
|
|
世評のとおり、Cクライバーの痛快無比の名演だと思います。“オペラ音痴”ゆえ、比較する盤を聴いていませんが、比較するまでもなく最上位におかれる名盤でしょう。何と言っても、Cクライバーの音楽の運びの良さが魅力で、ところどころ歌唱箇所を歌詞対訳から見失っても、音楽だけで十分に楽しめたほど。それは、歌手どうしの呼吸がピッタリあっているせいでもありましょう。さらに、序曲と“雷鳴と雷光”の躍動感と高速度ゆえのスリル、これもたまりません。
交響曲では、どれもこれも平板に聴こえてしまい、私の志向に会わないCクライバーですが、このオペレッタは、文句無し。次は、“椿姫”に進みたいと思います。
|
|
|
“オリエント急行殺人事件”で示した絢爛なワルツの作曲者が、クラシック音楽の世界でどのような曲を聴かせてくれるのか興味津々でした。さて、この第一集のアルバム。結果、私のような純素人には、マリンバ協奏曲は難解(無調?十二音技法?)で“無理!”、他は、交響曲はとっつきにくさを覚えたものの、サマーミュージックなどはスンナリと溶け込むことができました。ジョン・ウィルソン指揮BBCスコティッシュOは好演だと思います。演奏にメリハリがあるので、程よい緊張感を持って聴くことができます。録音も、やや音が近めなものの、各楽器の音が明瞭に聴こえ立体感があり、オーケストラを聴く楽しさが味わえます。第2集と第3集に挑むか否かは、もう少しマリンバとシンフォニーに馴染んてから判断します。
|
|
|
ここ数年、エリック・コーツを聴くようになりましたが、この盤は、ジョン・ウィルソンがシンフォニックにまとめているので、一曲一曲をじっくり味わうには好適でしょう。オケ奏者によるソロもうまくて、シンフォニアOLには益々長短軽重さまざまな曲に挑戦し、我々を楽しませてもらいたいと思います。
|
|
|
盤歴45年ですが、オペラと声楽曲は“からっきし”です。しかし、デフィニションシリーズでバルビローリの「蝶々夫人」に触れて、初めてプッチーニの旋律美を堪能、そして、この「ヘンゼルとグレーテル」では、童話に基づくオペラの楽しさに浸ることができました。オケの演奏とドイツ語の歌唱と歌詞対訳を追っかけながらの忙しい鑑賞でしたが、クリュイタンスとVPOの美しく軽妙な演奏と歌手の上手さで、存分にこの名作を味わうことごできました。素晴らしい音盤の復活ですね。音は期待したほど鮮明ではありませんでしたが、古いEMIの録音にありがちな、くぐもったような音ではないので、星数を減じるほどではないと判断しました。
|
|
|
比較対象する盤をもっていないので、単なる感想に過ぎませんが、デビュー間もないバティアシュヴィリは、すべての曲を屈託なくノビノビと弾ききっているように思われました。弾かれる音もきれいです。さらに、ブラームスは節度ある甘さが、シューベルトは動静のメリハリの強さが、印象に残りました。録音も優れています。
|
|
|
早めのテンポながら、歌うところはしっかり歌い、盛り上げるところはグッと盛り上げる、トスカニーニもかくやというエラス=カサドのシューマン。ミュンヘンフィルも、弦は艷やかで惚れ惚れするし、管もしっかり鳴っていて、シューマン和声に呑み込まれていない。録音もホール感を捉えた奥行きある音で、良し。惜しむらくは4番、もっと大胆に振る舞っても良かったのではないかしら。
|
|
|
曲に対しても、演奏に対しても、とかく外野が喧しい音盤ですが、楽器にも音符にも全く通じていない私には、雄弁で立派な演奏と思えます。1970年前後のEMIの音らしく、とてもまろやかな音に録られていますが、もう少しクリアであれば、とも思います。
|
|
|
“春の祭典”は、世間評のとおりの快演でした。複雑なリズムを物ともせず、快速でこの難曲を捌くマルケヴィチの手腕は見事!の一語に尽きますね。60年以上前の録音とは思えない立体感があって鮮明な音も、快演の立役者と言えましょう。“ロメオとジュリエット”は、逆に、じっくりと明と暗の旋律を歌わせた好演。愛の主題?は、無理に歌わせようとすると、しつこさが勝ると思うのですが、マルケヴィチは、そう感じさせない加減の良さが、また見事。しかし、“胡桃”は、“花のワルツ”にカットが多すぎて、私の趣向に合いません。よって、星4つです。
|
|
|
鄙びてくすんだような音色のバックに、バティアシュヴィリの澄明なソロが歌う。私には、この音色のコントラストが面白くて、飽きずに聴くことができました。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲は苦手な曲なので、比較する盤はさほど持っていませんから、取り敢えず星4つにしておきました。ツィンツァーゼの曲も聴き易くて、私には掘り出し物でした。
|
|
|
新譜に恵まれないコッペリアとシルヴィアに加えて、ネーメ・ヤルヴィ得意の秘曲を1つ加えて、とても魅力的なドリーブの音盤です。Nヤルヴィの持ち味は、明るくてダイナミックなことと屈託の無さだと思いますが、それがドリーブにはピッタリです。
|
|
|
両曲とも素晴らしい演奏です。チャイコフスキーもシベリウスも、民族臭と西欧的洗練のバランスのとり方が云々される作曲家ですが、バティアシュヴィリの美音とバレンボイムの情熱の前では、そのようなことはどうでも良くなります。録音も素晴らしく、適度なホール感と響きの奥行き深さに惚れ惚れします。
|
|
|
スッキリとした響きですが、表現は濃厚で熱い。4曲とも、しっかりと彫琢されていると言えばよいのでしょうか、随所にティチアーティ独自の工夫が聴こえるのですが、それらは、聴き終えても違和感として残らない。確たる全体感あっての、工夫なのだと思います。先に聴いたホリガーの全集が、オーソドックスに聴こえるほど。録音も澄明です。
|
|
|
決して重い音ではないのですが、聴手の胸にはズンと響くショパンのソナタとリストの巡礼。とても馴染みやすい演奏に思いました。私は、前者も後者も、重い音で攻められたり、強い思いを主張されると、聴き疲れしてしまうのですが、小林愛実は、その点、見事なバランスをとっていると感じます。
|
商品詳細へ戻る