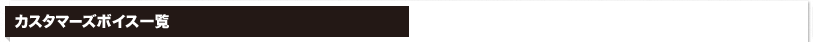
商品詳細へ戻る
いまちゃんさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
フェレンチクのネルソンミサはハンガリー国立交響楽団の音色がウイーンフィルを思わせるほどに美しくまた合唄のレベルも高い。あまり西側に出ることのなかったフェレンチクの再評価につながる名盤だと思う。この機会に昔買ってお蔵に入っていたハンガリーフィルとのベートーヴェン交響曲集を聴いてみた。購入当時の装置で再生できなかったヂイテールが聴きとれる。トスカニーニ流とだけでは分類はできない。第9番がお薦めできる。
|
|
|
ザンデルリンクのマーラー9番はベルリン響とフィルハーモニアのスタジオ録音とBBC響のライブ盤を所有している。今回の北ドイツ放響のライブは前評判通り暑い演奏であるが、ライブにかかわらず実に清澄な録音であり、細部まで各パートを聴くことができる。奇跡的なライブ録音である。マーラーの和声と対位法の到達点が不思議なことにバッハを感じさせるのも、他のザンデルリンクの演奏と共通していると思う。
|
|
|
この歴史的録音はニッポン放送の伝説的なエンジニア半田健一氏の功績を伝えるものである。こけら落とし公演の日生劇場であり経験がなかったホールでの一発勝負の録音でこれだけの物を残したのはすごい。録音機材についての記載もあればもっと良かった。1963年当時のノイマンのマイクとアンペックスのレコーダーという所かな。演奏でいえば独唱陣のすごさもあるが合唄団の上手さま驚く。オケは頑張りましたという所かな。
|
|
|
モ-ツアルトの22番はデームス若き頃の瑞々しい演奏です。指揮者のフランツ・パウル・デッカーは初めてですが、なかなかの実力者がいたのですね。問題作?である合唄幻想曲はフェルヂナント・ライトナーが指揮をすると安心して聴けますね。この曲の代表盤と言ッて差し障りないでしょう。
|
|
|
中学2年生の時にFMでこの演奏を聴きました。冒頭のティンパニーの強打には心底驚きました。なにせ初めて聴くブラームスでしたので、その後はさっぱり分からずに進みましたが「とてつもない曲である。極めずにはおかぬぞ。」と決心しました。今にして思えばこれが51年間の長いブラームス遍歴の始まりでした。
|
|
|
これは貴重な記録である。ザンデルリンクの2番のライブはこれしか無い訳であるし。日比谷公会堂のデットな音響のためディテールが良く分かる。1980年当時の読響が巨匠の指揮で必死なる演奏をしていることが興味深い。2楽章などはなかなか耽溺的である。ただ4楽章の演奏時間が16分となっているのはミスプリであり9分33秒程度であった。
|
|
|
これは大変な物が出てきた。今までザンデルリンクの4番は2種類のスタジオ録音で親しんできた訳であるが、このスェーデン放響とのライブは次元を超えた演奏である。これだけ耽溺的な4番は他には知らず、この曲の最高峰的な演奏と言って差支えない。録音も鮮明そのもの。カール・シューリヒトと並ぶ名演奏である。
|
|
|
1959年の録音ながらルビジュウムなんとかカッテイングのためか予想外に音は良い。1番は以前アルバン・ベルクQの旧盤を持っていたが、この演奏が私とは何とも相性が悪く曲のイメージまで損ねていた。今回のアマデウス盤でようやく1番の真価が判った。2番は東独のブラームスQの演奏を愛好しているが、アマデウス盤も好ライバルとなると思う。
|
|
|
今後ともテクニックでカール・ライスターを上回る奏者が出てくる可能性はあるが、音楽性で上回るのはなかなか大変ではないか。クラリネット協奏曲の可能性を不動のものとした名盤だと思う。もっとも新進気鋭の新人は常に出てくるもであり、コンサートの機会でもこの両曲は大いに注目していきたい。
|
|
|
ゲザ・アンダとクーベリックの相性の良さは抜群ですね。シューマンに関しては、ブレンデルとザンデルリンクの名盤と並び立つものだと思う。グリーグは正直他の演奏をあまり聴いてないのだが、この曲の最高演奏かもしれない。特に2樂章の夜霧が流れるような音色の美しさ素晴らしい。ドイツ・グラムフォンの栄光の時代ですね。
|
|
|
この4番は中学3年生の3学期に田舎の中学から東京の中学に転校。親類の家に下宿し都立高校を受験。合格。そうしたら壮絶ないじめに会う。などと14才の春の「背水も陣」が終わった時にアナログレコードで出会いました。1楽章の「老騎士の踊り」が自分の戦いを慰めてくれるかのようであり、もっと別の世界もあると言ってるかのようでした。ザンデルリンクの盤を入手した今も別格の1枚と言えるでしょう。
|
|
|
中学2年生の時に友人の家でアナログレコードで聴きました。第1楽章のホルンの音を友人が「なんだか牛の鳴き声みたいだ」と言ったのを覚えています。つまりは技術的には劣るハーグ・フィルから良くこれだけの演奏を引き出したという事です。3樂章の集中力も随一でしょう。 ザンデルリンクのライブ盤を入手した現在も別格の1枚と言えます。
|
|
|
この盤は24番が聴きたくて買いました。ケンプのピアノもさることながら、ライトナーの指揮も良いですね。自己主張はせずに曲をして曲を語りしめるというスタイルですが、カペルマイスターとはこういうものだったのでしょうね。22番のクラリネットも大変に美しいです。
|
|
|
この盤はクラリネット協奏曲が聴きたくて買いました。この名曲は何枚持っていても良いと思います。もっともミヒャリクの技術はカール・ライスターとは比べ物になりません。この盤はシュターツカペレ・ドレスデンとドレスデン・ルカ教会の音を楽しむためのものですね。
|
|
|
ワーグナーは貧乏大学生の頃、幸運にもライブで聴けました。実は当時付き合っていた裕福な彼女から別れの条件としてチケットをもらったのでした。それはとにかく当日の興奮がよみがえります。「火の鳥」はFMで聴きその濃厚な色彩に驚いたものでした。ヤナーチェクとコダーイは初めて聴きましたが、同じハプスブルク文化圏なのか共感にあふれていますね。
|
|
|
この盤はオーボエ協奏曲が聴きたくて買いました。この曲は室内オケのコンサートで聴いて虜になりました。この盤の伴奏は何とカール・ベーム指揮、ウィーン・フィル。何とお贅沢な。もっとも編成は室内オケ位の規模に聴こえます。トレチェックのオーボエもウィーンフィル仕込みで言うことはありません。
|
|
|
作曲者はベートーヴェンの第9を聴き同じような曲を作ろうとしたら、このような曲ができました。やはりメンデルスゾーンですね。グーテンベルクの生誕を祝した祝典で初演されたため、祝典的な雰囲気に満ちているのは良いのですが、時々、あまりのナイーブさに気恥ずかしくなることもあります。ライブでは一度アマチュアオケで聴いたことがありますが、演奏は難しくないのかな?
|
|
|
ブラームスは1960年と古い録音ですが、良い物は良いです。作品番号は交響曲1番の一つ前の作品ですが、別に兄弟曲ではなくむしろ対称的な世界を描いています。しかもブラームスらしいのですね。1番のようなごつごつしたところも無く、実にしなやかな曲ですね。
|
|
|
運良くこのライブは聴くことができました。日本人が好きな古き良きドイツのブラームスでした。低弦が良く鳴りました。特に2楽章ではステージの上に青白い稲妻が走ったような感じを受けました。でも、さすがにこのような感じはCDには入らないようです。思い出のCDとなりました。
|
|
|
大曲3番、4盤の次の曲ですので緊張して聴きましたが、実に肩の力が抜けた、晩年の明鏡な境地と遊びに満ちた曲でした。6番などは田舎旅行でもした気分になります。楽章を単独に聴くのであれば、5番は2楽章アダージョ、6番は4楽章アレグロでしょうか。グリュミオーが残した名盤です。
|
|
|
この偉大な両曲の決定盤と言えます。全盛時代のスメタナ四重奏団にヨゼフ・スークの第1ヴィオラとは歴史的組み合わせと言えるでしょう。美音を心ゆくまで楽しむことができます。ただ1976年のDENONの初期のPCM録音であるため少々電気臭いかなと言う気もします。
|
|
|
シベリウスの交響曲というものは決して「独立万歳」の曲ではなく、大自然の輪廻を描いた曲だと思います。その意味ではブルックナーが一番近い存在かなと思います。1974年のザンデルリンクの演奏を聴くと、1990年代以降のブルックナーの演奏に比べるとまだ特徴を出し切れていない感もあります。円熟期のライブ盤の発堀を望みたい所です。
|
|
|
ブラームスは好きですが、安心して聴けるヴァイオリン・ソナタ集といえば、このグリュミオー盤になりますね。陰影の濃い演奏ですが、実にバランス感覚が良いですね。ハンガリーのジェレジ・シェベェクのピアノ伴奏もこのCDを名盤としている理由だと思います。
|
|
|
このアルバムはLP末期に購入し、地の底から響いてくるかの音に驚愕したものです。ところがCD初期の盤は音が薄っペらでガッカリしたものです。今回のUHQCDによりどうやらLP時代の感動がよみがえってきました。ところでレーグナーは晩年に読響マチネーでオールフランス物を聴きました。それはそれで良かったのですが、最後まで実像が良く分からない人だという印象もあります。
|
|
|
ハイドンは面白い。フルトヴエングラーの演奏に比べ2楽章以外は皆遅いのに軽快に進んでいく感じがする。ブルームスは終大成ともいうべき演奏。特に終楽章は1990年のベルリン響盤に比べ40秒近く遅く、語り尽くしたという感じがする。ウイーン響とコンツェルトハウスの音も実に美しい。
|
|
|
39番は実に柔和な演奏。特に3楽章は冒頭からクラリネットを強く鳴らし、知る限りではベストな演奏と思われる。「田園」はフィルハーモニアの全集盤がやや生気が乏しい演奏であったため新盤を期待していたが、驚いた。テンポは更に遅くなり、ここまで来るともうブルックナーである。極めて特異な「田園」の出現と言って良いだろう。
|
|
|
ミサ・ソレムニスは1961年なBBCの放送録音ですが何とモノラル。無能なBBC官僚めと言いたくなりますが、まあ受忍すべき不利益でしょう。むしろホーレンシュタインがこの曲の録音を残してくれたことを望外の幸せとするべきです。録音はMaida Valeという歴史のあるスタジオで行われていますが、抽選で入場できた少数の聴衆を前にした公開録音のようです。
|
|
|
明快でエスプリの効いたジャン・フルネの指揮と、北国の空を思わせるオランダのオケの音色がこの曲の「立ち位置」を良く表していると思えます。あまり他の指揮者でも聴ける曲では無いのですが、この曲のトップのCDかもしれません。この曲はニキシュ指揮ベルリンフィルのパリ公演で演奏されて大ヒットしています。この辺が「立ち位置」ではないでしょうか。
|
|
|
モントゥーのブラームスは他には交響曲2番とヴァイオリン協奏曲しか無く、貴重な1枚です。32才のカッチェンの記録でもあります。1樂章は快走しますが、2・3楽章は良く歌い込まれています。リマスターも良好。録音会場のウォルサムストウ・アッセンブリーホールの音の美しさも特筆すべきだと思います。
|
|
|
まさに1960年代の超豪華メンバーを集めた協奏曲の名盤です。円熟味を増してきたフリッチャイの指揮振りも聴きもの。ベルリン放送交響楽団もベルリンフィルに遜色がなく、イエスキリスト教会の音色も見事です。このCDはシュナイダーハンの全集の一枚として作られていますが、このメンバーの中心にいることが良く分かります。
|
|
|
シューベルトは死の2ヶ前、交響曲「グレート」の後に作曲されていますが、この曲もグレートですね。チェロが2台でシンフォ二ックです。グリュミオーが親しい仲間達とさりげなく演奏しているようですが、室内楽の録音に歴史を残しました。ブラームスも単独では手に入りにくい曲なので、うれしいカップリングですね。
|
|
|
シューマンのレクイエムは、モーッアルトやフォーレに比べると残念ながらあまり華がありません。曲としては第2曲がシューマンらしい角があって良いかと思います。むしろ後半に収録されていえう「ミニョンのためのレクイム」の方が魅力的だと思います。ゲーテの作品を素材として、レクイエムの形式は全っく無視したドイツ語の合唱曲です。この方がシューマンらしいですね。
|
|
|
シューマンのヴァイオリン協奏曲は微妙な旋律と和声が移ろい、引き込まれて行きそうな曲である。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲に感動して短期間で書き上げた曲のようであるが、全ったくシューマンである。演奏も明るく鮮明な演奏である。何でヨアヒムが演奏拒否をして御蔵に入ってしまったのかな。1937年の初演はナチスに利用されてしまった。運の悪い曲か?
|
|
|
1番は美しい旋律を持つも、先人の古典派3人の引力圏の中でもがいているような感じがします。2番は難曲であり今回はコメントを避けます。さて3番になってようやくシューマンらしくなってきました。抒情豊かな名作です。ただ曲が盛り上がる同時に「やはりピアノが欲しい」とシューマンが叫んでいるような気がします。古典派との折り合いは難しいのか?
|
|
|
元々のクラリネツト・ソナタはライブで2番を聴いたことがありますが、ヴィオラでも演奏可とされており、どちらが優れているかという議論は必要ないと思います。ヴィオラ・ソナタで行くのであればヨゼフ・スークとヤン・パネンカのこの盤が現状では最高作だと思います。ブラームスファンには是非お薦めします。明るい気分と哀愁が入り混じった曲ですね。
|
|
|
1979年に東独を旅行したことがありますが、会場となった共和国宮殿はまだ建設中でした。こんな馬鹿でかい会場では思いましたが、音は完全に響き渡っています。演奏の熱いことは比類なく、ザンデルリンクのベートーヴェンの定評を得られたと思います。4楽章にいたってはフルトヴェングラー・バイロイト盤より2秒早いだけです。磁気テープ剥離が一部ありますが、これ位は我慢しましょう。
|
|
|
シューマンのヴァイオリン・ソナタ1番、2番とブラームスらと共作した珍しいFAEソナタ(3番)を収録した全集です。録音はイタリアの古い城で行われていえ、独特の温かい音色です。やはりシューマンの室内楽はピアノが入ると落ち着きますね。シューマンの情念が余す所なく表現された名演です。
|
|
|
この曲は以前、シュナイト指揮の神奈川フィルで弦楽合奏版を聴いたことがある。弦楽画合奏も一つの表現であるが、決してこの曲は「交響曲に成り損ねた大作」ではなく、室内楽として楽しむべき曲だと思う。弦楽5重奏曲としては、モーツアルト、シューベルト、ブラームスと並ぶ地位を占める曲と言って差しつかないと思う。
|
|
|
ザンデルリンクのベートーヴェンはブラームスほどの定評を得ていなかったが、この全集で定評を得たと思う。3,4,5番も素晴らしいが1,2番も実に美しい。さて3、4番は先行して国内盤を保有していたが、今回の輸入盤は音の粒立ちが良く奥域も深くなっている。デジタルでも輸入盤と国内盤で音質に差があることが判った。これは発見であった。
|
|
|
チャイコフスキーの4番はザンデルリンクにとって勝負曲という感じですね。ベルリン響の録音を買い損ねていましたので良い機会でした。記録ではザンデルリンクはレニングラードフィルやドレスデン・シュターツカペレとの来日時もこの曲を取り上げています。ウイーン響は相性は抜群であり、大いに楽しめました。
|
|
|
ブラームスの若き日の管弦楽曲、セレナード1番、2番が収録されているのがうれしいですね。1番は私にはややもすると、ハイドンの交響曲104番「ロンドン」のように聴こえる時があります。若きブラームスがハイドンを学んだのでしょうか。指揮者のハインツ・ボンガルツは東側にいたため知名度が低いですが、もっと再評価されるべきでしょう。ヘルビッヒのハイドン・バリエーションも良いです。
|
|
|
ブラームスのPCON1番などと言いますと、冒頭は青年期の暗い激情を表すフォルテイシモに身構えるものですが、ザンデルリンクの冒頭は実に柔らかい響きで、まるで別の曲のようです。エレーヌ・グリモーのピアノとも良く合い、ヒューマンな演奏が進んでいきます。これでライブであるというのも驚きです。ザンデルリンクはブラームスのPCON2番は残していないため、貴重な記録ですね。
|
|
|
1976年のベルリン響とのCDは保有しておりますが、やはりライブが聴きたくなります。マーラー9番と並びザンデルリクが晩年までレパートリーとしていた曲であり、名人が揃ったスゥエーデン放送響との演奏は実にスリリングです。他にもライブが残ってないかなという気持ちにもなります。
|
|
|
20世紀を代表するベルクの名曲ですが不思議と良いCDが無く、おなじみのグリュミオーで購入してみました。実にバランス感覚が良く中庸を極めた演奏です。また伴奏がイーゴリ・マルケヴィチ ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とは懐かしくも幸せな気分になる演奏ですね。 1966年の録音です。
|
|
|
1990年の読響としては渾身の演奏となっています。サントリーホールの響きも美しい。ハイドンは実に面白い。ハイドンを再認識させてくれます。18番のブラームスも記念碑的な演奏ですが、特に終楽章に盛り上がりは凄まじく、さすがライブです。この日の演奏に接することができた人達は幸せだったでしょうね。
|
|
|
実に格調の高い演奏であり、両曲の決定盤と言える。スメターチェクのCDは他に「わが祖国」と「ペールギュント組曲」しか所有しておらず、録音が少ないのが残念である。放送録音などは存在していると思うし、是非、他のレパートリーも聴いてみたいと思う指揮者である。
|
|
|
サンデルリンクの貴重なライブですね。会場のSWRベートーヴンエンザールというのはかなり巨大なホールのようですね。木管やハープなどは近接マイクで美しく音が取れていますが、弦はマイクからの距離が遠く細かいニュアンスがつかみかねる所は残念です。正規のスタジオ録音が存在しない以上、再生に工夫して愛聴するしかないと思います。
|
|
|
この曲の既存のイメージを変えてしまうような名演ですね。異次元の透明感と不思議な静けさに満ちた演奏です。金管のフォルテシモが少しもうるさくありません。また録音の分離も見事。白眉は2楽章のヴイオラと木管の美しさですね。3楽章、4楽章も少しも長さを感じさせません。「ロマンティク」というのは随分と漠然とした概念ですが、人間の深層心理に関するものかという気までしてきました。
|
|
|
70年代のドレスデン・シュターツカペレの全集は万人向けのリファランスという性格を持つが、ベルリン響との全集は透明感が増し、テンポはほとんどの曲がフルトヴェングラーの残したライブ盤より遅くなっているのに、全っくひっかかる所が無く美しく流れる音楽となっている。ブラームス全集の最高峰と言って良いと思う。
|
|
|
リマスターが優れ「異次元」の透明感を持った演奏である。対位法、多声法を極限まで駆使し調性音楽の限界に到達したといわれる曲であるが、ザンデルリンクのこの演奏は不思議なことにバッハを想起させる。1910年の作品なのに西洋音楽の不思議な歴史を感じさせる演奏である。
|
商品詳細へ戻る