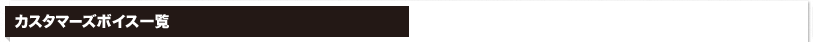
商品詳細へ戻る
カツドンさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
ピリオド楽器の演奏でありながら(だからこそ?)フレッシュな感性と、ついつい必要以上に重くなりがちなこの曲の演奏とは一線を画す立派な演奏。ジャケットのイメージそのものだ。
|
|
|
このグループらしい流麗でありながらも心のこもった音楽が聴ける。モーツァルト初期のカルテットがここまで立派に演奏されることもそうあることではないように思う。
|
|
|
仮にこれが作曲家が意図した響きであったとしても、正直、聞き耳を立てるような深さがないように思う。
|
|
|
古色蒼然として、テコでも動かないような強靭さをもったハウゼッガーの世界観を知るには良いCD。
|
|
|
「自分のものだけにしておきたいような秘曲」と言ってよさそうな佳作集。特に真ん中の収録された小品集が心象風景を映し出すような趣があって聴き入ってしまう。
|
|
|
ボッシュのドヴォルザークはエネルギーとロマンティックな表現がうまくミックスされたもの。普段あまり耳を傾けることが多くないこの作品も単調さに落ちることなく、立派な交響曲として聴かせてくれる。
|
|
|
北欧の音楽とブルックナーが折衷されたような音楽。少々胆汁質なのはニールセンとも共通するところか。
|
|
|
ワーグナー、R.シュトラウスが好きならば一度は耳を傾けてもいい作曲家。「夜に寄せる3つの賛歌」が秀逸。
|
|
|
普段着のドイツ・ロマン派。シューマンやブラームスと比較すればそれはいろいろと言いたいことも出てこようが、懐の深い落ち着いた色調の音楽は聴いていて和むことは確か。
|
|
|
「メタモルフォーゼン」の鋭さと深みを持った表現が秀逸。このコンビによる一つの到達点のように感じられる。
|
|
|
この組み合わせによるモーツァルトは先鋭的だと感じさせる部分と温もりを感じさせる部分がうまく両立していて、モーツァルトのピアノコンチェルトを聴く喜びを噛みしめることができる。録音も優秀。
|
|
|
このシリーズの中では若干マイナーな選曲だが、演奏は相変わらずフレッシュ。演奏する喜びに溢れ聴き手を釘付けにする面白さがある。
|
|
|
「安かろう悪かろう」の概念を覆すコスパ抜群の名盤。これを聴いてこの団体の管弦楽組曲全曲の録音を望みたくなった。
|
|
|
まずこのジャケットに目を奪われる。そしてジャケットから受けるイメージ通りの温かく親密な小部屋をのぞくような愉しみを与えてくれる演奏。ハイドンの疾風怒濤期の名曲がこびりついたイメージから離れ演奏される素晴らしさを実感できる。
|
|
|
この3曲をこの編成で聴くことはモーツァルト好きには密やかな楽しみと言えるべきものだが、ピリオドで演奏されることにその凛とした姿がより強調され、耳を洗われるような感覚が広がる。
|
|
|
どんな曲を演奏してもライプツィヒSQの流麗な演奏は一本筋の通ったものだが、モーツァルトの初期SQを演奏すると、これらの曲が決して初期の曲と軽んじる作品でないことがあからさまになる
|
|
|
本来2声で歌われるのを一人でこなすという離れ業が離れ業と感じさせないほど自然で、かえって曲の良さを素直に表出した演奏。ノットはガッティの代役だったわけだが、初ウィーン・フィルをしっかりとトライブしている。
|
|
|
この曲はブルックナーの生前は改訂版でしか演奏されなかったが、もし原典版で演奏されていたのならこういう演奏ではなかったのだろうか?と想像をさせてくれる演奏。「ブルックナーをピリオドで?」と思う人こそ素直に耳を傾けるべき演奏。
|
|
|
若いながらも老練な音楽を聴かせるというイメージがインキネンにはあるが、このブラームスもそれに当てはまる。しかし、ただスタイルが古いわけではなく、そこに清新さもあり、まさにブラームスの1番そのものが持つキャラクターをうまく表現した演奏。
|
|
|
マーラーだったからと言って決して大上段に構えず、自然体で臨んだ演奏。テノールとバリトンの組み合わせもノットの演奏に合っている。ウィーン・フィルとの演奏と録音時期は近いが、面白さはともかくオーケストラとの共同作業としてはこちらのバンベルク盤が勝っていると思われる。
|
|
|
ネルソンの清新さとゲヴァントハウスの堅固さが高次元でバランスされた演奏。ノットのそれと並び今最も新しいブルックナーと言えるだろう。全集化が楽しみだ。
|
|
|
モダン、ピリオド拘わらず、この2曲の四重奏曲を「これぞ」という盤で聴いたことがなかったが、初めて納得した演奏に出会った気分。演奏するのは思いのほか難しい曲のように思うが、それを感じさせないばかりか、今まで気が付かなかったこの曲の深さを感じることができる演奏。
|
|
|
MAKの1回目の録音と較べると良い意味で加齢による円熟があるが、精神は決して老けていないところがミソ。安定した演奏から繰り出されるあの手この手にうれしくなってしまう。
|
|
|
総体的にテンポは遅め。しっかりとしたつくりではあるがしなやかさを併せ持つ。シューマンでもピリオド・アプローチを多く聴くようになったが、だからと言って存在価値が下がる演奏ではない。MTTの若さを感じることができる演奏。
|
|
|
巨匠の安定した堅固かつ柔軟な演奏ではあるが、刺激はない。様々なブルックナーの表現が増えてきた昨今、有難く耳を傾けるべきものか?と思わないわけでもない。
|
|
|
これまでの6番、4番がよかったので期待していたが、録音のせいがあるかもしれないが多少とっ散らかった演奏に聴こえてしまう。生で聴いた方は感動の嵐かもしれないがCDとしての完成度は意外と低いのではないだろうか。
|
|
|
良くも悪くも小型ベルリン・フィルの演奏。大柄でマッチョな演奏は決してシューベルトには似つかわしくない。「これくらいのこと全然できるんだよ、僕達は・・・」的な言い分を感じるような演奏。聴いていて痛快ではあり耳は豊かになるが、果たしてそれでよいのか?という気にもなってくる。
|
|
|
これまでの3曲が腑に落ちる演奏だったので、第1番もある程度想定内の演奏だったが、何もしていないようで実は丁寧な目線が感じられる演奏。また一つのスタイルを確固と持った演奏ともいえる。
|
|
|
M.シュテンツ盤に続き初演を行ったオーケストラによる演奏という点も重要だが、ロトのセンス、実力を発揮できるレパートリーとしてのマーラーという点で興味を持たざるを得ないCD。決して重たくはないが、隅々までに感性の行き届いた演奏と言えるだろう。ジャケットのセンスが演奏とも共通している。
|
|
|
「斬るか斬られるか」を聴き手に迫るような表現主義の究極的演奏だが、ゾクゾクする感覚は何にも代えがたいもの。スピーカーではなくヘッドフォンやイヤフォンで聴くとその感覚はより鮮明となる。
|
|
|
この作品の純度を極限まで高めて表現した演奏。何の仕掛けもなくここまでこの巨大な作品を聴き手に押さえつけることなく聴かせるのは大したこと。日本のオーケストラがここまで立派なブルックナーを演奏できることを誇りに思う。
|
|
|
この世の演奏にはそれぞれの良さがあり、「これ1枚だけ持ってれば・・・」という事はあり得ないと思っているが、この全集は「これだけあれば他のベートーヴェンの交響曲はいらない」と思ってしまうほどの説得力がある。「これを凌駕するものはない」と敢えて言ってしまおう。
|
商品詳細へ戻る