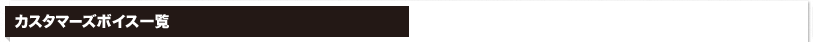
C.P.E.バッハ:マニフィカト/クリスマス・カンタータ 他 / ミヒャエル・アレクサンダー・ヴィレンズ、他
|
|
C P E Bachのマニフィカートは、数ある中でも名曲中の名曲だろう。特に最終楽章のフーガは恐らく彼の自信作であり、改定を重ね、Die Auferstehung unt Himmelfahrt Jesuのようなオラトリオでも歌詞等を変更して使っている。父親のゼバスティアンは、BWV243(a)のマニフィカートではSicut eratの部分にフーガを使わなかったが、G.B.サンマルティーニやハイニヒェン等、多くの作曲家達がそうしたように、彼もここにフーガを用いた。それは、コーダで一転してフランス序曲風の伴奏にリズムを変えて歌われるGloria Patriにより導入される。4声部の合唱に金管やティンパニ、オルガン付きのオーケストラのついたこのニ長調の壮大な2重フーガは、例えば古典派のヨーゼフ・ハイドンに見られるような、2つのテーマを同時に繰り出す形式ではなく、第1のテーマを提示・展開してから第2のそれを提示・展開し、2つを結合してさらに発展させていくという、後期バロック的な手法を用いて楽想を拡張している。それ故に、このフィナーレだけでも充分過ぎる程の聴きごたえがある。カップリングされたクリスマスカンタータの方も、彼のお気に入りの素朴で美しい曲だ。
0
|
商品詳細へ戻る
Antonioさんが書いたメンバーズレビュー
|
|
レオナルド ヴィンチはポルポラやレオと並び称される初期ナポリ派の主要かつ典型的な作曲家で、その創作活動は専らイタリア各地の劇場でのオペラ上演に向けられていたようだ。所謂Sinfoniaによる導入やメタスタジオの台本、カストラートにより巧みに歌われるダ・カーポアリアは定番としても、インテルメッゾにでもありそうなしゃれたパッセージや要所での活力のある起伏に富んだ勇壮な旋律、シンプルながら効果的なオーケストレーション等、彼の才能は正に劇場向きであり、そこにはバロックオペラのスペクタクルな劇的要素が余すところなく盛り込まれている。最近は、棄てられたディドーネ、ポーランド王ジスモンド、ウティカのカトーネ、アルタセルセといったオペラの全曲盤が斬新な解釈で次々とCD化され、その音楽の素晴らしさが再認識されている。Siroe Re di Persiaは1726年にヴェネツィアで初演された。台本はメタスタジオによる言わば愛憎劇で、忠誠と背信の狭間で葛藤するシロエや、最後はすべてを赦す寛大な父王の姿が描かれている。周知の通りメタスタジオのベストセラーの台本の一つであり、ハッセやヘンデルも同じ台本を使って作曲していて興味深い。第1幕のMedarseのアリア Fra l’orror de la tempestaは、嵐のイメージを波型の音型で描く一方、星の光や幸福をメロディアスに伝えている。第2幕のSiroeのMi credi infeliceは前期ナポリ派のこの手の典型的なアリアのイメージだ。第3幕のフィナーレ直前のMedarseのアリア、Torrenteは、ヘンデルのそれと比較すると面白い。ヴィンチのアリアは、フレーズの節回しの多いヘンデルのそれよりも奔流感は少なめだが、寧ろ心地よく流れる渓流といった雰囲気があり、テンポを落としての中間部の清涼感もまた印象的だ。
0
|
|
|
ゼバスティアン バッハやヘンデルの父親に当たる世代に属しながら、息子達の時代の音楽の流儀をも使い、持てる作曲技法のすべてを注ぎ込んで先鋭的なスタイルに仕上げたスカルラッティ最晩年のオペラがこの作品だ。全曲盤のCDとしては、20世紀の古い音源ではでミレッラ フレーニが、21世紀に入ってからはヤコブスの指揮でドロテア レシュマンがタイトルロールを歌った名演が残されているが、このDVD/CDもこれらの系譜に続いて、新たな金字塔を打ち立てる演奏になっている。冒頭に置かれたシンフォニアは典型的なイタリア式序曲の形式で書かれているが、後のナポリ派のそれよりも遥かにドラマティックで、作品の世界観を音楽で想起させる作りになっているように思われる。第1幕第6場のロベルトの勇壮なアリアCome, presto nel porto crudele は、当時のオペラによく出てくるアリアの一形態で、言わば「嵐の中の航海のアリア」だが、メロディに勢いが感じられて思わず歌いたくなる。第2幕第4場の、オットーネとの長いやり取りの後のグリゼルダのアリア Figlio! Tiranno! の、いかにもスカルラッティらしい切実な感情の伝え方が聴ける。過酷な謀略に翻弄される自分の運命を嘆きつつ眠りに落ちるグリゼルダの第2幕第10場のアリアfinira, Barbara sorte は抒情的で美しく、伴奏する澄み渡ったフルートの音色も心に染みる。スカルラッティの声楽作品は、いわばその「世界観」を捉えることはなかなか難しいが、個々のアリアを取り上げると、初期のナポリ派と比べてもはるかに純粋で歌いやすく思える。
0
|
|
|
Fredegunda は、5幕の音楽劇として1715年にハンブルクで初演された。彼が既に広く名声を得ていた壮年期の代表作である。台本は、イタリア語のそれを、一部を除いてドイツ語のリブレットに落とし込んだものが使われている。内容は要するにフランク王国の王位継承の逸話に基づく愛と謀略と権力闘争の物語だが、この時代のオペラの特徴で、ストーリーは込み入っている。カイザーと言えば、所謂独・伊語の折衷様式の使い手として知られるが、幾つかのオペラを聴くと、まさに劇場向きの音楽家であったことがわかる。彼はジンクシュピールの多作家でもあり、オペラでは台詞をある種レシタティヴォ化して使っているように思われる。そのためか、レシタティヴォの割合がナポリ派等のオペラよりも多い。器楽の伴奏はさすがに後代のそれと比べるとやや単調だが、場面に合わせた多彩な曲調のアリアの数々は、「歌の皇帝(Kaiser)」に相応しい特色の一つだ。メロディラインは晩年には後の世代のそれに近くなり、時にヴェネツィア風のフレーズが出てきたり、殆どヘンデルに聴こえたりするアリアもある。また、フランス的な要素が多めなのも特徴で、これはリュリの弟子だったJ S Kusserのオペラを見慣れていた当時のハンブルクの聴衆の好みによるものかもしれない。このFredegundaの冒頭のソナタは実質的なSinfoniaで、最初のファンファーレ風のフレーズはいかにも彼らしい。第1幕のGalsuindaのアリアLasciami piangereはヘンデルの「リナルド」のLascia ch’io piangaを想起させる。Fredegundaのアリアに着目すると、第2幕のIre reizende Blickeは歌詞そのままにとてもチャーミングだ。第4幕のヴァイオリンのオブリガートの付いたVieni a me dolce oggettoは哀しくも美しい。
0
|
|
|
ミュンヘン宮廷のホフカペルマイスターだったアンドレア ベルナスコーニは、一説によれば一時期、ヴィヴァルディ亡き後にピエタのマエストロ ディ カペラを務めたと伝えられているなど、前任のジョヴァンニ ポルタ同様、ヴェネツィアと関係が深かったようだ。とは言え、マルセイユ出身と言われているにもかかわらず、彼のオペラの作風は、専らナポリ派の影響下にあると考えられており、事実オリンピアーデやデモフォンテといった、言わばメタスタジオの定番の台本をよく使っている。「L’Huomo」は、L M Stampigliaのリブレットによるが、皇女ヴェルヘルミーネによる校訂があり、カヴァティーナは彼女により書き加えられている。彼が恐らくまだ副楽長だった頃の1754年に初演されているが、その時に幾つかのアリアが歌手たちによって差し替えを求められたという。このオペラの印象はナポリ派に近く、例えばアリア Caro Padreを聴くと、少なからずハッセの影響が感じられるし、作品の来歴からもそのことは知れる。実際、Tergi quei vaghi raiやQuando congiunge Amoreは、当時人気の高かったハッセやガルッピのオペラからの引用だ。当時の聴衆のように、彼らの音楽に慣れ親しんでいれば、この作品も聴きやすいのではあるまいか。
0
|
|
|
グラウンは生まれも育ちも北ドイツで、本国でオペラを作曲後、3年程ボローニャで就学したと伝わる以外は、イタリアそれもナポリ派のオペラとは余り多くの関係を持てていなかったようだ。(もし、オルランディーニに師事したことが事実であれば、弦のフレーズの細かい動きに彼からの影響が窺われる感じはする) にもかかわらず、フリードリヒ大王の下でホフカペルマイスターに就任すると、新築されたイタリアオペラ向け宮廷歌劇場のために、ナポリ派仕様のオペラを短期間で数多く書いているのは驚きだ。当時はベルリンでもナポリ派の全盛時代で、オペラの歌詞は当然イタリア語で歌われた。「Silla」の台本はフリードリヒ大王が自ら作成したが、王はフランス文化に傾倒していたが故に、ドイツ語ではなくわざわざフランス語で書いた。オペラでは、そのフランス語をイタリア語に訳して使っているのは興味深い。グラウンというと、例えば雄渾で華々しいParto qual navigante(Cleopatra e Cesare)や、Mi Spaventi il indegno(Britanico)のような、カストラート等の歌手たちに、コロラトゥーラの名人芸を要求するスケールの大きなアリアが真っ先に思い浮かぶ。オペラの冒頭に置かれるSinfonia もアリア同様に、伴奏やオーケストラも起伏の激しい多感的なフレーズやスピード感のある走句が多い印象だ。キャリアの後期に作曲されたこの「Silla」でもそれらの特徴は健在で、第2幕のCrisogonoのアリアInvan mortale arditoはその手の典型的な例だろう。第3幕のOttaviaのIn questo amplesso un pegnoでは、競合関係にあったハッセの同種のアリアの情感表現とはかなり異なる印象の、グラウン独自のそれが示される。加えて、第1幕のLenturoの Ah si cimento un corやOttaviaのSol nel caro amabil voltoは、彼のアリアのフレーズやリズム上の特徴が良く出ているように思われる。
0
|
|
|
ヴェネツィアには、そしてヴィヴァルディにはセレナータが良く似合う。なかでも多く聴かれているのがLa Senna Festeggante(RV693)とMio cor,povero cor(RV690)の2作とこの作品で、いずれもオペラ程の規模の大きさはないが、元来王侯貴族を対象にした祝賀行事のための祝典的な曲目だから、相応の豪華さや壮麗さを備えている。フランス風のシックでファッショナブルな雰囲気を感じさせるお洒落な曲調もあって、彼の声楽曲のファンならばいずれもお気に入りになること請け合いである。この作品は1725年、彼の創作の絶頂期に書かれており、聴き手の感性に訴求する熟達した作曲技法が随所に示されている。例えば、彼にしてはテンポを抑え気味にして、憂いを漂わせたイメネオのアリア、Tenero fanciulettoは個人的にお気に入りで、随所に現れる感傷的なフレーズや小節間でのリズムの変化、控えめな音程の飛躍が効果的で、聴いていて思わず心を奪われる。加えて、前年に作曲されたオペラ「ジュスティーノ」との関係が指摘されるアリアやデュエットもあり、聴きどころは多い。このCD以外の彼のセレナータにも、ヴェネツィア娘のたわいのないお喋りをそのまま音楽に差し替えたようなVorresti lusingarmi(RV690)や、フレスコ画に描かれた、嵐や雲に立ち向かう神話の巨神のようなスケール感のあるL’alta lor gloria immortare(RV693)等、聴いたり口ずさんだりして楽しいアリアがたくさんある。
0
|
|
|
現在のトスカナ州ルッカ近郊出身のガスパリーニは、ヴェネツィアやローマで要職を務めたが、そのオペラはイタリア以外でも幅広く称賛されていたという。また、ピエタではヴィヴァルディの前任のマエストロ・ディ・コーロであったこと、現地ではミケランジェロ・ガスパリーニと共に兄弟で教師として学生の育成活動に当たったことが知られている。CD化されている作品は少ないが、後期に作られたこの作品に加え、Lucio Vero(1719)やAmblete(1705)等のオペラアリアや、世俗的なカンタータ等の声楽曲を聴くことができる。この作品は最初「タメルラーノ」として1711年に初演されたが、「バヤゼット」に改名した版は1719年に初演されている。人気のある台本だったのか、ヴィヴァルディ等も後年、同じタイトルでパスティッチョを作曲しているのは注目に値する。冒頭のsinfoniaはスカルラッティ等の世代に近い書法で書かれているように思われるが、所々後のヴェネツィア派風のフレーズも聴かれる。アリアは特色のあるものが多い。Dolce e L’amorや La Vioretta (ともに第1幕)の歌唱部分のメロディラインはアルビノーニのそれを想起させる。あのファウスティーナ ボルドーニが19歳の時に担ったというイレーネの、Vieni ,vora (第1幕)は、シチリアーナ風のリズムで歌われる美しいアリアだ。また、伴奏では、オーボエやフラウト等様々な楽器が場面場面で入れ代わり立ち代わり使われている。Non e si fido il nido (第3幕)のダ・カーポ部分の撥弦楽器だけの伴奏は効果的だ。Vendetta si,(第1幕)やNo non disende no(第3幕)を聴くと、書法や旋律こそ世代の違いを感じさせるものの、ある種、ヴィヴァルディと同年代の作曲家以上に、彼に通じる生気や新奇性があるように思われる。
0
|
|
|
C P E Bachのマニフィカートは、数ある中でも名曲中の名曲だろう。特に最終楽章のフーガは恐らく彼の自信作であり、改定を重ね、Die Auferstehung unt Himmelfahrt Jesuのようなオラトリオでも歌詞等を変更して使っている。父親のゼバスティアンは、BWV243(a)のマニフィカートではSicut eratの部分にフーガを使わなかったが、G.B.サンマルティーニやハイニヒェン等、多くの作曲家達がそうしたように、彼もここにフーガを用いた。それは、コーダで一転してフランス序曲風の伴奏にリズムを変えて歌われるGloria Patriにより導入される。4声部の合唱に金管やティンパニ、オルガン付きのオーケストラのついたこのニ長調の壮大な2重フーガは、例えば古典派のヨーゼフ・ハイドンに見られるような、2つのテーマを同時に繰り出す形式ではなく、第1のテーマを提示・展開してから第2のそれを提示・展開し、2つを結合してさらに発展させていくという、後期バロック的な手法を用いて楽想を拡張している。それ故に、このフィナーレだけでも充分過ぎる程の聴きごたえがある。カップリングされたクリスマスカンタータの方も、彼のお気に入りの素朴で美しい曲だ。
0
|
|
|
ハッセは今日でこそバッハやヘンデルの陰に隠れて知名度が低いが、彼はまぎれもなく18世紀前半のヨーロッパの楽壇の中心的存在であり、その名声は古典派の時代にまで及んでいた。ナポリやヴェネツィア、ドレスデンやヴィーン等、各地に招かれて要職を務めるなど、彼程の成功を収めた作曲家は、他にはいないだろう。時代の王道を歩んだが故に批判に晒されたこともあるものの、新たな時流への適応も怠らなかった当代随一の偉大な作曲家であったことに疑いはない。彼の音楽の核心はナポリ派様式の所謂オペラセリアにあるが、インテルメッツォやミサ曲をはじめとしたラテン語の宗教音楽の傑作も数多く残している。オペラをはじめとする世俗的な声楽曲では、やはり、繊細な装飾音を伴う異国情緒に満ち溢れた珠玉のアリアの数々が聴き所になるだろう。ピラモとティスベは2幕のインテルメッツォ トラジコであるが、実質的にはオペラであり、例えば第1幕のアリア Perdero amato beneは、ギャラントな香りを残しながらも、もはや古典派と言ってよい曲調を持つ。各アリアの速度指示が非常に繊細なのも特徴的だ。また、ハッセのお好みのパッセージが随所で聴かれるものの、要所では旋律に暗示性や象徴性を持たせているようにも思える。通奏低音の伴奏だけではなく、レシタティヴォ アコンパニャートも効果的に使われており、これらの点がハッセ晩年の作品の特色を表しているといえる。
0
|
|
|
アントニオ ロッティは現代では専ら教会音楽の作曲家として知られており、神秘的なクルチフィクススやヘ長調のレクィエムが有名だが、ヴェネツィア派の系譜に属するだけに、ドイツとりわけドレスデンと関係が深かった。本国でオペラ作曲家として活躍した後は、ザクセンのアウグスト強王のイタリアオペラ楽団の創設に深く関わり、そこで多数のオペラを作曲している。そのため、ハプスブルク家に仕えたアントニオ カルダーラ等と同様に、神聖ローマ帝国各地の音楽家に与えた影響も大きかったと思われる。1719年にドレスデンを離れてからは、亡くなるまでヴェネツィアに住み、晩年はサン マルコのマエストロ ディ カペッラとして教会音楽の職務に専念し、多くの弟子達の指導・育成に当たったという。彼の世俗的作品にはアルビノーニやヴィヴァルディ等に通じるものがあり、器楽曲にも所々にそういった傾向が見られる。このCDは、現状では彼の世俗的な器楽曲と教会音楽の両方が聴ける数少ない音源だと言えよう。冒頭のGiove in ArgoのSinfoniaは、このCDに採り入れられた作品の中では比較的早い時期に作られたものだろう。Dies iraeはレクィエムから抜粋されたものだ。序奏部は荘重で聴きごたえがあり、続く合唱と共に葬儀に相応しい雰囲気を醸し出している。
0
|
|
|
この作品は1715年ローマでの初演後、1720年のロンドンでの彼のデビューに当たり、改作されたものだという。セネシーノやドゥラスタンティといった当代きっての歌手陣のために、調性からオーケストレーションに至るまで細かく手が加えられているという。彼の作品には重厚さは余り感じられないものの、どれも繊細で気品があり、全体的にこぎれいにまとめられている。恐らくA スカルラッティよりは後、ヘンデルよりも少し前の世代の技法で作曲していると思われるが、シンプルさを生かした優美なフレーズが多い。ナポリ派のそれとは異なり、アリア自体もカデンツァも、どれも時間的に短いので聴きやすい印象がある。また、彼はオペラではOvertureをよく使ったが、その割には単調になったり、重々し過ぎてもたれたりすることがない。コレルリ風のパッセージが織り込まれたりしていて、時にコンチェルトグロッソのような曲調にも聴こえ、明るさや華やかさの点では他の作曲家のそれをも上回ると言えるだろう。バロックオペラの抜粋版CDでも聴くことができる第1幕のフェニチオ(バス)のアリア、Si Periroは音階を登ったり降りたりしながら軽やかに歌われる。個人的にはニーノ(ソプラノ)のアリア、Mi da crdel tormento(第2幕)やL’esperto nocchiere(第3幕)等に彼の特徴が良く出ているかと思う。
0
|
|
|
声楽教師として多くのカストラートを育てたポルポラは、ナポリに生まれ、ヴェネツィア以外でもドレスデンやウィーンで要職に就いた。ヘンデルのライヴァルとしてロンドンでも活躍した、当時広く名の知られたナポリ派の作曲家である。室内カンタータに優れた曲があり、教会用の作品もあるが、創作の中心となるのはこの時代に共通するゼーノやメタスタジオ等の台本を使ったオペラセリア(Dramma per Musica)であろう。最近の研究により彼のオペラは見直されてきているようで、ジェルマニアのジェルマニコやナッソーのアリアンナといったロンドン時代の作品の全曲が次々とCD化されている。これらの作品は、土地柄もあってか、冒頭の序曲がナポリ派風のSinfoniaではなくヘンデル風のOvertureで書かれている。ポルポラのオペラやカンタータのアリアには、彼が手塩にかけて育てたカストラート達の持つ声楽の技量を最大限に発揮させるためなのか、特定の音型を反復・転回しながら延々と伴奏していくという特徴がある。この傾向は、同時代の他のナポリ派の作曲家達に比べても顕著だと思う。それが各場面であるときは絵画的な、あるときは劇的な効果をもたらしており、作品に様々な表情を与えている。ポリフェーモの物語はロンドンで人気が高かったのか、彼の他にもヘンデルやボノンチーニ等が題材に取り上げているので、聴き比べてみるのも面白いだろう。
0
|
|
|
ヴェネツィア生まれのカルダーラは北イタリアの音楽環境下で頭角を現したが、同郷のツィアーニの後任、フックスの下で長くハプスブルク家の副楽長を務め、後半生をヴィーンの宮廷の音楽の発展に捧げた。ラテン語の典礼音楽、オラトリオ等の宗教曲は、対位法の理論家でもあったフックスの影響もあってか、どちらかというと一時代前の書法で作られているように見えるが、時流に乗じたオペラやカンタータ等の世俗声楽曲や器楽曲も多数残している。中でも、メタスタジオの有名どころのオペラの台本の数多くが、1730年代に彼によって初演されているのは特筆すべきだろう。彼のオペラの特徴を一言で言い表すのは難しいが、恐らく、楽曲を形作る要素の多様性であり、それによりヴェネツィア派の画家達の作品を想起させるような色彩感がもたらされる気がする。結果として同世代の主要な作曲家達の好んだ音型や旋律と似ているようで似ていない、彼独自の音楽が立ち上がってくる印象を受ける。こういった特徴は恐らく楽派のそれとして後のコンティやロイター等に受け継がれていったに違いない。このCDで聴けるLa Clemenza di TitoのアリアSe mei senti sperartiはハッセの、 L’olimpiadeのアリアLo seguitai feliceはヴィヴァルディの同名の作品のそれが出回っている。いずれの作曲家も彼より下の世代になるが、各々の個性が際立っており、聴き比べてみるのも面白い。
0
|
|
|
トイヘルン近郊のクロスルンにあるハイニヒェンの生家跡には小さな石碑があり、その項目にはまず最初にドイツオペラの巨匠と記されている。彼は広くオペラの作曲家として知られていた。現在完全に残されているものだけでも5作品が知られているが、現状聴けるものはフラーヴィオ クリスポだけだ。彼のオペラの比較相手を探すなら、ステファニやグラウプナーよりはやはり同郷のヘンデル、もしくはヴェネツィア派の作曲家達が相応しいだろう。二人はハンブルクのオペラハウスと関係を持ったこともあり、この時期のオペラにはまだカイザー風のフレーズやカデンツが出てくるものの、 このフラーヴィオ クリスポを聴くと、ハイニヒェンだけはヴェネツィア風のフレーズが遥かに多い印象だ。これは一つにはロッティがドレスデンでこの時期、最後の4つのオペラを上演していることと関係があるかもしれない。また、ハイニヒェンはヴェネツィア滞在中に自作の作品を上演しただけでなく、ポッラローロやアルビノーニ、恐らくヴィヴァルディの初期のオペラを聴いたり、評判を耳にしたりする機会があった筈だから、影響下に置かれたことはあり得るだろう。彼のアリアは、例えば華々しい名人芸を要求するヘンデルのそれよりは、同等のスキルを持ってしても、どちらかというとフラットな色彩感で仕上げて耽美的に歌わせる要素の方が強いように思われる。フラーヴィオ クリスポは実質的に彼の完成された最後のオペラであり、以後は教会音楽家としての道を歩んで珠玉の典礼作品の数々を残すこととなる。ピゼンデル等により、器楽曲の分野ではなお交流が続けられていたものの、1729年のハイニヒェンの死により、既に途絶えていたドレスデン宮廷とヴェネツィア派のオペラとの蜜月関係は完全に終焉を迎えた。そして、1731年のハッセのホフカペルマイスターの就任により、ドレスデンにも本格的にナポリ派のオペラの時代が到来することとなる。
0
|
|
|
ハイニヒェンは通奏低音奏法の理論家として知られるが、ドレスデン宮廷のホフカペルマイスターとしてはハッセの前任者であり、46歳で亡くなるまでその職にあり続けた。この二つのミサ曲は、死期が迫っていた1728~29年に書かれた晩年の作品で、所謂荘厳ミサの様式を用い、後期バロック的な作風で作られている。全体として、歌唱部分では北ドイツの教会カンタータ風の、器楽部分では所々ヴェネツィア派の協奏曲にありそうな合奏が聴かれる印象だが、いかにもハイニヒェンらしいリズミカルなテーマや、憂いや儚さの漂うフレーズも健在だ。思うに、プロテスタント音楽の文化圏とカトリック音楽の文化圏の伝統下の音楽の、または北ドイツのコラールを始めとする合唱の活用と精巧なフーガの技法と、ヴェネツィア派の魅惑的な旋律美と絵画的な色彩感の高次な融合でもあるハイニヒェンの典礼音楽は、この時代のドレスデン宮廷の目指した教会音楽の在り方の、一つの完成形であるといえるのではないか。合唱とオーケストラはいずれも典礼的な雰囲気を良く伝える。フーガはどれも短めだが、型に嵌めず、崩した形で作られている。時にゼバスティアン・バッハのロ短調ミサ曲やマニフィカートを彷彿とさせる部分もあり、二人が一時近しい距離にあったことが知れる。
0
|
|
|
これらの作品は北ドイツ的な受難曲のようにも見えるが、実際は異なる。リストーリやハッセの台本作者としても知られる宮廷詩人、ステファノ ベネデット パッラヴィチーノの台本によるイタリア語の歌詞を持ち、当然ながらプロテスタントのコラールは用いられていない。オラトリオと言っても劇的な深刻さはなく、全体的にはむしろハイニヒェン流の穏健で甘美な宗教的カンタータといった印象である。いずれもドレスデンの伝統的なセポルクロの形態に基づいているといい、1曲目のCome? S’imbruna ilciel occhi piangete!は1728年に彼の最後のセポルクロとして作曲された。合唱の和声は美しく、ソプラノのアリアでは部分的にゼバスティアン・バッハの受難曲を思わせる雰囲気も聴かれる。2曲目のL’aide tempio ignudeは最近の研究では1724年頃、このジャンルでは彼の最も初期の作品だと考えられているという。冒頭には単楽章のSinfoniaが置かれており、伴奏付きのレシタティヴォも効果的だ。アリアはヴェネツィア派のオペラアリアに近い感じがするが、これはおそらく、この時期の彼の声楽曲の特徴なのだろう。リフレインが印象的なフィナーレの合唱には後ろ髪が引かれる。
0
|
|
|
G B サンマルティーニは前古典派から古典派に至る演奏会用交響曲の発展に貢献した作曲家として知られているが、ミラノのサンタンブロージョ教会のマエストロ ディ カペッラを長く務めたことからも理解できるように、優れた教会音楽家だった。実際彼はこの作品のような宗教的カンタータを数多く書いていたようだし、マニフィカート等の典礼音楽を聴いても、この手の音楽に必須の卓越したフーガの技法を持っていたことがわかる。この作品はGerusalemme sconoscento ingrataとして1759年に書かれたという。導入の第一楽章のSinfoniaにおいて、刻むようなアクセントのあるリズム進行とスピード感のあるセンテンスが組み合わされて切れ目なく続くのは、中期から後期に至る彼の交響曲のそれに見られる典型的な特徴だ。第5楽章のSo che nel cor volgaにもそれらは投影されている。一般的なダカーポ・アリアであるにもかかわらず、同じ北イタリアのヴェネツィア派の作曲家達のアリアとまた異なった、どちらかと言えばドイツやオーストリアの作曲家のオペラセリア系に近い曲調に聴こえてくる。
0
|
|
|
ガルッピは、現在ではカラフルな家並やレースの編み物で知られる観光の島、ブラーノ島出身で、ヴェネツィアを中心に活動し、後年サンマルコのマエストロ ディ カペラを務めた。一方で、英国やロシアに招かれて滞在した程名声があり、生前はとりわけオペラブッファが高く評価されていたという。その才能はオペラやセレナータの他に、鍵盤楽器のためのソナタや協奏曲などの器楽作品からオラトリオ・ミサ曲等の宗教的作品まで幅広い創作活動を可能にしていた。現状聴くことのできるものの多くは器楽曲であり、残念ながら声楽曲は少なめである。オペラセリアの分野では、1740年以降、時流の趨勢がナポリ派に移ってからの作品が多く、彼もご多分に漏れず、ティトの慈悲やオリンピアーデ、晩年サンクトぺテルブルクで書かれた棄てられたディドーネといったメタスタジオの定番台本を多く活用している。このラテン語の台本を持つオラトリオは彼の円熟期の作品で、旧約聖書のヤエルの物語を題材にしているが、音楽上の特徴からすれば、彼のオペラセリアと大差ないように思われる。例えば、冒頭のアリアNon sic a Celsa rupe velocesは、軽快なテンポと流麗な旋律、豊かな表情等の点で、彼のオペラアリアの特徴を余すところなく表していると言える。
0
|
|
|
ジョヴァンニ アルベルト リストーリはボローニャ生まれと伝えられているが、1717年以降。ポーランドの宮廷に仕えるようになってからは紆余曲折を経ながらも常にドレスデンと一定の関係を保ち、晩年はハッセの下で宮廷副楽長まで務めている。彼は器楽曲も残しているが、世俗的な声楽曲や、ミサ曲などの教会音楽が創作の中心であり、とりわけ彼の喜歌劇は好評を博したという。彼のオペラやカンタータはメタスタジオの台本も使っているが、寧ろ地元にゆかりのある作者のものを多用しており、その音楽も当時のドイツの趣味に従ったものと見ることができよう。CD化されているものはカンタータやミサ曲等があるが、数少ない。ここで聴ける皇女マリア アントニアのアルカディア風の台本によるナポリ派様式のカンタータはいずれも完成度が高く、美しい。Didone abbandonataのQuand volteはいかにもロココ風で爽やか、時にハッセ風なパッセージが交錯する。Nice e TirsiのNon V`e duoro uguale al mioは拍子に変化を持たせてあたかもオペラセリアの一場面のように劇的に聴かせてくる。
0
|
商品詳細へ戻る