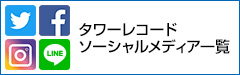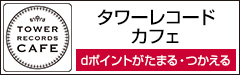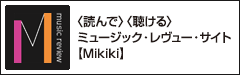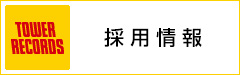山下達郎“白いアンブレラ/ラッキー・ガールに花束を”の〈チアー・タイム〉
変わらぬ圧倒的なポップス快感の高波なのである。強く印象に残るのは、1曲目と2曲目の〈曲間の短さ〉でだ。しかし、計測してみると“白いアンブレラ”のフェード・アウトが終了してから“ラッキー・ガールに花束を”のスタートまで4秒。これはシングルCDとしては決して性急なものではない。〈曲間の短さ〉は正に時差による錯覚、ポップスの魔法だったようだ。
ミドル・スイングのジャズ・ワルツから四つ打ち8ビートのギター・カッティングが続いたからではない。2曲がもたらす快感の大きさが等しく(あるいは、快感が圧倒的すぎて、2曲間の差が認識できない)、終わったと思ったらすぐに始まって、その早さに驚かされる。そんな快感。シングル・カット・タイムという短い時間でライブ会場にトリップする。そんな魔法。レコーディング・アーティストとしてのポテンシャルと、ライブ・アーティストとしてのポテンシャルに差がないという、今や〈昔気質のミュージシャン・シップ〉と言っても良い、彼の真骨頂だろう。3曲目の“風の回廊”のライブ・バージョンは、精密さと崇高さ、マニアックな凝集とポップスの爽快が等価であること。という、彼の信者ならずとも熟知している真理を、驚きと共に我々に、7年振りにプレゼンテーションする。
一見、50代に入った大人の山下達郎の提示。であるかのように見える“白いアンブレラ”ですら、そこにあるのは〈圧倒的な変わらぬ懐かしさ〉である。服部克久という、この国のあるクラスの、ある時間帯を象徴するような技術者と組むことは、彼にとって北野武が久石譲と組むこと(そして、離れること)の意味を大きく下回っている。服部克久のペンによるある種の〈(NHK的)国民音楽/上流階級の香り〉は、ほんの一滴の芳香。ほんの一瞬の手招きに過ぎず、そこにあるのは、彼の息子達が未だにかすることも出来ない濃厚かつ洒脱なメロディーとコード(歌の出だしに調性から遠隔気味のサブドミナント・マイナーをさりげなく置く。という〈さり気ないカマし〉の手さばきはジャズ・スタンダードに於いては手垢にまみれ、しかし、ポップスに於いては名匠の技と言える)である。雨上がりの虹の、七色のプリズムを見るようなサビの転調は、あまりに楽々と朗々と歌われるために、一瞬簡単であるかのようだが歌ってみると物凄く難しい(カラオケが付いているが、このカラオケには、こうした事実を確認させる意味も持ってしまっている)というプロフェッショナリズムを示し、全体のサウンドを覆う、ややずっしりとした音色彩は、スモーキーさとパステルさ、つまりは雨が降り出す雲と、雨が上がったあとの虹という、二態の空模様を見事に同居させて、つまりはこの曲が〈雨と街に関する歌〉として全方位的に完成されていることを意味している。
続く“ラッキー・ガールに花束を”は、一転し、何も変わっていないかのような彼の世界でさえ、実はコンピューターに制御された新時代を迎えていることを示している。ピアノとギター以外は総て打ち込みで作られた8ビート・ナンバーのドライブ感は、過去「まるで打ち込みみたいだ(打ち込みではないのに)」と驚嘆された彼の魔法を損ねることなく、より一層の力強さと共に新時代を迎えている。生演奏されるギターとピアノも、ソロや複雑な動きといった、打ち込みでは表現しずらいフレーズではなく、ほとんどが(打ち込みでも簡便である)8ビートのコード・カッティングのみ。この事が意味するのは、一方でフュージョンがブームになり〈技巧的であればあるほど偉い〉という価値観が席巻した80年代スタジオ・ミュージック界に於いて〈単純なリズムキープや、地道な和声の重ね方こそが宝石を生み出す〉という、フィル・スペクタリズム~ポップ・メイカーのマッドネスを我々に啓蒙し続けた彼の、逆転した悠々たる勝利である。アレンジの絶妙。はコンピューター時代になっても変わらない。単純な打点の緻密な計算からくる〈爽快だが重厚なドライブ感〉、奥行きや音域や定位などの完全なコントロールによる、贅沢すぎるほどのサウンド・エンヴァイロンメント(特に“ラッキー・ガールに花束を”に於けるサウンド・デザインは〈達郎アレンジ〉の進化/深化の見本。と言えるだろう。楽曲の特質を失わずに、余計な残響や滲みを丁寧に除去し、地味ながらワンダーな工夫を欠かせない。そしてフル・アコースティックである“白いアンブレラ”が、その実コンピューターの制御による緻密で自然な修正による効果に満ちていることは、ほとんど目に見えない)。〈You are my lucky girl for me〉というコーラスパートの歌詞に「Myが余計なんじゃねえの文法的に!」などと懐かしいツッコミを入れながら、我々の目は喜悦に輝く他はない。
デジタルは音質が悪いというのは、音楽ファンではなくオーディオ・マニアの病理から来る錯聴である。変わり映えしないつまらなさというのは、ポップスではなく時間の加速感に魅入られたが故の、つまりは近代に毒された味覚の麻痺に他ならない。
オリジナル・フルアルバムがCMソング集かよ。というのは、ポップ・ミュージック、そして資本主義という事の意味をいつからか取り違えた、歪んだエリート意識の賜である(彼等のコンセプトの中にはテレビコマーシャルに対する不当な蔑みがある上に、一方でテレビの中にいることを禁じ、もう一方でコンピューターの使用を禁じる意識は、袋小路の重症であり、責任は音楽にはない)。耳を澄ませば、または澄ますまでもなく、山下達郎のポップスの魔法は7年後の今日も不変であり普遍である。スピーカーから溢れ出るこの瑞々しさ。山下達郎は、生まれながらにして最先端で、生まれながらにしてスタンダードという、天才の中でも更に突出した才能を示している。その歌声は、スローライフなどというスローガンなどとは30年前から無縁にして、今この瞬間に於いても永遠の時を我々に与え、癒し、蘇生させる、我が国のポップスの至宝なのである。30年のキャリアが持つ意義はかくも輝かしい。
→ 山下達郎“白いアンブレラ/ラッキー・ガールに花束を”の〈ジャッジ・タイム〉はこちら
→ 「菊地成孔のチアー&ジャッジ」投票方法はこちら