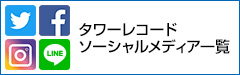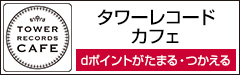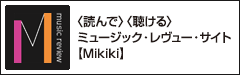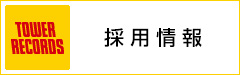作曲家・筒美京平(名前、もしくは作品のこと)は、彼がもっともヒット曲を量産していた70~80年代をうろ覚えな世代の人たちでもご存じなのではないだろうか。前述のいわゆる〈黄金期〉以降も、アーティストの発言のなかで彼の名前が挙がったり、カヴァーされたり、TVや雑誌の特集があったり、会社の上司がカラオケで歌っていたり……。とにかく幅広い世代の記憶のなかに、彼の存在は刷り込まれているはずだ。山崎まさよし、柴咲コウ、つんく♂、BONNIE PINK、melody.、草野マサムネ、クレイジーケンバンドなど、このたびリリースされたトリビュート・アルバム『筒美京平トリビュート the popular music』の参加アーティストを見ても、その影響力の幅広さは窺い知ることができるだろう。
筒美京平の名前が初めてクレジットされた望月浩の“黄色いレモン”がリリースされたのは66年。当時はレコード会社の洋楽ディレクターを務めていた彼だったが、翌67年には退社。本格的な作曲家活動をスタートさせる。グループ・サウンズ全盛だったその頃は、日本のポップス・シーンにも新たな才能が求められていた時期でもあり、彼の名前は早くから多くのレコードに記されていった。初のヒットは同年に発表されたヴィレッジ・シンガーズ“バラ色の雲”。そして68年に大ヒットしたいしだあゆみ“ブルー・ライト・ヨコハマ”によって、彼の名前は大衆に一気に知れ渡っていく。
そして70年代。〈歌謡曲黄金時代〉の幕開けは、彼の黄金時代の幕開けでもあった。〈犬も歩けば……〉のことわざではないが、時代を飾ったヒット曲、そのクレジットに目をやれば、たいてい彼の名前がそこにあった。その勢いは80年代に入っても衰えず、空前のアイドル・ブームの陰にもやはり〈筒美京平〉の名前はあった。
彼の書いた楽曲、編んだ楽曲の魅力は、ニッポン人のココロのツボを刺激するメロディーラインやコード感などといった、ヒット曲たるものの構造を熟知した作風であることもしかりだが、その時代時代のトレンドだった洋楽のスパイスを絶妙に織り交ぜていくワザもまた、見事だった。それを〈パクリ〉と揶揄する輩もいたが、そんな作風は、ピチカート・ファイヴや小沢健二など、90年代以降に台頭しはじめた、いわゆる〈サンプリング世代〉と言われるアーティストたちから大いに支持された。
黄金期に比べれば、さすがに世に出る数も少なくなった筒美作品だが、少し前には仲間由紀恵 with ダウンローズ“恋のダウンロード”をヒットさせるなど、筒美メロディーが現代においても十分に有効であることは変わりない。