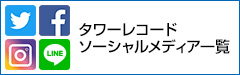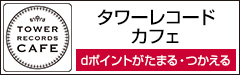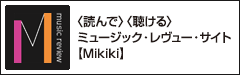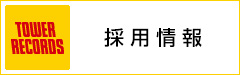90年代半ばに、それまで長らく活動の母体としていたON-Uを離れ、アシッド・ジャズやボンジョ・アイにて静かなリリースを行っていたアフリカン・ヘッド・チャージ(AHC)。彼らが新作『Vision Of A Psychedelic Africa』を引っ提げ、エイドリアン・シャーウッド率いるON-Uに帰ってきました。98年の『Drums Of Defiance』や2003年の『Shrunken Head』がアウトテイク集的な作品だったことを考えると、93年の『In Pursuit Of Shashemane Land』以来、実に12年ぶりのON-U本格参戦になります。首謀者であるパーカッション奏者、ボンジョ・アイことボンジョ・ イヤビンギ・ノアさんは、現在、ガーナに在住。
「ワシのジイサン、バアサンはラスタで、いつも〈アフリカ、アフリカ!!〉って言ってたから。それを聞いて、ワシも感じて、願って、実現したんだ。〈アフリカ〉〈ヘッド(向かうという意味)〉……つまりワシは何かをやるためアフリカに来たんじゃ。それでワシはここアフリカにいる。イエス、マン!! ワシらは〈アフリカ〉を〈チャージ(担当という意味)〉してるんじゃ。ジャマイカでは、みんながアフリカのことを話しておった。ジャマイカでラスタのコミュニティーに生きておったら、アフリカの影響は強くなる」。
小生にとっては、ある種トラウマともなっているそのユニット名が端的に表しているように、AHCの音楽には活動当初から、アフリカへの憧憬が色濃く現れていました。アフリカへの想いが強大な引力を生み、当時ON-Uの周辺に浮遊していたさまざまな音楽要素──ニューウェイヴやパンク、ダブ──を次々と吸い付けていった。そして、ゴツゴツとした謎の塊が生まれた。初期のAHCにはそんなイメージがありました。
「ワシらは特にグループを結成していたわけでもなかった。ワシとエイドリアン(・シャーウッド)はときどきスタジオに行っては録音をしてた」。
あくまで日々のセッションから、あるいは他のプロジェクトのアウトテイクから出来上がったのが、81年の衝撃的なデビュー作『My Life In A Hole In The Ground』だといいます。
「言ってみれば〈残り物〉だったんじゃ(笑)」。
数多くのセッションのなかでもやはり、クリエイション・レベルは特別だったようで「あのセッションでワシはエイドリアンやトニー(・ヘンリー)と出会い、ワシらの音楽をやり始めた。プリンス・ファーライや、多くのジャマイカン・アーティストのバック・バンドをやったもんじゃ。そこで浮かんできたアイデアをさらに前へ進めたものが、AHCだともいえる」。
24年に渡る彼らのキャリアに段落を付けるなら、第2期は90年『Songs Of Praise』から、そして第3期は95年『Akwaaba』から始まるように思います。前者は、80年代のON-Uから90年代のON-Uへの進化をいち早く表明しただけでなく、広く90年代ダブ(ダブ・ハウスを含む)の方向を示した作品です。一方の後者は、拠点をガーナに移したことがストレートに反映されている作品でして、アフリカ音楽としての深みが加わった反面、残念ながらON-U独特のダブ色は後退しています。
「あれ(『Akwaaba』)はな、それまでとは違う作品じゃ。ってのもな、ワシがガーナに来てから作ったものじゃから。ガーナに来て、いろいろなドラムを聴いたり、勉強したりした影響が出ている。あのアルバムはアフリカじゃ」。
そして、2005年。ふたたび古巣のON-Uに戻った新作では、『Akwaaba』以降に試みられていたアフリカ音楽の再考が、シャーウッドの強力なダブで、また新たな局面を迎えています。第4期AHCがいよいよ始動……そんな予感の大作であります。
「ここ(アフリカ)にいるあいだに音楽を作り始めたら、頭にいろいろなアイデアが浮かんでくるようになった。そこで、エイドリアンの所へ戻って──エイドリアンとは長いこと仕事をしてなかったんじゃが──それで、またいっしょにこれをやろうってことになったんじゃ。『Akwaaba』と『Sankofa』の何曲かは急いで作ったものもあったんだが、今回はちゃんとしたやり方でやろうとじっくりと時間をかけた。ワシにとってはこの作品がAHCの新たな始まりだと思っておるんじゃ」。