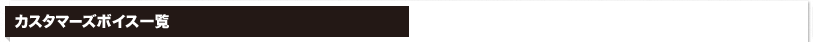
ハイドン:弦楽四重奏曲集<限定盤> / ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団
|
|
昔からの有名な演奏なのでご存知の方も多いと思いますが、演奏はスッキリしていて、変に持ってまわったところがなく、ポルタメントなどのちょっと古臭い癖もなく、とても聴きやすいです。もちろん『ハイドンはHIP』という方には向かないのでしょうが、HIP好きの私でも楽しめました。しかし驚くのは音質の良さ。なぜこんないい音で録音できたのか。室内楽は録音しやすいでしょうが、驚異の音質です。
|
商品詳細へ戻る
奥白根さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
小編成モダンオケによるいわゆるHIPの演奏。必然的にP.ヤルヴィとの比較になるのだろうが、アントニーニ盤も極めて素晴らしい。テンポは21世紀の標準、巨匠たちよりは早いが快速調ではない。過激な爆演ではないが切れ込みは鋭い。しかしレガートを挟んだりして芸も細かく素敵だ。HIPの形態だとやはり7番や8番は予想通りの素晴らしさで、第九も凄い。しかしHIPは田園と相性が悪いような気がする。伸びやかさが出にくいのかも。しかしアントニーニは十分満足させてくれた。全曲むらなくお勧めできる。パーヴォと並んでリファレンス足りうると思う。
|
|
|
同曲の本命の一つ。他にはフライブルク・バロック管は入手に時間がかかる。ベルナルディーニ指揮ゼフィーロは廃盤。鈴木雅明指揮BCJはセットでお安く買える。このベルリン古楽アカデミーは奇をてらったところは皆無、過激系ではないオーソドックスな名盤。特に第2番はしっとりとした美しさで驚かされる。何故か第2番と3番ばかり有名だが、私は1番、4番も良い曲だと思っていて大好きだ。この曲集はピリオドの録音も増えてきたが、ブランデンブルク協奏曲に比べて廃盤が多いように思うので、この全曲盤は早い者勝ちだ。
|
|
|
このディスクは凄い。長年の研究・探求の成果が表れていると思われる。ときに激しくときに優しくキリストの受難を描いていくが、まるで眼前に絵姿が浮かび上がってくるよう。通奏低音の扱いも納得させられる。ムジカ・アンティカ・ケルンにいた人だけあって技術的にも素晴らしいが、ゲーベルほど過激には走らず程よい演奏ぶりだ。解説書は必読内容なので、英語等苦手な方は国内流通仕様をおすすめします。ポッジャーも良かったが現時点ではこちらがベストか。
|
|
|
この作品集はオリジナル版とアムステルダム版があるが、私は断然オリジナル版が好きだ。トラヴェルソにオーボエやファゴットも絡みカラフル。奏者たちの技術も素晴らしく、この曲集の代表盤と言っていいだろう。耳馴染みの良い旋律が続き、価格も廉価なので多くの人に聴いていただきたい。
|
|
|
ここ数年、このような大全集ものが増えてきたが、どうしても演奏が玉石混淆であったり、録音にバラツキがあったり、まあ安いから買っておくか、というものも多かった。しかしこのアルバン・ベルクは凄い。録音も演奏も未だに現在の最高峰の一つだ。モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ベルク等は二種類の演奏が収録されているが、それぞれ趣が違うので聴き比べが楽しい。録音の違いの影響もあるだろうが、大まかに言えば、1回目の録音はしなやか、再録音はシンフォニックと言えるか。しいて言えばシェーンベルクも録音して欲しかった。バラでいくつか持っている方が多いだろうがこのセットで全貌を知ってもらいたい。
|
|
|
ロトにハズレ無し。やはりメッポウ面白い。あまりこの作品は数多くは聴いていないのだが、ラヴェルを前面に出したタイプであり、ラヴェルのシリーズの一環として録音されている。よって泥臭い、いわゆる土俗感は感じられず、いつもながらの風通しの良い演奏。だから物足りない人がいるのも理解できる。しかし楽器の色合いが面白く、ハルサイや幻想と並ぶ傑作だ。
|
|
|
第1番前奏曲が鳴り始めたとき、思わず、美しい、と言っていた。高音は伸びがあるが刺激的な部分は皆無、低音も良く伸び、素晴らしい楽器、素晴らしい録音であることが即座にわかる。よって前奏曲の様々な表情やフーガの各声部も非常によく分かる。演奏は良い意味で極めて中庸。テンポもアゴーギグも癖がなく、素直に曲の美しさに浸れる。ぜひとも第2巻の録音を切望する。
|
|
|
1台の協奏曲のみだが、すべてのディスクを凌駕する最高演奏と思っている。もちろん、ピノックのような繊細で爽やかな演奏を好む人もいるかもしれないが、シュタイアーの凄みは尋常ではない。彼のチェンバロは低音がよく響くが、オーケストラも低弦が唸りを上げて痛快。奇をてらったところのない正統派ながら、リズムははずみ歌心にも溢れた超定番と思う。
|
|
|
ベートーヴェンのピアノ作品をフォルテピアノで聴くのは、ちょっとパワー感、エネルギーが今ひとつ、と思っている方にこそ聴いて欲しい名盤誕生。フォルテピアノの音に伸びがあり、十分満足させてくれる。流石にシュタイアー、楽器の選び方が秀逸なのだ。ベザイデンホウトの協奏曲といい、フォルテピアノの最高演奏が続くのはベートーヴェンイヤーの恩恵か。
|
|
|
ベートーヴェンのピアノ作品をフォルテピアノで聴くのは、ちょっとパワー感、エネルギーが今ひとつ、と思っている方にこそ聴いて欲しい名盤誕生。フォルテピアノの音に伸びがあり、十分満足させてくれる。流石にシュタイアー、楽器の選び方が秀逸なのだ。ベザイデンホウトの協奏曲といい、フォルテピアノの最高演奏が続くのはベートーヴェンイヤーの恩恵か。
|
|
|
ちょっと修正と謝罪。以前、エグモントとコリオラン序曲がないので担当者の見識を疑うと書かせていただきましたが、この2曲はデジタル録音で、今回のセットはおそらくアナログ録音の集成を目指したものという考えに思い至りませんでした。失礼しました。演奏は20世紀の最高峰の一つですので、あらためて星5つで再投稿させていただきます。
|
|
|
意外と編成が大きく量感もあり抵抗感はなかった。というよりさすがクルレンツィス。細かな仕掛けは満載で、普通聴こえてこない楽器が耳に飛び込んだり、このへんは従来と同じ。しかしセッションとはいえ、このオーケストラは上手い。ピリオドならこのテンポは妥当だろう。昨年からベートーヴェンイヤーに向けて色々な新譜が出てきたが、これを聴かずしてベートーヴェンイヤーは語れないのではないか。1曲だけだが絶対買いだ。
|
|
|
レコード芸術誌では準特選だったが、なぜ特選でないかわからないほど素晴らしい。まず高音の美しさが耳に飛び込んでくるが、低音も十分見事な響き。テンポを微妙に動かすことで単調になることを防いでいるが、そこが好みに合わない人がいるのかもしれない。フランス組曲やパルティータと違って、形式がキッチリしているイギリス組曲は淡々と楽譜通り演奏されてはつまらない。彼女は勢いある快活さも併せ持っており聴き応えがある。
|
|
|
ヴァルヒャほど謹厳ではなく、コープマンほどの即興性はないが、作品の良さをじっくり味わえる名盤と思う。流石に3回めの全曲録音とあって、良い意味での中庸の美を聴かせてくれる。ヴァルヒャにしても、コープマンにしても、今後国内盤の復活はまず見込めないご時世だけに、アラン盤が国内盤として発売されていることは本当に貴重だと思う。解説書も充実しているので多くの方に勧めたい。
|
|
|
レコード芸術誌月評では意見が分かれ、2月号ViewPointでは絶賛されたので聴いてみました。これは凄い。完璧なテクニック、見事な粒立ちの音たちが紡ぎ出される。テンポは早めの部分もあるが、じっくりと間を活かしながら進めるなど、ただ早いだけの一本調子の演奏ではない。一枚一枚聴き進むのが楽しみでしょうがなかった。バックハウスのリマスター全集との聴き比べという贅沢な時間を過ごせた冬でした。
|
|
|
昔からの有名な演奏なのでご存知の方も多いと思いますが、演奏はスッキリしていて、変に持ってまわったところがなく、ポルタメントなどのちょっと古臭い癖もなく、とても聴きやすいです。もちろん『ハイドンはHIP』という方には向かないのでしょうが、HIP好きの私でも楽しめました。しかし驚くのは音質の良さ。なぜこんないい音で録音できたのか。室内楽は録音しやすいでしょうが、驚異の音質です。
|
|
|
半年以上待った甲斐がありました。旧盤のモノのベートーヴェン・ソナタは大きな音揺れがあったはずなのに、きれいに修復(マスターにさかのぼった)されています。国内版の廉価シリーズは聞くに堪えない音でしたが、さすがデッカ録音、元々は良い音で録音されていたことが確認できました。ただ、モノの協奏曲は若干ヴァイオリンの高音にシャリシャリ感があるのが残念ですが、分離は良くなっています。
|
|
|
大好きな作品なのでチェンバロ、ピアノでは様々なディスクを聴いてきたが、編曲物を聴くのは初めてであった。そもそも音がすぐに減衰する鍵盤作品を音の持続が可能な弦楽器で演奏すると違和感があるのでは、と思っていたが、これは素晴らしい名演。違和感が無いどころかあまりの美しさに唖然とする。音の美しさが際立っており、アンサンブルも当然ながら水も漏らさぬ鉄壁さ。編曲物も侮れないと反省。多くの人に聴いてほしい。
|
|
|
しなやかで力強さも感じさせるベルリン・フィルだが、重厚な低音を響かせながらも絶対に重くならない弾みも感じさせて流石。内田光子のピアノも相変わらず精緻・繊細。かつ力強さも兼ね備えるが、色合いの変化が素晴らしく、どの曲どの楽章も様々な表情を聴かせてくれ、旧盤以上に素晴らしい。同曲全集の中ではトップクラスと言っていいだろう。
|
|
|
楽しい、面白い、引き込まれる名演と思う。小編成ながらオケの薄さは気にならず、個々の奏者もアンサンブルも十分見事。低弦とティンパニは喧嘩を売っているよう。テンポの速さは最近HIPを聞き慣れたせいか気にならず、今年のトップクラスのお気に入りとなった。ネルソンスも発売になったが、全くタイプが違うので聴き比べが楽しい。
|
|
|
1回目の録音は聴いていないので比較はできないが、相変わらず精緻で考え抜かれた演奏。思わぬ楽器が耳に飛び込んできたり、まるで違う曲かと思うようなところがあったりと、十二分に楽しめる名盤。ミュンシュのような爆演ではないが迫力も十分。今までのロトに共感してきた人は必聴。名曲名盤企画ではトップ争いだろう。
|
|
|
ショスタコーヴィチの交響曲全集も増えてきたが、いかんせん国内盤がない。ハイティンクはだいぶ前の録音になるが、鮮明な録音とオーソドックスな解釈、100ページを超える解説も貴重。多少内容的な古さも感じるが(「証言」に疑義が投げかけられる前のものか)、ショスタコーヴィチ作品を知ろうという人には助けになる。オーケストラは流石に上手いが、切れ味ではV.ペトレンコが上か。ともかくこの国内盤復活は喜ばしい。
|
|
|
カバポチさんの気持ちは良くわかります。しかし、最近は前打音の扱い方が変化し、短前打音の扱い方をしているディスクも増えています。最初にやったのはシュタイアーらしいですが、確かに彼は短く弾いています。特にフォルテピアノ系の奏者は最初の音(前打音)を短くする人が多いようです。仲道さんも古楽器研究の末、この解釈に至ったのではないでしょうか。慣れれば大丈夫。全体は素晴らしい演奏だと思います。
|
商品詳細へ戻る