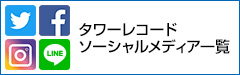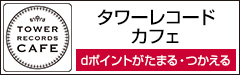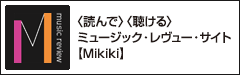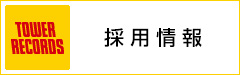さまざまな音楽ジャンルを丁寧に教えてくれる誌上講座が開講! 皆さん、急いでご着席ください!!
I カリプソの成り立ちと特徴

夏が来れば思い出していただきたいのです、〈カリプソ〉のことを。あなた方が一聴して〈南国っぽい〉と感じるもののうちの何割かは、この音楽の要素が含まれている、と断言してしまいましょう。すでにあなたはカリプソに触れたことがある! 心の準備はよろしいか?
カリプソは19世紀から20世紀初頭のトリニダード・トバゴで生まれた大衆音楽。奴隷貿易によってアフリカからもたらされた〈カリンダ〉と呼ばれる音楽が起源とされています。やがてこれがカーニヴァルで歌われる〈カイソ〉へと発展し、いつしかカリプソと呼ばれるようになった、というのが通説ですね。カリブ海に浮かぶ英語圏の島国ということでジャマイカとの共通点もありますが、メントやスカがダンス・ミュージックとしての役割に重きを置いていたのに対し、カリプソでまず大切にされたのは言葉。カリプソニアンと呼ばれるシンガーが、時事ネタなどを盛り込んで、圧倒的に独創的な歌詞を歌う――いわば新聞や週刊誌のような役割を果たしてきたのです。戦前の重要カリプソニアン、アッティラ・ザ・フンの“FDR In Trinidad”は、ルーズベルト大統領がトリニダードを訪れた際のエピソードを歌っていますし、同じくアッティラの“Women Will Rule The World”で描かれるのは女性の社会進出について。〈ピコン〉と呼ばれるこの風刺精神こそが重要な魅力で、気の利いた言い回しや鋭い視点などがアーティストの人気を決定付けていたのです。つまりカリプソはキャラクター勝負の音楽であるからして、歌の上手さや声の良さが第一の尺度ではありませんでした。というわけで、古い録音には美声とは程遠い歌も多く聴け、またそれが実に味わい深く、それぞれのキャラを伝えてくれたりも。こういった事情が〈ユルい音楽〉という印象を与える一因になっているのでしょう。

初期カリプソのサウンド面での特徴といえば、4拍子の2拍目を抜いたおっとりしたビート。これまたユルいです。ヴァイオリンやギター、ベースといった弦楽器にクラリネットなどの管楽器、そしてパーカッションがいたりいなかったりと、コンパクトな編成だったバンドは、50~60年代になってホーン隊やドラム・セットを導入していきます。そして70年代以降、ソウル・カリプソ=ソカ期へと突入。リズムが強化されることでダンス・ミュージックとしての機能を持ち、それが進化し続けて今日に至るのです。