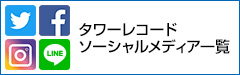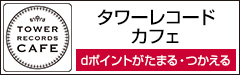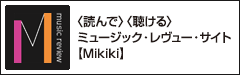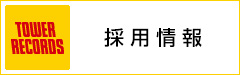11年目を迎えた元祖ロック・フェス〈FUJI ROCK FESTIVAL〉。今年も200以上のアーティストが揃い踏み! 苗場の大自然を舞台に、3日間に渡る大供宴が繰り広げられます。というわけで、2007年一発目のbounce.com夏フェス特集では、〈フジロック〉注目出演アーティストの作品をピックアップ。フェス前の予習&イメトレに、ぜひご活用あれ。
7月27日(金)に出演するアーティストの作品を紹介
初日の目玉は、なんと言ってもキュアーでしょう。来日ライヴは実に23年ぶり。今年のフジロック最大のトピックと言っていいはず。年内での解散が決定しているKEMURIや、インディー・ロックの至宝=ヨ・ラ・テンゴあたりも大注目。強力なビートが詰まった新作を発表したグルーヴ・アルマダは、〈WHITE STAGE〉を巨大なダンス・フロアに変換する? そして深夜の〈RED MARQUEE〉には、5年ぶりのアルバムを携えて帰還した国産ヒップホップの雄、THA BLUE HERBが登場です。
THE CURE
『The Cure』Geffen(2004)
昨今のロック・シーンを支える最大の影響源は、スミス/モリッシーとデュラン・デュランとキュアーである。これら三者は今年相次いで新作を発表するわけだが、再評価に押されてか、モリッシーと同様にキュアーも会心のアルバムを完成。ニュー・メタル・シーンの立役者であるロス・ロビンソンがプロデュースするという顔合わせも吉と出た。ラウド、ディープ、ヘヴィー、しかもポップ。キュアーの粋を凝縮し、かつてなく力強いロバート・スミスの咆哮と、ライヴ録音らしい肉感的かつ刺々しいダイナミズムで酔わせる、本年最高のロック・アルバムの一枚だ。89年のアルバム『Disintegration』にも通ずるが、むしろ思い出されるのは80年代初頭。『Faith』のテンション、『Pornography』の濃密なカオスを、緩急を強調したポスト・オルタナ時代の感覚で鮮明に切り取ったかのよう。2004年のUKロックの主役は、新人じゃなくて40代である!(新谷 洋子/bounce 2004年07月号掲載)
KEMURI
『our PMA』avex io(2007)
今年いっぱいで解散するKEMURIのラスト・アルバム。タイトルも象徴的だけど、内容もいままでの彼らを凝縮したかのよう。スカでパンクでコアで日本語詞もあって、終始アッパーでカラフル。にしても、ラスト・ナンバーを2分弱でパンキッシュに駆け抜けたうえに、タイトルが“I'm So Satisfied!”って! 納得しつつも泣ける。これから各地をフェス行脚する彼ら。泣いて踊って共に過ごす最後の1年に必携です。(高橋 美穂/bounce 2007年06月号掲載)
BLONDE REDHEAD
『23』4AD(2007)
ソニック・ユースのスティーヴ・シェリーが手掛けたデビュー作から12年。ジム・ジャームッシュ、ジェイムス・イハ、TVオン・ザ・レディオ、ギー・ピチョットと、彼らは多彩な才能との邂逅を重ねてきた。夢幻の回廊に轟くような残響と、甘美なメロディーが脳内を駆け回る衝撃的な本作は、そんな彼らのキャリアをすべて縫合し、一枚のタペストリーに仕立てた退廃的なプログレッシヴ・アート。残酷なまでに美しい作品である。(冨田 明宏/bounce 2007年04月号掲載)
YO LA TENGO
『I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass』P-Vine(2006)
ここのところ無敵のヨ・ラ・テンゴ。今回はオープニングから10分を越えるフィードバック・ノイズがファンファーレのように鳴り響き、エクスペリメンタルでファニーなロックンロール・ショウが幕を開ける。ストリングスやホーンを持ち込んで、いつも以上にヴァラエティー豊かなナンバーがズラリ。まるでNRBQやサン・ラー、キンクスあたりを招いたロック・フェスみたい。それでいて尻尾の先までヨ・ラ・テンゴ。傑作です! (村尾 泰郎/bounce 2006年09月号掲載)
RUB-A-DUB MARKET
『Digikal Rockers』BMG INDIES(2007)
すべてが規格外の東京発ノリノリ3人組ラガマフィン、RUB-A-DUB MARKETの2作目が出ちゃいました。これがグライム/ダンスホール/マイアミ・ベース/ダブ・ステップ/ジャングルなど、ありとあらゆるベース音楽を確信犯的にポップかつチープに仕立てた、いかがわしいことこのうえナシの激アブナイ一枚なのです。ロブ・スミスやCOOL WISE MENなどゲストの豪華さもさることながら、カスカスのビートにお経的フロウを乗せて四季の移ろいをセンチに綴った“Under Mi Senti”や、まさかの爽快ラヴソング“恋のファンデーション”(ヒロイン役はG.RINA)など反則スレスレの豊かなアイデアに終始口はアングリで、気付けばあっという間に1回転。〈何をやってもオレらはRUB-A-DUBだし〉――そんな開き直り感が作品からじっとりと滲み出ているのだからタチが悪いのよ! でもね、いまこれを聴かずして何を聴けっていうのかしら!? 最高です! (山西 絵美/bounce 2007年05月号掲載 )
FOUNTAINS OF WAYNE
『Traffic And Weather』Virgin(2007)
先日行われた一夜限りの来日公演に涙した人も多いのでは? グラミー賞にもノミネートされた大傑作から待たされること3年半、パワー・ポップ界の雄=ファウンテインズ・オブ・ウェインが4枚目となるニュー・アルバムと共に帰還しました! 〈久々だし、大丈夫?〉なんて心配した自分が愚かに思えるほど、どこから聴いても大満足の極上グッド・メロディー&ハーモニーが満載。これぞ完璧なポップ・ソング集です。(馬嶋 亮/bounce 2007年04月号掲載)
MUMM-RA
『These Things Move In Threes』Sony
ピュアなんです。キラキラしてるんです。ブライトンの小さな港町で退屈を持て余していた高校生5人組が、極上のメロディーを携えて大注目のデビュー作を発表しました。UK特有の澄んだギター・サウンドに心地良く絡まるハイトーン・ヴォイスは、胸をキュンと鷲掴みしてくれます。昨年の〈フジロック〉で溢れ出るパワーを目撃した人も、最近疲れを感じているアナタも、みんないっしょにキラメキ・ロックでジャ~ンプ! (柴田 かずえ/bounce 2007年06月号掲載)
イルリメ
『イルリメ・ア・ゴーゴー』カクバリズム(2007)
KAKUBARHYTHMからのリリースとなった約2年半ぶり5枚目のアルバムは、全10曲・27分強を一気に駆け抜けていく一筆書きのような作品集。ジャンルレスというよりもいろんな音楽のテイストの違いを楽しんでくよな彼持ち前の嗜好は、ここでまっすぐな音楽性、エネルギーへと収斂されて、いままで以上に力強く響く。イントロに続く“Land Of 10000 Dances”のイルリメ解釈たる“イルリメのダンス天国”から快調なそれは、誰もが引き込まれる無礼講パーティー・ミュージック。レーベルメイトのYOUR SONG IS GOODや、ECD、二階堂和美らゲストを随所で交えつつ、小さなその身体にショウマンたる資質をたっぷり詰め込んだ、イルリメ最高のエンターテイメント作でしょう。(一ノ木 裕之/bounce 2007年07月号掲載)
KINGS OF LEON
『Because Of The Times』RCA(2007)
どんなタイミングであれ、男にとって一皮剥けるというのは(いい意味で)一大事なわけだが、キングス・オブ・レオンにとっての正しい脱皮は3枚目となるこの新作で完了したことは間違いない。アメリカで硬派な男児の出生率がもっとも高いといわれる(俺調べ)テネシー州出身の3兄弟+従兄弟の4人組。〈ガレージを通過したサザン・ロック〉とも称されたデビュー時に蓄えられていた南部ヒゲを完全に剃り落として臨んだ本作では、初期の豪放まっしぐらな衝動的直情サウンドから深化した、豪放まじりの緩急自在的陰影サウンドが全面展開されている。畑は大違いだが、なぜかジョイ・ディヴィジョンを思わせる瞬間すらある。そして、ケイレヴ・フォロウィルの唯一無二なしゃがれヴォーカルに蓄積された哀切と痛切の分量はあきらかに増加し、聴く者の心を激しく揺さぶる。硬派な男のズルムケとは、こういうことだ。(北爪 啓之/bounce 2007年05月号掲載)
GROOVE ARMADA
『Soundboy Rock』SonyBMG UK(2007)
チルアウト・マスターという印象も今は昔、最近はアッパーなエレクトロやハウスを手掛ける彼らだが、この5年ぶりの新作では活動初期を思わせる楽曲も交えて彼らの魅力を凝縮。浮遊感のあるチルアウトからバウンシーなブレイクス、エレクトロ、テッキーなものまで、振り幅の大きさが実に愉快だ。ライムフェストやトニー・アレン、アンジー・ストーンらの多彩なゲストも効果的で、エッジーかつポップな傑作となっている。(青木 正之/bounce 2007年07月号掲載)
THA BLUE HERB
『LIFE STORY』THA BLUE HERB RECORDINGS(2007)
5年ぶり3枚目となる本作は、メンバー個々がさまざまな放浪を経て辿り着いた、TBHの最高傑作だ。もはや仮想敵を設けることもなく、ただ己と対峙するBOSSのリリックは、ヒップホップを生業とする彼自身のありのままが表現されているからこそ、聴く者の心に突き刺さる。さらに深化したO.N.Oのビートも攻めの姿勢を崩さない。珍しくゲスト(EGO-WRAPPIN'の中納良恵)を迎えた曲があるのも開けた意識の表れだろう。(稲村 智行/bounce 2007年06月号掲載)