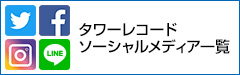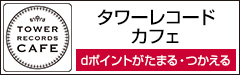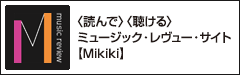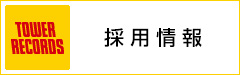一般的に日本では、中近東の音楽はラテンよりもアフリカよりも遠く、世界でもっとも遠い音楽と思われている。20世紀の欧米ポップ音楽とそこから影響を受けたJ-Popシーンを中心に見るかぎり、それは間違っていない。だが民謡~古典音楽にまで遡ると、尺八や琵琶など楽器の相似性、旋律やコブシ回しなど、日本と中近東の共通性が浮かび上がってくる。10月初旬に〈ラマダンの夜〉で来日したパキスタンのカッワーリー、イランの古典、モロッコのグナワ、マグレブ&イエメンのウード、トルコのスーフィー・エレクトロニカを聴いて、単なるエキゾティシズム以上の意外なシンパシーを感じたという感想を随分聞いた。
故ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンで有名になったイスラム神秘主義の宗教歌謡〈カッワーリー〉の若手注目歌手であるファイズ・アリー・ファイズ。10名近いメンバーがタブラと手拍子で猛烈なグルーヴを作り出し、インド古典直系ながらも、より激しいファイズの即興歌唱が稲妻のように斬り込む。手拍子を叩きながら聴いていると、自然に身体が前後に揺れてしまう。イラン古典は、NHK「シルクロード」の音楽にも参加していたカイハン・カルホール。中東の打弦楽器サントゥールを従え、ヴァイオリンに似た楽器カマンチャ1本で1曲1時間半。目をつぶると、イランの放牧地帯が脳裏に浮かぶような精神の旅行に連れていってくれた。マグレブ出身、パリで活動するウード(中東の琵琶)弾き2人+エレクトロニカのデュオウードは、ゲストにイエメン人ウード弾きのアブドゥルラティフ・ヤコブを迎えての公演。中世の形を留めるイエメンのアラブ音楽と、マグレブ~パリの未来形アラブ音楽が邂逅するコンセプトは素晴らしかったが、プログラミングのリズムに対応したデュオウードと、そのスタイルに慣れていないアブドゥルラティフの掛け合いがしっくりいかなかったのが残念。アルジェリア~モロッコの生トランス音楽であるグナワとレゲエを融合させたグナワ・ディフュージョンは、シアター・コクーンではアンプラグドなグナワ・セットを行った。客席後方から大太鼓とカルカベ(金属カスタネット)を鳴らしながら登場し、1時間半ほぼ全編がグナワ。この音楽は、カルカベとゲンブリ(ベース状の楽器)をバックに短い歌のフレーズを延々と繰り返し、現地では聴衆の多くがトランス状態に入ってしまうほど麻薬的な音楽。頭をガンガン振らずにはいられなかった。最後はトルコのスーフィー音楽をエレクトロニカとブレンドしたメルジャン・デデ。カーヌーンやクラリネット、ダルブッカ、そして旋回舞踊ダンサーを連れてのライヴだ。鋭いエレクトロニック・サウンドに尺八にも似た葦笛ネイの幽玄な音色を乗せ、女性ダンサーが旋回舞踊を舞う。その光景を見聞きしているだけで、東京からイスタンブールへと意識をトバされた。