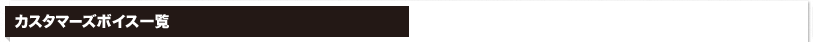
ベートーヴェン:交響曲 第3番「英雄」 / ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、他
|
|
フルトヴェングラーが1952年にウィーン・フィルとスタジオ録音したベートーヴェン『英雄』は、演奏の素晴らしさのみならず音質の良さもあって、この指揮者の遺した録音の中でも三指に入ると言われているものです。今回新たに取り寄せた、高音質のテープから復刻したというディスク(GS2280)は未開封のままの新品という、素材としてこれ以上はあり得ないものです。そして、そこから再生した音ですが、これは想像を絶するもので、今まで聴いていたディスクは何だったのだ、と思うほどです。オケの息遣いがはっきりとわかり、あたかも録音現場に立ち会っているような錯覚に襲われました。指揮者も気力体力ともに充実、圧倒的な音楽で聴くものに迫ってきます。アマデウス四重奏団の第1ヴァイオリン奏者、ノーバート・ブレイニンは「フルトヴェングラーとベルリン・フィルの演奏会で聴いた『英雄』の最初の二つの音がずっと忘れられない」と語っていたそうです。もちろん、このCDでの演奏はベルリン・フィルではなくウィーン・フィルですが、この奥深く幽玄な響きはその言葉を裏付けているのかもしれません。カップリングやボーナストラック無しは見識。ここ数年のグランドスラム・レーベルの新譜の充実ぶりは凄いの一言に尽きます。
|
商品詳細へ戻る
ポン太さんが書いたカスタマーズボイス
|
|
【1】(GS2297について)音質は「グランドスラムらしい仕事」と言えば十分だろう。前作GS2115の時点で本当に温かく、やわらかく、自然な広がりを持った音を獲得していたので今回は劇的な音質向上ではないが、リニューアルされた解説書のためだけに購入しても問題はない。【2】製作者様へお願い、かつてリリースされたワルター/コロンビアのベートーヴェン「英雄」(GS2125)や「交響曲第1・2番」(GS2116)が現在入手困難のようなので、最新リマスタリングで出し直して頂きたい。後者に収録されていたワルターの声に関し、平林氏が「MJ無線と実験」誌に書かれていた調査結果やGS2173(ブルックナー7番)掲載のワルターのカラー写真等も一緒に。【3】ワルターを逐った「第三帝国」なるものはわずか12年で崩壊し、社長の暴走を止めなかった巨大芸能事務所はあっけなく廃業が決定した。広告主の大手レコード会社の圧力に屈し、著作権切れ音源復刻CDの広告掲載を中止した音楽雑誌が日本に存在したが、最近廃刊になったらしい。対してワルターの名演はこれまでも、そしてこれからもずっとあり続けるのである。
|
|
|
フルトヴェングラーが1952年にウィーン・フィルとスタジオ録音したベートーヴェン『英雄』は、演奏の素晴らしさのみならず音質の良さもあって、この指揮者の遺した録音の中でも三指に入ると言われているものです。今回新たに取り寄せた、高音質のテープから復刻したというディスク(GS2280)は未開封のままの新品という、素材としてこれ以上はあり得ないものです。そして、そこから再生した音ですが、これは想像を絶するもので、今まで聴いていたディスクは何だったのだ、と思うほどです。オケの息遣いがはっきりとわかり、あたかも録音現場に立ち会っているような錯覚に襲われました。指揮者も気力体力ともに充実、圧倒的な音楽で聴くものに迫ってきます。アマデウス四重奏団の第1ヴァイオリン奏者、ノーバート・ブレイニンは「フルトヴェングラーとベルリン・フィルの演奏会で聴いた『英雄』の最初の二つの音がずっと忘れられない」と語っていたそうです。もちろん、このCDでの演奏はベルリン・フィルではなくウィーン・フィルですが、この奥深く幽玄な響きはその言葉を裏付けているのかもしれません。カップリングやボーナストラック無しは見識。ここ数年のグランドスラム・レーベルの新譜の充実ぶりは凄いの一言に尽きます。
|
|
|
夏真っ盛りだが、最近スイカ割り禁止の海水浴場や公園等の施設が増えているらしい。理由は「視覚障害者を侮蔑している」からだとか。増加といえばおめでたい席での忌み言葉、「希望」「忙しい」「忘れる」全部ダメ、なぜなら「『亡』の字が含まれているから」。もはやこじつけを通り越してギャグの世界、一体いつからこうなってしまったのだろう。めざましく音質が向上したクナッパーツブッシュのブルックナー『第五』(GS2294)を聴いていて、ふとこんな事を考えてしまった。ひたすら我が道を行くクナ、評判の悪い改訂版?テンポ設定が異様?小さい、小さい。他人に迷惑をかけぬ限り、やりたい事をやればいい、周囲の目など気にしたって仕方がない。そんなクナの声が聞こえたような。
|
|
|
(GS2293について)石井宏氏がこの録音に参加していたオーレル・ニコレから聞いたところによれば、ハイドン『V字』のセッションで、些細な吹き損じ・弾き損じの度に演奏を中断させるディレクターに、フルトヴェングラーは指揮棒を差し出した。「ならいっそ君が振れ、俺はもう知らん」。恐縮し謝るディレクターにフルトヴェングラー「もう一度だけ振る、テープを十分用意しておくように」。そしてその後本当に一度だけ、全4楽章を最初から最後まで一気に通して録ったのがこの演奏だという。その『V字』とシューベルト『グレート』の名演中の名演が素晴らしい音質でよみがえる。グランドスラム・レーベルの新譜でフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュを聴いていると、フルヴェンやクナは身体も大きかったが「人間」もでかかったな、とつくづく思う。他者の揚げ足取りに余念のない矮小な人間で溢れかえる現代社会のなんと窮屈なこと。
|
|
|
クナッパーツブッシュというと、今の若い音楽ファンにはとかく鈍重な、古くさい演奏をする指揮者と思われがちである。いや若い人だけではない。ぼくはこの指揮者のすばらしさを世に伝えようと、あらゆる機会をとらえて激賞し、その紹介につとめて来たが、結局ほんの一部の人に認められただけでレコードは売れず、没後60年になろうというのに、いまだ満足のいく音質でのCD化がされていないのが現状なのだ…と思っていたら、グランドスラム・レーベルがついにやってくれた。ボスコフスキー、バリリ、アントン・カンパー、オットー・シュトラッサー、エマヌエル・ブラベッツ等々、綺羅星のごときメンバーを擁した黄金時代の名門オーケストラの音色と、ゾフィエンザールの夢のような残響は筆舌につくしがたく、CDになるとそういう感覚的な美しさが減退しがちであるが、当CD(GS2289)はすばらしい復刻を示している。ワーグナーに興味はあるが、オペラは長くて苦手という人は、このCDを耳にタコができるほど聴きまくるのだ。フルトヴェングラーがいいとか、セル/クリーヴランド管弦楽団がいいとか、いろいろ言う人が出てくるが、絶対に迷ってはいけない。ワーグナーだけは指揮者が恥ずかしげもなく大見得を切れなかったり、録音がわるくては話にならないからだ。それにしても、一体どうやったらこのようにオーケストラが生き物のようにうごめき、深く呼吸するのか。クナはもういないが、音楽は永遠にここにあり続けるのだといえよう、といえよう。えっ、さっきからあれこれ御託を並べているお前は誰かだって?ぼ、ぼくは無能こ…。
|
|
|
クナッパーツブッシュは信条に基づいて行動する男であった。第二次大戦敗戦後、独墺では交響楽団や歌劇場を維持するだけでも大変であった。クナ指揮のある演奏会のあと、支配人がクナに「これしか出せませんから…」となけなしのギャラを差し出したところ、クナは紙幣を一枚だけ抜き取り、あとは返したというエピソードが残っている。逆にいくら金を積まれようと、自身の美学に反することはしなかった。メトの支配人ルドルフ・ビングがクナをアメリカに招聘すべく直々に指揮者の元を訪れ、金額欄が未記入の小切手を「どうぞお望みの額をご記入ください」と差し出したところ、クナは小切手を引き裂き、テーブルの上にパラパラと撒いたという。無論、クナがアメリカに行くことはなかった。レコード録音に対してもクナが自身の信条を曲げることはなかった。英デッカが史上初めての『指環』全曲のステレオ・セッション録音を計画した時、当初指揮者として起用しようとしたのが他ならぬクナその人であった。だが、デッカ側が録音に際し効果音を多用し、舞台とは異なる音響世界を創造しようとしているのを知るや「そんなもの、子供だましだ」とクナは露骨に不快感をを示し、とどのつまり計画から降りてしまった。結局指揮は「火事場の力馬鹿」ショルティに委ねられた。クナ自身典型的な19世紀生まれの指揮者であり、ライヴでこそ真価を発揮、セッション録音では集中力が長続きせず、管弦楽小品集はともかくオペラ全曲では問題があった。ではクナはなぜ1957年に無観客のゾフィエンザールでウィーン・フィルを振り、当CD(GS2290)にも収められた「ワルキューレ」第1幕を録音したか。これぞまさに演奏がすべてを語る。
|
|
|
フルトヴェングラーの場合、実演録音がグランドスラム・レーベルからつぎつぎと発売されるに対し、クナッパーツブッシュのディスクはきわめて少ない。日本のファンにまったくといってよいほど知られていなかったクナッパーツブッシュの名演奏に驚愕し、その超天才ともいえる芸術性を日本で最初に紹介したのはほかならぬ…それはさておき、今回グランドスラムよりリリースされたクナの『ウィーンの休日』(GS2286)、これには本当にびっくりした。試聴にあたり高品質のテープより復刻したというCDを新たに取り寄せ、それを拙宅のリスニングルームに持ち込み、万全に調整した装置で再生したが、「ウィーンの古き良き時代が彷彿とし、自分自身その時代を生き、知っていたかのような懐かしさで胸がいっぱいになる」(喜多尾道冬)し、最後の「ウィーンの森の物語」などは、「ドナウ河畔の木立を渡る風のようで、ベンチに腰かけて、善男善女の散策姿を眺めていたり、近くのカフェからくる、淹れたての、たびたびトルコと戦ったおかげでおぼえたウインナコーヒーの香をかぐような、いい気分にさせてくれる雰囲気」(平岡正明)があますとこなく再現されているではないか!これは本当におどろくべきことといえよう。
|
商品詳細へ戻る