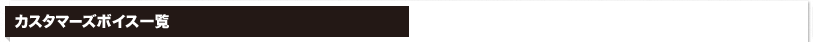
商品詳細へ戻る
すちゃらかちゃんさんが書いたカスタマーズボイス
|
|
アレンジものは、常にオリジナルと比較されるので大変である。しかし、このラフマニノフは、原曲らしさを保持しつつピアノ協奏曲らしさも出ている点で成功と言っていいと思う。むしろ、惜しむらくは、スケルツォ楽章(交響曲の第2楽章)が省略されていることだ。協奏曲だから3楽章形式で、ということなのだろうが、スケルツォのある4楽章協奏曲(ブラームスの2番)もあることだし、スケルツォもアレンジして欲しかったなあ。
|
|
|
素晴らしい!の一言に尽きる。もうすぐ80歳に手が届くチック・コリアの瑞々しくシャープな感性には、全くもって感服だ。パティトゥッチとウェックルは、従来からの颯爽とした魅力に加え、堂々たる風格を得て、コリアに対抗。三位一体となって、緻密で緊張感に溢れながらも、抒情的でまれに見る美しい世界を築き上げた。今年(2019年)の最高傑作ジャズ・ディスク!
|
|
|
初CD化!GRPバンドの前半4曲は、何と!全て歌ものだ。歌手は別人なので、当然バレンティンの出番は少なくなる。特に1曲目は「おいおいグルーシンさん、これは一体誰の作品なんだ?」というくらいで、これに業を煮やしたか、2~4曲目は、歌の間の隙あらば吹いてやる!という意気込みに溢れている。一方で、後半5~8曲目はバレンティン独壇場だ。この後半を見越して、前半4曲をセーブさせたのはグルーシンの戦略か。
|
|
|
ピアノの鮮やかなインプロビゼーション・ソロだ。こんなピアノがスイスイと弾けたら何と気持ちがいいことか、と羨ましくなる。曲もバーンハート作(共作含む)がほとんどで、作曲の才も充分だが、その中では(1)が飛び抜けてさわやかで印象深い。そのあとは、メロディアスという観点では、ややインスピレーションが落ちるか。
|
|
|
淫猥なジャケットの雰囲気に加えて、青春の空騒ぎとほろ苦さがブレンドされたような、なかなか面白い魅力を持った作品である。こんな音楽は、今のスムース・ジャズには望めないなあ。音質は、少し古ぼけている感はある。
|
|
|
まず、キリッとした別嬪さんのジャケットがいいね。声は、ややハスキーな中低音と、一方で、長く伸びる透明度の高い高音が魅力だ。比較的ゆったりした感じのミドルテンポの曲が多く、落ち着いて聴ける。特に(1)(2)(5)(9)がお薦めかな。スムースジャズ界期待の逸材だ。
|
|
|
初CD化!は、喜ばしいのだが、LPから37年もかかるか。この頃のバレンティンのディスクは、バックがGRPバンドのものとバレンティン・バンドのものが組み合わさっていて、テイストが異なる。本作では、前者は(1)Pied Piper、後者は(5)ShamballaがGOOD。次作「In Loves Time」次々作「Flute Juice」がCD化できれば、GRP時代のバレンティンは完成だ。
|
|
|
今なお色褪せることのない洗練された傑作だ。ミルト・ジャクソンやヒューバート・ロウズもさることながら、最も印象的なのは、シダー・ウォルトンのフェンダー・ローズではないだろうか。どこか甘く、どこか哀愁を帯びたそのサウンドが心に響く。
|
|
|
’80年作で初CD化(祝)。よくもまあ、ここまでCD化しなかったものだ(当のValentinは亡くなってしまったではないか)。前半のファンク系と、後半のラテン系では趣が異なるが、いつもValentinは鮮やかだ。(2)のMarcus Millerのチョッパー炸裂もすごい。本作の後続「Pied Piper」「In Loves Time」もCD化して欲しいものだ。
|
|
|
これはいいなあ。実に味わい深い。ラリー・カールトンの辿り着いた境地がよくわかった。やっぱり「ルーム335」は名曲ですなあ。
|
|
|
ジャケット写真は、清楚で可憐な感じだが、なかなかどうして、声量豊かでスケールの大きなヴォーカルだ。硬軟緩急バラエティに富む印象的な作品揃いで聴く者を飽きさせない。レニー・ホワイト率いるバック・バンド(ピアノはドン・ブラックマンだ)とストリングス・ホーンズが奥行きを与えて、一層魅力あるものにしている。隠れ傑作。
|
|
|
これがマリリン・スコットのデビュー・アルバムらしい。全体的に、なかなか力強いヴォーカルだ。そんな中で、初々しく、ひたむきな情熱に溢れているのがとてもよい。ラッセル・フェランテたちのバック・アップもGood。ファラオの顔をした鳥のような女神(?)が笛を吹くと、魚が飛び出してくるジャケットの絵も秀逸だ。
|
|
|
いいですねー。70年代から80年代にかけての、ダイナミックで手数がものすごく多いマッコイ・タイナーは最高だ!録音も素晴らしく、ライヴの臨場感がビンビンと伝わってくる。個人的には、タイナー・ベスト3に入る傑作。
|
|
|
クラリネット、サックス、フルートを自在に繰るマルチ・プレイヤーぶりを遺憾なく発揮したダニエルズの快作(’78年作)。バック陣も豪華で、随所に入るストリングスも効果的だ。ただ、ダイナミック・レンジが狭いのか、特に、ベース、ドラムスの低音がこもった感じで重量感に乏しい音質がやや残念。
|
|
|
ベルリオーズのテ・デウムは、(宗教曲のためか)幻想交響曲や序曲のような快活で情熱的なところは見られないが、優美かつ壮麗な作品で、アバドの誠実な指揮が光る。ローマの謝肉祭とのカップリングもなかなか良いと思う。
|
|
|
シベリウスのヴァイオリン&オーケストラ作品がまとめて聴ける好企画盤。有名なヴァイオリン協奏曲以外の小品集においても、シベリウスらしいオーケストレーションが施されていて、シベリウス好きにはたまらない。テツラフの透き通るような美しさは絶品だ。
|
|
|
シベリウスは、第4交響曲以上に寒々とした厳しいサウンドが特徴で、全体に緊張感に溢れている。はっきり言うと、しばしば聴きたくなるような作品ではない。ディーリアスのクウァルテットは、シベリウスに比較すると温かみがあり、ディーリアス調の息の長い弦楽合奏的な分厚いサウンドが魅力だ。オーケストラ曲の名手である二人にとっては、やや地味な作品であるが、それぞれの「らしさ」は十分認められる。
|
|
|
ネルソン・ミサは、多作家ハイドンの中でも最高峰の位置にある作品と言えるのではないだろうか。困窮時のミサとも言われるが、困窮時をひたすら耐え忍ぶのではなく、未来の希望へ向けた明るさも表現しているのが良い。フェレンチクの演奏は、派手さは無いが着実で、落ち着いて聴ける。併録のアバドの静謐なシューベルトも優秀。
|
|
|
枝葉末節なことだが、ドホナーニの六重奏曲の終わり方が面白い。この終楽章の基調はハ長調だが、終盤に転調して別の調(変ニ長調)になってしまい、そのまま終わるかと思った最後の最後でジャン、ジャンとハ長調に強制的に戻すのだ。これは、まるで吉本新喜劇のすっちーとギターの松浦が、落ちを言った直後にジャン、ジャンと〆るところと共通する大阪的ノリである。ドホナーニがお笑いの心を持っていることに敬意を表しておく。
|
|
|
2曲とも全体的には優美で、シューベルト、シューマン、ブラームスあたりを混ぜ合わせたような感じがあり、ドゥムキー(第4番)を始めとする後年充実期の作品と比較すると、ドヴォルザークの個性は薄い。でも、それはそれ。時折聴いてみたくなる魅力は十分有している。スーク・トリオの演奏も充実している。
|
|
|
恐怖をテーマにしながら、クラシック音楽の歴史を俯瞰できる面白い1冊。色々な恐怖が紹介されているが、一番怖く感じるのは、スターリン独裁国家権力に追われまくったショスタコーヴィチであろう。下手なサスペンスよりよっぽど怖い。
|
|
|
スタッフ3作目。それまでとは異なり、ブラス、ストリングス、コーラスが入るが、スタッフ特有のグルーヴ感は健在だ。1、2作目と比べて人気が低い(ように思う)のは何でだろう。リチャード・ティー作の④⑦、ゴードン・エドワーズ作及び歌の⑧⑨が出色。
|
|
|
ブルージー&ジャジー。少し聴きかじっただけでは安っぽい感じがするが、よく聴くと、下町情緒のある味わい深い軽妙なギターだ。タコ焼き、きつねうどん、串カツのような親しみがある。
|
|
|
グルーシン最初期の'62年録音。ライトでムーディなアレンジと洗練されたピアノは、その後のフュージョンやGRPビッグバンドでの活躍を彷彿とさせるものがある。自作⑧も秀逸。惜しむらくは、ストリングスの録音が、右側のみに定位していて広がりに欠けるところか。
|
|
|
フィリス・ハイマンが歌う3曲とサンタナが主役となる3曲が交互に配置されているが、雰囲気が異なるので、ちょっと戸惑う。個人的好みでは、ハイマンの3曲は五つ星。サンタナでは④のスタンリー・クラークのソロがいいと思う。ところで、日本語解説書やオビには、デジタル・ミラー(syn)とあるが、デンジル・ミラーの誤りだ。
|
|
|
宗教曲においても、プーランクは都会的で垢抜けている。両曲とも随所にプーランクらしい洗練されたハーモニーが現れて、宗教曲ながらとてもさわやか。プレートルの指揮は、荘厳性を保ちながらも重すぎず、絶妙の味付けだ。
|
|
|
小生は、古楽でも現代楽器派であるが、この盤は、正に現代楽器が威力を発揮している典型ではないかと思う。イタリアらしい軽妙でエレガントなコレッリの音楽に、グリュミオーの麗しく気品ある現代ヴァイオリンがピッタリとはまっている。痩せたサウンドの古楽ヴァイオリンでは、こうはいかない。
|
|
|
知る人ぞ知るシャルヴェンカとパデレフスキの協奏曲が入っているのがミソ。曲自体は、併録のガーシュイン、リスト、モーツァルトに比べると、格が落ちるのは否めないが、アール・ワイルドの華麗で鮮やかなパフォーマンスがカバーしている。バラエティに富む作品群が聴ける楽しいセット。
|
|
|
サティと言えばチッコリーニ、と口をついて出るくらいだが、実を言うと聴いていなかったので買ってみた。なかなか都会的で、うまいビールのようにコクとキレがある(ちなみに、田舎的という意味ではデ・レーウ盤がいいと思う。チッコリーニとは全然違う)。録音は、強音時にちょっと硬くなるところがあるようだ。
|
|
|
バッハがラテン風にアレンジしてある。マンドリン?、ギター、ベース、パーカッションが基本で、時折ピアノ、ヴァイオリン、クラリネットなどが入る。バッハ以外にヴィラ・ロボス始めブラジルの有名な音楽家の作品も散りばめられている。ラテン的パンチには欠けるが、スマートで楽しいアルバム。
|
|
|
81年作。相変わらず高級ブランデーのような芳醇なヴォーカルが素晴らしい。収録曲も、随所にちょっと屈折した哀愁が感じられる独特の味わいがある。30年以上経っても全く色褪せない傑作だ。
|
|
|
張りのあるシャキッとしたヴォーカルが魅力だ。R&B/ソウルというよりも、ジャズ・フュージョン系のサウンドで、そちらのファンも楽しめる。表題曲③で歌にサックスに活躍するロニーと④でソロをとるヒューバートのロウズ・ファミリーや、リズムを押さえるネイザン・イースト、ローランド・バティスタほかサイド陣も上等。
|
|
|
これがビル・エヴァンスの最後のスタジオ録音だそうだ。クインテットになっても、ビル・エヴァンスはビル・エヴァンス。最後まで自己の美学を貫いた究極の演奏だ。2曲のピアノ・ソロも泣かせる。
|
|
|
メインのピアノ協奏曲は、グリーク、プロコフィエフ、ラヴェル、ラフマニノフを混ぜたような感じで、時に現れる抒情が美しい。第一ラプソディ、パストラル、海の牧歌は、ドイツ・ロマン派風だ。全体にイギリスらしさはあまり感じられないが、それなりの佳曲集ではある。
|
|
|
今や押しも押されぬ大家となったコヴァセヴィチだが、70~80年代の若き頃の録音も、溢れんばかりの瑞々しい魅力がある。本BOXでは、作品自体が保有する意志の強さや奥深さの上に、コヴァセヴィチの水も滴るタッチの美しさと希望に満ちた生き生きとした表情が加わり、独自のベートーヴェン像を打ち立てている。
|
|
|
プーランクの洗練された音楽を、水を得た魚のごとく、自由自在に描き切るデュトワが素晴らしい。聴いているだけで、パリの街やフランスの風景が目に浮かぶようだ。録音も非常に優秀。
|
|
|
アンドレ・プレヴィンの鮮やかなピアノと、ディヴィッド・ローズ指揮のストリングスが絶妙に絡み合ってムード満点だが、モノラル録音でこもりがちな音質が難点だ。ヘッドフォンで聴くよりも、音量を抑えたスピーカー・システムで聴くほうがいいかも。
|
|
|
ビル・エヴァンス晩年の名作。自殺した元恋人や兄に捧げる曲が入っていることや、エヴァンス自身もこの録音後すぐに亡くなってしまうこともあり、人生のはかなさを感じさせる。涙無しには聴けない(というのはちょと大げさか)。
|
|
|
デイヴ・ウェックルは、世界屈指のドラマーの一人であることに異論はないが、リーダー作となると、「Dave Weckl Band」名義のものは、ハイテクニカルではあるものの、何か無味乾燥なところがあった。しかし、本作ではリーダー作デビュー時の盟友ジェイ・オリヴァーとのコラボが復活、実に生気溢れたダイナミックな音楽が繰り広げられている。やっぱりジェイ・オリヴァーが必要だった、ということか。
|
|
|
本盤のライナーには、デイヴ・グルーシンは1934年生まれとあるので、もう80歳ということになる。長らく共に活躍してきたリー・リトナーとのコラボなので、演奏内容は悪かろうはずがない。が、今回はすべて過去の人気曲のライヴ再録で、新曲のないのがちょっと寂しい。80歳なので、元気にやっている姿を見せてくれるだけで満足と言えば満足なんですが・・。
|
|
|
イリアーヌは、モダン・ジャズをやらしても素晴らしいが、こういうラテン系作品ではヴォーカル含めて実にリラックスしていて、楽しく聴ける。今回は、エレクトリック・ピアノやフュージョン調のリズムも取り入れて、この上なく洗練された音楽となっている。
|
|
|
シマノフスキのヴァイオリン曲は、2曲の協奏曲もそうだが、本盤のヴァイオリンとピアノの曲集においても、実に透明度が高く、気高さの中に妖艶さが漂うような不思議な魅力がある。後期ロマン派・印象派の音楽が好きな人にも薦められる。録音も優秀。
|
|
|
80年代ラトル若き日の生き生きとしたシベリウスだ。ポピュラーな第1番、第2番はもとより、第4番以降の内面的な後期作品でも決して底が浅くなく、充実したオーケストラの響きを見事にコントロールしている。さすがに、後年ベルリン・フィルを任せられるだけのことはある。ラトル初期の大傑作。
|
|
|
「フーガの技法」も「音楽の捧げもの」も、バッハ畢生の名作であることには変わりないが、短調の曲が続くためか、聴いていると疲れる(次は、ブランデンブルク協奏曲を聴こう、と思ってしまう)。でも、ミュンヒンガーの優美ながらも厳しく品格のある表現には脱帽だ。
|
|
|
Disc1のスクリアビンやプロコフィエフは、アシュケナージのような優等生的な演奏とは一線を画したグールド独特の香りが漂う。Disc3もグールドの独壇場だ。Disc2,4も含めて、実に広範囲の作品が楽しめる。
|
|
|
本盤に収録の傑作室内楽4曲(ます、アルペジオーネ・ソナタ、ヴァイオリンとピアノの幻想曲、八重奏曲)を聴いていると、シューベルトって本当にいいなあと思う。どの演奏も、落ち着いた中に華があり、何度も聴きたくなる。古いものは'57年の録音だが、最近のと比較しても遜色のない優秀録音だ。
|
|
|
少し鼻にかかったヴォーカルが魅惑的なアルバムだ。前半3曲は爽やかなポップスという感じだが、④以降はジャズ・フュージョン調になり、⑦はファンクっぽい。ストリングス&ホーンズのオーケストラに存在感があり、アレンジが優れている。ところで、このマデレインという人の作品はこれしかない(?)ようだが、その後どうしているのでしょう。
|
|
|
'69年の録音後、なかなか発売されなかったらしいが、名作「Happenings」、「Total Eclipse」に勝るとも劣らない傑作だ。立て板に水の如きハッチャーソンのヴァイブに、柔らかなハロルド・ランドのサックスがよく合う。④ではソロも取るレジー・ジョンソン、色々な技を繰り出すジョー・チェンバース、出しゃばらないスタンリー・カウエルら、サイドメンも秀逸。
|
|
|
トータルサウンドは垢抜けているが、ハッチャーソンのサウンドかと言うと、ちょっと違うように思う(③のみ比較的ハッチャーソンらしさがある)。ハッチャーソン自身もヴァイブは使わずマリンバのみの演奏で、他流試合あるいは出稽古をしに行った、というような作品だ。バックメンバーの良さで5つ星は進ぜましょう。
|
|
|
増尾好秋が最も輝いていた頃の最も充実した傑作アルバム。明るく爽やかな前半①~③、後半はやや趣向が変わり、寂しげな④、情熱的な⑥、和やかな⑦など、どの曲もメロディアスで親しみやすく、ハズレが無い。Keyboards、Bass、Drumsのバック3人もうまい。
|
商品詳細へ戻る