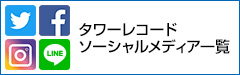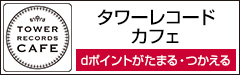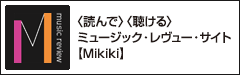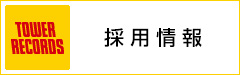――つまり、なんらかの制約みたいなものがあったほうが、ものは作りやすい。
石野 そうね。たとえば、好きなように絵を描いてくださいって言われても難しいじゃん。でも〈風景画〉って言われれば、そのなかでいろいろ考える。InKの場合、川辺が最初にネタを持ってきて、それをあれこれいじりまわすことが多い。最後のほうはそれもなくなってきて、フリー・スタイルになってたけど。
――どういうネタが多いの?
石野 いやもう、ダンスものかは関係なくて、誰も知らない昔のD級プログレとか、だっさいハード・ロックとかブラジルものとか。ふだんは絶対聴かないようなやつを、単なるネタとしてね。突拍子もないものをお題にして、それをいかに形にするかというので結構燃えたりして。元の素材に肉付けしたり、ズタズタにしたり、やっていくうちに元ネタはなくなっちゃったり。別のものに置き換えられたりするから、原型はまったくとどめなくなる。だから、昔の電気が“Shangri-La”でシルヴェッティをサンプリングしたのなんかとは全然違うよね。着地点が決まってないから、どこに行ってもいいっていうのがあってさ。それがさっき言った〈責任のなさ〉に繋がってるんだけど。そこが電気×スチャダラや(まりんがいた頃の)電気とは違うよね。決定的に違うのが、InKは落としどころがそこまではっきりしてない。スチャだったらラップを乗せるとか、電気だったら歌う人は決まってるけど、InKは、たとえば女性ヴォーカルが合うと思ったら自由に使える。自分が歌ってもいいし、歌わなくてもいい。今回も、最初はクラブ・トラックみたいなものを作ろうとしてたんだけど、やっていくうちに飽きて、箸休め的なものを作り始めたら、そっちのほうが面白くなって箸休めじゃなくなったり。
――なんか好きにやってる感じだね。
石野 思いつきっていうか。でもそれってすごく健全だと思うよ。
――じゃあInKに関しては、明確に方向性を決めてやる、みたいなことはない。
石野 そうだね。むしろ、それがこのユニットの特徴っていうか。InKってこういうグループ、みたいなものが定まってきちゃったら、存在意義も薄れてきちゃう。
――ファーストを出したことで、ファンの間では〈InKはこういうもの〉っていうイメージがある程度固まってると思うけど、今回それがぶち壊される可能性は大だよね。でもそれも想定の範囲内、と。
石野 そうだね。たぶんこの次はさらに変わるだろうし。ブランド・イメージみたいなものを、後生大事に守り続けていくのは性に合わないし。電気だって、やってる側としては明らかに視点が変わってきてるからね。
――まあ電気は瀧がいるから。
石野 うん。あとは何やってもいいっていうのはあるよね(笑)。
――川辺くんの存在は、あなたにとって創作のモチベーションを高める触媒として重要だと思うけど、ベテランのアーティストにとって一番重要なのはそこじゃないかな。ベテランだから引き出しはすごくたくさんあるけど、その中から、いかに中身を取り出していくかという、一番最初のモチベーション。それをどうやって設定していくか。
石野 うん、それは今のところ困ってないかな。締め切りとか、アウトプットしなきゃいけないっていう〈義務感〉がモチベーションをはるかに上回ってると、危険だけど。やってる側もつまらないし、聴いてもダメだと思う。
◆来週は〈四十路を控えて〉編をお送り致します!