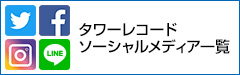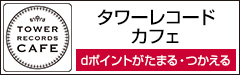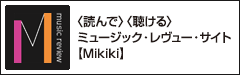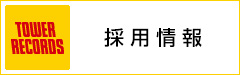――とあるミュージシャンが、はっぴいえんど『風待ろまん』のジャケットに4人のサインをもらってたのを見せてもらったことがあるんですけど、大瀧さんからもらう機会を得るのにすごく時間がかかったって言ってましたね。
湯川 あっ、私も同じことしてますよ。3人は埋まったんですけど、大瀧さんからはまだもらえていないですね。
――さて、今回お三方がカヴァーした楽曲についてお訊きしようかと思うんですが。まず、しおねとだんの“木の葉のスケッチ”から。
宮川 これは〈秋冬盤〉って言われたときに最初に浮かんだ曲で。そのときに、女性といっしょに歌いたいなっていうアイディアもなんとなく浮かんでいて。この曲が入っている『EACH TIME』は、ちょうど小学校5、6年のときによく聴いていたアルバムで、そのときは〈オトナになったらこういうことがあるんだろうな〉って妄想しながら聴いていたんですけど、実際にオトナになって、〈こういうこと〉ってほとんど……(笑)。
堂島 なかったんですね(笑)。
宮川 だから、そういう思いに決着を付けたいなっていうのもあってこの曲を選んだんですよ。そういう決着の場に潮音ちゃんを付き合わせて申し訳ないんだけど(笑)。誰と歌おうかっていろいろ考えてるとき、渋谷で偶然、潮音ちゃんに会って。なんか、その後ろ姿を見ながら、〈あっ、これだよね〉って(笑)。
湯川 (笑)。
――運命を感じますね。
宮川 はい、ここは無理矢理にでも〈運命です!〉って言いたいですね(笑)。
――潮音ちゃんのヴォーカルがいつもと違う印象を受けるんですけど。
湯川 この曲の中に出てくる女性は、〈弾さんと同じぐらいの年の女性かな?〉って思って(笑)。やっぱり、歌詞とメロディーの混ざり方は素晴らしいなと思ったし、すごく画が想像できたんです。映画のワンシーンみたいな。だから、ちょっと女優さんになった気分で(笑)。
――一方の堂島くんは“座 読書”。かなり挑戦的な楽曲を選びましたね。
堂島 実は、半強制的にこの曲に決まったんですけど。萩原健太さんと能地祐子さんが司会をされている〈ナイアガラまつり〉っていうトーク・イヴェントに出演したときに今回の企画の話をしたんですけど、いままで“君は天然色”と“ペパーミント・ブルー”をカヴァーしたことがあるんで、〈次は何をカヴァーしたらいいと思いますか?〉ってその現場で訊いてみたんですよ。そしたら健太さんが〈“座 読書”でしょう!〉って言って、会場もすごく盛り上がって。〈“座 読書”やったら男だよ!〉って言われて、逃げ場がなくなっちゃたんですよ(笑)。
宮川 その男道もどうかと思うけど(笑)。
堂島 (笑)。でまあ、この曲の原曲はセカンドラインの演奏をしてるんだけど、ミックスはぜんぜんセカンドライン風じゃなくて、シモンズみたいなエレドラも鳴ってたりして、結構異常な曲なんですよ。そのまんまはやらない大瀧イズムというか。だから、僕もそれに倣って、大瀧さんの“座 読書”のままにしないためにいろいろ考えたんですよね。で、楽団編成でライヴをやる機会があったんで、総勢15人のメンバーと800人のお客さんで〈読書!〉って叫んで、それをライヴで収録して。そういうところで、大瀧さんの音楽家としての精神を自分なりに表現してみたんですよ。
――ところで、大瀧サウンドのおもしろさ、魅力って、みなさんはどんなところだと考えてますか?
宮川 フィル・スペクターの〈ウォール・オブ・サウンド〉があって、〈ナイアガラ〉があってって、いうルーツの流れは僕にとってどうでもよくて。たしかに、ピアノを何台か同時に録ったりとか、ギター4人同時に録ったっていう話を聞くと〈へぇ~〉ってなりますけど、僕が(大瀧サウンドを)体験した時代が80年代だったから、もうその時代の音と思っちゃっていて、バックボーンみたいなものはどうでもよくなっちゃってて。日本においてこういうサウンドを確立させたってこと自体が、重要に思えるんです。松本隆さんとのコンビネーションとか、ここまで歌詞とメロディーの展開が同調しているものって、いまはそんなに作られていないというか。それをどうやって受け継いでいったらいいものかなあって、考えてるんですけどね。
――大瀧詠一的スパイスを効かせたものってご自身の作品の中にあります?
宮川 無意識に影響が出ちゃったっていうのはあるかも知れないですけど、なにを落とし込んだかっていうのは自分ではぜんぜんわかんないなあ。意識的にやったことはないですね。
堂島 僕はありますよ。去年出した『SMILES』っていうアルバムでやりましたけどね。大瀧さんの音楽で僕がいちばんすごいなって思うところは、ナンセンス・ソングとかノヴェルティー・ソングっていうものでも、あくまでもポップ・ミュージックとして仕上げているところ。それってすごく難易度の高いことだと思うんですよ。タフで自分に自信がないと出来ないことだなあって。実際、ものすごく時間がかかるし、精神力が要るし。で、自分も作り手としてトライする価値があるなって思って、言葉遊びみたいなところから熱量の高い曲を作ろうと思って作ったのが、『SMILES』に入ってる“てんでバラバラ”っていう曲なんですよね。
――潮音ちゃんは完全に後追い世代になるわけだけど。
湯川 大瀧さんがデビューされた頃っていうのは、日本の音楽もまだ土壌が固まってなかった時代だと思うんですけど、大瀧さんは日本のロックとかポップスの〈始め〉の方だと思うんですね。なにもなかったところからいろんなアイディアを生み出していって、おもしろいと思ったものに抵抗を感じず飛び込んでいって、それで結果的に新しいものを作り上げていった人。日本の音楽をすごく豊かにしてくれた方なんじゃないかなと思います。