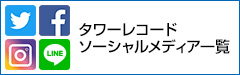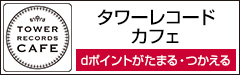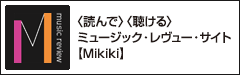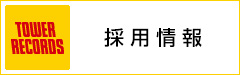ご好評のうちに終了した〈CDは株券ではない〉に引き続きbounce.comでスタートした音楽批評実験〈菊地成孔のチアー&ジャッジ~全ブロガー参加型・批評実験ショー〉。菊地成孔が1つの楽曲に対し、〈大絶賛〉と〈酷評〉の2つの立場からまったくことなるレビューを書き、「その2つのどちらが優れているのか?」を読者の皆さんのトラックバックによって決める。という、ブロガー参加が前提の実験場です。今回は、5年ぶりのアルバム『Sensuous』のリリースを10月25日に控えたCorneliusのニュー・シングル“MUSIC”を批評します。ブロガーの皆さんはぜひお気軽にご参加ください。
どうもどうも。お待たせしました。ワタクシ菊地成孔の仕事の中でも、進行が最も遅い事が定着し、〈遠洋漁業〉と言われている「菊地成孔のチアー&ジャッジ」です。今回はCorneliusさんの話題の最新作、実に5年ぶりのシングルである“MUSIC”をチアー&ジャッジさせて頂きます!
さて、Corneliusで検索してここに辿り着き「なんだこら?」という方々もたーくさんいらっしゃると思われますので、物凄く簡単に説明しますと当連載は〈ブロガー参加型のゲーム〉という趣向になっておりまして、
はいルールはコチラ!ドーン!
と、いつも思うのですが、〈コチラ〉をクリックして、全然関係ないエロ画像が出て来たら良いのに。どうして誰も〈デタラメなリンク貼って混乱させる〉というイタズラをしないのか? なんでも良いから難しい論文が書いてあって、難しい術語が出て来たら〈詳細はコチラ〉とし、クリックして飛んで行ったらヤギの交尾の写真が出て来た。最初から最後までそんなんばっかりのブログがあったら面白いのにー!といった、毎年おなじようにせつない夏の終わりですが、今回も早速行ってみましょう。
チア~エーンドジャーッジ!!
チアー菊地(以下「チア菊」)「ワタクシはCorneliusさんの“MUSIC”を支持致します」
ジャッジ菊地(以下「ジャチ菊」)「ワタクシはCorneliusさんの“MUSIC”を不支持します」
チア菊「お互い紳士的に、かつ徹底的にやりましょう」
ジャチ菊「はい。望む所であります」
チア菊「とはいえ今回、ちょっとやりずらいな~」
ジャチ菊「小山田氏とはほんの若干だけれども知古があるからね。ゲームとはいえ知古やリスペクトがある人の作品をチアーしたりジャッジしたりするのは難しい。“テルーの歌”みたいにはいかないよ(その後“テルーの歌”は結構売れましたね←菊地注)。一緒にタイにツアー行ったりしたしなあ。あのときは楽しかった。2年前の9.11。ツアー・コーディネーターがミュージシャンを二派に分けてね。オフデイの観光コースを2つ作った」
チア菊「ひとつは大自然の中、世界遺産の遺跡を見に行くツアーで、もうひとつはジョン・マーク・カーも入り浸ったと言われるバンコク市内の少女売春のマーケットを中心にしたあらゆるヤバい場所巡り」
ジャチ菊「どっちがどっち。なんてことは書けないけど、ファンの方々のためにも、小山田氏が前者だった事だけはハッキリと書いておこう」
チア菊「っていうか、後者はウチラ(菊地成孔)だけだったわけじゃない(笑)。二派つったって、ウチラとそれ以外なんだよ(笑)。川○正○さんはウチラと完全同行したけど(笑)」
ジャチ菊「ダメだぜんぜんはじめられない(笑)。まあ、小山田氏はスマート&クレバーな人だし、楽しんで貰える様にチアー&ジャッジするしかないな」
チア菊「恒例になってきたけど、最初に大ルール決めようよ。今回は〈 Flipper's Guitarについては触れない〉としない?」
ジャチ菊「どうして? 少なくとも現在(06年9月)におけるタワレコのインディー・チャートではFlipper's Guitarの再発群がブッチ切りで上位独占。という状況なのよ。フィッシュマンズ・リユニオンの一連の動きも含め、「CDは株券ではない」時代のテクニカル・タームである〈90年代ノットデッド派〉のパワーや〈リヴァイヴァル周期の縮化傾向〉などについて、触れずにおけるのだろうか?」
チア菊「だってリアルタイムでちゃんと聴いてないんだもの。少なくともフリッパーズからの派生関係、発展関係、小山田氏における90~00年代の推移。という視点からは何も書けないよ」
ジャチ菊「わかった。じゃあ、その事を断った上ではじめよう。我々は、宇宙に前ぶれなくいきなり93年にCorneliusがデビューしたかのような歴史観しか持ち得ない。という事でご了承ください」
チア菊「あともうひとつ。このシングルはトラックが5つ入ってるんだけど、扱うのはトラック1の“MUSIC”に限定しよう。いろんなタイプの曲が入っていて、話がまとまらなくなっちゃう可能性があるから」
ジャチ菊「了解であります」
チア菊「じゃあ聴きますよ。ワクワクするなあ。ポチンとな(CDプレイヤーのスイッチを押す)」
(4分54秒後)
チア菊「今回は簡単だろう。断然チアーだよ~」
ジャチ菊「同感だな。今回はイージーだよ、完璧ジャッジでしょう」
チア菊「何故? 前作『POINT』から言える事だが、そしてワタシも自著「歌舞伎町のミッドナイト・フットボール」の中で書いた事だが、〈アンファン・テリブル=恐るべきコドモ達〉としてデビューした小山田氏は、ソロ活動でオトナになって行く過程を実に見事に見せているではないか。渋いな~今回。一番グッと来たのは歌が上手くなっている所だけど、とにかく一切無理していない。全てがお家芸だけで出来ていて、しかも円熟の香りがするね」
ジャチ菊「そこが最大の争点になると思うけど、まんまジャッジの理由だね。Corneliusが〈驚かせたり、ワクワクさせたり〉をしない存在だとしたら、止めた方がマシだよ。と言ってしまおう」
チア菊「そうかあ? Corneliusって、実は一番最初から〈定番感/円熟感〉を築こうとしていた気がするけど。斬新さやエッジ感はオマケだったと思うな。オマケなのにもの凄かった訳だけど」
ジャチ菊「それはクールなポーズを鵜呑みにしただけでしょ。斬新さやエッジ感はCorneliusのライフラインだよ。定番感や円熟感なんて自然に出てくるモンじゃないの」
チア菊「それならいいじゃないか。ナチュラルな円熟感を味わおうよ」
ジャチ菊「いや~そこの判断が微妙じゃないの。円熟とエッジは本来相容れないが、今作には〈エッジという円熟〉みたいな、アンビバレンスに溢れてる。問題は、それがどう伝わるかだと思うのよ。これ、例えば〈『POINT』の手法で作られた“STAR FRUITS SURF RIDER”とかって、ライター諸氏に書かれちゃうと思うんだよ。すげえ大雑把な話ですが」
チア菊「まあ。そうかもね」
ジャチ菊「〈オトナになった〉つうのも、言われると思う」
チア菊「そりゃそうでしょ」
ジャチ菊「それじゃダメなんだよ。一カ所で良いからキレキレのエッジの瞬間を刻んでおかないと」
チア菊「どうして? どうしてCorneliusにだけそんな、義務みたいな物を与えるんだ?」
ジャチ菊「〈もう終わった〉もしくは〈素晴らしい円熟の境地〉という、同じ表面から導かれるであろう両極端な論調の分離を防ぐためよ。防げないんだったら良いんだよ。それこそナチュラルな衰退であり、落ち着きであり、円熟じゃないか。そういうのは本当に不可避的でしょう? それこそリアルにオトナになったって事だ。だけど、この作品は、はっきりしないわけよ。まだ余力が有るのに、敢えて余裕で円熟ぶりをポーズしている様にも見えるし、本当にエッジである事に興味もしくは実力を失ってしまっている様にも見えるわけ。ポップ・ミュージックにおけるエッジってのは、最短で1秒あれば充分示せるんだからさ」
チア菊「実際はどっちだと思うの?」
ジャチ菊「それが解らなくて気持ち悪いんだよ。凄く気持ち良い音楽なのに、気持ち悪い。だからジャッジであります」
チア菊「うーん。そんな事で苦悶する必要まったく無いと思うけどね。シンプルに気持ち良いじゃない。凄く。楽しもうよ“MUSIC”を」
ジャチ菊「それはCorneliusの中に青臭さとか生意気さとかの痕跡を必要としてないからだよ。単なる円熟至上主義、オトナ至上主義、もしくは逆に〈気持ちよければ何だっていいじゃん〉っていう退行的な幼児主義だろ。それは」
チア菊「だって最初に、フリッパーズからの派生関係、影響関係は触れないって言ったじゃないか。オトナ性とコドモ性という、結構重要な問題をCorneliusに仮託するとしたら、フリッパーズから考えはじめないと絶対に答えは出ないと思うぞ」
ジャチ菊「そりゃそうだな。解った。まとめに入ろう」
チア菊「オーケー。ではワタシから。これは音響派だとかエレクトロニカとか、言い方はなんでも良いんだが、例えば、シンセのシークェンスにだんだんとディレイがかかり、それがこう、ブワーと音量を上げていって、ブチっと止まり、次のフェイズに入る。なんていう手法は、現代では在り来たりなフィル・インとして、誰だってやる。アイドルだってやる。しかし、このトラックでのそれは、歌に入る直前の、最初のブレイクは、そんな〈当たり前になった、定着的な手法〉でも、名人がやると、その数小節だけでも感動してしまう程に美しいんだ。という事を余裕で示している。数ある〈シークェンスにディレイがかかって、それが切断される〉瞬間の中のベスト名人芸がここにある。ポップ・ミュージックを音響として捉える。という耳の良さにおいて、明らかに世界水準だ。そういう言い方をすれば、このトラックは隅から隅までそうした名人芸だけで構成されている。
〈青臭さ〉ですら、それは立派な名人芸であり、だからこそ小さいがはっきりと聴き取れる〈オトナ感〉が生じる訳だ。今作は、確かにビックリするようなガジェットは無い。挑発性も高踏趣味も無い。淡々と、ライフサイズ・ミュージックとして、全ての楽器の音がフラグメントにカッティングされ、ペーストされ、エディットされる。点描的な手法は、リキテンシュタインのドット画法を思わせる、エッセンシャルかつポップな物だ。そして、今までよりもちょっと力強く繊細な歌が歌われる。これこそ21世紀の、オトナのフォーク・ミュージックだ。その事に感動した。
比較するのは最初のルールに反するが、同じ〈アンファン・テリブル発オトナ行き〉の切符をまだ握ったままと思われる小沢健二氏が、オトナ化に関して、ジャズだニューヨークだとしゃにむに突っ込んでは自爆した後、実に奇妙な形に定着しつつある様な状況に対し、生物学的にも立派な大人である小山田氏の余裕は素晴らしい。5年間シングルというアイテムを待たせておいて、コレを出す。5年後にはエッジではなく、当たり前の手法として、そして自分こそがその名人として存在している事を見越していたかのようである。90年代リヴァイバルが欲しい人も、00年代スタンダードが欲しい人も、無理無く気持ち良く聴けるだろう。繰り返すが、これこそオトナの仕事だ」
ジャチ菊「優れた才能という物は、最初は青臭くそして危険極まりない物である。そしてそれはやがて、夭逝しない限り、オトナ化、老化、という道を辿るだろう。オトナ化、老化は、最初は隠された内的な準備として生じ、やがて一気に表面化するが、その瞬間というものは旧皮が剥がれるように痛い物だし、痛くない限り、それは痛みを回避しようと予防線を張った、先回りオトナぶりのポーズに過ぎない。我々はある日突然、黒木瞳が老け出した瞬間を知っている。ある日突然、ギター侍が面白くも何ともなくなった瞬間を知っている。ある日突然、エルヴィス・プレスリーからロックンロールの神様が出て行った瞬間も知っている。それらは全て痛みを伴ったが、姑息な〈オトナ先回り〉よりは遥かに尊いものだ。
Corneliusにもその日は来るかもしれない。来たらそれは受け入れるしかない。それは死と同じ、摂理の様な物だ。しかし、今がその時だとはとても思えない。確かに発される音は一音残らず美しい。音も絵もコンピュータライズに向かう現代にとっての、桃源郷の様でさえ有る。しかし例えば、シークエンスとディレイの作法に関しては、このトラックのエンディングを聴けば、そしてレイ・ハラカミの作品と比すれば解る。点描的な手法、それの整数的な組み合わせの秘法に関して、このトラックはレイ・ハラカミの平均的な作品より劣ってしまう。しかしそれはイマジネーションの実力差ではなく、単なる油断の様に思えてならない。
恐れるのは、前述の〈先回りしたオトナぶりのポーズ(力抜けましたよ。タイトルもストレートですよ。シーンも気にしませんよ今更。といった)〉をCorneliusが演じている様に〈見えて〉しまう事だ。Corneliusは、そんな、実にアンファン・テリブルがやりそうな事。を、今やする気も、必要性も無いだろうに。だからこれは〈批評家やファンが、そう誤解してしまう〉という意味ではない、〈見えてしまう〉というのは恐ろしい事で、実際に(本人も含め)〈そうなってしまう〉可能性があるからだ。円熟が痛みを伴った本物であるのなら、小山田圭吾名義にすれば良い。まだまだ〈Cornelius〉には出来る事がある筈だ」
※この記事を読んだブロガーのみなさんは、チアーとジャッジのどちらを支持するかをトラックバックで表明してください。詳しいルールはこちらをご覧ください。
▼菊地成孔関連作品を紹介