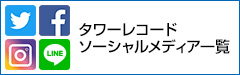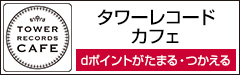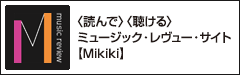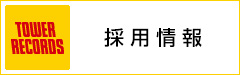ヤン富田が語る、ミーム(音楽遺伝子)たち その4BALLAD(バラード)、JAZZ(ジャズ)、SURF MUSIC(サーフ・ミュージック)、DOOPEES(ドゥーピーズ)
■BALLAD
音楽の琴線に触れる部分。メロディの美しいものがすごく好きで、音楽に目覚めたきっかけというのも、そこにある。それは楽典的にメロディが綺麗ということもあるんだけれども、楽典じゃないもの、普通はノイズ、サウンド・エフェクトって言われちゃったりするものでも、バラードのメロディーと同じくらいに琴線が触れることがあったりする。楽典以外のものも楽典と並列に音楽とすると音楽の幅や可能性はすごく広がるんだよね。
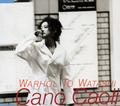
かの香織『ウォーホールと私』(現在は廃盤)
例えば、毎朝起きて〈今日は清々しい〉とか〈今日はどんよりしている〉とか思うでしょ? それってとても音楽的なんだよ。以前、かの香織さんのプロデュースを頼まれた時(ミニ・アルバム『ウォーホールと私』収録の"スコール")、その歌が〈彼のいるところに向かって小雨の中を歩いていく〉っていう情景のラヴ・ソングで、彼女のピアノの弾き語りがすごくよくて。僕は曲を聴いたときに、青山のベルコモンズの交差点のあたりの小高い坂、あの辺の感じだなって思った。それで朝早く青山に行って音を録ったんだよね。ちょうど雨が降っている感じ。「この空気感がこの曲の琴線に触れる部分とおんなじなんだよね」って。で、その録ってきた音を被せたの。アレンジという意味では自分としてはうまくいったな、と思っている。
■JAZZ
楽典的な部分で捉えると、コンピューターを使った音楽で一番それっぽく作れるものってジャズのアドリブなんだよ。マイルス・デイヴィス風のソロとか、チャーリー・パーカー風のソロとか、コルトレーン風とか、コンピューター・ミュージックの最前線では一番表現しやすいものなんだ。和声の進行に対する手癖とかあるじゃない? そういうものって意外と予測可能だったりする。だから〈魂の叫び〉とかいわれることもあるけれど、フレージングという手法に限定して言えば(ジャズは)すごく数学的な音楽だったりもして。
どんなフィールドでも好きなものもあれば、ピンとこないものもある。すごいものもあればたいしたことないものもある。ただ、「すごい」とか「面白い」って思うものには共通項があって、それはその人の生き方の姿勢とか、その人自身が面白かったりするんだよね。東西の冷戦が終わる前までは確固としたイデオロギーがあって、〈理論より行動が生まれる〉っていわれていた時代なんかもあったりして、人よりも沢山本を読んで理論武装したりするのだけど。でもその後、イデオロギーが飽和してしまって何が残ったかっていうと、理論よりも、物事に対する姿勢そのものが大事なんだっていうことなんだと思う。それはつまり、ジャズの和声理論を習得し技術を磨いたところで、その音楽の面白さや凄さはその点にあるのではなくて、音をだしてるその人の姿勢そのものが問われているのだと思う。
■SURF MUSIC
サーフ・ミュージックはね、70年代からずっと作ってきた。ただそれだけ。でもやってる人は気になる、ご縁があれば〈津波サウンズ〉で発売もしちゃう。
■DOOPEES
年とっていくと、段々手垢にまみれていくじゃん。40歳になったら40歳なりの音楽をやったりとか。50歳になったら50歳なりの音とか。それはそれでいいんだけど、でも、それだけじゃ嫌なんだよね。やっぱり最初に音をだした頃の、自分がこだわってきた気持ちっていうのは無くしたくない。だからさ、風貌とか見てくれは歳をとっても、音を出すところの気持ちは錆び付かせたくないわけ。自分のなかで音楽は、そこを再確認するものでもあるし、そこに立ち返ることもできるし、永遠に若くいられるものでもあるんだ。『DOOPEE TIME』を作ったときに、自分は43歳だった。キャロラインちゃん役のボーカルは実は当時30歳だったんだ。でも気持ちは17、8歳のときの気持ちで作ったの。もし、70歳になって音楽をやれてたら、多分DOOPEESもやっているんだよね。だけど、出てくる音楽はその頃の気持ちに立つ。そういう気持ちでやる。