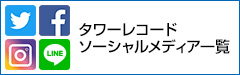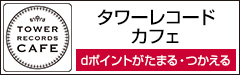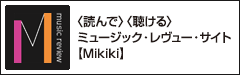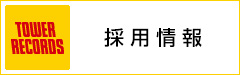チ「えー話戻しますが、それこそワタシのチアー・ポイントなわけです。〈彼女はこの作品の女神です〉とかね、〈ハウルの動く城〉で父親によって去勢された〈美少女キャラ〉という存在の、息子による大復活とかね、谷山浩子とかヤマハとか、萩原朔太郎にインスパイアされて息子が歌詞を書いたとかね。正直キツいと思わせるに充分な駒ばかり。ジブリというのは、キツイものだった筈の〈アニメ〉を、キツくないどころか、日本の文化的なスタンダードにまで押し上げたという、すさまじいカリスマがあったわけですが、39歳という息子の代になって、それが一挙に破綻するのではないかと思わせるに充分な」
ジ「きみチアーだろ!」
チ「いや。だからこそですよ! どんなキツい、困っちゃうような歌声で癒され、生きる力を与えられちゃうのかとドキドキしていたらですね。この人、普通に良い声の、普通にとても良い唄です」
ジ「まあ例によって同じポイントを両側から挟み込む形になったな」
チ「適度に音程修正された初々しさと、しかし大器の可能性は充分に感じる。という、〈良い新人〉の典型的なパターンだったので正直驚きましたよ。ワタシ今回、ジャッジに回るのかなー。と思ってましたから」
ジ「アレンジの力がでかいよね。寺嶋民哉氏はテレビ、映画、舞台ミュージカルなど、劇伴の職人肌ですが、この曲の大胆かつ緻密かつ雄大なオーケストレーションは、前回あたりに話題になった〈壮大なオーケストレーションはロールプレイング・ゲームの音楽にしか聴こえない〉という絶望的なテーゼを悠々とひっくり返してますなあ。コード進行でちゃっちゃっと手軽に分析出来ないよ。谷山浩子氏の童謡みたいなメロディーが、ありきたりなJ-POPサウンドや、癒しオーケストレーションに支えられたらトラックの魅力10分の1でしょ。寺嶋氏は世代的にル=グィンの思想に影響を受けて、心血を注いだ様にすら思えます。ちょっとワグナーみたいなね。オーケストラのリズムの動き方も凄いもんね」
チ「それこそあなたジャッジしてないじゃない!」
ジ「いやだからさ、唄がもっとエグい感じのさ、目がブッ飛んで児童唱歌でも歌ってるみたいな感じがあったら大爆発だったわけですよ」
チ「そうかなあ。それは旧ジブリの美学じゃない。代替わりしてセンス変わったと考えたいですね。少なくとも主題歌的には」
ジ「だったら、売り上げもファクターに入れよう。〈CDは株券じゃない〉時代と違って、もうこれ売ってるんだから」
チ「初登場5位で、月間10位以内をキープしています」
ジ「でしょう。これって、ここ最近のジブリ作品の主題歌の、平均的な売れ方そのままなのよ。少なくともセールス的には変わってないんだ。これって、代替わりして変わった。という事にならないんじゃないの?この曲だけは単体シングルとしてアニメを観ない人にもアピールしてどかーんと売れた。とかいうのであれば、多くの消費者に訴求する音楽単体の力があると認めるけど。ジブリって、〈千と千尋の神隠し〉がアメリカで興行的に惨敗しようと、全く影響なく、むしろ国内ではセールス延ばしてるわけですよ。セールスが音楽の質の高さと直接関わるとは言わないですよ。でも、何も変わってないという兆しと捉えられるんじゃない。この売れ方は」
チ「そこは難しいなあ。アニメの主題歌をアニメ文化と切り離して商品訴求力を計上するというのは(笑)」
ジ「そっちがアニメと切り離そうって言ったんじゃないか!(笑)」
チ「いやあだから、これからですよ。公開されたら二代目のカラーが更に歴然とするだろうから。国民全体がジブリをチアー&ジャッジするわけでしょ。角川春樹の例もあるし。でもそれは当企画とは関係ないです。とにかくこのシングルの出来は良いです。宮崎吾朗氏の萌えっぷりははっきりと暴走していると思うよ。ヘイリー・ミルズとかベッド・ミドラーに似てるって言うんだけど、はっきり言ってそんなに似てない。思い込みが激しい感じがする。でも、そういう周囲の思い込みを喚起させる魅力があるわけですよ。今様に言うと、雑味の無いナチュラルさがありまして、わざとらしいナチュラルはかえって雑味だからさ、良い意味での都会性を感じたけど。ワタシが連想したのは今井美樹とか古内東子とかです」
ジ「作詞はどうですか?萩原朔太郎の〈こころ〉に影響を受けて作ったのです。という、ちょっと考えられないような押し出し方ですけど」
チ「そんなもん、帝国の二代目だけに許される、良くも悪くも傲慢さでしょう。別に良いんじゃない。口にしないだけで、誰しも多少はあるよ。まあ〈こころ〉には、言われてみれば部分的に似てなくもない。という感じだけど、インスパイア。なんだからさ。歌詞がここに引用出来ないのが辛いなあ」
ジ「冒涜だと思う人も出ると思うけどねえ。セールス・トークに使っちゃってる訳だし」
チ「いやむしろ、萩原朔太郎なんて言わなきゃ良かったと思います。普通に訴求力のある良い歌詞だと思いますけど。朔太郎関係なく」
ジ「そろそろ時間だな。まとめに入ろう。ジブリ初プロデュースの大型新人。声優でも歌手でもある。女優もするかもしれない。プロフィールにあるのは〈現代的な物はみんなよくわかりません。古き良き物が好きです〉という押し出し。鈴木敏夫プロデューサーとヤマハの秋吉圭介と宮崎吾朗という、中年以上の男達の夢の結晶みたいな扱い。思い出すのは薬師丸ひろ子ですよ。でも、歌手としての薬師丸ひろ子は、アイドル全盛時代にあって中学の合唱部みたいな異形の声と佇まいによって歌謡史に残るシングルを出した。手嶌葵さんを薬師丸ひろ子リヴァイバルとするのは決めつけが過ぎると思うけれども、何にせよ〈異形感〉、もっと細かく言うと〈異形に近い程のイノセンスや青臭さ〉が、期待ほど感じられなかった。声優としては成功するのかもしれない。それこそ薬師丸ひろ子みたいに、齢を重ねてから素晴らしい境地に行くのかもしれない。でも、このシングルは中途半端感が拭えません。素晴らしいアレンジ、歌詞と楽曲も良いだけに惜しい。ジブリ帝国の住人として、それまでの主題歌と同じ様に、何の疑問もなく売れて、そこで止まってしまう予感が払拭出来ない」
チ「薬師丸リヴァイバルという仮説は、まあ納得できないでもない。記号的に符合する点も多いし。ヤマハ―ジブリ―二代目といったラインや、ギャルや萌え系などを吹き飛ばしてほしいという中年男性のいじましいほどの欲望は焦れる様にも見える。だけどはっきり言ってその欲望は挫折すると思う。成功者のロマンチシズムにしか見えないからだ。そんなことより、ジブリの主題歌というのは、見たくもない民族運動でも見せられてるみたいな、困っちゃう感じが常にあり、しかしそこが稀代のカリスマ、宮崎駿の実力だった。ガンダムシードの主題歌をタイアップ出来ればチャートではシード権がある。といったつまらないギャグや、萌え声の声優が歌うアキバ系アニソン全盛という状況に対し、〈凄く偉い人のヤリ過ぎ〉という、誰も何も言えないような強度でもって君臨していた。このシングルはその志は程よく残しつつ、手嶌葵さんの癖の無い、しかし質の高い声と歌唱によって〈宮崎思想体現の道具〉みたいな感じをさせず、普通に聴いて感動できる素晴らしさがある。アレンジも楽曲も確かに素晴らしいが、〈この唄の歌手〉という枠に踏みとどまらず、やがてはシティポップとかあるいはロックとか、いろんな物を歌ってゆけそうな期待感もある」
※この記事を読んだブロガーのみなさんは、チアーとジャッジのどちらを支持するかをトラックバックで表明してください。詳しいルールはこちらをご覧ください。
▼菊地成孔関連作品を紹介