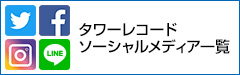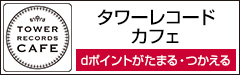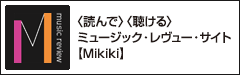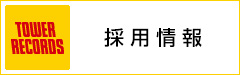Ⅱそれでは実際に聴いてみよう!
TIM BUCKLEY『Goodbye And Hello』 Asylum(1967)

null
近年は〈ジェフ・バックリーの父親〉として語られがちだが、アシッド・フォークというと真っ先に彼を思い浮かべる人も多いはず。無垢でいながらエキセントリックに飛翔するヴォーカルがとにかく素晴らしい。ここでは入手が容易な傑作としてこの2作目を推しておこう。
DINO VALENTE『Dino Valente』 Vivid/Koch(1968)
ジミ・ヘンドリックスでお馴染み“Hey Joe”の作者でもある男が唯一残したソロ作にして、USアシッド・フォークの代表的名盤。現れては消える砂漠の蜃気楼のような音像を、メランコリックな男気と感情に濡れた歌が彷徨う。先導役となる12弦ギターの響きも美しい。
LINDA PERHACS『Parallelograms』 Wild Place(1970)
カリフォルニアの謎の女性シンガーによる唯一の作品。木霊のように重なっては囁きかける歌声が、聴く者を束の間のインナー・トリップへと誘う。全編が静謐な空気感に支配されているが、妙にオカルティックな雰囲気を漂わせる曲もあり、油断は禁物だ。
PEARLS BEFORE SWINE『The Complete ESP Disk' Recordings』 ESP
異端のジャズ・レーベル、ESPは多くのアシッド・フォーク作品でも知られているが、特に有名なのがこの〈豚と真珠〉だ。優しく震えるラップの歌唱と効果音やコラージュを交えた演奏が、不思議にねじれた牧歌空間を構築。
DAVID CROSBY『If Could Only Re-member My Name』 Atlantic(1971)
バーズやCS&Nのメンバーとしても有名だが、この初ソロ作が幽玄かつスピリチュアルな逸品であることは意外と知られていない。グレイトフル・デッドのメンバーらによる緩やかなグルーヴと、複雑なコーラスが織り成す黄昏の世界観は実に酩酊的。
SYD BARRETT『The Madcap Laughs』 Harvest(1969)
過度のドラッグ中毒により、ピンク・フロイドどころか一般社会からもおさらばしてしまった精神の自由人。フロイドのファースト・アルバムで開陳したサイケなポップ感覚を、より内向的に脱力的に結晶化したこのソロ作はたまらなく純粋だ。引きこもりの美学。
VASHTI BUNYAN『Just Another Dia-mond Day』 Dicristina Stair(1970)
ブリティッシュ・フォークの深い森に咲いたひなげしの花のごとき名作。馬車での旅の情景を綴った清冽で無垢な音世界は、アシッドというよりはドリーミーで、ひたすら美しい。アニマル・コレクティヴらとの共演を経て、2005年はついに奇跡の復活!
TYRANNOSAURUS REX『My People Were Fair And Had Sky In Their Hair... But Now They're Content To Wear Stars On Their Brows』 Regal Zonophone/A&M(1968)
マーク・ボランは単なるグラム・ロッカーではない。簡素なバックに比類なきヨタレ声が乗ったこのデビュー作は、カラフルな夢幻の花を咲かせている。
NICK DRAKE『Pink Moon』 Island(1972)
夭逝のフォーク詩人が最後に残した本作ほど、儚く哀しく美しいアルバムはないと断言したい。全編アコギ一本の弾き語りで、消える寸前の蝋燭の炎のように揺らぎ、沈み込んでいく歌声はひどく生々しい。彼の行った先すら幻視される稀代の名盤だ。
SIMON FINN『Pass The Distance』 Durtro(1970)
かのデヴィッド・トゥープも参加した伝説的奇盤。もはやアシッドを超えて〈彼岸〉である。三途の川の向こう側に続くトロトロととりとめのない演奏に合わせて情念に満ちた歌を吐き出すのは、冥界の船頭か。帰り道はないので、心して聴くように。
吐痙唾舐汰伽藍沙箱『溶け出したガラス箱』 URC/avex io(1970)
五つの赤い風船の西岡たかしとジャックスの木田高介、斉藤哲夫によるユニットによる唯一の作品にして、日本産サイケ・フォークの最高峰。まず曲名が凄い。“あんまり深すぎて”“何がなんだかわからない時”“君は誰なんだ”。内容もそのままだ。受講者全員必聴!
野沢享司『白昼夢』 URC/avex io(1972)
ギターのオープン・チューニングを多用し、フルートやチェレステなどで装飾された特異な楽曲と、ドノヴァンやあがた森魚にも通じるどこかシニカルな寓話的歌詞が紡いだ白昼の夢。淡く残酷な郷愁に彩られた、日本フォーク史に埋もれた傑作。