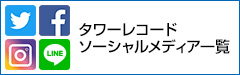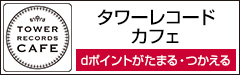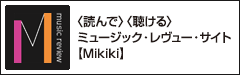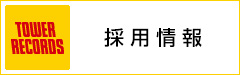音楽評論家の高橋健太郎氏は、今年3月に輸入権問題に対して反対を表明し、シンポジウムを開催したり、文化庁や国会議員と直接やりとりを行い、法案可決時に数々の附帯決議(注:国会の委員会が法案を議決する時に、その法案に追加される意見や希望)を設けさせた輸入権問題の中心的存在だ。高橋氏に、法案可決後の状況、今後の輸入権問題の見通しを伺った。
――輸入権問題の現状をどう見ていますか?
高橋 思ったより悪いですね(苦笑)。インターネット上の反対・署名運動や、音楽メディア関係者の声明などのおかげで法案自体には13項目もの附帯決議を付けることはできましたが、結局それがどれだけきちんと遵守されるかというところがポイントになるんでしょう。附帯決議が遵守されれば、それほど混乱は起きないだろうという希望的観測はあるんですが、今の時点(7月上旬)で、運用する際の細かいルールが何も決まってないんですよ。実際に輸入を差し止めるとすると税関でストップするしかないわけですが、現時点で税関側と文化庁、レコード会社の間でほとんど話し合いが行われていないみたいなんです。こんな状況で細則(注:法令で決めたことについての、こまかい規則)がいつ決まるのかって感じですよね。
――税関でストップさせる場合、具体的にどのように行われるのでしょうか
高橋 レコード店の人や卸業者の人からいろいろ聞いたところによると、今まで税関って輸入CDについてはほとんどスルーしてきたそうなんです。大手メジャーが数万枚単位で自社輸入しているものは完全スルーですし、1枚とか5枚みたいに小さいロットで輸入する輸入盤業者が輸入するCDは、インボイス(注:貿易品に付けられる詳細な明細書・伝票のこと)が付けられずに、単に「CD何枚」みたいに書かれて輸入されているんです。いざ輸入規制をするとなると、CDを輸入する際にインボイスを付けなければならなくなるでしょう。でもそうなると税関がいちいちインボイスの内容をチェックできるのかという問題が出てくるんですよ。今の税関の人数とか体制とか考えると絶対にそんなこと不可能ですし、税関職員が全部きちんとチェックしようとすると、絶対にそこでCDが滞留しますね。滞留しても通ればいいですけど、実際はそういうこと自体ができないんじゃないかという懸念が実際のCD輸入業務に携わっている人から出てきています。
――輸入権は運用面で問題が多いということでしょうか
高橋 まず、法案を通すときに出されたデータに信憑性がない。信憑性がないことは国会でも明らかにされているわけですから、運用の細則を定めるときに、データを出し直して洗い直すところから始めなければならないでしょう。また、この間あるシンポジウムで文化庁の森口審議官が「もともとこの法案は日本の音楽業界がアジアへの積極展開することが趣旨。2、3年たっても音楽業界がアジアへ積極展開せず、売上も伸びないようなら法案見直し、廃案も考えざるを得ない」と言ってたんです。僕個人の感覚ではこの法律ができたら売上がプラス成長に変わるかといえば、それは難しいんじゃないかと。現状アジア市場でどのくらいの売上があるかということを明らかにして、三菱総研が出した調査結果「今後8年間で14倍に成長する」ということを達成するつもりなのか、そうでなければ実際に実現可能な売上の達成目標はどれくらいなのかという明確な数値を文化庁なり音楽業界が出すべきではないかと思います。データの出し直しがなければ、なぜこのような運用細則を決めたのかという根拠がないですから、根拠をはっきりしてくださいということですね。
――当のレコード会社は輸入権問題や、音楽ファンから反対の声が上がっていることに対してどのように考えていると思いますか
高橋 一番困っているのは、レコード協会が公式に言っていることが実情に合っていないということですよね。実情に合ってないから、いくらでも突っ込みようがある状況になってしまったわけじゃないですか。例えば、この輸入権騒ぎがなければ、VELVET CRUSHの輸入盤が日本に入ってこなかったとしても、それは日本盤が発売される洋楽については「よくあること」で済んだんですよね。ところがこういう法律ができちゃったから、必要以上に騒がれるようになってしまったわけです。従来の契約慣行でやっていることでも、騒がれてしまうわけですからレコード会社はやりづらいでしょうね。今後輸入盤を見かけなくなったときに、ライセンス契約で輸入制限されたのか、法律で制限されたのかわからない。必然的に国内盤を出す際の契約条件なんかも変わってくるでしょうね。
――まだまだ先行き不透明なこの問題ですが、今後どうなるとお考えですか
高橋 一番怖いのはどこかで手のひらが返される可能性があるということです。〈還流盤の定義〉も、日本に原盤があるCDだけなのかと思っていたら、どうやらそれもあやしくなってきました。結局、洋楽のCDが中国などから相当な安値で入ってくる状況になったときに、輸入権を〈アジアから安値で入ってくる欧米CDを止めるための担保〉にしたいんでしょう。彼らが、洋楽にも輸入権は適用できるという部分を頑なに守っているのも、そういう隠された意図があるんじゃないかと思います。小泉内閣は今、知財計画という名目で業界保護政策をがんがん作っていますから、音楽のところで止めないとほかの業界にもどんどん波及していきます。今回この問題がインターネットで騒がれたことで、法律というものがこれほどまでにでたらめなデータを使って作られているということを多くの人が目の当たりにしました。そういう意味では消費者の意識も高まったんじゃないでしょうか。あとはそれぞれがこの問題に対して注視して、少しでもおかしなことがあったらおかしいと声を上げることが、状況を悪化させないために必要なことなんだと思いますね。