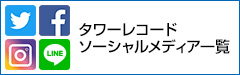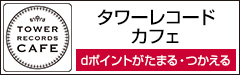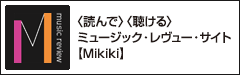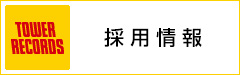言ってしまえば他人の曲を繋いでいるだけ。しかしながらそれはときに過激なまでの強度を持ち得る。ミックスCDとはそんな表現フォームだ。ここではそんな感動を与えてくれる日本のノンジャンルでアナーキックなダンス・ミュージック作品たちを紹介。まずは……この特集を組むきっかけとなったあのシリーズの首謀者たちの言葉からはじめよう!!

SESSIONSクルー。左から浅野森、小林弘幸
ミックスCDとは一体? いまでこそ〈DJが自他国内外を問わない楽曲を選盤し、ある作品ではそれをクラブさながらにプレイ/ミックスし、ある作品ではライヴ・プレイで再現出来ないほどにコンピューターで編集したアルバム〉と基本的な説明をせずとも、それが何であるかはおわかり頂けるだろうが、ミックス CDは市民権を得ると同時に、その提示のされ方や聴かれ方も間違いなく変化し続けている。そこでMOODMAN、タキミケンジというラインナップのもと、近年のダンス・ミュージック・シーンにおけるエポックメイキングなミックスCDシリーズ〈SESSIONS〉を世に送り出してきたディレクターの小林弘幸、浅野森両氏に冒頭の質問を投げかけてみた。
「もともとはミックス・テープとしてカセットで出回っていて、当初はDJのプロモーション・ツールだったわけですけど……」(浅野)
「今に至っては独立しつつあって、ここ最近の音楽誌ではミックスCDの年間ベストが選ばれていたり、国内外問わずここ最近のリリース数もとんでもないことになってきていて、ミックスCD文化は徐々に根付いてきてはいると思う。そんな状況下における〈SESSIONS〉シリーズの人選に関しては別に無理してるわけじゃなく、僕らが普段遊んでいるなかで自然に生まれてきたものなんですけど、一番の取っ掛かりはMOODMANで。彼は過去に自分自身をメインにした作品を何枚か出してはいたんだけど、現在のDJスタイルと同期した作品がなかったから、〈出しましょう〉っていう」(小林)
「で、その後のタキミさんのものを含め、ライヴ・ミックスで出していこうっていうことになっていて。というのも、かつては時間軸が移行していくなかで作られていた音楽が、いまはバンド・サウンドも含めハード・ディスク・レコーディングが一般的になるにつれ、時間軸を飛び越えてどうとでもいじれるようになってしまった。でもクラブなりライヴハウスなりその時その場所だけで成立する音の狂気も確実にあるわけで、そこにはこだわっていきたいなと」(浅野)
徹底した現場主義と、もっと、その先を体験したいという究極的なリスナー気質。ダンス・ミュージックは移り変わりが早いだけに送り手には、そういった感覚が要求されるのは間違いない。
「最近遊んでいて思うのはいい意味で粗雑になっているということ。言ってしまえば、ここ1、2年のダンス・ミュージックとパンクがクロスオーヴァーした音の表され方だったりとか、曲の繋げ方もスムースじゃないほうがいいっていうところまでいってる。それはハウスに限らずいろんなところでそうなってるのかなっていう気がするし、その反面マーク・ファリナみたいに完璧なミックスで踊らせるDJもいる。僕らはパンク・ハウス──最近では〈アナーコ・ハウス〉と呼ばれているけど──そういうパーティで遊んでいるから、いま言ったいい意味での粗雑さは大切にしているかな」(小林)
もちろんここでご紹介している2人の発言は総論を意図したものではないし、ましてミックスCDの楽しみ方を規定するものではないけれど、ここで語られているような背景は確かに存在しているし、そうしたことを踏まえて聴くミックスCDの楽しみもまた格別だ。
「そのDJが聴きたければパーティに行けばいいんだけど、それをミックスCDの(収録時間)マックス80分に何を閉じこめるか? その技量は今後より問われていくと思う。それからこと日本に関しては欧米と違ってミックスCDを聴く文化がないっていう前提に、90年代中盤くらいからミックスCDを出し始めたDJは苦労してきたわけだけど、いまはまた違うよね。リスナーというか、オーディエンスもアトモスフィアというか一枚で感じ取れる空気感を楽しむっていう方向に向かってると思う。有り難いことに『SESSIONS』に対するリアクションがこんなにいいっていうことは、そういう部分での楽しみ方が広がってきたのかな、と」(小林)
(構成/小野田雄)