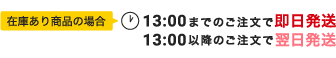構成数 : 52枚
合計収録時間 : 52:56:47
交響曲(CD1~CD2)
G515、G517、G518、G519、G520、G521、G522
エルクスレーベン、新ベルリン室内管弦楽団(1992)
収録された7曲の交響曲は、プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世のために1786年から1792年に作曲された作品。イタリア風序曲スタイルのG521から壮大なG522まで多彩な内容です。
指揮のミヒャエル・エルクスレーベンは、1960年ドレスデン生まれのドイツの指揮者でヴァイオリニスト。カプリッチョ・レーベルの録音。
チェロ協奏曲(CD3~CD5)
G479、G480、G477、G482、G478、G475、G483、G474、G573、G476、G481
ブロンツィ、アカデミア・イ・フィラルモニチ・ディ・ヴェローナ(2005)
ボッケリーニはチェロの名手で、まだ売り込み中だった若い頃にチェロ協奏曲書き始め、12曲が遺されています。超絶技巧を駆使してチェロの全音域を駆使、超高速パッセージのほか、弓使いの多様なバリエーションも必要とされ、珍しいオクターブの倍音に、弦を弾いたまま素早く開放弦に持ち替える奏法なども駆使。叙情的な部分では繊細な表現力も求められます。まだチェロが独奏楽器として認知されていない時代にこれだけの作品を書いたボッケリーニは若い頃から天才でした。
明るい音色の室内オーケストラをバックに、独奏チェロが颯爽としたテンポでカンタービレの極致を聴かせる見事な演奏。弾き振りのエンリコ・ブロンツィは、1973年パルマに生まれたチェリストで、室内楽で活躍しているだけあって、アンサンブルでの呼吸の良さも格別です。
弦楽六重奏曲(CD6)
G457、G454、G459、G456
ザイラー、ユダ、ポッペン、ディッケル、レスター、ペニー(1991)
収録された4曲は、1776年、マドリード西隣にあるボアディーヤ・デル・モンテのドン・ルイス宮殿で働いていた時期の作品。真新しい新古典主義様式の宮殿にふさわしい典雅で華やかな音楽。
オーボエ五重奏曲(CD7)
G431、G432、G433、G434、G435、G436
レンチェーシュ、パリジイ四重奏団(1992)
1797年に作曲。オーボエの名手であったガスパール・バルリのために書かれたもので、パリのプレイエル社に作曲のことを伝えています。
演奏のラヨシュ・レンチェーシュは、シュトゥットガルト放送響の元首席オーボエ奏者。濃密な演奏が楽しめます。カプリッチョ・レーベルの録音。
ギター五重奏曲(CD8~CD9)
G445、G447、G449、G450、G448「ファンダンゴ」、G446、G453「マドリードの帰営ラッパ」
ロゼッリ、ラ・マニフィカ・コムニタ(2005)
1798年に出版。ドン・ルイス亡き後、約11年に渡ってボッケリーニを支援したベナベンテ=オスナ公爵夫人は大のギター好きで自身も演奏。「ファンダンゴ」と「マドリードの帰営ラッパ」はボッケリーニ屈指の人気作。
演奏のエロス・ロゼッリはイタリアのギタリスト。ラ・マニフィカ・コムニタとの共演によるピリオド演奏です。
ピアノ五重奏曲(CD10~CD13)
G407、G408、G409、G410、G411、G412、G413、G414、G415、G416、G417、G418
グレゴレット、アンサンブル・クラヴィエーレ
1797年と1797年にプレイエルから出版。プロヴァンスなどフランスの素材も用いたボッケリーニの新機軸。「フランス国民と共和国に捧ぐ」として大使のリュシアン・ナポレオンに楽譜を送ったりしています。ヨーロッパ中が大変な時期だったのでボッケリーニも気を遣ったようです。
演奏のイラリオ・グレゴレットは、1805年シャンツ製のフォルテピアノを弾いてピリオド・アンサンブルのアンサンブル・クラヴィエーレと共演。
弦楽五重奏曲(CD14~CD34)
G265~G330(Op.10、Op.11、Op.13、Op.18、Op.20、Op.25、Op.27、Op.28、Op.29、Op.30、Op.31)、G337~G339(Op.39)
ラ・マニフィカ・コムニタ(2004~2008)、イ・ヴィルトゥオージ・デッラ・ロトンダ(2013~2016/Op.29~Op.31)
ボッケリーニの創作の中核を成すのが大量に遺され水準も高い弦楽五重奏曲。これまではドン・ルイス親王が追放されて奥地の城にずっと閉じ込められていたから楽員も少なくそれしか書けなかったように言われてきました。しかし、実際には追放ではなく国王カルロス3世の外国生まれの子どもになんとか王位継承権を与えるための無理な要求に対して、穏やかなドン・ルイスが応えていただけの話です。
そしてその奥地のモスケラ宮殿を利用していたのは、新築工事の関係で約1年8か月に過ぎません。ドン・ルイスがボッケリーニを雇っていた期間の残りの約13年間はいろいろな宮殿に滞在してたというのが真相で。これは当時のスペイン王家の年間行動スケジュールが、定期的に国内の宮殿を移り住んでいたことと関係があります。
楽員が少なかったのは、単にドン・ルイスが室内楽が好きだったからです。結果的にボッケリーニはドン・ルイスが亡くなった後、宮廷で働かずに国王カルロス3世と4世から約20年間も年金を支給され続けており、最後の支給は亡くなった翌月でした。
演奏の中心メンバーであるチェロのルイージ・プクセッドゥは、「ラ・マニフィカ・コムニタ」のメンバーとして、計51作品を録音していましたが、2012年にレーベルの体制が大きく変わったことでいったん中断。そして、4年後の2015年に、プクセッドゥが自ら結成したグループ「イル・ヴィルトゥオージ・デッラ・ロトンダ」での演奏によりシリーズを再開、18曲を録音しています。演奏は、活力、色彩とカンタービレの魅力にあふれたもので、ときに驚くほどのダイナミズムも交えながら、旧来の「穏やかな」ボッケリーニ像とは大きく異なるピリオド・アプローチを展開。
弦楽四重奏曲(CD35)
G195、G196、G197、G198、G199、G200
アンサンブル・シンポジウム(2015)
ボッケリーニは43年間に約90曲の弦楽四重奏曲を作曲していますが、ここでは1778年に作曲されたOp.26の6曲を収録。当時のボッケリーニは、マドリードの西隣に位置するカダルソ・デ・ロス・ヴィドロスにあるヴィリェナ宮殿で働いていました。
演奏のアンサンブル・シンポジウムは、イタリアの古楽器アンサンブル。ボッケリーニ独特の美しいラインを堪能させます。
フルート五重奏曲(CD36~CD38)
G419~G436(Op.17、Op.19、Op.55)
デ・トレス、フランシスコ・デ・ゴヤ弦楽四重奏団(2018)
Op.17とOp.19が1773年のマドリード西隣のボアディーヤ・デル・モンテのドン・ルイス宮殿時代、Op.55は1797年のフリーランス時代の作品。のちのベートーヴェンを思わせるところもあってたのしめます。
演奏のラファエル・ルイベリス・デ・トレスとフランシスコ・デ・ゴヤ弦楽四重奏団はスペインの古楽アーティスト。セビリアのサン・ペドロ・デ・アルカンタラ教会の響きも最高です。
弦楽三重奏曲(CD39)
G92、G90、G93、G94
ルボツキー・トリオ(2016)
1769年に作曲。当時のボッケリーニは前年からルイジ・マレスカルキの主催するイタリア・オペラ巡業団の楽団員となってスペインに滞在しており、出演歌手のクレメンティーナと恋に落ちたり、カザノーヴァと出会ったりしながら夏には結婚し、さらに自作の協奏交響曲まで披露していた時期。
演奏のルボツキー・トリオは、ロシア生まれのベテラン奏者ルボツキー夫妻とスウェーデンのカタリナ・アンドレアソンで構成。2つのヴァイオリンとチェロのための変則的な編成の作品を引き締まった演奏で聴かせます。
ヴァイオリン・ソナタ(CD40~CD44)
G25~G30、G46~G51、G52~G54、G20.1~6
ルハーゼ、ネポムニャシチャヤ、ドスタレル=ラロンド、プリーエフ(2020~2021)
ボッケリーニはチェロの名手で、作曲の面でもチェロの注目度が高くなっています。しかし音楽の需要という面では、弦楽器の花形がヴァイオリンというのは今も昔も同じであり、実際、若きボッケリーニが作曲家として最初にパリで大きな成功を収めたのもヴァイオリン・ソナタ集 Op.5でした。このOp.5は、ソナタ第1番の出だしがのちのベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番の開始に似ていたり、ソナタ第3番がどことなくベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第5番「春」を思わせるなど、表情豊かで美しい旋律の宝庫でもあり、後に曲集まるごと再出版したり、他の作品に素材を転用したりと、ボッケリーニ自身のお気に入りでもあったようです。
演奏は長くオランダやドイツを拠点としてきたロシアの古楽演奏家らによるものです。
2つのヴァイオリンのための二重奏曲(CD45~CD46)
G56~G61(Op.3)、G63~G68(Op.46)
ルハーゼ、ゴルバン(2021)
Op.3は1761年の作品。作曲当時18歳のボッケリーニはウィーンを拠点に活動しており、チェロ演奏のほか作曲にも力を入れ、グルックからも高く評価されていたとか。フレッシュな楽想が投入されたこの曲集も魅力十分で、レコーディングもすでにいくつか存在しますが、クリティカル・エディションの使用は初めてとなります。
ボッケリーニの場合、作品番号は出版社が付けたものとボッケリーニ自身が付けたものが違っている場合がけっこうあるため混乱しがちなので、G番号(ジェラール番号)で記載するのがわかりやすいです。この曲集の場合も、1768年にパリのルイ=バルタザール・ド・ラ・シェヴァリエール社から出版された際には「Op.5」とされていましたが、同年にパリのヴェニエ社から出版された「6つのヴァイオリン・ソナタ」(G.25~G.30)も「Op.5」と表紙に大きく印刷されてしまったため、のちにボッケリーニ自身が「6つのニ重奏曲」(G.56~G.61)を「Op.3」と変更しています。そのため、2007年出版のクリティカル・エディションでは「Op.3」としていますが、それ以前のものでは混乱もあります。
Op.46の作曲時期はわかっていませんが、ボッケリーニの旧作を改作しているため晩年のものと考えられています。この曲集の場合、作品番号の問題はさらにややこしくなっています。1799年にパリのプレイエル社から出版された際には「Op.46」でしたが、その後、ハンス・ジット[1850-1922]が曲集の前半3曲(G.63~G.65)を選んで「3つのニ重奏曲」として校訂し、紛らわしいことに「Op.5」としてペータース社が出版。その後、ジットは4番(G.66)などを収めた「2つのニ重奏曲」も「Op.5」として出版。1761年の曲集も最初はOp.5として出版されていたので、「Op.5」だらけです。加えて1793年作曲の「6つの弦楽五重奏曲」(G.359~G.364)が、自筆譜目録では「Op.46」とされてしまったことで大きな混乱を招いています。なお、ジット版の「3つのニ重奏曲 Op.5」の楽譜が広く出回ったため、第1曲(G.63)は昔からとりあげられたりしていましたが、「6つのニ重奏曲 Op.46」としての全曲レコーディングは存在しなかったので、今回の録音は歓迎されるところです。
チェロ・ソナタ(CD47~CD50)
G3、G2a、G1、G4a、G5、G4b、G2b、G6~G18、G565a、G565b、G566、変ホ長調、ト長調、イ長調
プクセッドゥ、ブラカレンテ、フェッラニーニ(2008)
ボッケリーニのチェロ・ソナタのほとんどは、若い頃の作品で、父の伴奏を念頭に置いていたのか、チェロ独奏と低音弦楽器による通奏低音という組み合わせになっています。音響としても面白く、随所に技巧的な要素も盛り込まれて聴き応えがあります。
演奏のプクセッドゥはボッケリーニのスペシャリストで、畳み込みの迫力から朗々としたカンタービレまで雄弁に聴かせます。
アリア・アカデミカ(CD51)
G557、G544、G545、G546、G547、G548
サンドラ&ギエルモ・パストラーナ、マッツォーリ&ルッカ・ルイジ・ボッケリーニ音楽院管弦楽団
ドン・ルイス親王に雇われてからは室内楽作曲が本業になったボッケリーニですが、その前にはウィーンの劇場やスペインの劇場で演奏していましたし、イタリアではオラトリオも書いていたほかスペインではサルスエラも書いていたので、オペラや声楽には通じています。ここに収められたのはコンサート・アリアで、内容は、ディドの嘆きや、ファルナスペが最愛の人に別れを告げる場面など、悲しい感情に焦点を当てたもので、ドラマティックな描写も見事で、チェロも大活躍します。
ソプラノのサンドラ・パストラーナとチェロのギエルモ・パストラーナはスペインの音楽家姉弟。珍しい作品を熱気のある演奏で聴かせます。
スターバト・マーテル、弦楽四重奏曲(CD52)
G214、G532
ボンコンパーニ、アンサンブル・シンポジウム(2016)
冒頭に置かれた弦楽四重奏曲ハ短調は1788年の力作。スターバト・マーテルの組み合わせにふさわしい悲痛な情感も迫力も十分です。
スターバト・マーテルは1781年作曲の第1版を収録。ボッケリーニは19年後の1800年に大幅な改訂を加えていますが、第1版のシンプルな美しさも魅力的です。
ソプラノのフランチェスカ・ボンコンパーニはイタリアの歌手でモンテヴェルディ合唱団のメンバーでもあります。アンサンブル・シンポジウムによる弦楽五重奏との共演。