詳細検索
いずれかのカテゴリを選択すると、より細かい検索が可能です。
カテゴリ
ジャンル
アーティスト名
アイテム名(商品名)
トラック名(曲名)
レーベル
規格品番
SKU
ジャンル
アーティスト名
アイテム名(商品名)
トラック名(曲名)
レーベル
規格品番
SKU
ジャンル
キーワード
アイテム名(商品名)
トラック名(曲名)
レーベル
規格品番
SKU
ジャンル
タイトル(商品名)
著者
出版社
SKU
発売日
国内輸入区分
その他
ジャンル
キーワード
タイトル(商品名)
監督、監督脚本
主演、出演、声の出演
規格品番
SKU
ジャンル
アーティスト名
アイテム名(商品名)
トラック名(曲名)
レーベル
規格品番
SKU
ジャンル
キーワード
タイトル
本文
コンテンツタイプ
掲載日
タグ
結果表示順
表示件数
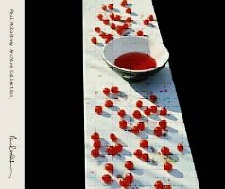


もちろん「ジャンク」は”ジャンク”な作品ではないし、「恋することのもどかしさ」も同様、”完成品”というレッテルを貼っていいくらい完璧に仕上げられていて、珠玉の”名曲”であることには違いない。前者はシンプルな佳曲だし、後者はエモーショナルでエネルギッシュな秀作だ。本作でも際立った存在感がある。しかし、それ以外は何とも中途半端で、途中で筆を置いてしまった描きかけの絵画や、出口の見えないままに掘削を止めてしまったトンネル、あるいは使われなかった部品や素材、屋根裏部屋の抽斗の奥に眠っていたメモ書きの断片みたいなものが、アルバムを構成するパーツとして集められ、並べられている、ようにしか見えない。長い時間、価値を見出そうと向き合ってみたが、結局、見出すことはできなかった。
ところが最近、このプライベート盤から伝わってくる微弱な電波を捉えることができるようになってきた。電波は微弱だが、ポールのエモーショナルなパッションのような微熱を含んでいて、不思議と”惹かれる”のだ。
この感覚は、自分にとって、映画『ストレンジャー・ザン・パラダイス』と似ている。通ぶっているわけではない。起伏のないドキュメンタリーのような粗い展開の中で、醒めた感性の登場人物がノイズのような何とも居心地の悪い映像空間を泳いでいる映画だが、全体に宿る空気の塊みたいなものが磁石のように自分を惹きつけるのだ。
それでも、本作を”五つ星評価”することはできない。多くて3つ。自分として、このアルバムに対する最大限の高評価だと思っている。ただ、確実に言えるのは、これからも本作とは向き合っていくだろう、ということだ。