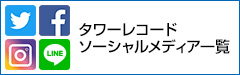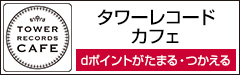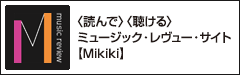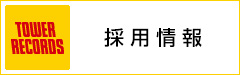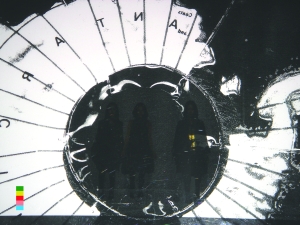
確信犯を通り越して、これはもう食わせ者と言うしかないかもしれない。いや、1年おきに首相が交替しては、ついに漢字もロクに読めない総裁の下、支持率が地に落ちてしまった〈辞任党〉をはじめとする現代日本の政治社会に向けたテロリスト、もしくはレジスタンスか。
2008年5月に全国流通されたファースト・アルバム『シフォン主義』が各所で大きな話題となり、灰野敬二やイルリメ、岸野雄一、石橋英子ら曲者たちと次々に共演を実現、バンドのウェブサイトや〈MySpace〉はあるものの、顔写真は出さずインタヴューなどにもまったく応じない素っ気なさも逆に奏効して、いまや随一のカルト性を持ったバンドへと成長した相対性理論。ともあれ、その正体は難解でも何でもない、奇妙にねじれた人懐っこさをも伴ったポップ・バンドだという事実が聴き手をよりいっそう混乱させてきた。そして、ここにいよいよセカンド・アルバム『ハイファイ新書』が届いた。
しかしこれ、渋谷系時代のアイドル・ポップと言っても通じるような内容だ。いや、やくしまるえつこの感情の起伏がない歌は変わっていない。一部ではジッタリン・ジンのデビュー当時を思い出させる……といったような評価もある彼女のヴォーカルは、例によって口の中に甘ったるいマシュマロを含んでいるような舌足らずなものだが、いわゆるオルタナ以降のギター・バンド然とした側面はかなり後退。展開にもさほど明確な抑揚がないし、ダンス・ポップ調、AOR調、フィリー・ソウル調、ギター・ポップ調と楽曲自体はかなりヴァラエティー豊かだが、全般的にダイレクトな攻撃性のほとんどない、いわば低体温気味なアレンジになっているのが大きな特徴と言えるだろう。小走りに言葉を多く詰め込む傾向は変わらないし、メロディーは純和風と言えるような歌謡曲さながらのわかりやすさ。その落ち着いたトーンの演奏のなかで、まるで静寂に呑み込まれてしまったかのように無垢な歌声だけがひっそりと息づいている、そんな印象さえ受ける。
そう、まさしくその〈落ち着いた演奏が生む静寂のなかで息づく無垢な歌声〉の持つある種の〈凶暴性〉とでもいうようなものこそ、このアルバムが、いや、相対性理論というバンドが世に問うているイデオロギーなのではないか。適度にものわかりの良い大人たちがひしめく現代社会で、いまもっとも必要とされているものはいったい何か――それは無垢という名のテロル。だから彼らの楽曲に添えられた揶揄とユーモアたっぷりの歌詞は、思わず手を止めて後ろを振り返りたくなるほど不気味だ。
今回のアルバムがなぜこうした路線になったのかはわからない。しかし、ファンキーなギター・カッティングやフィルインがスムーズなドラミングといった演奏技術からは、おそらくこうした嗜好の音楽性をもともと持っていたであろうことがわかる。だから〈食わせ者〉などとして紹介するのは適切ではなく、4人のメンバーたちをそれぞれに趣味の良い音楽リスナーであり、真面目なプレイヤーたちとして本来紹介すべきかもしれない。そのうえで彼らは適度に趣味が良くて演奏も安定していることの無意味さを、調子っぱずれでエモーションのカケラもないやくしまるの歌いっぷりによって崩そうとしている。白痴スレスレのピュアネス、感情ゼロの能動性がもっとも大きな力を持ち得ることを伝えようとしている。このニュー・アルバムはそんなことを痛切に感じさせる一枚だ。
これまでこのバンドについての感想を訊かれると、言葉をかなり選んできた。その気持ちはいまも変わらない。ただただ彼らの音楽に自分の解釈を与えるだけ。そうすることによってのみ成立する稀なバンド、それが相対性理論なのだと。
PROFILE
相対性理論
やくしまるえつこ(ヴォーカル)、永井聖一(ギター)、真部脩一(ベース)、西浦謙助(ドラムス)から成る4人組。2006年に東京で結成され、都内を中心にライヴ活動を開始。2007年にライヴ会場とバンドのウェブサイト限定で自主制作盤『シフォン主義』を発表。インターネットを中心に話題となり、4000枚のセールスを上げる。以降、注文に対応しきれなくなったため2008年5月に同アルバムを全国流通盤としてリリース。同年6月より自主ライヴ企画〈実践〉をスタートし、イルリメやナスノミツル、灰野敬二、石橋英子らを招くなど多くのアーティストとの共演でさらに知名度を上げ、2009年1月7日にはセカンド・アルバム『ハイファイ新書』(みらい)をリリースしたばかり。