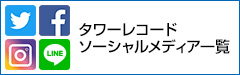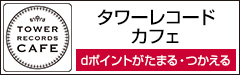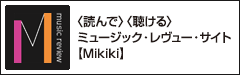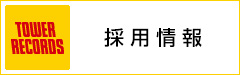KEN ISHII (c)Kazuhiro Kitaoka
どこかバック・トゥ・ベーシックなノリが漂うのもこの日のWIREの特徴だったのではないか。ウェストバムに続いて登場したKEN ISHIIは、機材のトラブルすら盛り上げのエネルギーに変える圧巻のパフォーマンスを披露。さらに懐かしの“Extra”をプレイし、その神々しいエナジーで往年のファンたちを涙と歓喜の海で踊らせていく。田中フミヤもお得意のクリックなミニマル・テクノをベースにしつつ、マッド・マイクによるプロジェクト〈ソウル・シティ〉が手掛けたダヴィーナ“Don’t You Want It”という往年のデトロイト・クラシックをフロアに投下するなど、随所でエモーショナルかつソウルフルなプレイで盛り上げる。新作DVD『Via』で、クラウドとコミュニケートすることへの妥協なき姿勢を披露している彼を見た後だけに、その感動もひとしおであった。

レディオ・スレイヴ (c) Masanori Naruse
そんな甘美でソウルフルな空間とは異なる世界を作り上げていたのが、ブライトンのダークサイドを体現するレディオ・スレイヴことマット・エドワーズだろう。超ディープ&スモーキーなDJで、宇宙空間へ飛び立ったはずのWIREを一気にマリアナ海溝にご招待。浮遊感を感じさせながらも常に緊迫したトーンでフロアを支配し、いま最も人気を博すミニマル/ディープ・ハウスのプロデューサーの実力を存分に見せつけていた。

モーター (c) Masanori Naruse
そして、“Red 3”などの往年のヒット曲で喝采を浴びていたデイヴ・クラークの裏で、この日の〈裏ベスト〉とクラウドの絶賛を受けていたのがモーターだった。“Bleep #1”や“Black Powder”など、ヴィタリックをさらに高圧的にしたパンク・テクノは、バンドで演奏することで色気を増し、さらにダイナミックに躍動。沸き起こるアンコールに応える彼らの勇姿にはまるで後光が射しているようで思わず合掌。

レナート・コーエン (c)Kazuhiro Kitaoka
さて、終盤。ゴールに向けてひた走るクラウドを加速させたのがレナート・コーエン。密度の高いクリッキーなサウンドを通過した疾走感バツグンのハード・テクノは、時折ラテンっぽいノリを交えながらシャープにクラウドを踊らせ、代表曲“Pontape”で勢いをさらに加速していく。
そんなレナートに反して意外にもかなりハウスっぽいサウンドを披露したのがヨリス・ヴォーンだった。名曲“INCIDENT”もやや控え目なアレンジ。それでもフロア中の観客の手を天にかざさせたのは若き天才の巧みな構成力からだろうか。

フェリックス・クロヒャー (c)Kazuhiro Kitaoka
そしてヨリスのまったりしたテンポに合わせてDJをスタートしたのは、昨年のセカンドフロアでその激烈にハードなプレイを大絶賛され、今年見事にメインフロアのトリに抜擢されたフェリックス・クロヒャー。「あれ? 意外とまったり?」と最初は油断してた観客だが、どんどんスピードの上がっていくビートに平手打ちを食らった形相に。シュランツ(大ネタ系超ハード・テクノ)を連発する彼だけに、顔がニヤけてくるような楽しすぎるハードなパーティに。ラストは“Born Slippy”に〈スーパーマリオ〉ネタのトラックで大団円。息を切らせつつも幸せそうな表情で帰路につくクラウドの顔がとても印象的だった。ちなみにセカンドフロアではディープでエレクトリックなテクノからメロディックなハウスで大合唱という毎年恒例のTOBY(祝! アルバム『Electric Smooch』リリース)による幸せDJで幕を閉じている。ラストは今年のNo.1アンセムの呼び声も高いGENKI ROCKETS“Hevenly Star”だったというのだから、その場にいた観客の皆さんはさぞかし楽しかったことであろう。
興味深いのは、多彩なラインナップ同様、DJの選曲の中身もバラエティに富んだものになっていたということだろう。それによってパーティ全体もこれまでに比べ、かなり起伏が富んだ構成になっていた。ハードに踊り明かしたい方にはその振れ幅に戸惑う部分もあったかもしれないし、逆に音楽好きにとってはアーティストたちのユニークなパフォーマンスと楽曲を存分に味わえる楽しい場となっていた。もちろんDJもダンス・フロアという現場と向き合いながら、その振れ幅を昇華していくという試みをしており、心地よいグルーヴが耳を魅了しながらも、試行錯誤的なムードも感じさせる不思議な一晩となった。

(c)Tsukasa Miyoshi
10周年という記念すべき年を目前に控え、今一度改めて自らを乱暴にかき回すことでマンネリという硬直化を打破する。それが今年のWIREだったとは言えないか。そうした意味において〈WIRE07〉は実に重要で意義のあるパーティだった。そのように私は思うのである。
▼文中に登場したアーティストの作品を紹介