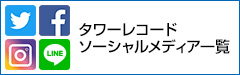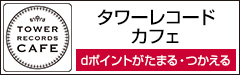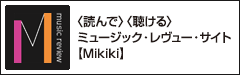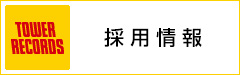アトム・ハートの華麗なる変身(ほんの一部)を紹介

アトム(TM)名義で2000年にリリースされた『XXX』(Rather Interesting)
アトム〈ヒップホップ〉ハート
果たして18歳未満は無事購入することができるのであろうか?という、いかがわしいジャケのなか、ポーズをきめるラッパー、ティー・タイム(実在するのかどうかは不明)のラテン言語なMCが、同じくラテン・フレイヴァーなトラック上にドンピシャはまった、アトム・ハート史上でも珍しいヒップホップ作品。DMC系のターンテーブリストたちにもいまだ手をつけられてなかった荒技、その名も〈HDスクラッチング〉(!)が飛び交います。
アトム〈コラージュ〉ハート
数秒~数十秒のトラックが、なんと! 99トラックも収録されているコンセプチュアルな作品。アトム・ハートらしいエディットの大技小技がほとんどのトラックで繰り広げられ、普通にかけてもラフ・スケッチを見ているような感じで楽しめます。しかし、CDプレイヤーにランダム機能が付いていればなおさら良し。曲間なしでトラックが収録されているため、毎回違ったアルバムを聴いているような感じで楽しめます。お得です。

LB名義で99年にリリースされた『Pop Artificielle』(KK)
アトム〈ロック〉ハート
アトム・ハートによる名曲ワンマン・ショウ。ジェイムズ・ブラウンやドノヴァン、プリンス、ジョン・レノン、デヴィッド・ボウイ、坂本龍一まで、カテゴリー/時代を超えてカヴァーしまくり、独自のロボ声マシンで唄いまくりシャウトしまくりの、ヴォーカリストとしての才能を知らしめた作品。往年のアイドルがステージで洋楽曲のカヴァーを挿入していってたように、機会があれば、ぜひここからいくつかやってもらいたいもの。

ロス・サンプラーズ名義で2000年にリリースされた『Descargas』(Rather Interesting)
アトム〈ラテン〉ハート
いま、チリでもっとも注目を集めているこの7人組! 担当楽器は全員サンプラー! えっ?というような感じの、いつものアトム・ハートお得意のジョークにパッケージされた〈裏・セニョール・ココナッツ〉とでも名付けておきたい作品。極端にザラついた音質のもと、ズタズタにエディットされまくりのヴォーカルやパーカッション、その他の生楽器が複雑怪奇に絡みあって、なんとも危なっかしい。新種のポップスを誕生させております。

フランジャー名義で99年にリリースされた『Templates』(Ntone)
アトム〈ジャズ〉ハート
ドラマーであり優秀なコンポーザー/アレンジャー/ミキサーとしても知られるバーント・フリードマンと、二人三脚でもって作りあげられたハイテク・ジャズ。もともと実験的にジャズを展開し続けていたアトム・ハートだけに、生ドラムとの相性もバッチリ。プログラミング制御された音と、生演奏された音との兼ね合いが非常にスリリングです。MIDI vs. 腕ですね。セカンド・アルバム『Midnight Sound』ではマイルス・デイヴィスの片鱗も。
アトム〈オムニバス〉ハート
とんでもなく膨大な作品量を抱えるアトム・ハートのカタログですが、手っ取り早く彼の世界観を堪能したいのなら、まずはここから。最初に聴くにはもってこいなラザー・インタレスティング作品が中心の選曲で、わっさわっさとラテンでジャズなアトムが目白押し。ミックス/エディット/オーヴァー・ダブを施すのは、フランジャー名義での良い相方、バーント・フリードマン。アトム・ハート初級講座としてはもちろん、そうでなくても楽しめる充実作。

リサ・カーボンが97年にリリースした『Trio De Janeiro』(Rather Interesting)
アトム〈ラウンジ〉ハート
コスタリカの女性ムーグ奏者、という肩書きの響きが妙にイロっぽく聞こえるリサ・カーボンも、いまではアトム・ハートの良き人生のパートナーであり、良き音楽制作のパートナーでもある。現在のアトム・ハートの作風に多大な影響を与えているのが彼女。ラウンジ趣味満点のトラックに、カクテルのグラスごしに垣間見るムーグを操る艶かしい手つき。本作以降、彼女のムーグはアトム・ハート作品中、何度となく登場することになる。
アトム〈セニョール・ココナッツ〉ハート
アミーゴ! セニョリータ(巻き舌で)! 故郷フランクフルトを離れサンティアゴに移住してからの出世名義、セニュール・ココナッツ。現地のネイティヴな音楽であるラテンやルンバを、アトム・ハート流のユーモアと卓越したテクニック、愛情でこねくりまわした、文字どおり〈早すぎた〉デジタル・ラテンの傑作『El Gran Baile』。そして、ラテンでクラフトワークをカヴァーするという、まるで酒の席で決めてしまったような、あるいは電子音楽界の大先輩に敬意をはらって(?)の、アホらしくも納得のコンセプトを掲げ、現地のコンボをMPC-3000一台で指揮をとり熱演させてしまったポップなセカンド・アルバム『El Baile Aleman』(車を出発させようにも、まったくエンジンのかからない“Autobahn”のアレンジが笑えます)。両方聴いていると、リチャード・ヘイマンのアルバム『Genuine Electric Latin Love Machine』のジャケでテンガロン・ハットを被っていたロボットの画や、タバスコがいい具合にかかった美味しそうなタコスの画で、頭の中がいっぱいに埋め尽くされていきます。サード・アルバム『Fiesta Songs』では、びっくりカヴァーが満載!! すべてがエスカレート!!